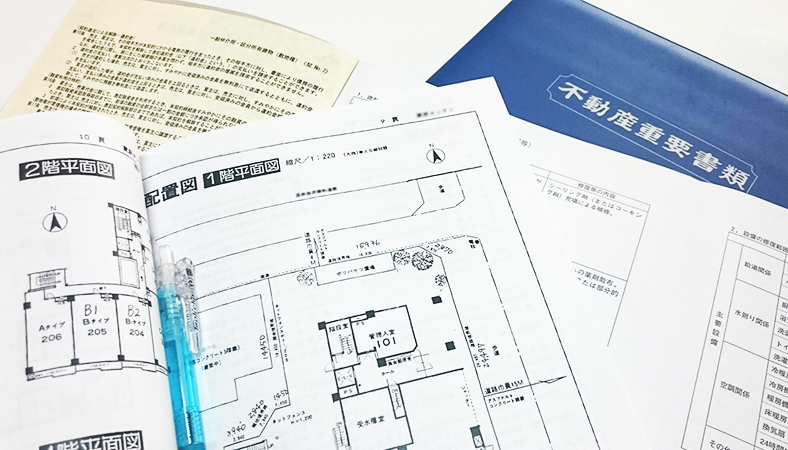懲戒解雇でも解雇予告手当は必要?支給の原則・不支給の例外・除外認定の手続きまで解説

労働者を解雇する企業は、30日前に予告するのが原則ですが、懲戒解雇の場合は即時解雇とするのが珍しくありません。そのようなケースでは、企業に解雇予告手当を支払う義務が生じる可能性があります。
当記事では、懲戒解雇における解雇予告手当の支払義務について、原則や例外的に不支給とできるケース、除外認定を受けるための手続き方法などを紹介します。
1. 懲戒解雇でも解雇予告手当は必要?原則と例外を理解する
労働者を解雇しようとする場合、30日前に予告するか、解雇予告手当を支給するのが原則であり、懲戒解雇の場合も同様です。しかし、懲戒解雇となる理由によっては例外的に手当の不支給が認められることもあります。
ここでは、解雇予告手当の支給について、原則と例外となるケースを紹介します。
懲戒解雇の場合も解雇予告手当が必要な理由(労働基準法20条)
結論からいえば懲戒解雇の場合も解雇予告手当は必要です。使用者が労働者を解雇しようとするとき、30日前に予告することを義務付ける労働基準法20条の規定は、懲戒解雇の場合も例外ではありません。
しかし、実際には懲戒解雇を30日前に予告することはほとんどないでしょう。そのため、懲戒解雇を言い渡してから実際に解雇するまでの日数と解雇予告で定められた日数(30日)を比較し、不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として労働者に支払う義務が生じます。
なお、解雇予告手当の目的は、労働者が次の仕事を探す間の生活を保障することです。
懲戒解雇の有効性と解雇予告手当の要否は別問題
解雇予告手当の支給が必要になることと、懲戒解雇の有効性には関連がありません。懲戒解雇で解雇予告手当を支払うことになるのは、「30日前に解雇予告する」という労働基準法20条の規定を満たさないことが多いためです。
また、このことは逆にいえば解雇予告手当を払えば懲戒解雇できるという意味ではないことにも注意が必要です。企業には懲戒権が認められているものの、懲戒権の濫用とみなされれば懲戒解雇をはじめとする処分が無効となる可能性があります。
やむなく懲戒解雇を行う場合は、不当解雇とされるのを避けるため、あらかじめ指導や注意など別の処分をする、本人に弁明の機会を与えるなど適切な手続きを経ることが大切です。
「労働者の責に帰すべき事由」があれば不支給にできる例外
懲戒解雇の場合でも解雇予告手当を支払うのが原則である一方、労働基準法20条では例外として「労働者の責に帰すべき事由」があれば不支給とすることも可能と定めています。過去の判例などによると、横領や窃盗、傷害などの刑法犯に該当する行為が「労働者の責に帰すべき事由」に該当すると考えられています。
懲戒解雇にする理由は企業によってさまざまです。勤務態度不良やハラスメント行為など、犯罪行為をしていなくても懲戒解雇されるケースはあります。
そのため、懲戒解雇になったからといって解雇予告手当を支給しないのは不適切です。なお、即時解雇かつ解雇予告手当不支給とするためには、所轄の労働基準監督署長の解雇予告除外認定が必要です。
2. 解雇予告手当の計算方法と支払いタイミング
懲戒解雇が理由であっても、解雇予告手当の計算方法や支払時期は通常と同様です。ここでは手当の計算方法と支払いタイミングを紹介します。
解雇予告手当の計算式:平均賃金×不足日数
解雇予告手当の額は以下の計算式で求められます。
平均賃金は2つの計算方法があるため、間違いのないよう注意が必要です。また、不足日数とは解雇予告から解雇日までの期間で30日に足りない日数のことです。解雇を申し渡した日から解雇日まで5日しかなかった場合、25日分が支給対象となります。
平均賃金の正しい計算方法と最低保障額
平均賃金とは、過去3ヶ月間に支払われた給与額の平均金額のことです。給与額には、所得税や社会保険料を含めますが、賞与や一時的な手当は含みません。
計算方法1|過去3ヶ月の給与額合計 / 過去3ヶ月の暦日数
計算方法2|過去3ヶ月の給与額合計 / 過去3ヶ月の労働日数 × 0.6
なお、計算方法2で求められる金額を最低保障額と呼びます。平均賃金を求める際は、計算方法1を用いるのが原則です。ただし、最低保障額を下回る場合は、計算方法2で出た結果を平均賃金として採用します。
解雇予告手当の支払時期と源泉徴収の処理
解雇予告手当の支払時期は解雇予告のタイミングによって異なります。
| ケース | 支払時期 |
|---|---|
| 解雇予告から解雇日まで30日以上 | 解雇日まで |
| 解雇予告から解雇日まで30日以内 | 遅くとも解雇日まで |
| 即時解雇 | 解雇と同時 |
なお、退職所得に該当する解雇予告手当は、企業に所得税の源泉徴収の義務があります。労働者から「退職所得の受給に関する申告書」を受け取っている場合は、課税退職所得金額や勤続年数に応じて処理しましょう。勤続年数や退職金の額によっては、源泉徴収が必要ない場合もあります。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、解雇予告手当に税率20.42%をかけた金額を源泉徴収します。
3. 解雇予告除外認定の手続きと認定基準
一定の条件を満たす場合には、解雇予告手当を支払わずに即時解雇することが可能になります。ここでは、解雇予告除外認定を受けるために必要な手続きと認定基準について解説します。
解雇予告除外認定とは?制度の概要とメリット
解雇予告除外認定とは、解雇予告なしで解雇することを労働基準監督署長から認定してもらう制度です。あらかじめ解雇予告除外認定を受けておくことで、解雇予告せずに労働者を即時解雇することが可能になります。懲戒解雇のほか、災害などのやむを得ない事情で労働者を解雇する際に利用される制度です。
解雇予告除外認定を利用するメリットは、即時解雇の場合でも解雇予告手当の支給が不要になることです。ただし、制度を利用するには所定の手続きが必要なうえ、認定を受けられないケースもあります。
認定が受けられる具体的な基準と該当事例
解雇予告除外認定が受けられるのは、労働者を解雇する理由が以下の2つのどちらかに該当する場合に限られます。
・天災事変などのやむを得ない事由のために事業の継続が不可能である
・労働者の責に帰すべき事由がある
厚生労働省の通達では、上記に該当するものとして以下のような事例を紹介しています。
・震災により建物や工場が倒壊した
・事業主の故意ではない事情で、事業場が火事により失われた
・事業場内における窃盗や横領、傷害などの行為(極めて軽微なものを除く)
・雇用時の経歴詐称
・正当な理由のない無断欠席が2週間以上続き、出社の督促にも応じない
除外認定申請の具体的な手順と必要書類
除外認定を申請する手順は以下の通りです。
・認定申請書を労働基準監督署長へ提出する
・会社と労働者の両方に対して聞き取り調査の実施
・労働基準監督署長から認定書または不認定書の交付
解雇しようとする労働者が支社や出張所などに所属している場合は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に認定申請書を提出しましょう。
また、公平な判断のため除外認定の審査過程では、書類審査だけでなく必ず労使双方への聞き取り調査が行われます。ただし、懲戒解雇の場合は「労働者の責に帰すべき事由」を証明する資料を併せて提出することで、よりスムーズな審査が行われると期待できます。
除外認定の審査期間と不認定になるケース
解雇予告除外認定の認定書もしくは、不認定書が交付されるまでには、2週間から1ヶ月程度かかります。
なお、除外認定の審査には、解雇の対象となる従業員への聞き取りなども含まれるため、労働者が協力的でない場合は、審査期間が長くなることがあります。あらかじめ従業員には、調査に協力するよう伝えておくとよいでしょう。
労働者が調査を拒否する場合や、解雇原因となる行為を認めない場合には、不認定の可能性が高くなります。
4. 懲戒解雇時の退職金と解雇予告手当の違い・注意点
懲戒解雇の場合、解雇予告手当とは別に退職金を支払うか迷う企業もあるでしょう。ここでは、懲戒解雇時の退職金の取り扱いや不支給とする際の注意点などについて紹介します。
退職金の不支給・減額と解雇予告手当は別の手続き
就業規則において、懲戒解雇した労働者に対して退職金のすべてまたは一部を不支給とすると定めている企業は多いでしょう。しかし、退職金には賃金の後払いなどの意味もあるため、懲戒解雇の理由によっては不支給または減額の措置が認められないことがあります。
また、退職金の不支給・減額は解雇予告手当とは別の手続きが必要です。解雇予告除外認定を受けている場合でも、退職金の支給が求められるケースもあるため注意しましょう。
懲戒解雇時の退職金不支給が認められる条件
懲戒解雇において退職金不支給が認められる条件は以下の2つです。
・対象の労働者による著しい背信行為があった
・就業規則または退職金規程に退職金不支給事由がある
退職金を不支給とできるのは、勤続中の功労を帳消しにするほどの背信行為があったときに限られます。たとえば、横領や刑法上の犯罪行為などがあった労働者に対しては、退職金不支給が認められる可能性が高いでしょう。
なお、著しい背信行為があった場合でも、就業規則や退職金規定に不支給事由が定められていなければ退職金を支払う必要があります。
解雇予告手当の不支給が違法になるリスクと罰則
すでに解説したように、懲戒解雇の場合でも解雇予告手当を支給するのが原則であり、不支給とするには、解雇予告除外認定が必要です。解雇された労働者の訴えにより、除外認定を受けずに即時解雇して解雇予告手当を支給しなかったことが認められると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。罰則が科されることによる企業イメージの低下もリスクです。
さらに裁判で懲戒権の濫用が認められ、懲戒解雇自体が無効となる可能性があることも解雇予告手当不支給における大きなリスクです。懲戒解雇の無効は、解雇通告後も雇用契約が継続していることを意味するため、遡って賃金を請求されたり職場復帰を求められたりするおそれがあります。
また、不当に解雇されたことに対する慰謝料請求がなされることもあるでしょう。このようなリスクを避けるには、懲戒解雇の場合でも解雇予告手当を支給すること、または解雇前に法律で定められた手続きにしたがって除外認定を受けることが大切です。
まとめ
懲戒解雇であっても、企業は労働者に解雇予告手当を支給するのが原則です。ただし、事前に労働基準監督署長から除外認定を受けている場合は、例外的に解雇予告手当の不支給が認められます。横領や刑法上の犯罪行為などの事情があれば、除外認定を受けられる可能性があるでしょう。
一方、除外認定を受けずに解雇予告手当を不支給とすることには、罰則を受けるリスクもあるため、懲戒解雇の際は正式な手続きを経て進めることが大切です。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
「知らないと危ない」2026年労働基準法改正で何が変わる?企業が今から備えるべきポイント
-
相続税がゼロ・申告不要でも要注意!必要になるお金の手続きについて解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
サナエノミクスとは?アベノミクスとの違いと日本経済への影響を徹底解説
-
高市政権の本当の影響とは?自民・維新連立の政策を解説
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説