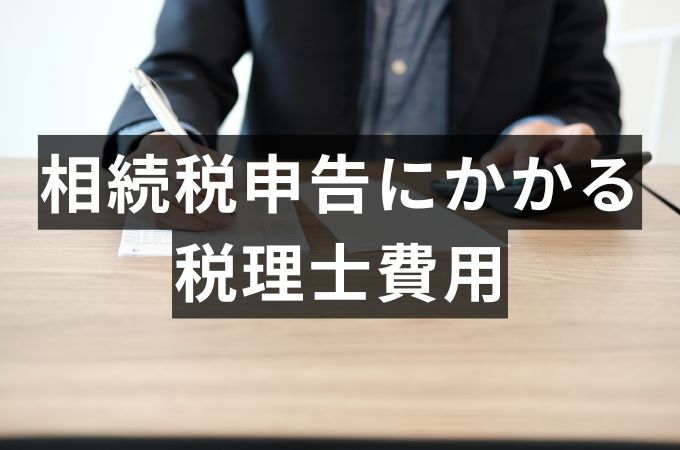相続税申告にかかる税理士報酬の目安
相続税申告を税理士に依頼する際の報酬は、2002年3月までは税理士法によって基準が定められていましたが、規制緩和により撤廃され、現在は各事務所が自由に価格を設定できるようになっています。この自由競争の結果、全体的な報酬水準は以前の基準と比べてやや低めとなっており、透明性のある料金体系を採用する事務所が増えています。
ただし、報酬は相続財産の総額だけでなく、不動産の数や株式評価の有無、相続人の数など、案件の複雑さによって変動します。まずは基本となる報酬相場を理解した上で、追加費用が発生するケースを把握しておくことが重要です。
相続税申告の税理士報酬相場
現在の相続税申告における税理士報酬は、「相続財産の1%」が一般的な目安となっています。例えば、預金2,000万円と不動産5,000万円で総額7,000万円の遺産の場合、報酬の目安は70万円程度となります。多くの税理士事務所はホームページ上で報酬を明示していますが、この1%基準を大きく超える場合は、相場より高いと判断できます。ただし、報酬の高さはサービスの質と必ずしも比例するわけではないため、総合的な判断が必要です。
料金の目安は、大体以下の通りです。
| 相続財産額 | 基本報酬相場 |
|---|---|
| ~5,000万円 | 15~50万円 |
| 5,000~7,000万円 | 25~70万円 |
| 7,000万~1億円 | 35~100万円 |
| 1億~1億5,000万円 | 50~150万円 |
| 1億5,000万~2億円 | 60~200万円 |
| 2~3億円 | 80~250万円 |
| 3~5億円 | 100~300万円 |
| 5億円~ | 要相談 |
追加報酬が発生するケース
基本報酬に加えて、不動産や非上場株式の評価、申告期限までの残り期間、相続人の数などによって追加報酬が発生することがあります。見積もり時に確認しておくことで、後から想定外の費用が発生することを防げます。
不動産関連の追加報酬
相続財産に不動産が含まれる場合、その評価方法によって相続税額が大きく変動する可能性があります。土地の評価は、形状や道路との接し方、用途(自宅か賃貸か)などの要因によって複雑に変化します。特に複数の不動産がある場合や、土地の形状が複雑で評価が難しい場合には、追加の作業が必要となります。また、現地調査が必要な遠隔地の物件がある場合も、追加報酬の対象となることが一般的です。
株式評価による追加報酬
非上場株式の評価は、相続税申告において特に専門性が求められる分野です。評価方法には、会社の純資産を基に算出する「純資産価格方式」、同業種の上場企業との比較による「類似業種比準方式」、配当金額を基準とした「配当還元方式」があります。これらの評価には複雑な計算と専門的な判断が必要となるため、多くの場合、基本報酬とは別に追加報酬が設定されています。
申告期限に関連する追加報酬
相続税の申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内」と定められていますが、この期間は想像以上に短く感じられます。特に申告期限まで残り3ヶ月を切っている場合や、相続人同士の遺産分割協議が難航している場合には、税理士側も特急対応を強いられます。また、必要書類の収集に予想以上の時間がかかるケースも少なくありません。このような緊急対応が必要な場合、通常の報酬に加えて特急料金が発生することがあります。
相続人数による報酬変動
相続人が多い場合、税理士の業務量は自然と増加します。必要書類の作成と確認、相続税の按分計算、相続人間の調整業務など、すべての作業が相続人の数に比例して複雑になります。また、相続人が遠方に居住している場合は、書類のやり取りや説明機会の設定にも追加の時間と労力が必要となります。このため、多くの税理士事務所では相続人の人数に応じた報酬体系を設定しています。
資産規模や相続内容による料金の変動
相続税申告の報酬は、案件の複雑さによって大きく変動します。相続財産の総額はもちろん、その内容(不動産、株式、預貯金など)によっても必要な作業量が変わってきます。特に事業承継が含まれる場合は、通常の相続に比べて専門的な判断や調整が多く必要となります。
また、相続に関する争いがある場合は、相続人間の調整に多くの時間と労力が必要となり、報酬額に影響を与えることがあります。さらに、小規模宅地等の特例など、各種特例の適用を検討する場合も、追加的な検討と確認作業が必要となります。
税理士選びで確認すべきポイント
税理士選びでは、報酬の安さだけでなく、相続税申告の経験値、事務所全体の体制、そして提供されるサービスの質を総合的に判断することが重要です。特に相続税申告の取扱件数や税務調査への対応実績が豊富で、財産調査を徹底して行う税理士を選ぶことで、適正な申告と節税効果が期待できます。
経験豊富な税理士の重要性
相続税申告においては、税理士の経験値が成否を大きく左右します。特に重要なのは以下のような実績です。
- 相続税申告の取扱件数が豊富であること
- 類似した資産規模や事業承継案件の経験があること
- 税務調査への対応実績があること
これらの実績に加えて、税制改正への対応力も重要です。相続税制は頻繁に改正されるため、常に最新の制度を理解し、実務に反映できる税理士を選ぶ必要があります。特に近年は、教育資金贈与の特例など、新しい制度が次々と導入されているため、継続的な学習姿勢を持つ税理士かどうかを確認することが大切です。
税理士事務所の専門分野と相続税対応力
優れた相続税申告のサポートには、事務所全体としての体制が重要です。以下のような特徴を持つ事務所は、相続税申告への対応力が高いと考えられます。
- 相続税専門のチームが存在し、複数の視点でチェックができる
- 不動産鑑定士や弁護士など、外部専門家との連携体制がある
- 過去の相続案件の解決事例を具体的に説明できる
- 定期的な相続税の相談会や勉強会を開催している
特に財産調査においては、徹底した調査姿勢が重要です。不動産の現地調査や金融資産の網羅的な調査など、基本的な作業を省略せずに行う事務所を選ぶべきです。税務調査において問題が指摘されるケースの多くは、初期の財産調査が不十分であることに起因します。
費用対効果を考慮した税理士の選び方
税理士選びで最も重要なのは、報酬の金額だけでなく、提供されるサービスの質です。良い税理士は以下のような特徴を持っています。
- 遺産分割について、税務面からの具体的な提案ができる
- 相続人全員に対して公平かつ丁寧な説明を行う
- 申告期限までのスケジュールを明確に示せる
- 追加報酬が発生する条件を事前に明確に説明する
特に重要なのが税務署対応です。税務調査は相続税申告の約10件に1件の割合で実施され、その多くで追徴課税が発生しています。そのため、税務調査への対応経験が豊富で、適切な説明ができる税理士を選ぶことが、長期的な観点では重要になります。
また、相続に強い税理士の選び方は下記の記事で詳しく説明しています。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 相続税は被相続人の財産状況により算定の難易度にバラつきがある税法です。大地主や富裕層で所有する不動産の数が多い・資産管理会社など自身がオーナーである非上場株式があるといった場合には財産評価が複雑になるので経験豊富な税理士に依頼するのが良いでしょう。
逆にそういった財産がない場合は、どの税理士が計算しても同じ結果になるので料金比較をして依頼先を選択するという方法で良いと考えます。ただし、相場を逸脱したような価格設定には品質の面で注意が必要です。
なぜなら読者の皆様の相続税申告を「誰が担当するか」が非常に重要だからです。極端な低価格サービスを前提とした場合、税理士資格を有する者(所長を含む)や優秀な職員を担当させることができません。誰でも同じ結果になるとは言いましたが、間違えてしまうケースが出てくるかもしれません。 - 徳永税理士事務所
所長 徳永 圭
税理士費用は誰が負担する?
相続税申告の税理士報酬は、法律上は誰が負担しても構いません。ただし、配偶者控除が使える場合は配偶者が負担することで二次相続を見据えた節税効果が期待できます。相続人が親子関係でない場合は、相続割合に応じて按分するのが公平です。なお、税理士報酬は債務控除の対象外となります。
税理士報酬は誰が負担してもよい
相続税申告の税理士報酬は、誰が負担しても構いません。「特定の誰かが必ず負担しなくてはいけない」などのルールは特にないためです。
一般的には、相続人全員が協議のうえで費用を分担することが多いですが、特定の相続人が全額負担することも可能です。この場合、負担する人や割合は、遺産分割協議の中で決定します。
ただし、相続人の関係性や相続税の負担状況によって、より有利な負担方法があります。以下で具体的なケースを見ていきましょう。
相続人が親子関係にある場合の負担方法
亡くなったのが父で、残された相続人が配偶者(母)と子など、親子関係にある場合は、税理士費用は配偶者が負担するのがおすすめです。
配偶者には「配偶者控除」があるため、相続税の負担が少ないケースが多いためです。配偶者控除とは、配偶者に対する相続税額の軽減のことで、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い方まで相続税がかかりません。
つまり、配偶者に多めに相続することで配偶者の相続税負担が少なくなり、税理士費用を負担しやすくなります。
また、二次相続という観点からも有効です。父の財産を相続した配偶者(母)が亡くなる際、その財産は子が相続します。配偶者(母)が税理士費用を負担し相続財産を減らしておくことで、子の相続税負担を減らすという狙いもあります。
相続人が親子関係でない場合の負担方法
相続人が親子関係でない場合、配偶者控除の特例による税額の軽減はできませんし、二次相続を見越す必要もありません。この場合は、相続する財産の割合に応じて税理士費用を按分するなど、公平に分担する方法がおすすめです。
各相続人の取り分は、被相続人が残した遺言や遺産分割協議に基づいて決定します。どの相続人がどれだけの財産を相続するかが決定したあとに、税理士費用の負担についても話し合うのがよいでしょう。
なお、遺産分割でもめそうな場合には、争いになってしまう前に専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
税理士報酬は債務控除の対象外
相続税の計算では、被相続人(故人)が残した借金などの債務や葬儀費用を遺産の総額から差し引くことができます。これにより相続税の計算の基となる遺産が減り、相続税額が減少します。これを「債務控除」といいます。
しかし、税理士報酬は債務控除の対象外となります。債務控除として遺産総額から差し引けるものは相続税法(相続税法基本通達)で定められており、税理士報酬はその中に含まれていません。
葬儀費用は相続開始時点で発生が確定している費用として控除できますが、相続税申告にかかる税理士報酬は相続開始後に相続人が選択して発生させる費用であるため、控除の対象とはならないのです。この点は誤解されやすいポイントですので注意が必要です。
支払いのタイミングと実務上の対応
税理士報酬の支払いタイミングは、事務所によって異なりますが、一般的には以下のようなケースがあります。
- 着手金として一部を契約時に支払い、残りを申告完了時に支払う
- 申告書提出時に全額を支払う
- 段階的に中間金と最終金に分けて支払う
相続人が複数いる場合、支払い窓口を一本化すると手続きがスムーズです。代表相続人が一旦立て替えて税理士に支払い、後日、遺産分割協議の中で精算する方法が実務上は多く採用されています。
ただし、相続人間で費用負担について意見が分かれる可能性もあるため、税理士への依頼前に「誰がどのように負担するか」を明確にしておくことが、円滑な相続手続きの第一歩となります。
税理士報酬を抑える方法
税理士報酬を抑えるには、複数の事務所から相見積もりを取り、料金体系や業務範囲を比較することが有効です。ただし、報酬の安さだけで判断するのではなく、提供されるサービスの質とのバランスを見極めることが重要です。適切な評価方法による節税効果を考えると、多少報酬が高くても専門性の高い税理士を選ぶ方が結果的に有利になることもあります。
相見積もりの活用と注意点
相見積もりは報酬額の相場を把握する有効な手段ですが、単純な価格比較だけでは不十分です。初回相談時には以下のポイントを必ず確認しましょう。
- 基本報酬に含まれる具体的な業務範囲
- 想定される追加報酬の内容と金額
- 相続財産の評価方法と節税提案の具体的な内容
- 税務調査対応の費用の取り扱い
特に重要なのは、見積もり時に相続財産の概要を正確に伝えることです。後から相続財産が追加で見つかった場合や、当初の想定以上に複雑な案件だと判明した場合には、見積額が大きく変動する可能性があります。
相談時に確認すべき料金の内訳
適正な報酬額を見極めるためには、料金体系を詳細に理解する必要があります。多くの税理士事務所では、基本報酬に加えて、着手金や中間金が設定されています。これらの支払いタイミングと金額を事前に確認し、資金計画を立てることが重要です。
また、税務調査対応の費用については、特に注意が必要です。基本報酬に含まれている場合もあれば、別途費用が発生する場合もあります。調査対応の範囲と費用について、契約前に明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
適切な業務内容と報酬の見極め方
適正な報酬を判断するためには、提供されるサービスの質を総合的に評価する必要があります。例えば、相続財産の評価方法一つをとっても、より有利な評価方法を提案できる税理士と、単純な評価しかできない税理士では、節税効果に大きな差が生じます。
以下のような項目について、具体的な対応方針を確認しましょう。
- 相続財産の評価方法と節税方針
- 相続人間の調整に関するサポート範囲
- 申告書作成から提出までの作業工程
- 申告後のフォローアップ体制
重要なのは、報酬の安さだけで判断せず、提供されるサービスの質と報酬のバランスを見極めることです。場合によっては、多少報酬が高くても、より専門性の高い税理士を選ぶことで、最終的な相続税額を大きく抑えられることもあります。
相続税申告の準備と税理士の役割
相続税申告では、税理士が相続財産の洗い出しから評価、申告書の作成・提出まで一貫してサポートします。特に不動産や非上場株式などの複雑な評価や、各種特例の適用検討において専門知識が必要となります。10ヶ月という申告期限内に効率的に作業を進めるため、税理士は全体のスケジュール管理も行います。
相続財産の洗い出しと書類の整備
相続税申告の第一歩は、相続財産の正確な把握です。税理士は、この重要な段階で専門的な知見を活かしたサポートを提供します。相続財産調査では以下のような項目を詳細に確認していきます。
- 預貯金や有価証券などの金融資産
- 不動産(土地・建物)の所在と状況
- 生命保険金や退職金
- 貴金属や骨董品などの動産
- 債務や葬儀費用などの控除対象
特に重要なのが不動産の評価です。土地の評価には路線価の確認や各種補正の検討が必要で、建物については構造や築年数など様々な要素を考慮する必要があります。税理士は、これらの評価を正確に行い、適切な評価方法の選択をサポートします。
必要な手続きと税理士が行う作業
相続税申告の過程で、税理士は多岐にわたる重要な業務を担当します。まず財産の評価計算から始まり、相続人の特定、相続割合の確認、そして申告書類の作成へと進みます。特に重要なのが、相続人それぞれの状況を考慮した上での最適な分割方法の提案です。
また、各種特例の適用可能性についても詳細な検討を行います。例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、適用要件を満たすことで大きな節税効果が期待できる制度について、丁寧な説明と提案を行います。
税務署への申告までの流れ
相続税申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に完了させる必要があります。この期限内に効率的に作業を進めるため、税理士は以下のような流れで申告準備を進めていきます。
まず、相続開始直後に全体的なスケジュールを立案します。その後、相続財産の調査・評価、分割方法の検討、申告書の作成という順で作業を進めていきます。特に重要なのが、分割協議です。相続人全員の合意を得られるよう、税理士は専門家の立場から適切なアドバイスを提供します。
申告書の作成段階では、以下の点に特に注意を払います。
- 財産の評価額の正確性
- 各種特例の適用要件の充足
- 必要書類の網羅性
- 計算の正確性
- 申告期限の遵守
また、納税資金の準備についても、申告期限に間に合うよう、早めの計画立案をサポートします。
相続税申告をスムーズに行うためのポイント
相続税申告を円滑に進めるには、税理士との適切なコミュニケーション、相続人間での情報共有、そして計画的なスケジュール管理が重要です。特に複数の相続人がいる場合は、窓口を一本化し、重要な局面で密に連絡を取り合うことで、期限内に確実に申告を完了させることができます。
税理士とのコミュニケーションのコツ
効率的な相続税申告のためには、税理士との適切なコミュニケーションが不可欠です。信頼関係を築きながら進めることで、より良い申告が可能になります。
まず、相続に関する情報は可能な限り早期に共有することが重要です。被相続人の財産状況や相続人間の関係性など、気になる点があれば率直に相談しましょう。特に複数の相続人がいる場合は、主たる窓口となる相続人を決めておくことで、情報の伝達漏れを防ぎ、スムーズな進行が可能になります。
定期的な進捗確認も欠かせません。特に以下のような重要な局面では、税理士との密な連絡が必要です。
- 相続財産の評価額が確定した時点
- 分割方法の検討段階
- 各種特例の適用を検討する際
- 申告書の最終確認時
相続人間での情報共有と連携
相続税申告を円滑に進めるためには、相続人全員の協力が必要不可欠です。特に複数の相続人がいる場合、情報共有と合意形成が重要になります。
まず、相続財産に関する情報は、できるだけ早い段階で相続人全員で共有しましょう。特に被相続人の生前の資産移動や、負債の存在などについては、後から判明すると申告内容に大きな影響を与える可能性があります。
分割方法の検討では、以下のような点について、相続人間で十分な話し合いが必要です。
- 各相続人の希望する相続財産
- 事業用資産の承継方法
- 不動産の共有や単独所有の選択
- 納税資金の準備方法
相続税申告のスケジュール管理
10ヶ月という申告期限を効率的に使うため、計画的な準備が重要です。税理士と相談しながら、以下のような段階的なスケジューリングを行いましょう。
申告開始直後(1~2ヶ月目)
- 相続人の確定と基本情報の収集
- 相続財産の概要把握
- 必要書類の洗い出し
中間期(3~7ヶ月目)
- 相続財産の詳細な調査と評価
- 分割方法の検討と協議
- 特例適用の検討
申告直前期(8~10ヶ月目)
- 分割協議書の作成
- 申告書の作成と確認
- 納税資金の最終確認

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- (法的に有効な)遺言書がある場合を除き、円滑な相続には相続人同士の合意が欠かせません。つまり「遺産分割協議がまとまるか」がカギとなるわけです。よって、できれば生前から十分な準備をしたいところです。
早期合意を実現するため、分割しにくい(揉めそうな)不動産があれば売却し、他の資産に入れ替えることを検討しましょう。共有名義という選択もありますが私は推奨しません。今後の資産活用に全員の同意が必要となり話がまとまりにくいからです。
また、事業承継がある場合には誰に引き継ぐかを明確にし、後継者に株式を相続させなければ経営上支障がでることもあります。
上記に該当する方は専門家とよく相談しながら事前準備しておくことをオススメします。 - 徳永税理士事務所
所長 徳永 圭
まとめ
相続税申告における税理士の選択は、申告手続きの成否を左右する重要な決定です。報酬の相場を理解した上で、経験や専門性、コミュニケーション能力などを総合的に判断し、信頼できる税理士を選ぶことが大切です。
特に重要なのは、単に報酬の安さだけで判断せず、提供されるサービスの質を十分に見極めることです。適切な税理士選びは、相続税の節税はもちろん、スムーズな相続手続きの完了にもつながります。
ご自身の相続案件に合った税理士をお探しの場合は、相続財産センターにご相談ください。経験豊富な税理士コーディネーターが、お客様の状況やご要望を丁寧にお伺いした上で、最適な税理士をご紹介いたします。
[おすすめ動画]3分でサクッとわかる!相続税申告と税理士
相続税申告でお願いする税理士の先生はどんな基準で選べばいい?|3分でわかる!税金チャンネル
相続税申告の税理士報酬の目安ってどのくらい?|3分でわかる!税金チャンネル
ビスカス公式YouTubeチャンネルのご案内
ビスカス公式YouTubeチャンネル「3分でわかる!税金チャンネル」では、お金に関する疑問を分かりやすく簡単に紹介中!
チャンネル登録はこちら:3分でわかる!税金チャンネル