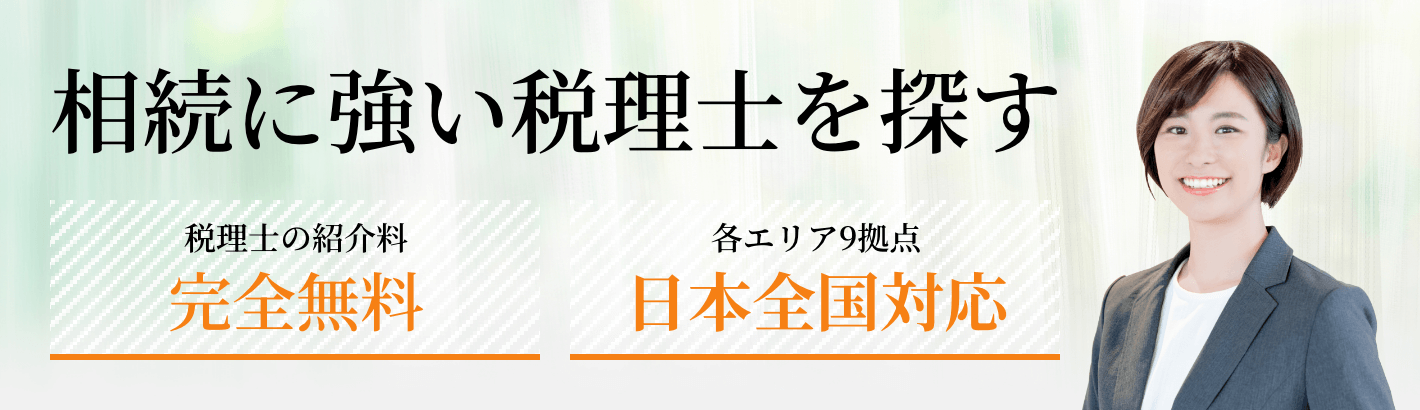生前贈与とは何か?
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を他人に無償で譲り渡す行為です。相続税の課税対象となる財産を生前に減らすことで、相続税の負担を軽減する効果があります。ただし贈与税の仕組みを正しく理解しないと、かえって税負担が増えるリスクもあるため、計画的な実行が求められます。
生前贈与の基礎知識
生前贈与は親から子へ、祖父母から孫へといった形で行われるのが一般的で、主に相続税対策、早期の財産移転、資産管理の効率化を目的として活用されます。
贈与を行うと、原則として受贈者(財産をもらう側)に贈与税が課税されます。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つの課税方式があり、どちらを選択するかで税負担や相続時の扱いが大きく変わります。暦年課税では年間110万円までの基礎控除があり、この範囲内の贈与であれば贈与税はかかりません。一方、相続時精算課税制度では2,500万円までの特別控除がありますが、贈与財産は将来の相続時に加算されます。
生前贈与の主な目的は以下の3つです。第一に、相続税の課税対象となる財産総額を減少させることで相続税負担を軽減できます。第二に、子育てや住宅購入など資金需要の高い時期に財産を移転することで、受贈者が早期に財産を活用できるようになります。第三に、分散された財産を適切に管理し、家族間での資産分配を円滑に進めることができます。
生前贈与と相続の違い
生前贈与は贈与者が生きている間に財産を移転するのに対し、相続は贈与者の死亡後に財産が移転します。この違いにより、税負担や手続きの面で大きな差が生じます。
相続税の基本的な仕組み
相続税は被相続人(亡くなった方)の財産を相続した際に発生する税金で、相続財産の総額から基礎控除を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算され、相続財産がこの金額を超える場合に相続税が発生します。
法定相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円となります。相続財産が1億円あれば、4,800万円を超える5,200万円に対して相続税が課税されます。相続税の税率は累進課税方式で、10%から最高55%まで段階的に上がります。課税遺産総額が1,000万円以下なら10%、3,000万円以下なら15%、5,000万円以下なら20%と、財産が多いほど税率が高くなる仕組みです。
生前贈与が相続税対策として有効な理由
生前贈与が相続税対策として有効なのは、課税対象となる相続財産を事前に減らせるからです。たとえば暦年課税で毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、1,100万円を相続財産から確実に減らすことができます。この1,100万円には贈与税も相続税もかからず、純粋に財産を移転できます。
複数の子供や孫がいる場合、節税効果はさらに高まります。3人の子供にそれぞれ年間110万円ずつ贈与すれば、年間330万円、10年で3,300万円の財産移転が可能です。相続財産を3,300万円減らすことで、相続税の税率区分が下がったり、基礎控除内に収まったりする可能性があります。
ただし相続時精算課税制度を選択した場合、贈与時は2,500万円まで贈与税が非課税となりますが、この贈与財産は相続時に加算されて相続税の計算対象となるため、相続税の節税効果はありません。むしろ贈与税の負担を先送りする制度と考えるべきです。
生前贈与のその他の利点
生前贈与には贈与者の意思に基づいて自由に財産を分配できるという利点もあります。相続では法定相続分や遺留分といった法的制約がありますが、生前贈与であれば贈与者の判断で特定の相続人に多く財産を渡すことも可能です。
また、不動産や事業用資産など分割が難しい財産について、生前に計画的な承継を進められます。相続発生後に遺産分割協議で揉めるリスクを回避し、円滑な資産承継を実現できます。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 生前贈与を検討すべき対象となる方は、一般的には基礎控除額を超える財産を保有する方に限られます。まずはご自身の遺産総額(債務も含む)を確認しましょう。もし基礎控除以下になると予測されれば、わざわざ申告を要する大掛かりな贈与に手間を掛ける必要がないからです。※暦年贈与による非課税枠活用や他の相続対策により基礎控除以下となるケースは多々あります。
逆に、明らかに適用される相続税率が高いと予想される方は積極的に活用することをおススメします。贈与の時期、方法、金額などについてはケースバイケースであり顧問税理士とよく相談して進めましょう。一次相続(配偶者あり)の場合は、二次相続も含めて考えることになります。
ただし、生前贈与の難しいところは寿命(未来)は誰にも分らないという点にあります。専門家にとっても不確定要素を含んだ検討となり計画通りに進むとは限りません。 - 徳永税理士事務所
所長 徳永 圭
生前贈与による相続税対策
生前贈与で相続税を軽減するには、「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つの課税方式を正しく使い分けることが重要です。暦年課税は年間110万円までの基礎控除を活用して長期的に財産を移転する方法で、相続時精算課税制度は2,500万円までの大型贈与を一度に行える制度です。それぞれにメリット・デメリットがあり、一度選択すると変更できないため、慎重な判断が求められます。
暦年課税とは?
暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額に対して課税される方式で、年間110万円までの基礎控除が認められています。この基礎控除内の贈与であれば贈与税はかからず、税務署への申告も不要です。
暦年課税の基本的な仕組みと活用例
たとえば、60歳の父親が30歳の子供に対して毎年110万円ずつ10年間贈与を行えば、10年間で1,100万円の資産移転が可能となります。贈与税の負担なく、将来の相続財産も1,100万円減らすことができるため、長期的な節税効果が期待できます。
複数の子供や孫がいる場合、それぞれに年間110万円まで贈与できるため、贈与者が3人の子供に贈与すれば年間330万円、10年で3,300万円の財産移転が可能です。基礎控除を超える贈与を行う場合は、超過分に対して10%から55%の累進税率で贈与税が課税されます。200万円以下なら10%、400万円以下なら15%と段階的に税率が上がります。
定期贈与とみなされるリスクと回避策
ただし、定期贈与とみなされるリスクに注意が必要です。「毎年同じ時期に同じ金額を贈与する」「最初から総額と期間を決めている」といった場合、税務署から「最初から1,100万円を贈与する契約があった」と判断され、初年度に1,100万円の贈与があったとして高額な贈与税が課される可能性があります。
これを避けるには、贈与の都度、贈与契約書を作成する、贈与時期や金額に変化をつける、受贈者自身が財産を管理する(通帳や印鑑を受贈者が保管する)といった対策が有効です。特に贈与契約書は、贈与の都度、日付と金額を記載して双方が署名・押印することで、計画的贈与ではないことを証明できます。
相続開始前7年以内の加算ルール
また、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される点にも注意してください。2024年1月1日以降の贈与から、加算期間が従来の3年から7年に延長されました。ただし延長された4年分(4年目~7年目)については、総額100万円まで相続財産への加算が免除されます。
たとえば、父親が2024年に亡くなった場合、2017年から2023年までの7年間の贈与が相続財産に加算されます。この期間に毎年110万円ずつ贈与していれば、110万円 × 7年 = 770万円が相続財産に加算されることになります。ただし2020年~2023年の4年分については、合計100万円を控除できるため、実際の加算額は670万円となります。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与について選択できる制度で、累計2,500万円までの特別控除が認められています。この特別控除を超える部分には一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度の基本的な仕組み
この制度の最大の特徴は、贈与時の税負担を軽減できる反面、贈与した財産は相続時に相続財産として加算され、相続税の計算対象となる点です。つまり贈与税の節税にはなりますが、相続税の節税効果はありません。むしろ相続税の対象財産を事前に確定させる制度といえます。
たとえば、父親が子供に3,000万円相当の不動産を贈与する場合を考えます。暦年課税であれば(3,000万円 - 110万円)× 50% - 250万円 = 1,195万円の贈与税が課税されます。一方、相続時精算課税制度を選択すれば、2,500万円までは贈与税が非課税となり、超過分500万円に対してのみ20%の贈与税100万円が課税されます。贈与時の税負担は大幅に軽減されますが、この3,000万円は父親の相続時に相続財産として加算されます。
2024年1月1日以降の贈与からは、相続時精算課税制度を選択していても年間110万円までの基礎控除が新設されました。この基礎控除内の贈与であれば、贈与税の申告が不要となり、相続時の加算対象からも除外されます。これにより相続時精算課税制度の使い勝手が向上しました。
相続時精算課税制度が有効なケース
相続時精算課税制度が有効なケースとしては、将来値上がりが見込まれる財産の贈与があります。不動産や株式など、贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、贈与後に価値が上昇しても相続税額は変わりません。たとえば贈与時に2,000万円だった不動産が相続時に5,000万円になっていても、相続税の計算では2,000万円として扱われます。
また、収益不動産を贈与すれば、贈与後の賃料収入は受贈者のものとなり、贈与者の財産増加を抑えられます。月額30万円の賃料収入がある不動産を贈与すれば、年間360万円の財産増加を防げます。10年間で3,600万円の相続財産圧縮効果が期待できます。
相続時精算課税制度の注意点
ただし、一度この制度を選択するとその贈与者からの贈与について暦年課税には戻れません。父親からの贈与について相続時精算課税を選択した場合、以後の父親からの贈与はすべて相続時精算課税が適用されます。母親や祖父母からの贈与については、別途選択できます。
また、贈与財産は相続時まで記録を保管する必要があり、贈与者が亡くなるまでの期間が長い場合、管理の手間が生じます。贈与時の評価額を証明する書類(不動産の評価証明書、株式の取引明細など)は相続時まで保管してください。選択は税理士に相談しながら慎重に行ってください。
直系卑属への贈与税非課税制度の活用
親や祖父母から子・孫への贈与には、特定の目的に応じた贈与税の非課税制度が用意されています。教育資金は最大1,500万円、住宅取得資金は最大1,000万円、結婚・子育て資金は最大1,000万円まで非課税で贈与できます。これらの特例は金融機関を通じた専用口座での管理が必要で、用途が制限される反面、まとまった金額を非課税で贈与できる利点があります。
教育資金贈与の特例
教育資金贈与の特例は、30歳未満の子・孫の教育資金として、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。学校等以外(学習塾や習い事など)に支払う費用は500万円が上限となります。
この特例を利用するには、金融機関で教育資金管理契約を締結し、専用口座を開設する必要があります。贈与者は金融機関に資金を一括で預け入れ、受贈者が教育資金として支払った際に、領収書などを金融機関に提出して払い出しを受ける仕組みです。対象となる教育資金は、入学金・授業料・教材費といった学校等に直接支払うもののほか、学習塾・習い事の月謝、通学定期代、留学渡航費なども含まれます。
受贈者が30歳に達した時点で口座に残額がある場合は贈与税が課税されます。ただし、30歳時点で学校等に在学している場合や教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている場合は、最長40歳まで非課税措置が延長されます。また、贈与者が死亡した時点で口座に残額がある場合、その残額は相続財産として相続税の課税対象となります。この特例は2026年3月31日までの期間限定措置です。
住宅取得資金贈与の特例
住宅取得資金贈与の特例は、18歳以上の子・孫が住宅を新築・取得・増改築する際の資金として、最大1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅は500万円が上限となります。
この特例の適用を受けるには、受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)であることが求められます。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、同日までに居住を開始する(または確実に居住すると見込まれる)ことが必要です。
対象となる住宅は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であることが条件となります。この特例は暦年課税や相続時精算課税制度と併用でき、2026年12月31日までの期間限定措置です。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、18歳以上50歳未満の子・孫の結婚・子育て資金として、最大1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。結婚に際して支出する費用は300万円が上限となります。
この特例を利用するには、金融機関で結婚・子育て資金管理契約を締結し、専用口座を開設する必要があります。対象となる結婚資金は、挙式費用・衣装代等の婚礼費用、新居の住居費・引越費用(結婚の日の1年前から結婚の日以後1年を経過する日までの間に支払われるもの)などです。子育て資金は、不妊治療・妊婦健診費用、分娩費・産後ケア費用、子の医療費、保育料などが含まれます。
受贈者が50歳に達した時点で口座に残額がある場合は贈与税が課税されます。また、贈与者が死亡した時点で口座に残額がある場合、その残額は相続財産として相続税の課税対象となります。この特例は2027年3月31日までの期間限定措置です。
生前贈与のメリットと注意点
生前贈与には相続税の軽減、早期の財産移転、円滑な資産承継といったメリットがある反面、贈与者の老後資金不足リスク、税務上の複雑な制約、一度選択した課税方式の変更不可といった注意点もあります。暦年課税で長期的に財産を移転するか、相続時精算課税制度でまとまった金額を贈与するか、どちらが適しているかは財産状況や年齢によって異なります。メリットを最大化しリスクを最小化するには、計画的な贈与設計と専門家への相談が不可欠です。
生前贈与の3つのメリット
第一のメリットは相続税の負担軽減効果です。暦年課税で毎年110万円ずつ贈与すれば、その金額は相続財産から確実に除外されます。たとえば3人の子供に10年間贈与を続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を相続財産から減らせます。相続財産が8,000万円で基礎控除が4,800万円の場合、課税対象は3,200万円から相続財産を減らせれば、税率区分が下がったり基礎控除内に収まったりする可能性があります。
さらに教育資金贈与の特例(1,500万円まで非課税)や住宅取得資金贈与の特例(最大1,000万円まで非課税)を活用すれば、暦年課税の基礎控除と併用して大型の財産移転も可能です。たとえば孫の住宅取得資金1,000万円と暦年課税110万円を同年に贈与すれば、合計1,110万円を非課税で贈与できます。
第二のメリットは資金需要の高い時期に財産を移転できることです。子育て世代は教育費や住宅購入で多額の資金が必要となりますが、相続を待っていては時期を逃します。30代で住宅を購入する際に1,000万円の贈与を受ければ、住宅ローンの負担を大幅に軽減できます。また、孫の大学進学時に教育資金1,500万円を贈与すれば、4年間の学費と生活費を十分にカバーできます。
第三のメリットは相続時のトラブル防止です。生前に財産分配を済ませることで、相続発生後の遺産分割協議を円滑に進められます。特に不動産や事業用資産など分割が難しい財産については、後継者に生前贈与しておけば事業承継をスムーズに行えます。複数の相続人がいる場合でも、生前に贈与の趣旨を説明し理解を得ておくことで、相続時の争いを防げます。
生前贈与の注意点とリスク
最も重要な注意点は、贈与者の老後資金が不足するリスクです。60歳で3,000万円を子供に贈与したものの、その後の医療費や介護費用で資金が枯渇し、結局子供に経済的負担をかけるケースがあります。平均寿命を考慮すれば、60歳から30年以上の生活費が必要です。月25万円の生活費なら30年で9,000万円必要となるため、贈与は余裕資金の範囲内で行ってください。
税務上の注意点として、一度選択した課税方式は変更できない点があります。父親からの贈与について相続時精算課税制度を選択した場合、以後の父親からの贈与はすべて相続時精算課税が適用され、暦年課税には戻れません。110万円の基礎控除を毎年活用したいと考えても、相続時精算課税を選択してしまうと2024年以降の新設された110万円の基礎控除のみしか使えず、従来の暦年課税の柔軟性は失われます。
また、相続時精算課税制度では2,500万円までの特別控除を超える部分に一律20%の贈与税が課税されます。3,000万円の不動産を贈与すれば、超過分500万円に対して100万円の贈与税が発生します。さらにこの3,000万円は相続時に相続財産として加算されるため、相続税の節税効果はありません。
相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される点にも注意が必要です。2024年1月1日以降の贈与から加算期間が3年から7年に延長されたため、暦年課税で毎年110万円ずつ贈与していても、相続発生前7年分は相続財産に加算されます。10年間贈与を続けた直後に相続が発生すれば、最後の7年分770万円(ただし4年目~7年目の合計から100万円控除)が相続財産に加算されることになります。
受贈者の資産管理能力も考慮すべきポイントです。20代の子供に一度に1,000万円を贈与した場合、浪費してしまったり詐欺被害に遭ったりするリスクがあります。また、贈与後に家族関係が悪化するケースもあります。特定の子供だけに多額の贈与を行った結果、他の兄弟姉妹との関係が悪化し、相続時にトラブルに発展する事例は少なくありません。
リスクを最小化する対策
計画的な贈与設計が最も重要です。まず贈与者の老後資金を確保し、医療費・介護費用の予備費を含めた生活費を試算してください。余裕資金が明確になってから贈与額を決定します。暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かは、贈与者の年齢、財産額、相続までの期間によって異なります。若い世代で相続まで時間がある場合は暦年課税で長期的に贈与し、高齢で財産額が大きい場合は相続時精算課税制度の活用も検討してください。
贈与の記録を確実に残すことも不可欠です。贈与契約書は贈与の都度作成し、贈与者と受贈者の双方が署名・押印したものを最低15年間保管してください。贈与税の申告書控えも同様に保管します。定期贈与とみなされるリスクを避けるため、毎年異なる時期や金額で贈与を行い、受贈者が自分で通帳と印鑑を管理する体制を整えてください。
不動産を贈与する場合は、贈与後すぐに所有権移転登記を行い、固定資産税の納税義務者変更手続きも済ませます。登記を怠ると第三者に対抗できないだけでなく、税務署から贈与の実態がないと判断されるリスクがあります。
これらの対策は税理士に相談しながら進めてください。特に相続時精算課税制度の選択は一度決定すると取り消せないため、将来の相続税額をシミュレーションした上で慎重に判断する必要があります。財産状況、家族構成、贈与の目的に応じた最適な方法を専門家と一緒に検討することで、生前贈与のメリットを最大限に活用できます。
生前贈与の具体的な手続き
生前贈与を確実に実行するには、贈与契約書の作成、贈与税の申告、不動産の場合は登記手続きという3つの手続きが必要です。特に贈与契約書は贈与の事実を証明する最も重要な書類で、定期贈与とみなされるリスクを避けるため贈与の都度作成してください。年間110万円以下の贈与であれば税務署への申告は不要ですが、それを超える場合や特例制度を利用する場合は翌年2月1日から3月15日までに申告が必要です。手続きの誤りは追徴課税や特例の適用不可につながるため、税理士への相談を推奨します。
贈与契約書の作成方法
贈与契約書には、贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与財産の内容、贈与日、双方の署名・押印を必ず記載してください。これらの記載がないと、税務署から贈与の事実を否認されたり、定期贈与とみなされて高額な贈与税が課される可能性があります。
現金贈与の場合、「贈与者○○は、受贈者△△に対し、令和6年12月25日、金110万円を贈与する」といった形で、金額と日付を明確に記載します。不動産贈与の場合は、「所在 東京都○○区○○一丁目、地番 ○○番○、地目 宅地、地積 100.00平方メートル」のように登記簿謄本の記載どおりに物件を特定してください。株式の場合は「○○株式会社の普通株式1,000株」と銘柄と株数を記載します。
贈与の目的を記載する欄は必須ではありませんが、教育資金贈与や住宅取得資金贈与の特例を利用する場合は「子の教育資金として」「住宅取得資金として」と明記しておくと後の手続きがスムーズです。条件付き贈与の場合は「受贈者が大学に入学することを条件として」といった条件も記載します。
契約日は実際に贈与を行う日付と一致させてください。12月25日に贈与契約書を作成したのに振込が1月10日では、契約書の信憑性が疑われます。銀行振込であれば振込日と契約日を同じにする、現金手渡しであれば手渡した日を契約日とします。
訂正がある場合は修正液や修正テープを使わず、二重線で消して訂正印を押してください。贈与者と受贈者の双方が訂正印を押す必要があります。契約書は2通作成し、贈与者と受贈者がそれぞれ1通ずつ保管します。保管期間は最低15年間です。相続時に贈与の事実を証明する必要が生じる場合があるため、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)を経過した後も保管を続けてください。
高額な贈与や不動産贈与の場合は、公証人役場で公正証書にすることを推奨します。公正証書にすれば、公証人が契約内容を確認し、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを防げます。手数料は贈与額によって異なりますが、数千円から数万円程度です。
必要な書類と申告手続き
贈与税の申告が必要なのは、年間110万円を超える贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を初めて選択する場合、住宅取得資金贈与などの特例制度を利用する場合です。申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までで、この期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されます。
申告に必要な書類は贈与の内容によって異なります。現金贈与の場合は贈与契約書の写し、不動産贈与の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)、株式贈与の場合は取引明細書や株式の評価証明書が必要です。相続時精算課税制度を初めて選択する場合は、受贈者の戸籍謄本または抄本、受贈者の戸籍の附票の写しも提出します。
住宅取得資金贈与の特例を利用する場合は、売買契約書または工事請負契約書の写し、登記事項証明書、住宅性能証明書(省エネ等住宅の場合)を添付してください。教育資金贈与の特例や結婚・子育て資金贈与の特例を利用する場合は、金融機関を通じて手続きを行うため、税務署への直接の申告は不要ですが、金融機関から交付される書類は保管しておく必要があります。
提出先は受贈者の住所地を管轄する税務署です。贈与者ではなく受贈者の住所地である点に注意してください。東京都在住の父親から大阪府在住の子供への贈与であれば、大阪府の税務署に申告します。申告書は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成でき、e-Taxを利用すればオンラインで提出可能です。
不動産を贈与した場合は、税務署への申告とは別に法務局での所有権移転登記が必要です。登記申請には贈与契約書、登記原因証明情報、登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、固定資産評価証明書が必要で、登録免許税として不動産の固定資産税評価額の2%を納付します。登記完了後は、市区町村役場で固定資産税の納税義務者変更届を提出してください。
専門家の活用方法
税理士に相談すべきタイミングは、贈与額が500万円を超える場合、不動産や株式など評価が複雑な財産を贈与する場合、相続時精算課税制度の選択を検討している場合です。税理士報酬は贈与額や業務内容によって異なりますが、贈与税の申告のみであれば3万円から10万円程度、贈与の計画立案から含めると10万円から30万円程度が相場です。
税理士は贈与税額のシミュレーション、暦年課税と相続時精算課税制度のどちらが有利かの判断、将来の相続税額を含めた総合的な節税プランの提案を行います。特に相続時精算課税制度は一度選択すると取り消せないため、選択前に必ず税理士の意見を聞いてください。複数の子供や孫への贈与を検討している場合、誰にいくら贈与すれば全体として最も税負担が少なくなるかといった最適化も税理士の専門分野です。
不動産を贈与する場合は司法書士への相談も必要です。司法書士は所有権移転登記の申請を代行し、登記に必要な書類の準備から法務局への申請まで一貫してサポートします。報酬は5万円から10万円程度が相場ですが、登録免許税(評価額の2%)は別途必要です。不動産の評価額が高い場合や共有持分の贈与など権利関係が複雑な場合は、司法書士に依頼することで手続きミスを防げます。
弁護士への相談が必要なのは、遺言書の作成を併せて行う場合、家族間で贈与の方針について意見が対立している場合、相続を見据えた法的なアドバイスが必要な場合です。特に特定の子供に多額の贈与を行う場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないよう弁護士と相談しながら遺言書を作成してください。
専門家選びのポイントは相続税に詳しいかどうかです。贈与税と相続税は密接に関連しているため、相続税の知識が豊富な税理士を選ぶことで、将来の相続も見据えた最適な贈与計画を立てられます。初回相談は無料としている事務所も多いため、複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- お客様との相談時に伺う点は①贈与の対象物②贈与の相手方③贈与の目的です。これらを事前に検討しておけばスムーズに税理士と話を進めることができます。
また、多くの財産を贈与する予定がある方については、その資産配分についても検討することをおススメします。特定の人に偏った贈与を行うと相続時に争いを生む種となりかねないからです。偏った贈与を行わざるを得ない事情があるならば、セットで必ず遺言書の作成も行うべきです。遺留分を考慮した法的に有効な遺言書があれば遺産分割協議を経ることなく被相続人の意思に沿った財産の相続が行われます。
ただ、それでも偏った贈与は兄弟姉妹を不仲にさせる要素となる点だけはお知り置きください。 - 徳永税理士事務所
所長 徳永 圭
生前贈与の活用事例
生前贈与の成功には、制度の正しい理解と適切な手続きが不可欠です。成功事例に共通するのは、贈与契約書の確実な作成、特例制度の要件確認、専門家への相談という3つの要素です。一方、失敗事例では贈与の記録不備や制度要件の確認漏れが原因となっています。以下の事例から、効果的な贈与戦略と避けるべき失敗パターンを学んでください。
相続時精算課税制度の活用事例
60歳以上の親が子供に対して相続時精算課税制度を利用し、2,500万円までの特別控除を活用して生前贈与を行った事例では、贈与税の負担を最小限に抑えることに成功しました。2024年以降は年間110万円の基礎控除も新設されたため、この基礎控除と特別控除を組み合わせることで、より柔軟な贈与計画が可能となりました。
この事例のポイントは、相続時精算課税制度の特性を理解した上で選択した点です。贈与時は贈与税が非課税となりますが、贈与財産は相続時に相続財産として加算されるため、相続税の節税効果はありません。ただし贈与後に財産価値が上昇しても贈与時の評価額で計算されるため、値上がりが見込まれる財産の贈与には有効でした。
教育資金贈与の特例の活用事例
祖父母が孫の教育資金として、教育資金贈与の特例を利用し、1,500万円までの非課税贈与を行った事例では、孫の大学進学に必要な費用に充て、教育費の負担を大幅に軽減しました。金融機関で教育資金管理契約を締結し、専用口座を開設することで、確実に特例の適用を受けられました。
この資金は入学金、授業料、教材費といった学校等への支払いのほか、学習塾や習い事の費用にも充てられました。受贈者が30歳に達するまでに口座残高を使い切ったため、贈与税も相続税も課税されず、家族全体の財産管理が円滑に進みました。
事業承継における活用事例
製造業を営む父親が、後継者である長男に対して、10年かけて計画的に自社株式の贈与を実施した事例では、毎年の基礎控除と事業承継税制を組み合わせることで、円滑な事業承継を実現しました。
暦年課税の基礎控除110万円を活用しながら、少しずつ株式を移転することで、贈与税の負担を最小限に抑えました。同時に事業承継税制の納税猶予を併用することで、後継者への株式集中を進めながら税負担を回避できました。計画的な贈与により、経営権の移転と税務対策の両立に成功しました。
贈与契約書の不備によるトラブル事例
贈与契約書を作成せずに現金を贈与したため、相続時に財産の分配に関するトラブルが発生した事例では、贈与の記録不備が大きな問題となりました。贈与の事実が証明できず、相続税の計算に混乱が生じただけでなく、相続人間での争いにも発展しました。
税務調査の際にも贈与の事実を証明する書類がなかったため、税務署から贈与を否認される可能性が高まりました。この事例から、贈与契約書の作成と適切な記録保管がいかに重要かがわかります。贈与の都度、契約書を作成し、双方が署名・押印した上で最低15年間保管してください。
特例制度の要件未確認による失敗事例
相続時精算課税制度を利用して贈与を行ったものの、受贈者が制度の条件を満たしていなかったため、特例の適用が受けられなかった事例では、事前の要件確認不足が高額な贈与税負担につながりました。
相続時精算課税制度は60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与に限定されています。この要件を満たさない贈与に対して制度を適用しようとしたため、税務署から否認され、暦年課税での高額な贈与税が課税されました。特例制度を利用する際は、必ず事前に適用要件を確認し、不明点があれば税理士に相談してください。
効果的な贈与のポイント
成功事例と失敗事例から導き出される効果的な戦略は以下のとおりです。
第一に、贈与の記録を確実に残すことです。贈与契約書は毎年作成し、贈与者と受贈者の双方が署名・押印してください。契約書には贈与日、贈与財産の内容、金額を明記し、定期贈与とみなされないよう前年の贈与には言及しないでください。
第二に、特例制度の要件を事前に確認することです。住宅取得資金贈与の特例、教育資金贈与の特例、結婚・子育て資金贈与の特例には、それぞれ受贈者の年齢、所得要件、使途の制限などがあります。適用を受ける前に国税庁のホームページで要件を確認するか、税理士に相談してください。
第三に、家族間でのコミュニケーションを十分に取ることです。特定の子供に多額の贈与を行う場合、他の相続人の理解を得ておかないと相続時にトラブルが発生します。贈与の目的や理由を説明し、必要に応じて遺言書を作成することで、将来の争いを防げます。
複雑な贈与や高額な贈与を行う場合は、税理士や弁護士といった専門家に相談することをお勧めします。贈与税と相続税は密接に関連しているため、将来の相続も見据えた総合的な対策が必要です。
まとめ
生前贈与は、相続税の節税や資産の早期移転を目的とした有効な手段です。 特に「相続時精算課税制度」や「年間110万円の新非課税枠」を活用することで、効率的な資産移転が可能となります。しかし、贈与には贈与税の負担や家族間のトラブルなどのリスクも伴います。そのため、計画的かつ慎重に進めることが求められます。専門家の助言を受けながら、適切な贈与計画を立てることが重要です。
まずは自身の財産状況を確認し、年間110万円の基礎控除の活用から始めることをお勧めします。より具体的な節税プランについては、税理士に相談することで、ご自身の状況に合わせた最適な方法を見つけることができます。生前贈与を活用した効果的な資産移転で、大切な財産を次世代に円滑に引き継いでいきましょう。
よくある質問(FAQ)
生前贈与の非課税枠はいくら?
生前贈与には、年間110万円の基礎控除と、相続時精算課税制度を利用することで累計2,500万円までの特別控除があります。年間110万円以下の贈与は贈与税がかからず、相続時精算課税制度を選択することで、それを超える贈与財産が累計2,500万円まで非課税となります。
贈与税の申告期限は?
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。贈与を受けた翌年の確定申告期間内に、所定の申告書を税務署に提出する必要があります。申告期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される場合がありますので、期限内の申告が重要です。
生前贈与が相続に与える影響は?
生前贈与は、相続時の財産総額を減少させることで、相続税の負担を軽減します。しかし、相続時精算課税制度を利用した場合、累計2,500万円を超える贈与部分に対して贈与税が課されるため、総合的な資産管理が必要です。また、生前贈与を行うことで、家族間の財産分配に関する合意形成が必要となり、適切なコミュニケーションが求められます。
生前贈与を受けた現金や不動産は、すぐに使えるのでしょうか?
贈与を受けた財産は、贈与契約が成立した時点で受贈者の所有となり、原則としてすぐに自由に使うことができます。ただし、不動産の場合は登記手続きが必要です。また、贈与契約に条件が付されている場合は、その条件に従う必要があります。
生前贈与を受けた後に、贈与者が認知症になった場合はどうなりますか?
適切に贈与契約が締結され、贈与が完了している場合はその後贈与者が認知症になっても贈与の効力には影響ありません。ただし、贈与時に既に認知症であった場合は、契約自体が無効となる可能性があるため注意が必要です。