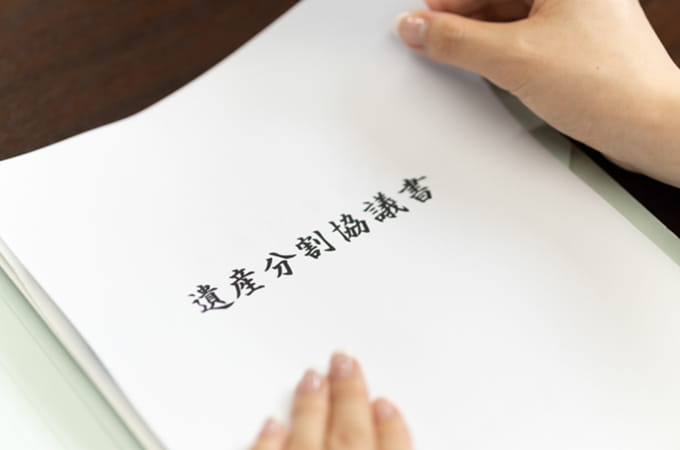遺産分割協議書がないと、預金が引き出せない
遺産分割協議書を作らなければならない大きな理由は、それがないと、不動産の名義変更や銀行口座からの預金の引き出しなどの手続きができないからです。被相続人が遺言書を残していれば、それを添付することでそうした手続きは問題なく実行できるのですが、ない場合には、「すべての相続人が、この分け方で一致しました」という証明が必要になるのです。
この「協議書」を作成するために行われる遺産分割協議には、当然「要件」があります。それを満たさないと、「協議書」自体が無効になってしまうので、注意が必要です。
遺産分割協議には「すべての相続人」の参加が必要
最も気をつけるべきなのは、「協議には相続人全員が参加する必要がある」ということです。相続では、ケースによっては、被相続人の孫、兄弟姉妹、甥や姪が相続人になることがあります。養子や、愛人の子どもにも相続権があります。どんなに疎遠でも、被相続人に勘当を言い渡された息子でも、法が定めた相続人であれば、呼び寄せて協議に加わってもらわなくてはならないわけです。
意図的に排除するのはもちろんNGですが、協議書が出来上がってから、誰も知らなかった相続人がひょっこり現れる、といったこともあり得ない話とはいえません。そんなことにならないために、話し合いを始める前に、被相続人の戸籍を出生から確認して、「相続人は誰なのか」を明確にしておく必要があります。あえて言えば、相続人以外の人間が加わった場合にも、協議自体が無効になってしまいます。「協議に参加すべき人がいなかった」場合にも、「余計な人が混じった」場合でも、遺産分割協議はやり直し、ということになるのです。
なお、相続の権利はあっても、未成年者は協議に加わることができません。その時には、親などが法定代理人として、代わって参加することになります。ただし、その親自身も相続人の場合には、子どもとの間に法的な利益相反(※1)が生じるため、別に特別代理人を立てることが求められます。
また、被相続人の子どもであれば、胎児にも相続の権利があります。正確には、生きて生まれたら、相続の権利を得ます。逆に言えば、死産だったらその権利はなし。それがはっきりするまで、すなわち出産まで遺産分割協議はできません。相続税が発生する場合には、その申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヵ月。協議は、かなり慌ただしいことになるかもしれません。
当事者の一方の利益が、他方の不利益になる状態。この場合は、例えば親が自分の遺産の取り分を増やすために、子どもの取り分が少ない状態で合意する可能性があるため。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 遺産分割協議は相続の様々な手続きの中でも、相続人間の感情が入り乱れやすく揉めやすいです。「なるべく話がしやすい人だけ呼ぼう」という感情は分かりますが、それでは無効となってしまいます。
- 河鍋公認会計士・税理士事務所
代表 河鍋 優寛
(税理士・公認会計士)
遺産分割協議書は作り直せるのか?
このほか、判断に迷うケースについてまとめました。
遺言書の中身が曖昧で、分け方がよくわからない
そのような場合には、やはり遺産分割協議が必要になるでしょう。遺言書に記載されていない財産があったときにも、その部分について協議しなくてはなりません。
そもそも、相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる遺産分割を行うことも可能です。例えば、長男は現金が欲しい、次男は不動産がもらいたかったのだけれど、父の遺言書には逆のことが書かれていた。そんなときには、子ども同士が話し合って、それぞれが望む通りの遺産分割協議書を作成することが許されるわけです。
遺産分割協議はやり直せるか?
いったん遺産分割が終わった後でも、相続人全員の合意があれば、遺産の分け方を変える、すなわち遺産分割協議をやり直す=遺産分割協議書を作り直すことは可能です。不動産の名義変更などについても、修正することができるのです。
ただし、税金は基本的に「やり直し」が認められませんから、要注意です。例えば、1回目の遺産分割で長男が取得した財産に関しては、税法上、長男がその所有権を持ったと解されます。遺産分割協議をやり直して、それを次男に渡した場合には、新たな財産の贈与、譲渡(※2)とみなされて、前者なら次男が贈与税、後者ならば長男が所得税を支払わなくてはならないのです。財産が不動産ならば、不動産取得税や名義変更登記の際の登録免許税も発生することになります。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 遺産分割協議のやり直しは「贈与」もしくは「譲渡」としてみなされるという税務リスクが高い行為です。1度合意した後はやり直さない方が良いことは間違いありません。
- 河鍋公認会計士・税理士事務所
代表 河鍋 優寛
(税理士・公認会計士)
協議が終わってから、新たな財産が見つかったら
その時には、元の遺産分割を反古にすることなく、見つかった遺産についてあらためて協議して、分割できることになっています。
ちなみに、さきほど「相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は、やり直し」という話をしました。不幸な状況ではありますが、この場合は協議が最初からなかったのと同じなので、やはりいま説明したような「新しい税」が課税されることは、原則としてありません。
財産を無償で渡すのが「贈与」、何らかの対価を受け取って渡すのが「譲渡」。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 弊事務所を含め、専門家が遺産分割協議書の文案を作成する場合には、新たに判明した財産と債務の相続も遺産分割協議書に織り込みます。そうすることで遺産分割協議を再度行わずに済みます。
- 河鍋公認会計士・税理士事務所
代表 河鍋 優寛
(税理士・公認会計士)
まとめ
遺産分割協議は、相続人が過不足なく参加しなければ無効です。全員の合意で協議をやり直すことは可能ですが、その結果財産を移動すれば、新たに贈与税、所得税などが発生しますから、1回でまとめるのがベター。不安なときは、相続に詳しい税理士などの専門家に相談しましょう。
記事監修者 河鍋税理士からのワンポイントアドバイス
今回は「故人に勘当された子ども」という特殊なケースを例に挙げてご紹介しましたが、上記を含めて相続権があるすべての相続人が遺産分割協議に参加しなければ無効となってしまいます。
遺産分割協議が形式的に無効となってしまわないよう留意ももちろん必要ですが、遺産分割協議の場では誰もがピリピリしていて、関係が悪化してしまうケースも珍しくありません。
そのようなケースが事前に想定される場合は、事前に遺言書を作成して遺しておくことが大切です。適切な遺言書がある場合は相続人全員の合意がない限り、遺言書の内容どおりに分割することになりますので、相続人間の感情が入る要素が幾分か減ります。
「遺言書」や「遺産分割協議書」はどちらも法的な重要書類です。作成の際には専門家の助言を受けることをお勧めいたします。