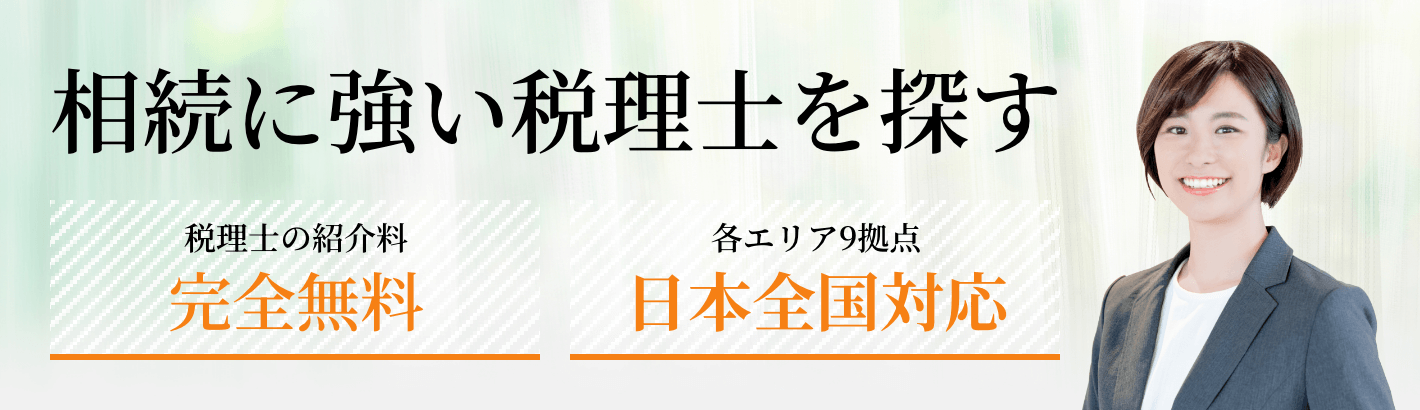相続税対策の基本とは
相続税対策は生前対策と相続発生後対策の2つの視点から検討します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、この金額を超える財産に相続税が課税されます。生前対策は計画的な資産移転で将来の相続税を抑制し、相続発生後の対策は特例や控除を活用して実際の税額を軽減する方法です。
相続税の基礎控除額と節税の目的
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、相続財産がこの金額以下であれば相続税はかかりません。配偶者と子供2人の場合は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)、配偶者と子供1人なら4,200万円となります。法定相続人が増えれば基礎控除額も増加するため、養子縁組による基礎控除の拡大も対策の一つです。
相続税対策の目的は、この基礎控除額を考慮しながら相続人の税負担を適正な範囲で軽減することです。ただし節税だけを追求して老後資金が枯渇したり、名義預金と認定されて贈与が無効になるリスクもあります。税負担の軽減と生活の安定、家族間の円滑な資産承継をバランスよく実現する視点が重要です。
生前対策と相続発生後対策の違い
生前対策は時間をかけて効果を発揮し、相続発生後の対策は申告期限(10ヶ月)内に実行する必要があります。生前対策は暦年贈与や不動産活用など、計画的に資産を移転・活用することで将来の相続税を抑制する方法です。早く始めるほど選択肢が広がり、例えば年110万円の暦年贈与を20年続ければ2,200万円の資産移転が可能です。
相続発生後の対策は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、法律で定められた各種特例や控除を適切に活用して実際の相続税額を軽減する方法です。申告期限までに遺産分割を確定させ、適用要件を満たす必要があります。効果的な相続税対策には、生前から計画的に準備しつつ、相続発生後も適切な特例適用を行う両方の視点が不可欠です。
生前にできる相続税対策13選
生前対策は早期開始ほど効果が高まりますが、2024年改正で贈与のルールが変わりました。暦年贈与は相続前7年分が加算対象となる一方、相続時精算課税の基礎控除(年110万円)は持ち戻し対象外です。高齢の方には後者が有効で、孫や子の配偶者への贈与も7年ルールの対象外となるケースが多くあります。不動産の評価減、生命保険の納税資金確保、養子縁組による基礎控除増加など、13の対策それぞれにメリットと注意点があります。
暦年贈与の活用(年間110万円までの非課税枠)
毎年110万円まで贈与税が非課税となる暦年贈与は、最も基本的な相続税対策です。20年間継続すれば2,200万円の資産移転が可能で、受贈者の数だけ活用できるため、計画的な実施で大きな節税効果が期待できます。
名義預金とみなされないための3つのルールを守ることが重要です。贈与契約書を作成し、受贈者が通帳と印鑑を自分で管理し、実際にその資金を使う──この実態がなければ、税務調査で「名義だけ借りた親の財産」と判定され、相続税の課税対象になります。贈与の事実を客観的に証明できる体制を整えてください。
ただし2024年の改正により、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるルールが適用されます。贈与する側の老後の生活資金を確保しながら、早めの開始が効果を最大化するポイントです。
相続時精算課税制度の基礎控除(年110万円)の活用
2024年の改正で新設された「申告不要の年110万円枠」は、相続時精算課税制度を選択している場合でも使える独立した非課税枠です。暦年贈与の110万円とは別物で、最大の特徴は「相続前7年ルール」の対象外になる点、つまり亡くなる直前に贈与しても相続財産に戻されません。
高齢の方や健康不安がある方には、暦年贈与よりこちらが最強の対策となります。相続時精算課税を一度選択すると暦年贈与には戻れませんが、この年110万円枠は「贈与時に非課税」「相続時にも持ち戻しなし」という二重のメリットがあります。贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上の推定相続人または孫という年齢要件を満たせば活用可能です。
特に「あと数年で相続が起きそう」という状況では、暦年贈与の7年持ち戻しルールを避けられるこの制度が効果的です。相続時精算課税制度の2,500万円枠と併用できるため、まとまった資産移転を計画している場合は、税理士に相談の上で戦略的に活用してください。
相続時精算課税制度の利用(2,500万円特別控除)
60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与で、2,500万円までの特別控除が適用されます。将来の相続税額から贈与税額が控除される特徴があり、計画的な資産移転に適しています。
この制度は、贈与時点で財産を移転できることに加え、将来の資産価値上昇分を移転できる可能性があるメリットがあります。ただし、一度この制度を選択すると暦年贈与への変更はできないため、贈与者と受贈者の年齢要件や相続までの期間を考慮した慎重な判断が必要です。2024年改正で新設された年110万円の基礎控除と併用できる点も、制度選択の判断材料となります。
教育資金や結婚資金の贈与特例
教育資金の一括贈与は1,500万円まで、結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで非課税となります。孫の将来のための資金準備と節税を同時に実現できる効果的な方法です。
教育資金の贈与では、学校等への支払いが対象となり、使用状況の記録と領収書の保管が必要です。また、結婚・子育て資金についても、結婚式費用や育児関連費用など、使途が限定されることに注意が必要です。ただし、通常の贈与とは別枠で設定されているため、有効な相続税対策の手段となります。
生命保険の非課税枠の活用
死亡保険金の相続税非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。生命保険は、節税効果と納税資金の確保を両立できる有効な手段となります。
特に重要なのが「すぐに現金化できる」という実務的なメリットです。不動産や非上場株式ばかりで現金がない場合、相続税の納付期限までに資産を売却できず「黒字倒産」状態に陥るリスクがあります。生命保険金は受取人固有の財産として遺産分割の対象外となり、保険金請求から数日〜2週間程度で現金を受け取れるため、納税資金の確保という防衛的な側面でも極めて有効です。
契約の際は、保険料の支払いが贈与税の対象となる場合があることや、保障内容と保険料のバランスを考慮する必要があります。また、契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって税務上の取り扱いが異なるため、慎重な検討が重要です。
賃貸不動産の活用による評価減効果
賃貸不動産は、現金や株式と比べて相続税評価額が低く算定される特徴があります。土地は路線価(時価の約80%)、建物は固定資産税評価額(時価の約70%)で評価され、さらに賃貸中の場合は借家権割合などで減額されるため、適切な物件選定と管理により、相続税評価額を抑えながら収益も得られる対策となります。
物件選定の際は、立地や将来性はもちろん、以下の点についても十分な検討が必要です。
- 物件の収益性と維持管理費用のバランス
- 将来の相続時における評価方法の確認
- 賃貸経営の手間と管理体制の整備
タワーマンション節税については2024年の税制改正で評価方法が見直されました。従来は階数が高いほど時価と評価額の乖離が大きく、極端な節税が可能でしたが、改正後は市場価格との乖離が大きい物件については評価額が引き上げられる仕組みが導入されています。まだ一定の評価減効果はありますが、以前のような「魔法の節税策」ではなくなったため、安易な購入は避け、収益性や流動性も含めた総合的な判断が必要です。
不動産小口化商品の活用
一口数百万円から購入できる不動産小口化商品は、アパート一棟買いのハードルが高い方でも、手軽に不動産の評価減メリットを受けられる選択肢です。現物不動産と同様に相続税評価額が時価の約70〜80%に圧縮されるため、退職金で少し対策したい層に適した商品といえます。
小口化商品には「任意組合型」「匿名組合型」「賃貸型」の3種類があり、このうち相続税対策に有効なのは「任意組合型」と「賃貸型」です。これらは不動産の所有権を持つ形式のため、相続税評価額の圧縮効果が適用されます。一方、匿名組合型は金銭債権として評価されるため、評価減効果は得られません。
商品選定の際は、運営事業者の信頼性、想定利回り、中途換金の可否、最低投資額などを確認してください。流動性は現物不動産より高いものの、すぐに現金化できるわけではない点にも注意が必要です。あくまで「相続税評価を下げる」ことが主目的であり、収益性や換金性を過度に期待すると判断を誤るリスクがあります。
配偶者への居住用不動産の贈与(配偶者控除)
婚姻期間20年以上の場合、配偶者への居住用不動産の贈与は2,000万円まで非課税となります。配偶者の生活基盤を確保しながら、相続財産を減らすことができます。
この制度を活用する際は、贈与後の居住継続が要件となるため、配偶者の健康状態や今後の居住予定を考慮する必要があります。また、贈与後は固定資産税などの諸経費の負担者が変更となることにも注意が必要です。配偶者の収入状況や資産状況を踏まえた上で、贈与の時期や範囲を検討しましょう。
小規模宅地等の特例に向けた準備(要件の整備)
自宅や事業用地は、要件を満たせば最大80%の評価減が可能です。生前から居住や事業の実態を整えることで、将来の相続税負担を大きく軽減できます。
特例の適用を確実にするためには、以下の準備が重要です。
- 不動産の登記や契約関係書類の整備
- 居住や事業の実態を示す証拠書類の保管
- 将来の相続人との同居や事業承継の計画策定
孫・子の配偶者への贈与(相続人以外への贈与)
相続人以外への贈与は「7年持ち戻しルール」の対象外になるケースが多く、駆け込み対策として有効です。相続人(子供)への贈与は亡くなる前7年分が相続財産に戻されてしまいますが、孫(遺贈を受けない場合)や息子の嫁・娘の婿への贈与はこの制限を受けません。
特に健康不安がある方や高齢の方は、子供への贈与だけでなく「孫への直接贈与」「子の配偶者への贈与」を組み合わせることで、7年ルールの影響を最小化できます。例えば、子供に年110万円、その配偶者に年110万円、孫2人にそれぞれ年110万円を贈与すれば、年間440万円の資産移転が可能で、仮に3年後に相続が発生しても、孫と子の配偶者への贈与分は持ち戻しの対象外となります。
ただし、孫が遺言で遺贈を受ける場合や、代襲相続人となる場合は、持ち戻しルールが適用されるケースもあります。また、贈与を受けた孫や子の配偶者が財産を適切に管理できるか、離婚リスクなども考慮する必要があります。家族関係や将来の相続構造を見据えた慎重な判断が重要です。
墓地や仏具など非課税財産の取得
墓地、仏壇、位牌などは相続税が非課税となります。これらの財産を生前に購入することで、課税対象となる相続財産を減らすことができます。
ただし、非課税となるのは実際に祭祀の用に供するものであり、通常必要と認められる範囲内である必要があります。購入時の領収書等は適切に保管し、将来の相続時に備えることが重要です。相続税対策としてだけでなく、家族の意向も踏まえた検討が望ましいでしょう。
養子縁組の活用(法定相続人を増やす)
法定相続人が増えることで基礎控除額が増加します。ただし、相続税対策のみを目的とした養子縁組は認められないため、実質的な親子関係の構築が必要です。
養子縁組を検討する際は、以下の点について十分な検討が必要です。
- 家族関係全体への影響
- 扶養義務の発生と将来の負担
- 相続人間での理解と合意形成
孫を養子にする場合は「相続税の2割加算」というデメリットが発生します。基礎控除額は1人あたり600万円増えますが、孫が相続する財産には通常の相続税額の1.2倍が課税されるため、必ずしも節税にならないケースがあります。養子縁組による基礎控除増加のメリットと、2割加算のデメリットを試算した上で判断してください。実子がいる場合、養子として認められるのは1人まで、実子がいない場合は2人までという制限もあります。
財産の分割や整理の計画(争族対策として)
生前に財産の分割方針を明確にし、遺言書を作成することで、相続人間のトラブルを防ぎ、スムーズな相続を実現できます。これにより、余計な費用や税負担を抑制することも可能です。
特に重要なのは、相続人間での十分なコミュニケーションです。財産の現状や分割の基本方針について、できるだけ早い段階から情報共有を行うことをお勧めします。必要に応じて専門家の関与を得ながら、遺言書の作成や財産の整理を進めていくことで、将来の紛争リスクを軽減することができます。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 生前対策に挙げられている「暦年課税制度(暦年贈与)」と「相続時精算課税制度」は、いずれも2024(令和6)年1月1日以後に行う贈与から改正がなされています。
暦年課税制度では、生前に被相続人が贈与した財産のうち相続時の相続財産に加算される期間が相続開始前3年以内から7年以内に延長されました。
一方、相続時精算課税制度では、従前になかった基礎控除(110万円/年)が暦年課税制度の基礎控除とは別に新たに設けられ、その基礎控除分については贈与時に非課税となる上、相続時にも精算する必要がない(相続財産に加えない)ことになりました。
このため、生前贈与にどちらの制度を利用するのが得策かは、贈与者(贈与をする人)の年齢や受贈者(贈与を受ける人)との関係によっても変わってきますので、今まで以上に熟慮して選択する必要があります。
- 松井信行公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行
相続発生後でも間に合う相続税対策6選
相続発生後の対策は申告期限(10ヶ月)までに実行する必要がありますが、適切な選択で大きな節税効果を得られます。配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)と小規模宅地等の特例(最大80%評価減)が2大柱ですが、安易に配偶者へ全額相続させると二次相続で子供の税負担が膨らむ罠があります。土地評価では不整形地や騒音など悪条件による減額、分割協議が難航する場合の未分割申告、現金納付が困難な場合の物納制度など、状況に応じた選択肢があります。いずれも申告期限内の手続きが必須で、税理士の評価技術によって結果が大きく変わるため、早期の専門家相談が重要です。
配偶者の税額軽減と二次相続を見据えた遺産分割
配偶者は法定相続分または1億6,000万円までの財産を相続税なしで取得できます。この特例を適切に活用することで、実質的な相続税負担を大きく軽減できます。
「とりあえず配偶者に全部相続させれば税金ゼロ」は二次相続の罠になり得ます。配偶者が全財産を相続すれば一次相続の税額はゼロですが、その配偶者が亡くなった時(二次相続)には、子供たちが基礎控除や配偶者控除を使えず、巨額の相続税を支払うケースがあります。一次相続であえて子供も一定額を相続し、トータルの税負担を最小化する分割方法を検討してください。
配偶者の税額軽減を効果的に活用するためには、以下の点に注意が必要です。
- 一次・二次相続のトータル税額シミュレーション
- 相続する財産の選択(現金や換金性の高い資産の優先検討)
- 配偶者の今後の生活設計と必要資金の確保
- 申告手続きに必要な書類の準備
小規模宅地等の特例の適用
相続した居住用宅地や事業用地について、条件を満たせば最大80%の評価減が可能です。申告期限までに適切な選択と手続きを行うことが重要です。
この特例を適用する際は、以下のような実務的な対応が必要となります。
- 相続開始時から申告期限までの居住・事業継続の確認
- 適用対象となる宅地の選定
- 必要書類の収集と期限内申告の準備
「家なき子特例」により、別居している子供でも適用できるケースがあります。同居要件を満たさない場合でも、相続人が持ち家に住んでいない、過去3年以内に自己または配偶者の持ち家に住んでいないなどの条件を満たせば、親の自宅の土地評価を80%減額できる可能性があります。賃貸住まいの子供が実家を相続する場合は、この特例の適用を検討してください。
複数の土地が対象となる場合は、どの土地に特例を適用するかの選択が節税額に大きく影響します。相続人間での十分な協議と、専門家への相談を踏まえた判断が望ましいでしょう。
土地の評価減(不整形地・無道路地・騒音など)
土地の相続税評価額は「路線価×面積」だけでは決まりません。形がいびつな不整形地、道路に面していない無道路地、線路や幹線道路沿いの騒音がひどい土地、傾斜地や高低差がある土地などは、利用価値が低いため評価額を減額できます。
評価減が適用できる主なケースは以下の通りです。
- 不整形地(三角形や極端に細長い土地):最大40%程度の減額
- 無道路地(道路に接していない土地):最大40%程度の減額
- 騒音・振動・悪臭などがある土地:10〜30%程度の減額
- 傾斜地や高低差がある土地:10〜30%程度の減額
- 広大地(500㎡以上の宅地):面積に応じた減額
これらの評価減は、税理士の専門知識と経験によって適用の可否や減額幅が大きく変わります。素人判断では見落としがちな減額要素も多いため、相続財産に土地が含まれる場合は、土地評価に強い税理士への相談を強くお勧めします。適切な評価により、数百万円から数千万円単位で税額が変わるケースも珍しくありません。
未分割財産の申告と申告期限後3年以内の分割見込書の提出
相続財産の分割が決まらない場合、とりあえずの申告を行い、その後3年以内に実際の分割を確定させることができます。これにより、慎重な検討時間を確保できます。
この制度のメリットは、以下の点にあります。
- 相続人間での慎重な協議時間の確保
- 財産評価や分割方法の詳細な検討が可能
- 相続税の納税を遅延なく行える
ただし、申告時点での法定相続分で仮の申告を行う必要があり、最終的な分割が確定した際には、更正の請求または修正申告が必要となることに注意が必要です。
延納制度・物納制度の利用(現金納付が困難な場合)
相続税の納付が困難な場合、延納(分割払い)または物納(不動産などの現物納付)が認められます。延納は最長20年の分割払いが可能ですが、利子税が発生します。物納は延納でも納付困難な場合の最終手段で、不動産や国債などが対象となります。
物納を検討する際は、財産の管理状況や収益性が審査の重要なポイントとなります。物納が許可されるまでの手続きには一定の時間を要するため、早めの検討と準備が重要です。なお、物納財産は相続税評価額で引き取られるため、時価との差額を考慮した判断が必要です。
特定の相続財産の適正評価と専門家相談
美術品や事業用資産、非上場株式、知的財産権など、評価が難しい財産については、専門家の助言を得ながら最適な評価方法を選択することで、適正な申告と節税が可能です。
特に慎重な検討が必要なケースとして、以下のようなものがあります。
- 事業承継が絡む相続案件(非上場株式の評価)
- 不動産の評価方法の選択が必要なケース(土地の減額要素の洗い出し)
- 相続人間で意見の相違があるケース(遺産分割協議の調整)
- 特殊な財産(ゴルフ会員権、リゾート会員権、貸付金など)
このような場合、税理士や弁護士など、複数の専門家との連携が必要となることもあります。相続開始後できるだけ早い段階での相談を心がけ、適切な対応を検討していくことが重要です。
相続税対策の注意点
相続税対策には節税効果がある一方、実行時の落とし穴も存在します。名義預金とみなされると贈与が無効となり相続財産に加算され、認知症発症後は資産が凍結され対策が一切打てなくなります。過度な生前贈与は老後資金を枯渇させ、一度選択した相続時精算課税は取り消せません。税制改正や家族状況の変化にも対応が必要です。これらのリスクを理解した上で、専門家の助言を得ながら慎重に進めることが重要です。
名義預金認定のリスク
贈与の実態がない「名義だけの預金」は、税務調査で相続財産とみなされます。親が子供名義の口座を作って預金していても、通帳や印鑑を親が管理し、子供が存在すら知らない場合は「名義預金」と判定され、贈与は無効となり相続税の課税対象になります。
名義預金と認定される典型的なパターンは以下の通りです。
- 通帳・印鑑・キャッシュカードを贈与者(親)が管理している
- 受贈者(子)が口座の存在を知らない、または自由に使えない
- 贈与契約書が作成されていない
- 贈与税の申告をしていない(110万円超の場合)
名義預金認定を避けるには、贈与契約書の作成、受贈者による通帳・印鑑の管理、実際に資金を使う(または受贈者が管理する口座に移す)という3つの実態を整えてください。「子供のために貯めておいてあげよう」という善意が、かえって相続税の増税を招く結果となります。
認知症による資産凍結リスク
本人が認知症を発症すると、預金の引き出し、不動産の売却、贈与契約などが一切できなくなります。金融機関は本人の意思確認ができない状態での取引を拒否するため、相続税対策が必要な時期に何も実行できない事態に陥ります。
認知症による凍結で起きる典型的な問題は以下の通りです。
- 生前贈与が実行できず、相続財産が減らせない
- 老人ホームの入居費用のために自宅を売却できない
- 医療費や介護費用の支払いで家族が立て替える負担
- 成年後見制度を利用すると、贈与や相続税対策が原則不可
対策としては、元気なうちに家族信託や任意後見契約を検討してください。家族信託は、財産の管理・処分権限を信頼できる家族に託す仕組みで、本人が認知症になっても受託者が財産を動かせます。ただし、信託後の贈与や相続税対策には制限があるため、信託契約の設計段階で税理士や司法書士に相談し、節税と資産保全のバランスを取った設計が必要です。
過度な節税策のリスクと老後資金の確保
節税を優先しすぎて老後資金が枯渇すれば、本末転倒です。生前贈与や不動産購入で資産を手放した後、医療費・介護費用・生活費の不足で子供に経済的負担をかけるケースがあります。
特に気をつけるべきポイントとして、以下のような項目があります。
- 平均寿命を考慮した生活費の見積もり(90歳まで生きる前提で試算)
- 医療費や介護費用の予備費(年間100万円〜300万円を想定)
- 年金収入と生活費のバランス(不足分を資産で補う計画)
生前贈与は効果的な節税対策ですが、資産を手放してしまうと、予期せぬ支出が必要になった際に対応が困難になる可能性があります。また、将来の税制改正により、新たな対策が必要となることも考えられます。そのため、流動性の高い資産(現金・株式など)は手元に残し、不動産など換金に時間がかかる資産の比重を下げる工夫も重要です。
専門家への相談の重要性(税理士や弁護士)
相続税対策は一度実行すると取り消せない選択が多く、専門家の助言なしに進めるとリスクが高まります。税理士や弁護士などの専門家に相談し、自身の状況に最適な対策を選択することが重要です。
専門家に相談することで得られる主なメリットとして、以下のようなものがあります。
- 最新の税制(2024年改正含む)に基づいた具体的なアドバイス
- 家族状況や資産状況に応じた総合的な提案
- 相続税対策と事業承継の両立
- 名義預金認定や税務調査リスクの回避策
特に相続税対策は、一度実施すると変更が難しい選択も多くあります。たとえば、相続時精算課税制度を選択した場合は暦年贈与に戻すことができません。また、不動産取得や養子縁組なども、安易な判断は避けるべきです。そのため、実施前に専門家の意見を聞き、慎重に判断することをお勧めします。
なお、税理士と弁護士では専門分野が異なります。税理士は税務の専門家として具体的な節税方法を提案し、弁護士は法的な観点から遺言作成や相続手続きをサポートします。案件によっては両方の専門家に相談することで、より適切な対策を講じることができます。
相続税対策は一度の相談で終わりではありません。税制改正や家族状況の変化に応じて、定期的に見直しを行うことが望ましいでしょう。専門家との継続的な関係を築き、状況の変化に応じて適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 相続が生じた際、遺族が行わなければならないことには相続税の申告以外にも葬儀の執行から行政機関等への各種手続きまで様々なものがあります。
その中で遺族が最初に直面する問題は、被相続人(亡くなられた方)が生前どのような財産を保有していたかがよく分からないということです。
そのため、自宅に遺された書類の中から通帳や保険証券など必要なものを探し出し、あるいは行政機関や金融機関に問い合わせ被相続人の財産を一つずつ確認・整理しなければなりません。遺族にこのような負担を掛けないためには生前に遺言書を作成しておかれるのが理想ですが、そうでなければ簡単な財産目録を遺しておくか、最近はスマホのパスワードやネット上で契約したサービスのログインIDなどの情報も含めて一覧形式でノートに纏めておかれるのが良いでしょう。
- 松井信行公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行
まとめ
相続税対策は早期開始ほど選択肢が広がりますが、2024年改正により持ち戻しルールが変わりました。暦年贈与は相続前7年が加算対象、相続時精算課税の基礎控除(年110万円)は持ち戻し対象外です。孫や子の配偶者への贈与は7年ルールの対象外となるケースが多く、駆け込み対策として有効です。生前対策13選、相続発生後の対策7選から、自身の年齢・資産状況・家族構成に合った方法を選択してください。
節税は重要ですが、名義預金認定のリスク、認知症による資産凍結、老後資金の枯渇に注意が必要です。配偶者への全額相続は二次相続で子供の税負担が膨らむ罠があります。流動性の高い資産を手元に残し、将来の不測の事態にも対応できる余裕を持った計画を立ててください。
一度実行すると取り消せない選択(相続時精算課税、養子縁組、不動産取得など)も多いため、実施前に税理士や弁護士など専門家に相談し、慎重に判断してください。税制改正や家族状況の変化に応じて定期的に見直しを行い、元気なうちに家族信託や財産目録の作成も検討しましょう。
よくある質問
Q. 相続税の基礎控除額はいくらですか?
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となり、相続財産がこの金額以下であれば相続税はかかりません。
Q. 相続税対策はいつから始めるべきですか?
相続税対策は早ければ早いほど効果的です。暦年贈与は時間をかけるほど効果が高まり、不動産活用や生命保険も長期的な視点が必要です。ただし認知症を発症すると対策が一切打てなくなるため、遅くとも60代のうちに専門家に相談し、計画的に進めることをお勧めします。
Q. 配偶者に全額相続させれば相続税はかからないのですか?
配偶者は1億6,000万円まで相続税が非課税ですが、配偶者に全額相続させると二次相続(配偶者が亡くなった時)で子供の税負担が膨らむ罠があります。一次相続であえて子供も一定額を相続し、一次・二次相続のトータル税額を最小化する分割方法を検討してください。
Q. 暦年贈与と相続時精算課税制度はどちらを選ぶべきですか?
2024年改正後、暦年贈与は相続前7年分が加算対象となる一方、相続時精算課税の基礎控除(年110万円)は持ち戻し対象外です。高齢の方や健康不安がある方には相続時精算課税が有利ですが、一度選択すると暦年贈与に戻せないため、贈与者の年齢と相続までの期間を考慮して慎重に判断してください。
Q. 税理士に相談するタイミングはいつがよいですか?
相続税対策は実行前の相談が重要です。生前贈与や不動産取得、養子縁組など一度実行すると取り消せない選択が多いため、計画段階で税理士に相談し、名義預金認定や税務調査のリスクを回避する設計が必要です。相続発生後は申告期限(10ヶ月)までに土地評価や特例適用を決める必要があるため、できるだけ早い段階で相談してください。