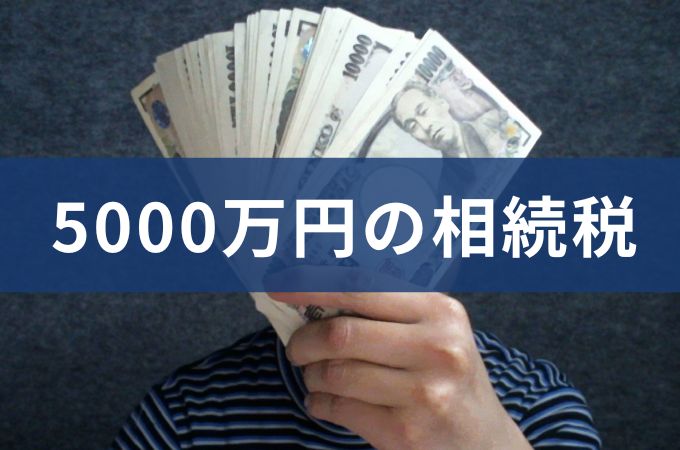まず確認!5000万円が課税対象になる条件(基礎控除の判定)
相続税が課税されるかどうかは、まず「基礎控除額」を超えるかどうかで決まります。この基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」で計算されるため、相続人の人数によって課税の有無が変わってきます。5000万円の相続財産が課税対象になるのは、次の人数別早見表のとおりです。
【相続人数別・課税ライン早見表】
- 相続人1人:基礎控除額3600万円→5000万円は課税対象
- 相続人2人:基礎控除額4200万円→5000万円は課税対象
- 相続人3人:基礎控除額4800万円→5000万円は課税対象
- 相続人4人:基礎控除額5400万円→5000万円は非課税
- 相続人5人以上:基礎控除額6000万円以上→5000万円は非課税
つまり、相続人が3人以下の場合、5000万円の相続財産は相続税の課税対象となります。一方、相続人が4人以上であれば、基礎控除額が5000万円を上回るため、課税されません。
相続財産5000万円は「正味額」か?評価・差し引き項目をチェック
相続税の計算で使う「5000万円」は、単純な財産の合計ではなく「正味の相続財産」を指します。実際の課税対象額を正確に把握するためには、次の項目を確認する必要があります。
【正味相続財産の計算に影響する項目】
- 債務控除:被相続人の借金や未払金、葬式費用などは差し引けます
- 非課税財産:生命保険金の一定額や死亡退職金の一部は非課税です
- みなし相続財産:暦年課税による贈与が相続財産に含まれます(相続開始前7年以内、令和6年1月1日以降の贈与より適用)
- 土地・建物の評価減:路線価や固定資産税評価額を基に評価されます
※相続時精算課税による贈与は、令和6年1月1日以降の贈与分について年間110万円の基礎控除を差し引いた残額が相続財産に加算されます。
例えば、預貯金4000万円と不動産3000万円を所有していても、住宅ローン2000万円が残っている場合、債務控除により正味相続財産は5000万円(7000万円-2000万円)となります。ただし、団体信用生命保険(団信)に加入している場合は、相続開始とともに保険金でローンが完済されるため、債務控除はできません。この場合の正味相続財産は7000万円となります。このように、相続開始時点での「正味額」を正確に把握することが第一歩です。
基礎控除を超えたらどうなる?課税遺産総額と税率適用の流れ
相続財産が基礎控除を超えた場合、次の手順で相続税が計算されます。
- 課税遺産総額の算出:正味相続財産から基礎控除額を差し引く
- 法定相続分による按分:課税遺産総額を法定相続分で各相続人に分配
- 税率の適用:各人の取得金額に応じた税率を適用
- 総額の計算:各相続人の税額を合計
- 実際の取得分に応じた税額再計算:実際の遺産分割に応じて再計算
例えば、相続人2人(配偶者と子1人)で正味相続財産が5000万円の場合、基礎控除額は4200万円なので、課税遺産総額は800万円になります。これを法定相続分(配偶者1/2、子1/2)で按分し、それぞれ400万円ずつに税率(10%)を適用します。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
基礎控除額や相続税の計算を自分自身で行う場合に注意すべき点は以下の2点です。
・法定相続人数
・財産価格の計算方法
まず、法定相続人の数を誤ると基礎控除額が大きく変動し、相続税額がブレます。よって、誰が法定相続人になるのかは慎重に判定する必要があります。特に、先に亡くなっている人がいる場合、代襲相続があるのか否かなど、確認すべき事柄が増えます。
また、財産の価格についても、基本は亡くなった時点での時価となりますが、財産の種類によりその算定方法は様々です。特に、土地の価格算定は、形状や立地条件により、考慮すべき事項は多岐にわたります。
最終的に、チェックのみ行ってもらえる専門家を探すことも検討しましょう。 - スエナガ会計事務所
代表 末永 寛
5000万円の相続税はいくら?家族構成別シミュレーション
相続税額は、相続人の続柄や人数によって大きく変わります。5000万円の相続財産に対する家族構成別の相続税額を見ていきましょう。
【家族構成別・相続税額早見表(5000万円相続で法定相続分通りに相続した場合)】
- 配偶者+子1人:配偶者0円、子40万円(合計40万円)
- 配偶者+子2人:配偶者0円、子各5万円(合計10万円)
- 配偶者+親1人:配偶者0円、親27万円(合計27万円)
- 配偶者+兄弟姉妹1人:配偶者0円、兄弟姉妹24万円(合計24万円)
- 子のみ2人:各40万円(合計80万円)
- 配偶者のみ:0円(配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)適用)
これらの金額は、配偶者が法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい方まで控除が受けられることを前提としています。実際の税額は遺産分割方法や各種特例の適用によって変動します。
ケース1|配偶者+子(最多パターン)
最も一般的な「配偶者と子」のパターンでは、配偶者控除の活用がポイントです。配偶者が取得する財産には、法定相続分または1億6000万円までの金額について相続税がかかりません。
【子の人数別相続税額(5000万円相続の場合)】
・子1人の場合:
基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2人)
課税遺産総額:800万円(5000万円-4200万円)
配偶者(法定相続分1/2):400万円→配偶者控除で0円
子(法定相続分1/2):400万円×10%=40万円
・子2人の場合:
基礎控除額:4800万円(3000万円+600万円×3人)
課税遺産総額:200万円(5000万円-4800万円)
配偶者(法定相続分1/2):100万円→配偶者控除で0円
子2人(各法定相続分1/4):各50万円×10%=各5万円
このように、子の人数が増えるほど基礎控除額も増え、相続税負担は軽減されます。特に相続人3人(配偶者+子2人)の場合、課税遺産総額が200万円と少額になるため、税負担も大幅に減少します。
ケース2|配偶者+親(子なし)
子がいない場合で親が相続人になる場合は、次のような計算になります。
- 基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2人)
- 課税遺産総額:800万円(5000万円-4200万円)
- 配偶者(法定相続分2/3):533万円→配偶者控除で0円
- 親(法定相続分1/3):267万円×10%=26万円
親が相続人になる場合、法定相続分は子がいる場合より少なくなります。ただし、親の年齢が高い場合は、相続後の資産管理が困難になる可能性や、親が亡くなった際の再度の相続についても考慮する必要があります。
ケース3|配偶者+兄弟姉妹(2割加算対象)
兄弟姉妹が相続人となる場合は、2割加算という税負担増の要素があります。
- 基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2人)
- 課税遺産総額:800万円(5000万円-4200万円)
- 配偶者(法定相続分3/4):600万円→配偶者控除で0円
- 兄弟姉妹(法定相続分1/4):200万円×10%×1.2(2割加算)=24万円
兄弟姉妹は配偶者・一親等の血族以外にあたるため、計算された税額に2割が加算されます。このため、同じ相続財産額でも、子や親が相続する場合より税負担が大きくなります。
ケース4|子のみ(配偶者なし)
配偶者がいない場合、配偶者控除が適用されないため、相続税負担が増加します。
・子1人の場合:
基礎控除額:3600万円(3000万円+600万円×1人)
課税遺産総額:1400万円(5000万円-3600万円)
子(相続分全額):1400万円×15%=210万円
・子2人の場合:
基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2人)
課税遺産総額:800万円(5000万円-4200万円)
子各人(各相続分1/2):各400万円×10%=各40万円(合計80万円)
配偶者がいない場合は、基礎控除額が少なくなり、さらに配偶者控除も使えないため、相続税の負担は大きくなります。ただし、子の人数が増えれば基礎控除額も増えるため、負担は軽減されます。
ケース5|配偶者のみ(子なし)
配偶者のみが相続人の場合、配偶者控除(法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい方)が適用されます。
- 基礎控除額:3600万円(3000万円+600万円×1人)
- 課税遺産総額:1400万円(5000万円-3600万円)
- 配偶者(相続分全額):1400万円→配偶者控除(1億6000万円まで)で0円
5000万円の相続財産であれば、配偶者控除の範囲内に収まるため、相続税は0円になります。ただし、配偶者が亡くなった後の二次相続では、基礎控除額が少なくなり、相続税負担が大きくなるリスクがあります。
相続税の正式な計算方法と税率早見表
相続税の計算は次の5ステップで行われます。
- 1.正味の相続財産の計算:総財産-債務-葬式費用+みなし相続財産
- 2.基礎控除額の計算:3000万円+600万円×法定相続人数
- 3.課税遺産総額の計算:正味相続財産-基礎控除額
- 4.各相続人の税額計算:課税遺産総額を法定相続分で按分し税率を適用
- 5.最終税額の計算:各種税額控除を適用(配偶者控除、未成年者控除など)
【相続税の税率早見表】
- 1000万円以下:10%
- 3000万円以下:15%-50万円
- 5000万円以下:20%-200万円
- 1億円以下:30%-700万円
- 2億円以下:40%-1700万円
- 3億円以下:45%-2700万円
- 6億円以下:50%-4200万円
- 6億円超:55%-7200万円
相続税は超過累進税率が適用されるため、相続財産額が大きくなるほど税率も高くなります。5000万円程度の相続では、主に10%の税率が適用されることが多いでしょう。
計算ミスあるある|「×税率-控除」で即答すると危険
相続税の計算でよくある間違いは、単純に「財産額×税率」で計算してしまうことです。しかし、実際の計算はもっと複雑です。
【よくある計算ミスの例】
- 基礎控除を考慮せずに総財産に税率をかける
- 財産評価を市場価格のまま計算する(実際は路線価など評価減がある)
- 法定相続分で按分せずに実際の取得分に直接税率をかける
- 控除・特例の適用要件を確認せずに計算する
例えば、5000万円の相続財産があり、税率15%と考えると「5000万円×15%=750万円」と計算してしまいがちですが、実際は基礎控除や配偶者控除などを適用した後の課税遺産総額に税率をかけるため、大きく異なる結果になります。特に5000万円程度の相続では、これらの控除を適切に適用すれば、相続税がゼロになる可能性もあります。
このような複雑な計算は専門家に相談することで、正確な額を知ることができます。間違った計算で予想外の税負担が発生することを避けるためにも、税理士などの専門家に確認することをお勧めします。
控除・加算の適用順序と書類提出のコツ
相続税の計算において、控除や加算の適用順序は非常に重要です。
【適用順序の基本】
- 基礎控除の適用(3000万円+600万円×法定相続人数)
- 各相続人の相続税額計算(法定相続分で按分後、税率適用)
- 税額控除の適用(配偶者控除、未成年者控除、障害者控除など)
- 2割加算の適用(配偶者・一親等の血族(親に先立たれた孫を含む)以外)
- 贈与税額控除(相続開始前3年以内の暦年贈与や相続時精算課税制度を利用していた場合)
申告書類の提出には次のようなコツがあります。
- 相続財産は漏れなく記載する(預貯金、有価証券、不動産、生命保険金など)
- 土地・建物の評価方法を適切に選択する(路線価方式、倍率方式など)
- 特例適用の要件を確認し、必要書類を添付する
- 遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印での押印と印鑑証明書の添付が必要
- 提出期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)を厳守する
これらのポイントを押さえて、漏れのない申告を行うことが重要です。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
財産総額が5000万円前後の場合に想定されるトラブルが「遺産相続争い」です。
相続財産が5000万円の場合、その大部分が不動産という事が一般的です。それにより、以下のようなことから争いが起こり得ます。
・不動産は分けにくい財産なので、遺産分割において不公平が起こる
・相続税は「現金一括納付」が原則だが、納税資金が不足する
不動産の権利を分割することは非常に難しく、その解決策として共有名義にすると、売却等の意思統一が図れない場合、新たな火種となり得るので、できる限り一人が相続する事が望ましいです。よって、不公平が起こりやすくなります。
また、財産の大部分が不動産の場合、納税資金が不足する事もあり得ます。
よって、早めに財産を把握し、不公平感の解消や納税資金対策に着手する事が有効です。 - スエナガ会計事務所
代表 末永 寛
5000万円でも使える!主な節税対策と活用シナリオ
5000万円程度の相続財産でも、適切な節税対策を講じることで税負担を軽減できます。以下に主な節税対策を優先度順に示します。
【主な節税対策】
- 配偶者控除の活用
- 小規模宅地等の特例の適用
- 生命保険金の非課税枠の活用
- 計画的な生前贈与
これらの対策を組み合わせることで、相続税負担を大幅に減らすことができます。
配偶者控除を使いすぎない二次相続対策
配偶者控除は強力な節税手段ですが、使いすぎると二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)で税負担が増加するリスクがあります。
【配偶者控除と二次相続のバランス】
- 一次相続:配偶者がすべて相続→相続税0円
- 二次相続:子が全額相続→基礎控除が少なく税負担大
例えば、5000万円の相続で配偶者が全額相続した場合、一次相続の税額は0円になりますが、その後配偶者が亡くなると、子が5000万円を相続することになり、基礎控除額が少なくなるため(3000万円+600万円×子の人数)、税負担は大きくなります。
【分散相続のシミュレーション(5000万円の場合)】
- 一次相続:配偶者3000万円、子2000万円→配偶者0円、子32万円
- 二次相続:配偶者の3000万円を子が相続→基礎控除内で収まる可能性
【一次・二次相続の総税額比較】
・全額配偶者相続パターン:
一次相続「0円」(配偶者控除により)
二次相続「160万円」(1400万円×15%)
合計「160万円」
・分散相続パターン(一次相続で配偶者2500万円、子2500万円):
一次相続「40万円」(課税遺産総額800万円のうち子相続分400万円×10%)
二次相続「0円」(基礎控除内)
合計「40万円」
このように、一次相続と二次相続のバランスを考慮した遺産分割を行うことで、総合的な税負担を軽減できます。
小規模宅地等の特例で不動産評価を80%減に
自宅や事業用の土地がある場合、小規模宅地等の特例を利用することで、土地の評価額を最大80%減額できます。
【小規模宅地等の特例の概要】
- 居住用宅地:330㎡まで評価額80%減
- 事業用宅地:400㎡まで評価額80%減
- 貸付事業用宅地:200㎡まで評価額50%減
例えば、相続税評価額2000万円の居住用宅地がある場合、この特例を適用すると評価額は400万円(2000万円×20%)になります。5000万円の相続財産のうち不動産の割合が大きい場合、この特例は非常に効果的です。
【適用要件の主なポイント】
- 被相続人が居住・事業に使用していた土地であること
- 相続人が申告期限まで、居住・事業を継続すること
- 相続税の申告期限まで所有していること
特例の適用には厳格な要件があるため、専門家に相談のうえ、適用可能か確認することをお勧めします。
生命保険金の非課税枠「500万円×人数」を最大活用
生命保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。この非課税枠を活用することで、課税対象となる相続財産を減らすことができます。
【生命保険の非課税枠活用例】
- 相続人3人の場合:1500万円(500万円×3人)まで非課税
- 被相続人が契約者・被保険者、相続人が受取人の生命保険に加入
- 複数の相続人に受取人を分散させる
例えば、相続財産5000万円のうち1500万円を生命保険金として受け取れば、課税対象となる相続財産は3500万円に減少します。特に基礎控除額が少ない場合、この対策は効果的です。
暦年・相続時精算課税など生前贈与の最新ルール
計画的な生前贈与も有効な節税対策です。2024年の税制改正で、贈与税の暦年課税制度における相続税への加算期間が3年から7年に拡大されましたが、それでも計画的な贈与は節税に効果的です。
【生前贈与の主な方法】
- 暦年贈与:年間110万円までの基礎控除を活用
- 相続時精算課税:2500万円までの特別控除を活用+年間110万円の基礎控除(23年改正)も併用可能
- 教育資金贈与:1500万円まで非課税(条件あり)
- 結婚・子育て資金贈与:1000万円まで非課税(条件あり)
これらの制度を組み合わせて活用することで、5000万円程度の相続財産でも相続税を大幅に軽減できる可能性があります。ただし、贈与の時期や方法によっては効果が異なるため、専門家に相談することをお勧めします。
申告・手続きの落とし穴と専門家に相談すべきタイミング
相続税の申告・手続きには多くの落とし穴があります。主なリスクと専門家に相談すべきタイミングを見ていきましょう。
【主なリスクと対策】
- 申告期限の徹底管理:被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内
- 財産評価の漏れ防止:預貯金、有価証券、不動産、生命保険、その他財産の洗い出し
- 特例適用要件の確認:小規模宅地等の特例など、適用要件の厳格な確認
- 二次相続設計:配偶者控除の使い方と将来的な相続税負担の予測
専門家に相談すべきタイミングは、相続の発生後できるだけ早い段階です。特に財産が複雑な場合や、特例の適用を検討する場合は、早期の相談がトラブル防止につながります。
申告期限10か月を過ぎた場合のペナルティ
相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)を過ぎると、以下のようなペナルティが課されます。
【期限後申告・納付のペナルティ】
- 無申告加算税:期限内申告をしなかった場合、本来の税額の5%~20%
- 延滞税:期限内納付をしなかった場合、年率2.4%~14.6%
- 重加算税:隠ぺいや仮装があった場合、本来の税額の35%~40%
5000万円の相続で仮に相続税が100万円だった場合、無申告だと5万円~20万円のペナルティが発生し、さらに延滞税も加算されます。期限内の適正な申告・納付が重要です。
財産目録の作り方と評価漏れ防止チェックリスト
財産目録の作成は相続税申告の基本です。財産の評価漏れを防ぐためのチェックリストを示します。
【財産目録作成のポイント】
- 預貯金:銀行・証券会社等の残高証明書を取得
- 有価証券:評価額の算定方法を確認(上場株式、非上場株式など)
- 不動産:固定資産評価証明書、路線価図などを確認
- 生命保険:保険会社から支払通知書を取得
- その他財産:貴金属、美術品、名義預金、海外財産など
特に名義預金(実質的に被相続人の財産だが、他人名義になっている預金)や海外財産は見落としがちなので注意が必要です。財産目録は相続税申告の土台となるため、漏れなく作成することが重要です。
【相続手続きに必要な書類チェックリスト】
- 戸籍謄本一式(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の現在戸籍)
- 住民票(相続人全員の現住所が記載されたもの)
- 遺言書(ある場合)
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印するため)
- 財産目録(預貯金、有価証券、不動産、生命保険金など全ての相続財産)
- 不動産登記簿謄本(不動産がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の評価額を証明するもの)
- 小規模宅地等の特例に必要な確約書(特例適用を希望する場合)
- 配偶者控除や各種特例の証明書類(適用条件を満たすことを証明する書類)
これらの書類を早めに準備し、専門家のアドバイスを受けながら、申告期限内に漏れなく提出することが重要です。
よくある質問(FAQ)
相続税に関するよくある質問にお答えします。
Q1:5000万円でも申告が不要になるケースはありますか?
A1:相続人が4人以上いる場合は、基礎控除額が5400万円以上になるため、5000万円の相続財産であれば申告は不要です。例えば、配偶者と子3人の4人家族の場合、基礎控除額は5400万円(3000万円+600万円×4人)となります。ただし、基礎控除額を超えていなくても、小規模宅地等の特例を適用したい場合には申告が必要です。詳しくは「まず確認!5000万円が課税対象になる条件(基礎控除の判定)」や「小規模宅地等の特例で不動産評価を80%減に」の節をご参照ください。
Q2:二次相続まで見据えた最適な分割方法はありますか?
A2:一次相続では配偶者控除を最大限に活用しつつ、二次相続の税負担も考慮した分散相続が有効です。例えば、配偶者と子がいる場合、一次相続では配偶者に法定相続分以下(基礎控除+配偶者控除で非課税範囲内)を相続させ、残りを子に相続させることで、全体の税負担を抑えられます。具体的な数値シミュレーションは「配偶者控除を使いすぎない二次相続対策」の節で解説しています。
Q3:税務署から指摘を受けやすいポイントはどこですか?
A3:相続税申告で特に注意すべき点は以下の通りです。
- 財産の網羅性:預貯金や有価証券など、全ての財産を漏れなく申告しているか
- 評価の適正性:不動産や非上場株式など、適正な評価方法で計算されているか
- 債務控除の妥当性:葬式費用や借入金など、債務として控除できる項目の証拠は揃っているか
- 特例適用の要件充足:小規模宅地等の特例など、要件を満たしていることを証明できるか
詳細は「財産目録の作り方と評価漏れ防止チェックリスト」の節を参考にしてください。
まとめ
5000万円の相続財産に対する相続税について、ポイントをまとめます。
- 相続税が課税されるかどうかは「基礎控除額」(3000万円+600万円×法定相続人数)で決まる
- 相続人が3人以下の場合、5000万円の相続財産は課税対象となる可能性が高い
- 配偶者控除を活用すれば、配偶者の税負担をゼロにできる
- 小規模宅地等の特例や生命保険の非課税枠を活用することで、課税対象額を大幅に圧縮できる
- 計画的な生前贈与も有効な節税対策となる
- 申告期限(10か月以内)を守り、財産評価の漏れを防ぐことが重要
- 一次相続と二次相続のバランスを考慮した相続設計が必要
相続税の計算は複雑で、適切な特例の適用や節税対策の選択には専門的な知識が必要です。少しでも不安や疑問がある場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
相続財産センターでは、相続税に関する無料相談を承っております。5000万円の相続税でお悩みの方も、お気軽にご相談ください。経験豊富な税理士が、あなたの状況に最適な相続税対策をアドバイスいたします。相続税の負担を最小限に抑え、大切な財産を次世代に確実に引き継ぐためのサポートをいたします。まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。