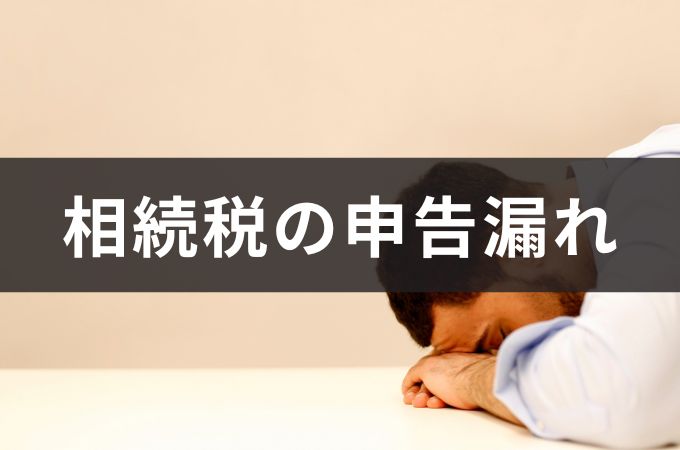相続税の申告漏れとは?基本的な定義と実態
相続税の申告漏れとは、本来申告すべき財産を申告しなかったり、相続税自体を期限内に申告・納付しないケースを指します。これは単純なミスから意図的な隠蔽まで幅広い状況を含みます。
相続は人生で何度も経験するものではなく、手続きが非常に複雑なため、知識不足や見落としによって申告漏れが生じることは決して珍しくありません。実際、国税庁の令和6事務年度調査によると、相続税の実地調査を受けた9,512件(前年比+11.2%)のうち82.3%で申告漏れなどの誤りが見つかっており、これは調査を受けた約5件のうち4件以上という非常に高い割合です。申告漏れ等があった件数自体は7,826件と前年比+8.7%も増加しています。
申告漏れには大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
- 財産の申告漏れ:被相続人の財産の一部を申告書に記載しなかった場合
- 評価額の過少申告:財産の価値を実際より低く評価して申告した場合
- 申告義務の見落とし:相続税の申告が必要な状況を認識できず、申告自体を行わなかった場合
これらのいずれも税務署による調査の対象となり、発覚すれば追徴課税やペナルティが科される可能性があります。まずはこの基本的な意味と背景を押さえた上で、具体的なケースや対策を見ていきましょう。
申告漏れが起こりやすい財産と典型的なケース
相続税の申告漏れは、被相続人の財産把握が不十分であったり、意図的な隠蔽によって生じます。特に現金や預貯金、不動産、株式といった主要な資産から、美術品や骨董品のような個人の趣味の品まで、様々な財産で申告漏れが発生しがちです。
現金・預貯金の申告漏れ - タンス預金と名義預金の落とし穴
国税庁の令和5事務年度調査の申告漏れ財産の構成比を見ると、現金・預貯金等が 29.1%と最も多く、約3割を占めています。
タンス預金の見落とし
被相続人が自宅に保管していた現金(いわゆる「タンス預金」)は、相続財産として見落とされやすい代表例です。故人が銀行口座以外に現金を保有していた場合、遺族がその存在を把握できず申告漏れとなるケースが頻発しています。
名義預金の誤解
子・孫名義の預金口座に預けられた実質的には被相続人の資金(名義預金)も要注意です。生前に家族名義の口座へ資金を移していた場合でも、実質的な管理者が被相続人であれば相続財産として申告が必要です。
複数口座の管理不足
被相続人が複数の銀行に口座を持っていた場合、一部の口座を見落として申告から漏らしてしまうケースも多く見られます。
そのため、被相続人の利用していたすべての口座や自宅保管の現金の所在を漏れなく把握することが重要です。
不動産の申告漏れ - 遠方の土地と共有名義の見落とし
土地や建物など不動産の申告漏れも頻繁に発生します。土地は現金・預貯金等に次いで申告漏れ額が大きい財産であり、評価の誤りや申告対象から外してしまうミスが発生しやすい項目です。
遠方の不動産
被相続人が所有していた不動産を遺族が把握しきれておらず、特に遠方にある土地を申告から漏らしてしまうことがあります。
共有名義不動産
共有名義になっている不動産は、被相続人の持分のみが相続財産となりますが、特にその持分が1/2以下の場合に見落とすケースが多く見られます。
農地や山林
住宅用地以外の農地や山林などは、相続人が存在を認識していても申告対象から外してしまうミスが起こりがちです。
相続発生時には不動産登記簿や固定資産税の納税通知書などを確認し、すべての土地・建物を漏れなく洗い出すことが大切です。
有価証券・金融資産の申告漏れ - 複数口座と海外資産の盲点
株式や投資信託など有価証券の申告漏れも深刻な問題です。有価証券は申告漏れ財産の中で3番目に金額が大きい項目で、年間約388億円もの申告漏れが指摘された年もあります。
複数の証券口座
証券会社の口座を複数持っていた場合、一部の口座を見落として申告から漏れてしまうことがあります。
古い株券の存在
電子化される前の紙の株券を保有していた場合、その存在を遺族が把握できないケースがあります。
海外資産の見落とし
国外の銀行口座や海外資産についても見落とされがちですが、一部のケースを除いて課税対象となるため注意が必要です。国税当局の報告では、海外資産の申告漏れも数十億円規模で確認されています。
証券口座の残高や取引履歴をすべて洗い出し、国内外問わず金融資産を一覧化しておくことが重要です。
趣味・収集品の申告漏れ - 価値の見極めが困難な動産類
美術品や骨董品、宝石類といった趣味性の高い財産も、申告漏れになりやすいものです。
市場価値の認識不足
遺族がそれらの市場価値を正しく認識しておらず、単なる思い出の品として申告しなかった場合、後に高額な資産と判明して課税対象となるケースがあります。
コレクション品の評価漏れ
切手・コイン、着物や工芸品なども同様に、評価額の見積りを怠ると申告漏れにつながります。
専門知識の不足
これらの動産類は一般の方には適正な価値判断が困難なため、専門家による鑑定評価を受けることが重要です。
こうした動産類は専門家に鑑定評価を依頼するなどして、適正な価値を把握した上で漏れなく申告することが大切です。

松井 信行
記事監修者からのワンポイントアドバイス
相続税申告の依頼を受けて相続人の方に被相続人の財産をヒアリングさせていただいた際、相続人の方が相続財産だと思っていない最も代表的なものは「名義預金」です。
そもそも相続財産だと考えていないわけですから、誰かに指摘されなければ当然申告からは漏れてしまいます。
また、被相続人が亡くなられる直前に、将来生じる医療費や葬儀費用等の支払いに備えて相続人の方が被相続人の預貯金口座から纏まった資金を引き出し相続開始時点で手許に残っていたもの(いわゆる「手許現金」)を相続財産に含めなくて良いと思われている方が非常に多いです。
これらはいずれも実質的には被相続人の財産と考えられますから、相続財産から漏れると申告漏れとして追徴課税の対象になりますので注意して下さい。
申告漏れはなぜバレる?税務調査の実態と時効の仕組み
「申告漏れしても税務署に見つからないのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、実際には相続税の申告漏れは高い確率で発覚します。税務当局がどのような情報を把握しているか、そして法定申告期限から何年間追及が可能かを理解することで、申告漏れを安易に放置する危険性をご理解いただけるでしょう。
相続税の税務調査実施状況 - 調査を受けた8割以上で申告漏れ発覚
先述したように国税庁の令和5事務年度調査によれば、相続税の実地調査を受けた8,556件のうち、84.2%にあたる7,200件で申告漏れ等の非違が指摘されました。これほど多くのケースで不備が発覚していることから、申告漏れは相当な高確率で「バレる」ものと考えておいたほうが良いでしょう。
税務署が把握している膨大な情報網
税務署は被相続人や相続財産に関して多くの情報源を持っており、申告漏れを発見する手がかりとしています。
不動産関連情報
被相続人が死亡時に保有していた不動産の情報は、法務局の登記情報や市町村の固定資産税台帳から把握可能です。
金融機関からの情報
銀行や証券会社の口座残高・取引履歴、生命保険の支払記録などは金融機関からの報告により税務署が把握しています。
過去の所得・納税記録
被相続人の生前の所得や納税記録から、申告されていない財産の存在が推測される場合があります。
資金の流れの追跡
特に大口の現金の動きや、不動産の名義変更状況などは重点的に確認されるため、そうした点から申告漏れは見破られやすいのです。
相続税の時効(除斥期間) - 原則5年、悪質な場合は7年
相続税の時効は、法定申告期限から原則5年です。これは国税通則法第70条1項に明確に定められています。
国税通則法第70条1項では「次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。」と規定されています。
また、法定申告期限は相続の開始があったこと(通常は被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月なので、相続税の時効は原則として、亡くなったことを知った日から5年10か月後ということになります。この期間を経過すると、税務署は追加の課税処分ができなくなります。
悪質な場合の時効延長 - 7年間の追跡
ただし、意図的な財産隠しや虚偽の申告など悪質な行為が認められた場合には、時効期間が7年(亡くなったことを知った日から7年10か月後)に延長されます。これは隠蔽や仮装などの不正行為に対する厳格な措置として設けられており、単純なミスによる申告漏れとは明確に区別されています。
時効成立の実際的な困難性
多額の財産を隠蔽して5年間逃げ切れば税金を払わずに済むと考える人もいるかもしれませんが、現実的には極めて困難です。税務署は広範囲にわたる情報収集能力を持っており、金融機関からの報告や不動産登記の変更、過去の所得状況など多角的な視点から財産の動きを把握しています。
税務調査のタイミングは納税者がコントロールできるものではなく、仮に時効成立直前であっても調査により申告漏れが発覚すれば、当然ながら追徴課税の対象となります。実際に「バレずに5年間逃げ切る」ことは現実的ではありません。
時効前発覚時のリスクとペナルティ
時効が成立する前に申告漏れが発覚した場合、本税に加えて後述する各種加算税や延滞税が課されることになります。さらに、意図的な隠蔽が立証された場合には重加算税の対象となり、最悪の場合は脱税として刑事罰(懲役刑や罰金刑)が科される可能性もあります。
また、滞納が続けば最終的には滞納処分として財産の差押えなどの強制徴収措置が取られるリスクもあります。これらのペナルティを考慮すると、申告漏れを放置して時効を期待することは、リスクとリターンが全く見合わない極めて危険な行為と言えるでしょう。

松井 信行
記事監修者からのワンポイントアドバイス
「被相続人の預貯金口座から少しずつ引き出して自宅に現金で置いておけば税務署も分からないだろう」と思われるかもしれませんが、税務署には長年蓄積してきた被相続人の所得や財産に関する膨大な情報があります。
また、被相続人が亡くなった事実を市役所等から知らされると、税務署はそれらの情報に加えて被相続人のみならずその配偶者や子・孫といった相続人の預貯金口座等についても必要に応じて過去10年間遡って入出金履歴を調査します。
それによって被相続人の財産が生前どこにどの程度あったかがおよそ推測できることから、あるべきはずのものが相続財産として申告されていなければ更に詳しく調査することになります。
最近は情報の入手先も国内にとどまらず海外の金融機関や税務当局にまで拡がっていますので、海外資産も含めて財産を隠し通すことは難しいと考えるのが賢明でしょう。
申告漏れで課される厳しいペナルティ一覧
申告漏れが発生した場合に課される主なペナルティ(追徴課税)について整理します。相続税の申告漏れや納付遅れに対しては、追加の税金や延滞金が科されます。具体的には、期限までに税金を納めなかった場合の延滞税、申告した税額が過少だった場合の過少申告加算税、申告をしなかった場合の無申告加算税、そして悪質な隠蔽等があった場合の重加算税といった種類があります。
延滞税 - 日割りで増え続ける利息相当額
延滞税は、本来の納期限までに納税しなかった場合に課される「延滞利息」です。期限日から実際に納付する日までの日数に応じて日割りで算出されるもので、年利(例えば直近では最大14.6%)で日割計算されるペナルティです。
詳細な延滞税の計算方法や税率については、国税庁の延滞税についてをご参照ください。
要するに、支払いが遅れたことによるペナルティとして利息相当額を追加で納めるものです。申告漏れで追徴課税を支払う際には、この延滞税が加算されるため、漏れに気づいたら一日も早く納付することが重要です。
過少申告加算税 - 申告額不足に対する10~15%の追徴
過少申告加算税は、申告した相続税額が本来より少なかった場合に、その不足分に対して課される追加の税金です。税務調査などで申告漏れが発覚し、修正申告により税額が増えた場合に賦課されます。
基本的な税率
加算税の税率は不足税額に対して概ね10%~15%が基本ですが、状況により変動し、悪質な場合には後述する重加算税の対象となります。
自主修正による免除
また、税務署から調査の連絡を受ける前に自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税が課されない取り扱いとなっています。つまり、早めに誤りを訂正すれば、このペナルティを回避できる制度になっています。
無申告加算税 - 申告しなかった場合の重いペナルティ
無申告加算税は、期限までに相続税申告をしなかった場合に課される加算税です。期限後に申告(期限後申告)をしたときや、税務署が指摘して追徴課税を行う際に賦課されます。
税率の詳細
税率は本来納めるべき税額に対して原則5~20%程度ですが、過少申告加算税と比べて全体的に高めに設定されています。期限後1か月以内に自主的に申告すれば加算税はかからない特例がありますが、それ以降は調査通知前に自主的に申告しても5%、調査通知後に申告すると10~20%になるなど、申告が遅れたことに対する厳しいペナルティとなっています。
令和5年度の税制改正による厳罰化
さらに、令和5年度の税制改正により納付すべき税額が大きいケースでは加算税率が引き上げられ、具体的には50万円超~300万円以下部分は20%、300万円超の部分は30%もの税率が適用されることになりました。このように、無申告に対する罰則は年々強化される傾向にあります。
重加算税 - 悪質な隠蔽に対する最大40%の重罰
重加算税は、財産の隠蔽や仮装など悪質な行為によって申告漏れが発生した場合に科される最も重いペナルティです。通常の過少申告加算税等に代わって適用され(重加算税が課された場合、他の加算税は課されません)、税率は非常に高く設定されています。
重加算税の税率
具体的には、正しく申告していれば課税されていたはずの税額に対して、申告書を提出していた場合は35%、申告書自体を提出していなかった場合は40%もの重加算税が上乗せで課されます。
適用される行為
故意の隠蔽が認定されるとこのように厳しい罰則となるため、絶対に意図的な申告漏れは行わないようにすべきです。
申告漏れを確実に防ぐための3つの重要ポイント
そもそも申告漏れを起こさないことが何より重要です。相続税の申告漏れを未然に防ぐために有効なポイントとして、「早めの着手」「財産や贈与の記録管理」「専門家への相談」の3点が挙げられます。これらを実践することで、申告漏れの発生を大幅に減らすことができるでしょう。
早期着手が成功の鍵 - 10か月の期限を有効活用
相続が発生したら、できるだけ早い段階で相続税申告の準備に着手することが重要です。相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内ですが、葬儀後のできる限り早い時期から遺産の洗い出しや相続人同士の話し合いを進めることで、申告漏れのリスクを減らせます。
時間的余裕の確保
時間に余裕があれば、被相続人の預貯金口座や証券口座、不動産の名寄帳などを漏れなく調査することで、忘れがちな財産も見逃さずに済みます。
生前準備の重要性
また、将来的に相続が予想される段階であっても、生前準備として財産目録を作成するなど早めの対策をしておくと安心です。
記録管理の徹底 - 証拠書類で申告漏れの疑いを回避
生前に行われた贈与や、相続発生前後に家族間で行った資金のやり取りについては、必ず書面や記録を残しておきましょう。
口約束の危険性
口頭の約束や認識だけでは、後から税務署に指摘された際に証明ができず、結果的に申告漏れと同様に扱われてしまうことがあります。
必要な記録の例
特に預金の名義変更や現金の受け渡しなどは、贈与契約書や領収書を交わすなど、第三者にも説明できる形で記録しておくことが大切です。
証拠の効果
こうした証拠があれば、本来生前贈与加算の対象ではない贈与分まで相続財産に計上されることを防ぎ、申告漏れの疑いを晴らすのにも役立ちます。
専門家活用のメリット - 税理士への相談で安心確実な申告
相続税の申告漏れを防ぐうえで、相続に強い税理士など専門家の力を借りることも非常に有効です。
専門知識の活用
税理士は相続財産の調査や評価に習熟しており、素人では見落としがちな財産や特例の適用漏れなども含めて、正確に申告書を作成してくれます。
時間と労力の節約
また、相続税の計算は複雑で、専門知識がないと対応が難しいケースも多いため、プロに依頼することで時間と労力の節約にもなります。
費用対効果の考慮
費用はかかるものの、後から申告漏れで追徴課税を受けるリスクを考えれば、専門家に相談・依頼して適切に申告を行う価値は大きいでしょう。
申告漏れが判明した場合の適切な対処法
万一申告漏れが判明した場合の対応策を解説します。自分で漏れに気付いた場合と、税務調査で指摘された場合では対応方法が異なりますが、いずれも迅速かつ誠実な対応が重要です。
自主発覚時の対応 - 速やかな修正申告でペナルティ軽減
自身で相続税の申告漏れに後から気付いた場合は、一刻も早く自主的に申告内容の訂正(修正申告)や、未申告であれば期限後申告を行うことが重要です。
加算税の軽減効果
税務署から連絡が来る前に不足分を申告・納税すれば、過少申告加算税や無申告加算税といった加算税が最小限で済む可能性があります。
延滞税の増加防止
一日でも放置すれば延滞税も増えていくため、発覚を恐れて先延ばしにするのではなく、早期に正直に申告し直す方が結果的に有利です。
専門家への相談
必要なら税理士に手続きを依頼し、適切な修正申告書の作成と納税を速やかに完了させましょう。
税務調査対応のポイント - 誠実な対応で重加算税を回避
税務署から相続税の税務調査(問い合わせや現地調査)が入った場合は、落ち着いて真摯に対応することが大切です。
基本的な対応姿勢
調査官の質問には事実に基づいて簡潔に答えることを心掛け、要求された書類や資料は速やかに提出しましょう。感情的になったり、指摘に反発したりすると状況が悪化しかねません。
隠蔽行為の絶対禁止
特に、申告漏れを指摘された財産について新たに隠そうとしたり虚偽の説明をしたりすれば、重加算税の対象となる可能性が高まります。
建設的な対応
現地調査の段階では既に申告漏れが顕在化している可能性が高いため、税務署側の認識や指摘に間違いが無ければ潔く不足分の納税に応じる姿勢を示すことが重要です。
専門家のサポート
また、必要であれば税理士に速やかに相談し、調査への対応方法や主張すべきポイントについてアドバイスを受けると良いでしょう。専門家の助けを借りることで、調査後の修正申告や追徴課税の手続きもスムーズに進めることができます。
滞納時のリスク - 財産差押えの可能性
最悪の場合、滞納が続けば財産の差押えなど強制徴収の措置も取り得るため、指摘を受けた税額や延滞税は速やかに納付してください。
まとめ:申告漏れのリスクを回避し、安心な相続手続きを実現しよう
相続税の申告漏れについて、その原因やペナルティ、防止策と対処法を詳しく見てきました。申告漏れは決して稀な問題ではなく、多くの相続で起こり得る身近なリスクですが、放置すれば多額の追徴課税や延滞税といった厳しいペナルティを受ける可能性があります。
しかし、早めに準備を進めて正確に申告すること、万一漏れに気付いたら速やかに修正すること、そして専門家に相談することで、こうしたリスクは大きく減らすことができます。特に以下の3点を心がけることが重要です。
まず、相続発生後はできるだけ早期に財産調査に着手し、10か月の申告期限を有効活用して漏れのない申告を目指しましょう。
次に、生前贈与や資金移動については必ず書面で記録を残し、後から疑義を持たれないよう証拠を整備しておくことが大切です。
そして最も重要なのは、相続税に精通した税理士など専門家の力を借りることです。
相続税の申告に不安がある方や、自分では把握しきれない財産がありそうな場合は、ぜひ相続財産センターにご相談ください。相続財産センターでは、相続税申告の経験豊富な税理士を無料でご紹介しており、専任のコーディネーターがお客様のご状況に最適な専門家をマッチングいたします。
プロのサポートを受けることで適切な申告と安心を得られるはずです。大切な財産を守るためにも、申告漏れの不安は専門家とともに早めに解消していくことが大切です。