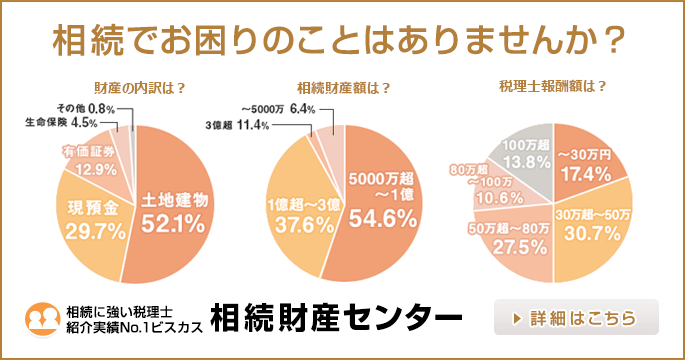儲けや資産に公平にかけられる税金。課税内容は、法律でさぞや明快に決められているかと思いきや、実際には資産などの評価の仕方によって支払額が大幅に変わる、といった“グレーゾーン”が、予想以上に広いのです。しかも、法律自体もネコの目のように変わるから、一筋縄ではいきません。今回は、「だからこそ、常日頃の情報収集が欠かせない」と語るイノベンス税理士法人の岩村浩秀先生に、注意すべき相続対策あれこれをうかがいました。
税は政策で変わり、「時代」でも変わる。
大事なのは、たゆまぬ情報収集です

2018/5/8
宅建士向け法定講習の講師が語る、不動産の“今”
含み損のあるマイホームは、「損切り」できることも

先生は、不動産協会と神奈川県宅地建物取引業協会の「宅地建物取引士」法定講習の税務担当講師という肩書をお持ちです。

はい。宅建士向けの法定講習講師として、税務を教えているんですよ。当然のことながら、人に教える以上、それなりに勉強しなくてはなりません。特に、関連する法律や通達の類は、常に最新情報を仕入れておかないと、嘘を伝授することにもなりかねませんから。本業の傍らそれをやるのは大変ではありますけど、逆にそうした勉強が税理士としての仕事に役立つことも、多々あります。
話の中身は、基本的に不動産を扱う人間ならば知っておかなければならない論点についてなのですが、けっこう実戦的なテーマを扱うんですよ。例えば、ミニバブルの時にマンションなどを買ったのだけど、その後住宅価格は値下がりし、今現在結構な額の含み損を抱えている方も少なくないでしょう。そんなふうに、「しまった」と頭を抱えている人には、さっさとマイホームを買い換えて「損切り」する手があるんですね。
話の中身は、基本的に不動産を扱う人間ならば知っておかなければならない論点についてなのですが、けっこう実戦的なテーマを扱うんですよ。例えば、ミニバブルの時にマンションなどを買ったのだけど、その後住宅価格は値下がりし、今現在結構な額の含み損を抱えている方も少なくないでしょう。そんなふうに、「しまった」と頭を抱えている人には、さっさとマイホームを買い換えて「損切り」する手があるんですね。

具体的に教えてください。

旧住宅を売って、新たに住宅を購入した結果生じた「譲渡損失」は、一定の要件を満たせば、その年の給与所得や事業所得といった他の所得から控除することができるのです。例えば、家の買い換えで2000万円の譲渡損失が出たとします。そうすると、その年の2000万円分の所得と相殺できるんですね。所得が2000万円だと、所得税+住民税で約40%=800万円ほどの税金を納める必要があるのですが、それが丸々「免除」されるわけです。これを譲渡損失の「損益通算の特例」と言います。

損失が大きい場合には、かなりのメリットがありますね。

しかも、その年に控除しきれなかったら、翌年以降、譲渡の3年以内に繰り越すことができる「繰越控除の特例」も認められているんですよ。今の例だと、その年に所得が1500万円だったら、500万円分は翌年「使う」ことができます。
このテクニックのポイントは、含み損が出るご時世というのは、売りに出ている物件も割安感があるということです。税金で得をした上に、以前と同等以上の条件の住宅に住み換えられる可能性も広がるわけですよ。
このテクニックのポイントは、含み損が出るご時世というのは、売りに出ている物件も割安感があるということです。税金で得をした上に、以前と同等以上の条件の住宅に住み換えられる可能性も広がるわけですよ。

「ピンチをチャンスに」というようなお話です。バブルのような時期に比べれば、住宅価格が落ち着いている局面だからこそ、使える技なんですね。

そういうことです。まあ教科書にもちらっと載っている話ではあるのですけれど、現場の不動産屋さんなどは、意外とそういうことに気づいていないのです。
不動産屋さんが知らないと言えば、今のように不動産の売却で得た所得=譲渡所得には、長期譲渡所得と短期譲渡所得があるんですね。分岐点は、「売却する不動産を、5年を超えて所有しているかどうか」です。実はこの分岐点には大きな意味があって、前者すなわち5年を超えて所有していた物件を売る場合にかかる税金=譲渡所得税と住民税を合わせた税金の税率が約20%なのに対して、後者は倍の約39%にハネ上がるのです。「不動産を投機目的で短期に売り買いするのなら、高い税率をかけますよ」ということなんですね。

分岐点に近かったら、今の投機目的だとか、よほどの事情がない限り、「5年が過ぎてから売ろう」という気持ちになるでしょう。

そこで問題になるのが、「5年」という期間の判断です。普通の感覚だと「買ってから売るまで5年」になると思うのですが、正解は「譲渡した年の1月1日現在で5年が経過していること」なのです。これを誤解している人がけっこういて、例えば、「今年の3月で、買ってから5年だから」と売ったら、その年の1月1日時点では4年10ヵ月しか経っていなかった、という悲劇が起こり得るわけです。
これはさっきの話とは反対で、「手持ちの不動産に含み益があるから、このタイミングで売りたい」といった場合に、気をつける必要があるでしょう。利益が出ても、高い税率を課せられては、元も子もありませんから。
これはさっきの話とは反対で、「手持ちの不動産に含み益があるから、このタイミングで売りたい」といった場合に、気をつける必要があるでしょう。利益が出ても、高い税率を課せられては、元も子もありませんから。
よりシビアになった相続税と譲渡所得税の「二重課税」

直接相続に関わる問題では、最近大きな変更のあった点の1つが、不動産に対する相続税と譲渡所得税の課税方法なんですよ。この点は、これまでも税の二重取り、「二重課税」ではないかという批判があります。

大枚の相続税を払って取得した不動産を売ったら、今度は譲渡所得税を取られる……。

そうです。特に問題になるのが、先祖代々の土地を相続したのはいいけれど、相続税が高すぎて手持ちの現金では賄いきれない。泣く泣く相続した土地の一部を売って納税資金に充当しようというのに、売れば譲渡所得だからと、それにも税金がかかってくる、というパターンです。
こうした税金の徴収については、学者も含めた論争があり、裁判にもなりました。ただ、税務当局は、「相続のために払う相続税と、売却不動産の値上がり益=含み益に課税する譲渡所得税はまったく次元が違う税であり、二重課税には当たらない」という認識で一貫しているわけです。
こうした税金の徴収については、学者も含めた論争があり、裁判にもなりました。ただ、税務当局は、「相続のために払う相続税と、売却不動産の値上がり益=含み益に課税する譲渡所得税はまったく次元が違う税であり、二重課税には当たらない」という認識で一貫しているわけです。

では、「最近の変更」とは何ですか?

譲渡所得税の計算式は、さきほど説明した長期譲渡であれば、「(売却金額-取得費-諸経費)×20%」となるんですね。実は税務当局は、「譲渡所得税を取るのは二重課税ではない」という原則を貫きつつ、今の取得費に相続税を加算するのを認めていたんですよ。なおかつ、土地の場合は、その一部分を売却した場合であっても、相続した土地すべてにかかった相続税をそこに含めることができました。
例えば、10億円の評価の土地を相続して、4億円の相続税を支払うとします。納税資金がきついので、受け継いだ土地の一部を売って、2億円用立てました。このパターンをさきほどの式に当てはめると、取得費に加算できる相続税額4億円が売却額2億円を上回りますから、譲渡所得税はゼロになるのです。
例えば、10億円の評価の土地を相続して、4億円の相続税を支払うとします。納税資金がきついので、受け継いだ土地の一部を売って、2億円用立てました。このパターンをさきほどの式に当てはめると、取得費に加算できる相続税額4億円が売却額2億円を上回りますから、譲渡所得税はゼロになるのです。

このケースでは、売った土地に含み益はなかった、という判断になるわけですね。土地にかかった相続税を丸々取得費にできるのならば、譲渡所得税の縮減効果は大きいように感じます。

ところが、法改正により状況は変わりました。2015年1月以降に発生した相続では、実際に売った土地に対応する相続税分しか、取得費に加算できなくなったんですよ。これがどれくらいインパクトの大きな変更なのかというと、今の例だと、受け継いだ土地すべての評価額が10億円でしたよね。売却したのはそのうち2億円ぶんですから、それに対応する相続税は、4億円の5分の1=8000万円と判断されるわけです。諸経費などを省いて単純計算すると、(2億円-8000万円=1億2000万円)×20%で、なんと2400万円もの譲渡所得税を覚悟しなくてはならなくなったのです。

不動産をたくさん持っている人にとっては、大問題です。

「実際に譲渡した土地の相続税分だけを、取得費として認める」という法改正が、理屈として間違っているのかといえば、一概にそうとは言えないかもしれません。一方、できれば全部守りたかった代々の土地を手放してまで納税するのに、その仕打ちはひどいという相続人の心情も、痛いほどわかります。

なんとも割り切れないというか……。

税というのは、時として、そのような矛盾が避けられない仕組みなんですね。いずれにせよ、相続になってから何かテクニックを駆使しようと思っても手遅れ。「そんなバカな」ということにならないためには、まずはそういう事実を知ること。慌てることのないように納税資金の調達方法を考えておくとか、遺産分割の仕方を工夫するだとか、事前の準備がとても大事になるのです。
意外に知らない相続の「怖さ」「難しさ」
なぜか少額遺産のほうが揉める

これまで、いろんな相続を経験されてきたと思います。印象に残る事例には、どんなものがありますか?

納税資金の問題だとかは物理的に解決できるのですが、やはり相続自体が揉める、いわゆる「争続」は大変ですね。以前、105歳で大往生された方の相続を頼まれたことがあって、それは骨が折れました。すでに亡くなっている子どももいて、代襲相続(※1)の対象になる孫も含め、法定相続人が20人近くいたんですよ。孫の中には、海外に移住して、連絡の取りにくいような人もいた。そんな相続人たちが、それぞれ自由気ままなことを言うわけです。

そういう状況だと、お互いをあまり知らない相続人も多いでしょうから。

そうです。そもそも、亡くなった方は大資産家というほどでもなかったし、それだけ相続人がいるのだから、1人当たりの取り分も、多くて数百万円程度だったのです。ちなみに、結局相続税は課税されず、従って税務署への申告もしませんでした。

それだけ相続人がいれば、基礎控除(※2)に収まる可能性が高いでしょう。

ところが、そんなレベルの相続にもかかわらず、争いになるのです。経験上、相続はもらう遺産が少額なほど揉めやすい。裏返せば、「金持ち喧嘩せず」なんですね(笑)。結局この案件は、法定相続分(※3)に近い形で折り合いがついたわけですが、2年近くも争ったでしょうか。
あと、必ずと言っていいほど揉めるのが、死んだお父さんの戸籍謄本を取り寄せてみたら、「知らない親族」が記載されていたというような相続。
あと、必ずと言っていいほど揉めるのが、死んだお父さんの戸籍謄本を取り寄せてみたら、「知らない親族」が記載されていたというような相続。

それは、愛人の子どもとかですか?

そうですね。家族の知らない誰かを養子にしていたりするケースです。あるいは、薄々気づいていた子どもたちはあえて無視していたけれど、いざ相続になったので、仕方なく「先生、実はどこそこにもう1人相続人がいます」というような告白をされることもあります。逆に先方から、「私は今まで日陰者の身で……」なんていう手紙をいただくことも。

聞いているだけで、「争続」の臭いがしてきます。

ただし、私たちの仕事は、あくまでも税金に関わる部分をうまくまとめて、相続人の利益になるよう貢献すること。ですから、おかしな争いになりそうな場合は、弁護士さんなどの力も借りて解決を図るわけですね。まあ、そんな案件ほど、印象には残るのですが(笑)。
※1 代襲相続
本来、血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していた時などに、その子や孫が代わって相続人になる、という制度。被相続人の子が亡くなっていた場合には、その子(被相続人の孫)が相続の権利を持つ。
※2 相続税の基礎控除額
課税のボーダーラインとなる金額。「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、遺産総額がこれ以下なら相続税はかからない。
※3 法定相続分
民法に定められた、被相続人の遺言書がない場合の、相続人の遺産の取り分。
本来、血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していた時などに、その子や孫が代わって相続人になる、という制度。被相続人の子が亡くなっていた場合には、その子(被相続人の孫)が相続の権利を持つ。
※2 相続税の基礎控除額
課税のボーダーラインとなる金額。「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、遺産総額がこれ以下なら相続税はかからない。
※3 法定相続分
民法に定められた、被相続人の遺言書がない場合の、相続人の遺産の取り分。
最も効果的な相続税対策は2つ

相続税対策、要するに「支払う相続税をできるだけ少なくするために打てる手立て」というのは実はシンプルで、2つなんですよ。1つは、現金で持っているとそのまま100%の金額に課税されてしまうから、不動産や金融資産といった「相続価値」を下げられるものに変えること。もう1つは、養子をもらって法定相続人を増やすことです。さきほどの話にも出てきたように、相続人が増えれば基礎控除額が広がって、相続税を支払うにしても、その金額を圧縮することができますから。

ただ、闇雲に養子を取ったりすると、それが親族間に軋轢(あつれき)を呼んで、争いのタネになるという話も聞きます。

もちろん、事前に家族で十分話し合うことが必要になるでしょう。先々を見越した検討が不可決なのは、不動産の購入にも言えることで、ただ「税金が下がるから」というだけで「対策」すると、痛い目に遭う危険性はあります。
特に、ローンを組んで賃貸アパートなどの事業物件を購入する場合は、そこにきちんと入居者が入ってくれるのかどうか、見極めなければなりません。このところ、大都市圏ではバブル期並みに高騰しているような物件もありますから、それが弾ける可能性も念頭に置くべきでしょう。当てが外れると、確かに相続税は節約できたけれど、トータルコストでマイナスになってしまった、などという笑えない話になりかねません。
特に、ローンを組んで賃貸アパートなどの事業物件を購入する場合は、そこにきちんと入居者が入ってくれるのかどうか、見極めなければなりません。このところ、大都市圏ではバブル期並みに高騰しているような物件もありますから、それが弾ける可能性も念頭に置くべきでしょう。当てが外れると、確かに相続税は節約できたけれど、トータルコストでマイナスになってしまった、などという笑えない話になりかねません。

不動産は大きな買い物ですから、慎重を期す必要がありますよね。
ところで、土地の「時価」とは?

確かに相続税の節約にはなるけれども、それだけに申告の時に我々が非常に気を使うのも、不動産なんですね。例えば、相続税法には「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による」と定められています。平たく言えば、「相続税課税のベースになる不動産価格は、時価になります」ということなのですが、では、「時価」はどうやって決めて、申告したらいいのか?

「時価」といえば、普通は「その時点での取引価格」「実勢価格」を指します。

被相続人である父親が、亡くなる間際に買ったタワーマンションを子どもが相続し、その物件を国税庁の財産評価基本通達に則って5000万円と評価して申告した半年後、3億円で売却した――という事例がありました。その後の税務調査で申告は否認され、結局3億円の「時価」に課税されたのですが、これなどは、ある意味わかりやすいケースでしょう。実際には「いくらにするのか」は、簡単な話ではありません。言い方を変えると、「時価」にもいろいろあるのです。
土地に関して言うと、今お話しした財産評価基本通達では、路線価(※4)などを基に評価額を算出することになっています。この路線価は、基本的に国税庁が実勢価格に位置付ける公示価格(※5)の8割で決められているんですね。税法の本などには、どこにも8割という数字が出てこないのですけど、内部ルールでそうなっている。
土地に関して言うと、今お話しした財産評価基本通達では、路線価(※4)などを基に評価額を算出することになっています。この路線価は、基本的に国税庁が実勢価格に位置付ける公示価格(※5)の8割で決められているんですね。税法の本などには、どこにも8割という数字が出てこないのですけど、内部ルールでそうなっている。

だから、現金で持つよりも低い評価額になるわけですね。

加えて、同じ面積でも土地の状態は同じではありませんから、様々な補正を行う余地があります。形がいびつだったり、間口が狭かったりといった条件によって、さらに評価額が下げられるんですよ。また、今のやり方とはぜんぜん別に、不動産鑑定士の鑑定結果を基にした評価額でも、それが常に認められるか否かは別に、「不動産の時価」としての意味を持ちます。相続人にとってそちらが有利であれば、選択することが可能です。

要するに、どんな評価をするかによって、「時価」は大きく違ってくる。

それだけに、お客さまをフォローする側にどれだけの引き出しがあるか、税務当局に対してきちんとその正当性を証明する力があるのかどうかが、問われることになるのです。
※4 路線価
毎年国税庁が公表する、道路に面する土地の1平方メートル当たりの評価額。
※5 公示価格
地価公示法に基づいて、毎年1月1日における標準地を選定して「正常な価格」を判定し、公示したもの。
毎年国税庁が公表する、道路に面する土地の1平方メートル当たりの評価額。
※5 公示価格
地価公示法に基づいて、毎年1月1日における標準地を選定して「正常な価格」を判定し、公示したもの。
気をつけたい会社への貸付け

当事務所には、法人のお客さまが数多くいらっしゃいますが、「社長の相続」には、一般の方とは違った問題の生じることがあります。顧問のお客さまには、相続も見越した対策を提案させていただくのですが、急に駆け込んでくるケースなどでは、けっこう困った状況に陥っていることもあるんですよ。私が特に危ないと思うのは、会社に貸付けを行っている社長さんですね。

決して珍しくないと思います。

例えば、社長が会社に5000万円貸した状態で亡くなった場合、その金額がそのまま相続財産に加えられてしまうんですね。5000万円は会社への債権だ、と判断されるわけです。でも、債権といっても、相続した人がそれを会社から返してもらえるのか? 会社が苦しいからこそ、貸したままになっていたのでしょうから、その可能性は低いと言わざるを得ません。

相続人は、返してもらえない親の借金に、税金を支払わなければならなくなる。

そうならないためには、相続発生前に対策を講じる必要があります。1つの手立てとしては、社長が会社に対する債権を放棄する、会社からすると債務免除を受けるという方法があります。そうすれば、5000万円の債権はなくなりますから、相続税の問題はクリアできるでしょう。
ただし、残念ながらそれですべてがOKというわけにはいきません。債務免除により、会社には5000万円の利益が発生したことになるため、今度は会社のほうに法人税が課税されることになるのです。
ただし、残念ながらそれですべてがOKというわけにはいきません。債務免除により、会社には5000万円の利益が発生したことになるため、今度は会社のほうに法人税が課税されることになるのです。

5000万円が消えてなくなるわけではないんですね。

そう。でも、実はその一部を、場合によっては全部を「消す」ことも、会社の状況によっては可能です。赤字を抱えていれば、それと債務を相殺することができるんですよ。繰越欠損金(※6)が膨らんでいるような場合には、それを「活用」すべきでしょう。
とはいえ、たまたま大赤字という、会社にとって好ましからざる状況にないと、このやり方のメリットはあまり生まれません。「自分の会社だから」と安易な気持ちで用立てると、あとあと困った事態を引き起こす危険性のあることを、経営者の方はしっかり認識して欲しいと思います。
とはいえ、たまたま大赤字という、会社にとって好ましからざる状況にないと、このやり方のメリットはあまり生まれません。「自分の会社だから」と安易な気持ちで用立てると、あとあと困った事態を引き起こす危険性のあることを、経営者の方はしっかり認識して欲しいと思います。
※6 青色申告をしている法人は、赤字(欠損金)を最大9年間繰り越すことができる。平成28年度の税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされている。
年間110万円までの「贈与」なら、無条件で非課税か?

こうしたお金の貸し借りの類は、当然、一般の方の相続の際にも問題になることがあります。

例えば、親が子どもにお金を貸した状態で亡くなれば、それは親の債権、すなわち相続財産にカウントされることになります。

以前、こんな事例がありました。旦那さんが亡くなって、調べてみたら10年ほど前に奥さんに1000万円が振り込まれていたんですね。旦那さんから借りたのだったら、おっしゃるように相続財産になります。でも、「もらった」のだったら、それは贈与ですから、1000万円は奥さんのお金ということになります。ただし、贈与に必要な申告はされておらず、贈与税も支払われてはいませんでした。

当事者の一方が亡くなっていますから、判断は難しいですね。

結論を言うと、このケースでは奥さんは1円の税金も払わずにすみました。贈与が認められたうえに、贈与税の時効は6年、意図的に隠したりした場合でも7年ですから、もうそれを過ぎていたのです。

贈与は、年間110万円までなら税金がかかりませんよね。それを利用して、少しずつ子どもなどに生前贈与を行うという相続対策も推奨されています。

ただ、その場合にも「110万円」という金額だけにとらわれていると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。そもそも贈与というのは、する側に「あげる」、受ける側に「もらう」という、双方の意思のあることが前提条件になるんですね。昔よくあった、勝手に息子名義の通帳を作ってそこにせっせと入金していくというようなやり方は、贈与とは認められません。

いわゆる「名義預金」ですね。相続になったら、お父さんの財産としてカウントされてしまいます。

だから、今の「双方の意思」をしっかり証拠に残しておく必要があるのです。さっきも指摘があったように、相続の時には「あげた」ほうはいないわけですから。具体的には、1回ごとに契約書を作成すること。もし忘れていたら、後日の「覚書」でもいいですから、文書にしておいてください。細かなことですが、その際、税務署に痛くもない腹を探られないよう、印鑑は別のものを使うよう、私はアドバイスしています。
また、中には「わざと110万円を超えて贈与を行い、申告しておけば大丈夫」と指南する本などもあるのですが、やめたほうがいいでしょう。「贈与申告している」と主張したにもかかわらず、契約書がないことを理由に贈与とは認められなかった例もあるんですよ。
また、中には「わざと110万円を超えて贈与を行い、申告しておけば大丈夫」と指南する本などもあるのですが、やめたほうがいいでしょう。「贈与申告している」と主張したにもかかわらず、契約書がないことを理由に贈与とは認められなかった例もあるんですよ。
やはりノウハウがものをいう相続税対策

最初にお話ししたように、私は宅建士の講師をしていますし、日常的な勉強、情報収集を欠かさないように心がけています。そういう立場で痛感するのが、税というものがいかに「理論的でない」か、ということなんですよ。得てして、理屈の前に政策が顔を出すのです。
例えば、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に、ローンの一部に相当する金額が所得税や住民税から控除される「住宅ローン控除」制度があります。国税庁は廃止したいというのが本音で、実際にかなりの確度をもって「来年度から打ち切り」という話がアナウンスされたことが、何度かありました。それを信じて、お客さまに住宅の買い替えを勧めたら、その数ヵ月後に、延長どころか拡充するという話になったり(笑)。制度を廃止すると、住宅購入が陰って景気に悪影響を及ぼすのではないか、という懸念があるからに他なりません。
例えば、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に、ローンの一部に相当する金額が所得税や住民税から控除される「住宅ローン控除」制度があります。国税庁は廃止したいというのが本音で、実際にかなりの確度をもって「来年度から打ち切り」という話がアナウンスされたことが、何度かありました。それを信じて、お客さまに住宅の買い替えを勧めたら、その数ヵ月後に、延長どころか拡充するという話になったり(笑)。制度を廃止すると、住宅購入が陰って景気に悪影響を及ぼすのではないか、という懸念があるからに他なりません。

税の公平性とかではなく、まさに政策で動くわけですね。

そういう意味では、生き物というか……同じ行為なのに「時代」によって課税の判断が変わってくることもあるんですよ。これも相続とは直接関係ないのですが、面白い例を紹介しましょう。社長が会社の経費で車を購入しますよね。かつて、ポルシェを買ったお客さまがいて、「社会通念上、認めがたい」と言う税務官とやり合ったことがあるのですが、そんな私でも、さすがにフェラーリとなると、「社用ではなく趣味の領域だ」という指摘に反論できませんでした。しかし、「時代は変わった」のです。

どのような変化ですか?

近年、中古のフェラーリに高値が付くようになりました。こうなると、使うための動産というよりも資産。減価償却(※7)しないで、簿価のままにしておけば、投資とみなすことができるはずです。

将来売却すれば、会社の利益になるから。

そういうことです。実際、その論点を主張して、税務署にも認められたんですよ。中古のスポーツカー市場が盛り上がったからこそ、使えた技です。

今のお話も大変面白いのですけれど、やはりそれなりの蓄積がないと、そういう論点で税務署と対峙する勇気は出ないと感じます(笑)。

特に相続税、資産税は扱う金額も大きいですから、ノウハウを持っているかどうかで、結果はかなり違ってくると思います。お手伝いする側からみれば、リスクも背負うわけですね。

税理士の先生の中には、「怖いからその分野には触らない」という方もいます。

私自身、この世界でのキャリアは20年を超え、今では、税務調査は一種の“ディベート”で、自分が申告した案件に関しては絶対に負けない自信があります。でも、振り返ると、若い頃はよくあの程度の知識でやっていたな、と思いますね(笑)。
実際の相続では、税法の本に載っていないことが当たり前のように起こるし、お話ししてきたように、理論で説明のつかない事態も起こる。そうした部分にも対応する、懐の深さが求められるのです。
実際の相続では、税法の本に載っていないことが当たり前のように起こるし、お話ししてきたように、理論で説明のつかない事態も起こる。そうした部分にも対応する、懐の深さが求められるのです。

特に大きな資産をお持ちの方は、なにより信頼できるプロを選ぶことが大事なんですね。
※7 減価償却
機器、設備などの固定資産は、年々価値が減少していく。その目減り分を費用として計上すること。
機器、設備などの固定資産は、年々価値が減少していく。その目減り分を費用として計上すること。
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士は聞いた!お金の現場
- 税は政策で変わり、「時代」でも変わる。 大事なのは、たゆまぬ情報収集です

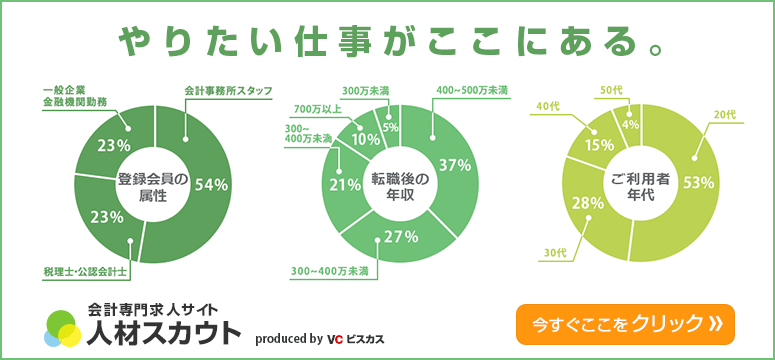
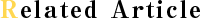 -あなたにおすすめの記事-
-あなたにおすすめの記事-
-あなたにおすすめの記事-
-
去年と今年、ガラリと変わった「相続環境」

2015.8.7
-
子どもの「争続」を助長する親の態度

2016.1.19
-
メリットとリスクを比較しよう ~本当は怖い「事業承継税制」・その3~

2019.2.20
-
予想外の感情があふれ出る それも相続の真実です

2017.8.7