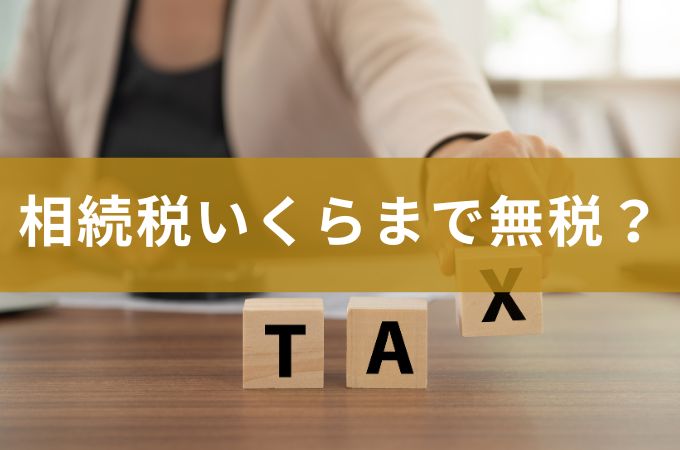相続税がかからない金額の目安
相続税には基礎控除額があり、通常(暦年課税の場合)は課税価格(プラスの財産-マイナスの財産+生前贈与財産)の合計が基礎控除額以下であれば、相続税は課されず申告も不要です。
ただし、特例により税額がゼロになる場合は申告が必要であり、不動産評価等の見直しにより基礎控除を上回る可能性もあるため留意してください。
基礎控除額は、被相続人の遺産額(課税価格の合計額)から無条件で差し引くことができる金額で、法定相続人の数によって変動します。
例えば、課税価格が1億円で基礎控除額が4,800万円の場合、相続税が課税されるのは5,200万円となります。一方、課税価格が基礎控除額以下であれば、課税される遺産額はゼロとなり、相続税は発生せず、原則として税務署への申告も不要です。
なお、課税価格が基礎控除額を1円でも超えた場合は申告が必要となります。
基礎控除額の計算式と家族構成別の早見表
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人が最少の1人の場合、基礎控除額は3,600万円になります。つまり、課税価格が3,600万円以下ならば、相続人の数にかかわらず税金はかかりません。そして、相続人が1人増えるごとに、600万円ずつ基礎控除の枠が広がります。
例えば、相続人が妻と子ども2人の計3人だった場合には、3,000万円+600万円×3=4,800万円となり、課税価格が4,800万円以下であれば、相続税は課税されません。
家族構成別基礎控除額早見表
| 相続人の構成 | 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1人 | 3,600万円 |
| 配偶者+子1人 | 2人 | 4,200万円 |
| 配偶者+子2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者+子3人 | 4人 | 5,400万円 |
| 配偶者+子4人 | 5人 | 6,000万円 |
| 子のみ1人 | 1人 | 3,600万円 |
| 子のみ2人 | 2人 | 4,200万円 |
| 子のみ3人 | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者+父母 | 3人 | 4,800万円 |

松井 信行
記事監修者からのワンポイントアドバイス
相続税の基礎控除額は前述の算式で定められていますので、被相続人の「法定相続人の数が何人なのか」ということが大事になります。
つまり、被相続人の「法定相続人が誰なのか」、そして基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数が何人になるのか」を間違えないようにしなければなりません。
具体的には、後述される法定相続人の順位や代襲相続の範囲、養子の有無・人数などによって"法定相続人の数"が変わってきますので注意が必要です。
また、相続財産の課税価格については、被相続人が生前保有していた本来の相続財産だけでなく、後述されるみなし相続財産や一定の生前贈与財産などがある場合には相続財産に含めて計算することを忘れないようにして下さい。
よくあるケース別の無税ライン
実際の相続でよく見られる家族構成での無税ラインを具体例で確認しましょう。
配偶者のみの場合
夫婦に子どもがいない場合で、被相続人に直系尊属(父母や祖父母等)や兄弟姉妹がいなければ、法定相続人は配偶者1人となり、基礎控除額は3,600万円です。課税価格がこの金額以下であれば相続税はかかりません。なお、配偶者が唯一の相続人である場合は、後述する配偶者の税額軽減により実務上はゼロとなります(ただし、税額軽減を適用する場合は申告が必要)。
配偶者+子1人の場合
法定相続人が2人となり、基礎控除額は4,200万円です。例えば、課税価格が4,000万円の場合、基礎控除額内に収まるため相続税は発生しません。
配偶者+子3人の場合
法定相続人が4人となり、基礎控除額は5,400万円です。子どもが多い家庭では、無税の範囲が広がります。
子のみ複数人の場合
配偶者が既に亡くなっており、子ども2人が相続する場合、基礎控除額は4,200万円となります。課税価格が4,000万円であればやはり相続税は発生しません。
これらの計算では、課税価格が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからない点が重要です。

松井 信行
記事監修者からのワンポイントアドバイス
課税価格の合計額が基礎控除額を超えていなければ、通常、相続税の申告は不要ですが、その基になっている"課税価格"を見誤っていると元も子もありません。
例えば、相続人以外の者が受け取った生命保険金や名義は被相続人以外の口座でもその原資を生前に被相続人が拠出・管理していた預貯金(いわゆる名義預金)など、相続財産に含めるべきものを含めていない場合です。
また、相続財産の土地を評価する際に『小規模宅地等の特例』の要件を満たしていないにもかかわらず適用して申告するなど、相続財産の価額を過少に評価してしまっているような場合です。
いずれも課税価格の計算に大きく影響してきますので、正しく計算し直すと課税価格が基礎控除額を超えることになって、後日税務署から指摘や調査を受けるケースがよく見受けられます。
法定相続人の数え方
基礎控除額の計算で基礎となる「法定相続人」の正しい数え方を解説します。法定相続人の範囲や順位、特殊なケースでの注意点を理解することが重要です。
相続人の範囲と順位
法定相続人には明確な範囲と順位が定められています。
まず、被相続人の配偶者は、常に法定相続人です。それ以外の親族に関しては、第1順位~第3順位までが決められており、前の順位の者が1人でもいる場合には、後の順位の者は相続人にはなれません。
例えば、子どもが1人でもいれば、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
法定相続人の順位
| 順位 | 相続人 | 代襲相続 |
|---|---|---|
| 常に(順位なし) | 配偶者 | - |
| 第1順位 | 子ども | 孫・ひ孫等(直系卑属) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母等) | - |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥姪(1代のみ) |
代襲相続の具体例 被相続人Aさんに子Bさんがいたが、Bさんが先に亡くなっている場合、Bさんの子(Aさんの孫)が代襲相続人となります。孫も亡くなっている場合は、ひ孫へと続きます。
参考:代襲相続とは?
養子や相続放棄の場合の注意点
法定相続人の数え方では、以下の特殊なケースに注意が必要です。
養子の取扱い
実子に限らず養子も法定相続人となるため、相続税対策として養子縁組が行われることもありますが、基礎控除額の計算で相続人にできる養子の数には制限があります。
- 実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
例えば、実子2人と養子3人がいる場合、法定相続人は5人ですが、基礎控除額の計算では「実子2人+養子1人=3人」としてカウントします。
基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続放棄者の扱い
法定相続人の中に相続放棄をした者がいても、基礎控除額の計算においては「相続人」としてカウントします。相続放棄を行った者は法的な相続人の立場を失いますが、基礎控除額の計算には影響しません。
例えば、配偶者と子2人の計3人が法定相続人で、子1人が相続放棄した場合でも、基礎控除額は4,800万円のまま変わりません。
ただし、相続欠格や廃除による場合は、基礎控除額の計算でカウントできませんので注意が必要です。
遺言による受遺者の扱い
被相続人が遺言書で法定相続人以外の者に遺産を分けていたとしても、その者(受遺者)は法定相続人ではありません。基礎控除額の計算は、あくまでも民法が定めた相続人の人数を基準に行われます。
事実婚などの場合の取扱い
なお、法定相続人として認められる配偶者は、法的に婚姻関係を結んだ相手(役所に婚姻届を提出した場合)に限られます。内縁の妻や愛人は法定相続人ではありません。ただし、これらの関係の間に生まれた実子については、被相続人の認知があれば法定相続人になります。
相続財産と課税対象の範囲
どこまでが相続税の課税対象となる財産なのか、加算・控除の対象も含めて説明します。正確な課税価格の把握が、相続税計算の前提となります。
相続財産の詳細はこちらをご覧ください。
課税対象となる財産・ならない財産
相続税の課税対象となる課税価格は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて計算します。プラスの財産には次のようなものがありますが、中には相続税の課税対象とならないものもあります。
プラスの財産例
- 現金・預貯金
- 株式などの有価証券
- 不動産(土地・建物)
- 貴金属類、骨董品、美術品
- 自動車・家財道具
- 事業用資産
- 貸付金
課税対象とならない財産例
- 墓地・墓石・仏壇・仏具(ただし、投資目的は除く)
- 公益法人等に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利
- 弔慰金(業務上死亡の場合は給与の3年分まで、その他は6か月分まで)
- 損害賠償金(精神的苦痛に対するもの)
- 遺族年金(法定のもの)
生前贈与財産(2024年以降)
被相続人の相続財産ではありませんが、相続等によって財産を取得した者が相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。3年超~7年以内に受けた贈与については、合計100万円まで加算対象外となる経過措置があります。
みなし相続財産
同じく被相続人の相続財産ではないものの、相続税法上は相続財産とみなされる「みなし相続財産」があります。その代表的なものに生命保険金や死亡退職金がありますが、政策的な配慮からそのうちの一定金額までは非課税とされています。
生命保険金の非課税枠
被相続人が被保険者で、かつ保険料を負担していた生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円まで非課税です。この非課税枠を超えた金額が課税対象となります。
非課税枠は相続人が受け取った保険金に限り適用されます。受取人が法定相続人以外の場合(孫、内縁の妻など)は、この非課税枠は適用されず、保険金の全額が課税対象となります。
死亡退職金の非課税枠
被相続人の死亡により勤務先から支給される死亡退職金も、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
これらの非課税枠は、相続税の節税対策として活用されることが多く、基礎控除額とは別に課税価格を抑える一つの有効な手段になっています。
マイナス財産(債務)と債務控除の考え方
課税価格からは、以下のマイナス財産を差し引くこと(債務控除)ができます。
マイナスの財産例
- 借入金
- 未払税金
- 未払医療費
- 公共料金の未払金
- 預り金等
葬式費用の控除
相続人が負担した被相続人の葬祭費用も控除対象となります。ただし、法要費用や香典返しの費用は控除できません。
マイナス財産がプラス財産を上回る場合、相続すると損をすることになります。そうしたケースでは相続放棄によって債務の肩代わりを免れることができますが、プラスの財産も相続できなくなります。
相続税を軽減できる特例とその他の控除
基礎控除以外にも相続税が軽減できる主な特例を紹介します。これらの特例を活用することで、課税価格が基礎控除額を超えていても相続税をゼロにできる場合があります。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減の内容
配偶者は、相続した財産額が1億6,000万円まで、または法定相続分相当額までのいずれか多い金額について、相続税が課税されません。この特例により、配偶者が財産を上手に相続することで、残りの財産額を大幅に減らし、相続税を減額またはゼロにすることが可能です。
活用例
課税価格が8,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は4,800万円のため、残りの3,200万円に対して相続税がかかります。しかし、配偶者が法定相続分(2分の1 = 4,000万円)を相続すれば、配偶者の税額軽減により配偶者の相続税はゼロとなります。
適用要件と注意点
- 申告期限(10か月以内)に申告が必要:申告をしないと特例が使えません
- 二次相続のリスク:配偶者が亡くなった際の相続(二次相続)では、子どもに高額の相続税が課税される可能性があります
- トータルでの税負担を検討:一次相続での配偶者の税額軽減の利用は、二次相続まで見通した計画性が必要です
小規模宅地等の特例
自宅や事業所等の敷地を相続する場合に利用できる特例で、土地の評価額を最大80%減額できる強力な節税制度です。
小規模宅地等の特例の詳細はこちらをご覧ください。
その他の控除
未成年者控除
満18歳未満の法定相続人は、「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」を相続税額から差し引くことができます。
障害者控除
心身に障害を持つ法定相続人に適用できる控除で、「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円」を相続税額から差し引けます。特別障害者の場合は20万円となります。
これらの控除は、該当する相続人の相続税額から直接差し引かれるため、相続税をゼロにできる可能性もあります。
相次相続控除
今回の相続の前10年以内に、被相続人が相続によって財産を取得し、相続税を納めていた場合、前回の相続時に納めた相続税額の一部を、今回の相続税から控除することができます。
相続税の申告が不要な場合・必要な場合
「相続税がかからない=申告不要」ではないケースや、特例利用時の申告義務などを明確に解説します。申告漏れによるペナルティを避けるための重要な知識です。
申告不要となるケース
課税価格が基礎控除額以内で、かつ特例を利用しない場合には、相続税の申告も納税も必要ありません。
例えば、
- 課税価格4,000万円、相続人が配偶者と子2人(基礎控除額4,800万円)の場合
- 課税価格3,500万円、相続人が配偶者のみ(基礎控除額3,600万円)の場合
これらのケースでは、課税価格が基礎控除額を下回っているため、申告の必要がありません。
また、みなし相続財産の非課税枠(生命保険金・死亡退職金)を利用しても、課税価格が基礎控除額以内に収まる場合は申告不要です。
国税庁のホームページには「相続税の申告要否判定コーナー 」があり、簡単な入力で申告の必要性を判定できます。判断に迷った場合は、このツールを活用しましょう。
申告が必要なケースと注意点
特例利用時は相続税がゼロでも申告が必要
課税価格が基礎控除額を超えているものの、各種特例を利用した結果、相続税がゼロになる場合には申告は必要です。
申告が必要な主なケースは以下のとおりです。
- 配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロになった場合
- 小規模宅地等の特例を利用して相続税がゼロになった場合
申告期限と遅延のペナルティ
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると以下のペナルティが発生します。
- 無申告加算税:納付すべき税額の5~30%
- 延滞税:年利は毎年変動(令和7年は年2.4%又は8.7%)
- 特例の適用不可:原則、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなる
申告漏れの深刻なリスク
特例を使って相続税がゼロになったからといって申告をしないと、税務署から指摘を受け、特例の適用が認められず多額の相続税を支払うことになる可能性があります。「申告してこそ特例が使える」ことを必ず覚えておきましょう。
相続税の計算例とシミュレーション
家族構成・課税価格ごとの具体的な計算例で、実際にいくらかかるのかをイメージできるようにします。基本的な計算の流れから実践的なシミュレーション例まで解説します。
基本の計算ステップ
相続税の計算は、以下の5つのステップで行います。
- ステップ1:課税価格の算出
プラスの財産からマイナスの財産(債務・葬式費用)を差し引き、生前贈与財産を加算して課税価格を求めます。 - ステップ2:課税遺産総額の計算
課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
課税遺産総額 = 課税価格 - 基礎控除額 - ステップ3:相続税の総額の計算
課税遺産総額を法定相続分で一旦按分し、各人の取得金額に応じた税率・控除額を適用して算出した相続税額を合計し総額を求めます。 - ステップ4:各相続人の税額計算
相続税の総額を、実際の財産取得割合で按分して各相続人の税額を算出します。 - ステップ5:税額控除の適用
配偶者の税額軽減、未成年者控除などの各種控除を適用して、最終的な納税額を決定します。
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
家族別・遺産額別のシミュレーション例
ケース1:配偶者と子2人、課税価格6,000万円
- 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 課税遺産総額:6,000万円 - 4,800万円 = 1,200万円
- 法定相続分で計算:配偶者600万円(税率10%=60万円)、子各300万円(税率10%=各30万円)
- 相続税の総額:60万円+30万円+30万円=120万円
- 配偶者が法定相続分(1/2)を相続すれば配偶者の税額軽減で配偶者の相続税額はゼロ、子2人の相続税額は計60万円
- 実質的な相続税負担は1/2に軽減
ケース2:子2人のみ、課税価格5,000万円
- 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 課税遺産総額:5,000万円 - 4,200万円 = 800万円
- 法定相続分で計算:子各400万円(税率10%=各40万円)
- 相続税の総額:40万円+40万円=80万円
- 実際の財産取得割合(例えば各1/2)で按分:各人40万円ずつ
ケース3:配偶者のみ、課税価格8,000万円
- 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円
- 課税遺産総額:8,000万円 - 3,600万円 = 4,400万円
- 相続税額計算:4,400万円×20%-200万円=680万円
- 配偶者の税額軽減により相続税はゼロ(配偶者のみは実務上0円・無制限)
ケース4:小規模宅地等の特例を活用した場合
課税価格7,000万円(自宅(土地)5,000万円+現金2,000万円)、配偶者と子1人
- 小規模宅地等の特例:自宅(土地)5,000万円→1,000万円(80%減額)
- 特例適用後の課税価格:1,000万円+2,000万円=3,000万円
- 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 課税遺産総額:ゼロ(基礎控除額以下)
これらのシミュレーションからわかるように、家族構成や特例の活用により、相続税の負担は大きく変わります。
まとめ
相続税には基礎控除額が設けられており、課税価格(プラスの財産-マイナスの財産+生前贈与財産)の合計が基礎控除額以下であれば、相続税は課されず申告も不要です。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、法定相続人が多いほど無税の範囲が広がります。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を活用することで、基礎控除額を超える遺産があっても相続税をゼロにできる場合があります。
ただし、遺産の評価や特例の適用要件については専門的な判断が必要なケースが多く、特に不動産を含む相続では想定外の税負担が生じる可能性もあります。相続が発生した際は、早めに相続に詳しい税理士に相談することで、適切な節税対策と申告手続きを行うことができます。
よくある質問Q&A
Q:相続税はいくらから申告が必要ですか?
A:課税価格が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。ただし、各種特例を利用して相続税がゼロになる場合でも申告は必要となります。
Q:法定相続人が配偶者しかいない場合の無税ラインはいくらですか?
A:配偶者が唯一の相続人であるときは、配偶者の税額軽減により「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額(=全部)」のいずれか多い金額まで配偶者の相続税はかからないため、実務上は上限なく0円になります(※ただし、税額軽減を適用する場合は申告が必要)。
Q:生命保険金がある場合の計算方法は?
A:相続人が受け取った生命保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。この非課税枠を超えた金額が課税価格に加算され、そこから基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。
Q:相続放棄をした人がいる場合の基礎控除額は?
A:相続放棄をした人も、基礎控除額の計算では法定相続人としてカウントされます。実際に相続しなくても、基礎控除額の計算に影響はありません。
Q:生前贈与を受けていた場合はどうなりますか?
A:相続等により財産を取得した者が被相続人から相続開始前7年以内に受けた贈与は、相続財産に加算されます。3年超~7年以内分は合計100万円まで加算対象外となる経過措置があります。贈与税を納付していても、相続税の計算では加算対象となります。
Q:申告期限に遅れるとどうなりますか?
A:申告期限(10か月以内)に遅れると、無申告加算税や延滞税が課されます。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなり、大幅な税負担増となる可能性があります。
Q:専門家に相談すべきケースは?
A:不動産を含む相続、事業承継、課税価格が基礎控除額に近い場合、特例の適用を検討する場合などは、相続に詳しい税理士への相談をお勧めします。特に申告が必要かどうか判断に迷う場合は、早めの相談が重要です。
相続税の計算や特例の適用は複雑な部分も多いため、具体的なケースについては相続に強い税理士に相談されることをお勧めします。相続財産センターでは、資産税・相続に詳しい税理士を無料でご紹介しておりますので、お気軽にお問い合わせください。