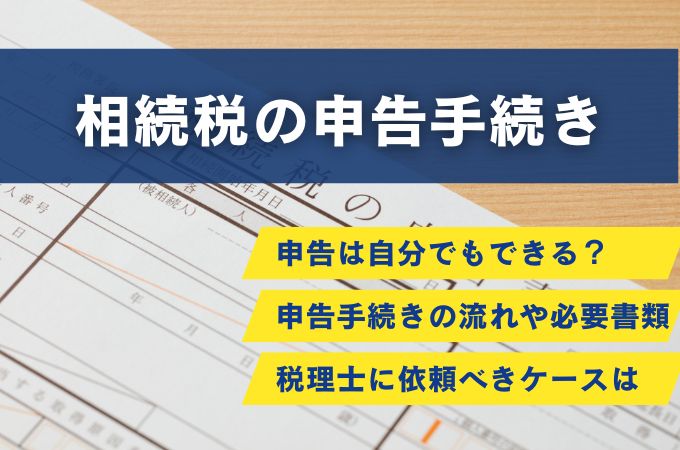相続税申告が必要となるケース
相続が発生したら誰もが相続税申告をしなければならないわけではありません。基礎控除額を超える財産がある場合のみ申告義務が生じます。ただし、特例を利用して納税額をゼロにする場合でも申告は必要です。
相続税の対象となる人と財産の範囲
相続税の対象となるのは、被相続人(亡くなった方)から財産を取得したすべての相続人・受遺者です。法定相続人に限らず、遺言によって財産を受け取った人や、生命保険金・死亡退職金の受取人も対象に含まれます。
相続税の課税対象となる財産には、現金・預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払税金などのマイナスの財産(債務)も含めて評価します。生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われ、一定額を超えると課税対象となります。相続開始前7年以内の贈与財産も、相続財産に加算して申告する必要があります。
相続税申告が必要となる基準は「基礎控除額」
相続税申告が必要かどうかは「基礎控除額」を超える遺産があるかで判断します。基礎控除額は次の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円です。相続財産の課税価格の合計額が4,800万円を超える場合に申告義務が発生します。
ここで注意すべきは「課税価格の合計額」の計算方法です。預貯金や不動産などすべての相続財産を時価評価し、そこから債務・葬儀費用を差し引いた金額で判断します。不動産は路線価や固定資産税評価額をもとに評価するため、単純に預貯金残高だけで判断することはできません。
相続税申告が不要なケースは基礎控除以下
相続財産の課税価格が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は一切不要です。税務署への届出も必要ありません。
ただし、財産評価を誤って「基礎控除以下」と判断し、本来は申告が必要だったケースで無申告となると、後日税務署から指摘を受ける可能性があります。特に不動産評価は複雑で、自己判断が難しい場合があります。財産総額が基礎控除額ぎりぎりの場合や、評価方法に不安がある場合は、税理士に相談して確認することをおすすめします。
特例適用で納税額ゼロでも申告は必要
相続税には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、税負担を大幅に軽減する特例があります。これらの特例を適用した結果、納税額がゼロになる場合でも、特例適用には相続税申告書の提出が必須条件となります。
例えば、配偶者の税額軽減を使えば配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。しかし、この特例を受けるには申告期限内に申告書を提出する必要があります。「納税額がゼロだから申告不要」と誤解して申告しないと、特例が適用されず本来不要だった税金を納めることになります。
相続税申告の期限と遅れた場合のペナルティ
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。例えば2025年4月1日に死亡を知った場合、申告期限は2026年2月1日となります。期限日が土日祝日の場合は、その翌営業日が期限です。
この10ヶ月という期間は、財産調査・評価、遺産分割協議、申告書作成など多くの手続きを進めるには決して余裕のある期間ではありません。特に不動産が多い場合や相続人間で意見が分かれている場合は、早めに着手しないと期限に間に合わなくなる可能性があります。
申告期限を過ぎると、無申告加算税(納付税額や申告タイミングによって5%〜30%、悪質な場合は40%)や延滞税が課されます。財産規模が大きければペナルティも高額になるため、期限内の申告・納税が重要です。やむを得ず期限に間に合わない見込みの場合は、早めに税理士に相談してください。
相続税の申告は自分でできる?判断のポイント
相続税申告は自分で行うことも可能ですが、財産構成や金額によって難易度は大きく異なります。シンプルなケースなら国税庁の記載例を参考に自力で完結できる一方、複雑なケースでは専門知識がないと申告ミスや節税機会の損失を招きます。
自力申告が現実的なケース
財産構成が単純で評価が明確、かつ相続人間で争いがない場合は自分で申告できる可能性があります。具体的には以下の条件を満たすケースです。
- 相続財産の総額が基礎控除を大きく超えていない(5,000万円程度まで)
- 財産の大半が預貯金・上場株式など評価方法が明確な金融資産
- 不動産がない、または自宅1軒のみで評価が単純
- 相続人の関係が良好で遺産分割に争いがない
- 生前贈与の加算や名義預金などの複雑な要素がない
- 特例適用が不要、または配偶者の税額軽減のみで完結
こうしたシンプルなケースなら、国税庁ホームページの申告書記載例や手引きを参考に、時間をかけて自分で作成することは可能です。ただし、財産評価や税額計算のミスは後日の追徴課税につながるため、不安がある項目は税務署の無料相談や税理士への部分的な相談を活用してください。
税理士に依頼すべき複雑なケース
財産規模が大きい、不動産が複数ある、特例適用が必要な場合は税理士への依頼を検討すべきです。自力申告のリスクが税理士報酬を上回る可能性が高いためです。
- 相続財産の総額が1億円を超える
- 複数の不動産や事業用資産、非上場株式が含まれる
- 小規模宅地等の特例など複数の特例適用を検討する必要がある
- 相続人が多数、または遺産分割で意見が分かれている
- 相続開始前7年以内の贈与財産の加算が必要
- 名義預金や貸付金など、実質的な財産の判定が必要
これらのケースでは、財産評価の専門知識、特例適用の可否判断、二次相続も見据えた遺産分割の提案など、税理士の専門性が不可欠です。自力で申告して評価ミスや特例適用漏れがあると、本来払わずに済んだ税金を納めることになります。税理士報酬を払っても、適切な節税提案によってトータルでプラスになるケースが多いのが実情です。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
先に例示されているケースのように相続税額がそれ程高額にならないか、あるいは相続財産が明らかで相続税額の計算過程で間違う可能性が低い場合は自分で申告してしまっても良いでしょう。
具体的には、被相続人の相続財産の大半が預貯金や上場株式などの金融資産で構成され、その内訳や所在が財産目録や遺言によって明らかな場合などが挙げられます。
また、相続人が配偶者のみの場合や配偶者以外の相続人がいても遺言や遺産分割協議によって大半の財産を配偶者が相続するような場合は、「配偶者の税額軽減」を使えば配偶者が相続した財産には1億6千万円まで相続税がかかりませんので、被相続人の相続財産がそこまで高額でなければ自分で申告されてもあまり問題になることはありません。 - 松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行
自力で行う相続税申告の手続きの流れや必要書類
自分で相続税申告を行う場合、大きく分けて「財産調査・評価」「申告書作成」「提出・納税」の3ステップを進めます。それぞれの段階で国税庁の手引きや記載例を活用しながら、慎重に作業を進めることが重要です。
ステップ1:法定相続人の確定と財産の洗い出し
まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。これは基礎控除額の計算に必須のステップです。法定相続人には配偶者、子、親、兄弟姉妹などが該当し、養子や認知された子も含まれます。
並行して相続財産の洗い出しを行います。預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、自動車、貴金属などプラスの財産に加え、借入金、未払税金、葬儀費用などマイナスの財産も漏れなくリストアップしてください。通帳の履歴や郵便物から「見えない財産」が判明することもあるため、丁寧に調査することが重要です。
ステップ2:財産評価と相続税額の計算
各財産を相続税評価額に換算し、総財産額から債務・葬儀費用と基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。預貯金は残高証明書の金額、上場株式は相続開始日の終値などで評価できますが、不動産は路線価や固定資産税評価額をもとに計算する必要があり、自力では難易度が高い部分です。
課税遺産総額が確定したら、法定相続分に応じて各相続人の取得金額を計算し、相続税の税率(10%〜55%の累進税率)をかけて相続税総額を求めます。その後、実際の遺産分割割合に応じて各相続人の納税額を按分し、配偶者の税額軽減などの特例を適用して最終的な納税額を確定します。
ステップ3:申告書の作成と提出・納税
相続税申告書は国税庁ホームページからダウンロードし、第1表(申告書)と必要な明細書(第2表以降)を記入します。初めての方は国税庁の記載例を参照しながら作成すると理解しやすいでしょう。
申告書には戸籍謄本、マイナンバー確認書類、遺産分割協議書(特例適用時)、印鑑証明書などを添付します。財産評価に使用した登記簿謄本や残高証明書は税務署への提出は不要ですが、手元に保管しておいてください。
完成した申告書は被相続人の死亡時住所地を管轄する税務署へ提出します(相続人の住所地ではありません)。提出方法は窓口持参または郵送(書留推奨)で、申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。納税も同時に行い、原則として現金一括納付となります。
自分で相続税申告を行う際の注意点と申告ミスのリスク
自力申告の最大のリスクは、申告ミスによる追徴課税と、本来受けられる節税機会の損失です。相続税は一生に一度の申告であり、専門知識がない状態で正確に処理するのは容易ではありません。特に財産評価と特例適用の判断で誤りが生じやすく、結果として数百万円単位の不利益を被る可能性があります。
典型的な申告ミスと追徴課税のリスク
自力申告で起きやすいミスは、財産の申告漏れ、評価額の誤り、控除・特例の適用漏れ、計算ミスの4つです。これらは税務調査で指摘されると追徴課税の対象となります。
財産の申告漏れは、名義預金(被相続人が家族名義で管理していた預金)や生前贈与の加算対象財産、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約などを見落とすケースが典型例です。税務署は金融機関への照会権限を持っているため、申告後に発覚するリスクが高い項目です。
財産評価の誤りは特に不動産で頻発します。路線価図の読み方、間口・奥行補正率の適用、不整形地の評価、貸家建付地の判定など、専門的な知識が必要な場面が多く、自己判断での評価は過大評価・過小評価どちらのリスクもあります。過小評価の場合は過少申告加算税(5%〜15%、悪質な場合は35%)と延滞税が加算され、本来の税額より大きな負担となります。
節税機会の損失、特例の適用漏れ
控除や特例の適用漏れは「払いすぎ」を意味し、本来不要だった税金を納めてしまうことになります。代表的なのが小規模宅地等の特例で、要件を満たせば評価額を最大80%減額できますが、適用要件の判断や申告書への記載方法を誤ると特例が受けられません。
配偶者の税額軽減も適用漏れが起きやすい特例です。1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税になりますが、申告書への記載と遺産分割協議書の提出が必須です。「配偶者は非課税」と誤解して申告自体をしないと、特例が適用されず満額課税となります。
こうした払いすぎは更正の請求(申告期限から5年以内)で取り戻せますが、手続きは煩雑で時間もかかります。小規模宅地等の特例の場合、所定の要件を満たしていなければ更正の請求自体が認められないケースもあります。
税務調査のリスクと時間的・精神的負担
相続税申告は税務調査の対象となりやすい税目で、高額な遺産や財産評価に疑義がある場合は調査対象となる可能性が高まります。税理士が作成した申告書でも調査は入りますが、自力申告の場合は評価ミスや申告漏れの可能性を疑われやすく、調査率が上がる傾向があります。
調査では相続人が税務署職員の質問に直接回答する必要があり、財産評価の根拠や遺産分割の経緯を説明しなければなりません。専門知識がない状態で適切に対応するのは難しく、精神的負担も大きくなります。
また、自力申告には想像以上の時間と労力がかかります。戸籍収集、財産の洗い出し、評価額計算、申告書作成を、仕事や家事の合間に進めると数ヶ月かかることも珍しくありません。税務署の無料相談は申告書の書き方や制度説明が中心で、個別の財産評価や節税アドバイスは受けられません。相談窓口も混雑しており、十分な時間を取ってもらえないことが多いのが実情です。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
相続税の申告は一生のうちに一回あるかどうかというものですので、自分で行う場合に間違いや誤りが生じても何ら不思議はありません。
申告する相続財産は被相続人が生前保有していたものですから、遺言や財産目録が遺っていなければ相続人は限られた時間で被相続人の居宅に保管されている書類の中から自分で調べて洗い出さなければならず、本来申告しなければならない財産が漏れてしまうことも往々にしてあります。
また、相続税は所得税などと比べて納付税額が高額になることが多いため、財産評価や税額計算を間違えると追徴税額も高額になる傾向があります。
このように、時間と労力を掛けて細心の注意を払い行ってもちょっとした間違いで大きな損失を被ってしまう恐れがあることが相続税申告を自分で行う最大のリスクでありデメリットでしょう。 - 松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行
相続税申告を税理士に依頼すべきケース
財産規模が大きい、不動産が複数ある、特例適用が必要な場合は税理士への依頼を強く推奨します。自力申告のリスクが税理士報酬を上回る可能性が高く、適切な節税提案によって報酬以上のメリットが得られるケースが多いためです。
税理士依頼を検討すべき代表的なケース
以下のいずれかに該当する場合、税理士への依頼を検討してください。これらは申告ミスや節税機会の損失が起きやすく、専門知識が不可欠なケースです。
【財産規模・構成面】
- 相続財産の総額が1億円を超える
- 複数の不動産(自宅以外に賃貸物件、農地、山林など)がある
- 事業用資産や非上場株式が含まれる
- 海外資産がある
【特例・控除適用面】
- 小規模宅地等の特例の適用を検討している
- 配偶者の税額軽減と二次相続対策を同時に考慮する必要がある
- 相続時精算課税制度や暦年贈与の加算が必要
【手続き面・人間関係面】
- 相続人が多数いる、または遺産分割で意見が分かれている
- 申告期限まで6ヶ月を切っている
- 本業や育児で申告手続きに時間を割けない
これらのケースでは、財産評価の専門知識、特例適用の可否判断、二次相続も見据えた遺産分割提案など、税理士の専門性が不可欠です。特に小規模宅地等の特例は要件判定が複雑で、適用できれば最大80%の評価減となるため、専門家の判断を仰ぐべき代表的な項目です。
税理士に依頼するメリットと選び方
税理士に依頼する最大のメリットは、申告ミスによる追徴課税リスクの回避と、適切な節税提案による納税額の適正化です。相続税専門の税理士なら、税制改正にも対応し、様々なケースの経験から最適な申告方法を提案できます。
また、戸籍収集から財産調査、申告書作成、税務調査対応まで一貫してサポートを受けられるため、相続人の時間的・精神的負担が大幅に軽減されます。税務署との折衝も税理士が代行するため、専門知識がなくても安心して手続きを進められます。
税理士を選ぶ際は、相続税申告の実績件数、不動産評価や特例適用の経験、報酬体系の明確さを確認してください。すべての税理士が相続税に強いわけではなく、年間申告件数が少ない税理士では評価ミスや特例適用漏れのリスクがあります。相続税専門をうたっている税理士事務所、または年間50件以上の申告実績がある事務所を選ぶのが安全です。
税理士報酬の相場と費用対効果
相続税申告の税理士報酬は「相続財産の1%」が一般的な目安です。遺産総額5,000万円未満なら15万円〜50万円、5,000万円〜7,000万円なら25万円〜70万円、7,000万円〜1億円なら35万円〜100万円、1億円〜1億5,000万円なら50万円〜150万円程度が相場となります。
ただし、これは基本報酬であり、不動産が複数ある場合や非上場株式の評価が必要な場合、申告期限まで3ヶ月を切っている場合、相続人が多数いる場合などは、追加報酬が発生します。見積もり時に、基本報酬に含まれる業務範囲と追加報酬が発生する条件を明確に確認しておくことが重要です。
報酬の安さだけで税理士を選ぶのは避けるべきです。適切な財産評価と特例適用によって相続税額が数百万円単位で減少するケースも多く、税理士報酬を差し引いてもトータルでプラスになることは珍しくありません。特に小規模宅地等の特例は適用できれば最大80%の評価減となるため、専門性の高い税理士を選ぶ方が結果的に有利になります。
まとめ
相続税申告は自分で行うことも可能ですが、財産構成や金額によって難易度は大きく異なります。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産がある場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告が必要です。
預貯金中心で財産構成がシンプルなケースなら、国税庁の記載例を参考に自力で申告できる可能性があります。一方、財産総額が1億円を超える、複数の不動産がある、小規模宅地等の特例を適用する場合は、税理士への依頼を強く推奨します。申告ミスによる追徴課税リスクや、特例適用漏れによる節税機会の損失を避けるためです。
「相続財産センター」は、税理士紹介のパイオニアである株式会社ビスカスが運営する相続特化メディアです。1995年の創業以来、26万件以上の相談実績をもとに、全国4,700所以上の登録税理士事務所ネットワークを活かし、相続税申告に強い税理士を無料でご紹介しています。
「自分で進めるか専門家に依頼するか迷っている」「複雑な財産構成で不安がある」という方は、ぜひ相続財産センターへご相談ください。専任の税理士コーディネーターがお客様のご状況をヒアリングし、最適な税理士をご紹介いたします。初回相談から税理士のご紹介まで一切費用はかかりませんので、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
相続税申告は自分でできますか?
財産構成がシンプルで評価が明確な場合は自分で申告できる可能性があります。ただし、財産総額が1億円を超える、複数の不動産がある、小規模宅地等の特例を適用する場合は、税理士への依頼を推奨します。
相続税申告が必要かどうかはどう判断しますか?
相続財産の課税価格が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告義務が生じます。ただし、特例適用で納税額がゼロになる場合でも申告書の提出は必要です。
相続税申告の期限はいつまでですか?
被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されるため、早めの準備が重要です。
自分で申告した場合のリスクは何ですか?
財産の申告漏れや評価ミスによる追徴課税、控除・特例の適用漏れによる節税機会の損失が主なリスクです。特に不動産評価や小規模宅地等の特例は専門知識が必要で、誤ると数百万円単位の不利益を被る可能性があります。
税理士報酬の相場はどのくらいですか?
遺産総額の1%が一般的な目安です。遺産総額5,000万円未満なら15万円〜50万円、7,000万円〜1億円なら35万円〜100万円程度が相場となります。不動産の数や特例適用により追加報酬が発生する場合があります。
相続税申告に必要な書類は何ですか?
被相続人と相続人の戸籍謄本、マイナンバー確認書類、遺産分割協議書(特例適用時)、印鑑証明書などが必要です。財産評価に使う登記簿謄本や残高証明書は税務署への提出は不要ですが、手元に保管しておく必要があります。
配偶者が相続すれば相続税はかかりませんか?
配偶者の税額軽減により、配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。ただし、この特例を受けるには申告書の提出が必須です。
小規模宅地等の特例とは何ですか?
被相続人の自宅や事業用地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる特例です。適用できれば数千万円単位の節税効果がありますが、要件判定が複雑なため税理士への相談を推奨します。
税務調査が入る可能性はどのくらいですか?
相続税申告の約10件に1件の割合で税務調査が実施されています。特に高額な遺産や財産評価に疑義がある場合は調査対象となりやすく、自力申告の場合は評価ミスや申告漏れの可能性を疑われやすい傾向があります。
申告期限に間に合わない場合はどうすればよいですか?
期限に間に合わない見込みの場合は、すぐに税理士に相談してください。遺産分割が未了でも未分割申告という方法で期限内に申告することは可能です。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されるため、早めの対応が重要です。