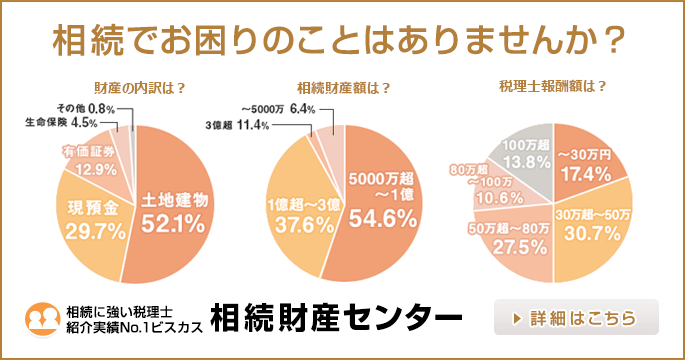「税務調査」と聞くと、誰もが思い浮かべるのは、テレビや映画でおなじみの“マルサ”(査察調査)。「でもあれは、企業などの巨額の脱税が疑われた場合のことでしょ。うちのような、少額の相続には関係ないよ」とお考えでしょうか。逆に、「税務署に調査に入られて、あれこれ探られたらどうしよう」と戦々恐々の方も? 税理士法人KMCパートナーズの木村智行先生に、その実情をうかがいました。
あなたの相続にも「税務調査」が入る!?

2015/5/27
◆調査に入られたら、修正の可能性が高い
税務調査とは、ひとことで言えば、「納税者の申告が正しいかどうかをチェックするために、国税局や税務署が行う調査」のこと。納税者の同意のもとに税務調査官が実施する任意調査と、裁判所の令状を得て行われる強制捜査(これが“マルサ”ですね)があります。
もちろん、闇雲に調査に入るほど、税務署はヒマではありません。「この申告は、何となく怪しい」、さらに言えば、「ここからは追徴できそうだぞ」という感触を持ったからこそ、わざわざやってくるのです。ですから、どこもいじられる余地のない、「正確な申告」をしていれば、恐れることはありません。当たり前のことですが、それが税務調査を回避する王道です。
ところで、不幸にして、調査の対象になると、どうなるのでしょう? あなたは、やってきた調査官に、「故人の財産」について根掘り葉掘り“インタビュー”されることになります。彼らは、時折、雑談なども交えながら、「お亡くなりになる時のご様子はどうでしたか?(お金の管理ができるだけの意思能力があったのか)」「旦那さんのご趣味は?(高い絵画や骨董を集めていたのでは)」といったことまで、聞き出そうとします。
税務署は、職権で金融機関に照会し、預貯金の動きを調べることができるのですが、その場で過去数年間の通帳の提示を求めて、資金の流れを見ながら説明を求めたりもします。それこそ、「バッグを開いて、中を見せてください」の世界なんですね。 言うまでもなく、彼らは税のプロであり、「公平な徴税」に使命感を抱く人たちです。隠す意図のない、誤解やミスによる「申告漏れ」だったとしても、見逃してはくれません。調査に入られた場合、申告漏れ等の割合は8割を超えており、申告の修正率はかなり高いのが実情です。
ちなみに、「過少申告」だった場合、税務調査前に自主的に修正申告すれば、加算税はゼロですが、調査で発覚すると10%ないし15%のペナルティが課せられることになります(*)。財産を意図的に隠したりする「仮想隠蔽」が指摘されれば、さらに税率の高い重加算税を支払わなくてはなりません。
「小規模だから調査には来ない」のウソ
では、相続税の税務調査って、実際にはどれくらい行われているのでしょうか? 私の担当する限りでは、5件に1件くらいの割合で調査に入っている、という感覚です。ただ、当事務所のお客さまの相続は、遺産総額2億円以上の、わりと「大きな」案件が多いので、これが平均値とはいえないと思います。遺産相続の規模の大きいほうが、目を付けられやすいのは確かでしょうから、全体を見れば、もっと頻度は下がるでしょう。
しかし、「相続額が少ないから、税務調査には来ない」というのは間違い。それでは、「公平な徴税」が損なわれることになりかねません。 実際、税務当局は、例えば法人の税務調査について、大規模、中規模、小規模、赤字法人それぞれをターゲットにする「階層型調査」を行います。相続税についても、同じような発想で臨んでいるのは、間違いありません。「父の遺産は、そんなに大したことないから」と、いい加減な申告を行うと、後で痛い目に遭うかもしれませんよ。
新たに納めることになった税金の10%相当額が課される。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になる。なお、自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない。
◆相続税調査の「簡素化」に乗り出した税務当局。キーワードは「書面添付」
首都圏では、4割以上が相続税を申告
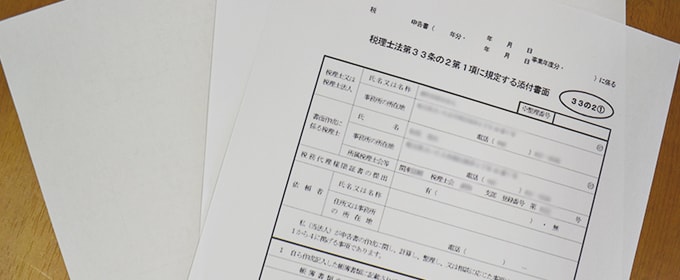
今年年初からの相続税の基礎控除の引き下げにより、従来は4%程度だった課税対象者が、6~7%まで拡大する、といわれます。ただし、これは全国平均のお話で、地価の高い都市部では、このパーセンテージは当てはまりません。首都圏(東京国税局管内=東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)では、課税対象者は、従来の約7%から15%程度まで高まるものとみられています。
なおかつ、例えば、「小規模宅地の特例」といった税の軽減措置は、申告しないと受けられません。その結果、相続税がかからなかった人たちも含めると、首都圏で相続税の申告を行う人は、全体の20%程度から、今年以降は44%にまではね上がる、といれているのです。 首都圏では、2人に1人に近い比率で申告しなければならなくなるわけですから、大変です。でも、「仕事」の増えるのは、納税者だけではありません。そうした申告を受ける税務署の負担増も、非常に大きなものになるんですね。そこで、そうした状況を見越して、当局は、昨年の秋、「相続税調査の総点検」に乗り出しました。
相続税調査の簡素化へ「書面添付制度」を活用
各種報道などによれば、今年1月からの課税ベースの拡大を控え、当局は申告内容の見直し、実地調査選定基準の見直し、実地の調査以外の接触手法の活用、申告前の自己点検手法の積極的な活用――などが、その具体的な取り組みとして挙げられています。このうち、「申告前の自己点検手法」としてクローズアップされているのが、税理士法33条の2に定められた「書面添付」事案への取り組みです。従来からある「書面添付制度」をさらに積極的に活用して、税務調査の効率化を図ろうというわけです。
簡単に制度の仕組みを説明しましょう。実は、相続税の申告書には、「各項目について、どのような資料に基づいて検討・判断したのか」といったことを税理士が記載した、文書を申告書に添付することができることになっています。ざっくりいうと、税理士が申告書についてお墨付きを与えるものともいえます。申告を受けた当局が、「税務調査の必要があるのでは」と判断した場合、この書面添付があると、調査に入る前に書面を記載した税理士に対して、同じく税理士法35条に定められた「意見聴取」を行うのです。ちなみに、書面添付がなければ、即、調査に入ることになります。
意見聴取では、当局が申告審理などで把握した疑問点を税理士に示し、それに対する税理士の意見陳述を行いますが、今後は必要に応じて、自発的な見直し、修正申告の提出を要請する「行政指導」が行われることになるようです。 また、疑問点が解消され、調査の必要がないと判断された場合には、税理士に対して「現時点では調査に移行しない」旨の通知が行われるのです。
税務当局にとっては、わざわざ調査に出向いて時間とエネルギーを使わなくても、申告の「誤り」を正すことができる、場合によっては「無駄足」を防げるわけですね。猫の手も借りたい状況下で、この制度を積極活用しようという意図は、よく分かります。 同時に、申告する側にとっても、うまく使えば、「税務調査を、より確実に回避することが出知る」というメリットがあります。次は、その点を中心に、「書面添付制度」について、さらに掘り下げてみましょう。
◆「書面添付」で税務調査を回避する
「『書面添付』で終わる」可能性は高まった

前述で相続税の申告における「書面添付制度」についてお話ししました。申告書に、税理士が「どのような資料に基づき、どんな検討・判断を行ったのか」といった内容を記載した書面が添付されていれば、税務署が税務調査の必要性を感じたとしても、直接調査に出向く前に、税理士への「意見聴取」を行う――というのが、この制度の概要です。
国が、今年1月からの基礎控除額の引き下げに伴う相続税申告の大幅増加を見据え、これを積極的に活用することによって、「調査の簡素」を意図していることも、前で述べました。要するに、時間もコストもかかる税務調査をやらなくても、適正な申告をしてもらおう、そのために、今まで以上に書面添付を重視しよう、ということですね。 実際のところ、今までは、税理士への意見聴取を行っても税務調査に入る、というケースが少なくありませんでした。しかし、前で述べたような税務当局の動向を見る限り、今後は「書面添付案件についての疑問は、極力意見聴取の段階で解決する」という方向性が明確になってくるのではないか、と私は考えています。
このことは、相続税を申告する側からみると、「きちんと書面添付された申告については、税務調査に入られるリスクが減る」ことを意味します。税務調査を回避する有意義な手段であることは、間違いないでしょう。
「小規模の申告」には、特に有効?
書面添付は、法人税など他の税金の申告でも認められています。私は多くの企業の顧問税理士をしていますが、経験上、特に年商1億円以下の規模の会社だと、書面添付さえしておけば、ほとんど税務調査は行われない、という感触を持っています。
相続税の申告においても、基本的に同じ傾向になるのではないでしょうか。前々回、税務申告に関しては「階層型調査」が実施されるため、「小規模、少額の申告だから、税務署は来ない」ということはない、と述べました。それはそうなのですが、実際に調査のターゲットになるのは、やはり「大規模」のほうが多いのも事実。「小規模の申告」に書面添付を行えば“鬼に金棒”である、ということが言えると思います。
あえて付け加えると、大規模な法人の法人税の申告においては、書面添付をし、意見聴取を受けたにもかかわらず、調査に入られることも、たまにあります。ただし、その場合にも、意見聴取で税務署の「狙い」を知ることができます。実地の調査まで数週間程度の期間がありますから、十分な事前の準備も可能なんですね。書面添付のない場合には、意見聴取なしに調査になりますから、添付するのかしないのか、その点でも大きな差になります。これもまた、相続税申告の場合にも当てはまるのではないでしょうか。とはいえ、「どんな中身でも、とにかく書面添付をやっておけばOK」というわけでは、もちろんありませんよ。次は、そのあたりのお話を。
◆「書面添付」のメリットを享受するために、必要なこと
「書面」には、何を書くのか?

前述で税務申告書への書面添付の有用性についてお話ししました。それは、言ってみれば、「この申告書の内容は、適正ですよ」という、税理士による“お墨付き”です。当然のことながら、何も付いていない申告書に比べれば、税務署の信頼度はアップするでしょう。申告をすんなり受理してもらう、重要な補完材料になるのは間違いありません。仮に彼らが何か疑問を持ったとしても、税理士への意見聴取の段階で、解決のためのやり取りができます。いきなり税務調査になる「書面添付なし」とは、大違い。
では、添付される書面には、どのようなことが記載されるのでしょうか? 相続の場合、税金の計算は、遺産の中身(現金、不動産、有価証券、会社経営者の場合は自社株などなど……)によって複雑化することがあります。通常は、そうした税務当局に特に「目を付けられそうな」部分を中心に、主要な項目について、目を通した資料、計算のやり方、あるいはクライアントから相談を受けた事柄などについて、コメントを書きます。
例えば、「現預金に関して、過去5年間に遡って、提示された通帳をすべて確認しました。被相続人から相続人への生前贈与などは認められません」とか、「相続人が、確かに被相続人と同居していた事実を確認し、小規模宅地の特例による相続税の軽減措置を講じています」といった具合ですね。
「洗いざらい話してくれる」ことが前提
ただし、ここで問題になるのが、“お墨付き”を与えたはずの中身が、実は事実と異なっていた、というような場合です。万が一、それが発覚したら、形勢逆転。税務当局の心証は、一気に悪化することになります。
分かりやすい例を挙げましょう。前にもお話ししましたが、税務当局は、職権で被相続の預金通帳を調べることができます。その結果、添付の書面では「全部で5通の預金通帳」となっていたのに、かなりの金額の残る別の口座の通帳が、もう1通出てきたら……。相続人は、当然、申告書の修正を求められますし、もし意図的に隠そうとしたことが明らかになれば、重加算税という重い罰金を支払う羽目になるでしょう。さらに、結果的に「虚偽」を記載することになった税理士は、厳しいことになります。税理士法上、懲戒処分や罰則を科せられる可能性があるんですよ。
これは、書面添付を行う・行わないに限らずですけれど、申告書の作成に当たっては、「被相続人の財産については、包み隠さず、明らかにしてください」とお願いしています。少しでも依頼人の利益になるよう働くのが、我々税理士の務めです。でも、その責任が果たせるのも、こちらを信頼し、すべてを任せてくれる環境にあってこそ。その点は、理解していただきたいと思うのです。
◆「書面添付」にはテクニックも要る
活用しているのは、全体の数%?
「書面添付」とはどんなものか、そのメリットは何か? について、3回にわたって述べてきました。では、相続税の申告の際、実際にはどのくらい活用されているのでしょうか? 法人税に関しては、約7%の申告書に書面が添付されている、という統計があります。でも、相続税に関しては、正確な数字はありません。恐らく、法人税よりはかなり低いでしょうから、2~3%、いや、もっと少ないかもしれませんね。いずれにしても、「相続税申告書の書面添付」は、現状では極めて少数にとどまっている、ということです。そもそも、書面添付について正確に知っている方は、税理士でもあまり多くないというのが実情でしょう。税務調査を回避するうえでも有効なのに、なぜそんな状況なのか? その理由は、主として、書面を記載する立場の税理士の側にある、と感じます。
「書面添付ができるかどうか」は、税理士選びの一つの基準
前述のように、もし自らが書いて、申告書に添付した書面にミスがあれば、税理士は法的なペナルティを課せられる可能性がある、と言いました。このことが、書面添付を躊躇させる一因になっているのは、確かだと思います。書面添付は、申告を依頼する相続人にとっては、いいことづくめ(頼んだ先生によっては、「追加料金」を請求されるかもしれませんが)。一方、書面の記載を頼まれた税理士は、決して軽くはないリスクを背負わなければならない、というわけです。
ただし、もっと根本的な問題もあります。税理士ならば、みんなが書面添付をできるわけではない、という現実があるのです。依頼人にとってメリットのある内容にするためには、やはりノウハウが必要。税務署の担当者と話すと、「通り一遍のことではなくて、具体的に踏み込んだ中身にしてほしい」といった要請を受けることもあります。経験がないと、それはなかなか難しいわけですね。
私自身は、法人税は7年ほどまえから、相続税については4年ほど前からの申告書への書面添付を本格的に始めています。相続の内容や、依頼人の方の希望にもよりますけど、今は請け負った相続税申告の8~9割が書面添付です。 「意見聴取」(*)も、数多く経験しています。「被相続人と相続人の預貯金が問題になりそうだ」と直感した相続では、税務署に通帳を全部持ち込んで、「被相続人から相続人への、この資金移動はこういう理由です」と、実地の税務調査に近いようなことをやったこともあります。2時間近くやり取りしましたが、それで税務調査は行われず、調査省略通知を頂きました。
前にも述べたように、税務当局は、この書面添付制度を活用して、税務調査の簡素化を図ろう、という姿勢を明らかにしています。そういう流れに上手に乗るのも、「賢い相続」ではないでしょうか。我田引水に取られると困るのですが、「書面添付を頼めるか」は、相続の申告を任せる税理士を選ぶ際に、一つの基準になると思いますよ。
税の申告書に書面添付が行われていれば、税務署は税務調査に入る前に、書面を作成した税理士から意見聴取を行う。その結果、申告に対する疑問が解消されれば、調査は行われない。国税庁は事務運営指針を改正し、意見聴取後に提出された修正申告にかかる加算税を適用しないこととしており、平成25年1月1日から運用されている。
◆税務調査で問題が次々発覚したのに“お咎め”なし。いったいなぜ?
ずさんな中身が、次々明らかに

我々税理士は、依頼者の利益を守るために、税務署と「攻防」を繰り広げることもあります。そんな例を、一つご紹介しましょう。 新しく顧問契約を結んだ会社に、相続税の税務調査が入りました。社長をやっていたお父さんが急死し、急遽息子さんが事業を継いだ、というパターンでした。相続税の申告をしたのは、前に顧問をしていた税理士事務所でしたが、「そこには頼みにくい」という新社長に、調査への対応を依頼されたのでした。
あらためて申告書を調べてみると、ずさんなものであることが、一目瞭然。あろうことか、お父さんの死亡保険金が記載されていないとか、自社株の評価の計算方法を間違えているだとか……。そうした点は、当然のごとく、税務署に厳しく指摘され、やり直してみると、相続財産は2千万ほど「膨らんで」しまいました。
保険金まで漏れていたのですから、通常なら、間違いなく修正申告、追徴課税です。ところが、この相続に関しては、結局「修正の必要なし」で幕引きとなったんですよ。我々が、「ある事実」に気づいたからでした。
税務署は、「損」になる修正は求めない
法人の顧問をしていましたので、念のために決算書などを調べ直してみると……なんと「粉飾」を発見したのです。恐らく、金融機関対策などを目的に、前の顧問税理士が前社長にアドバイスしていたのでしょう、実際にはほとんど存在しない在庫が、何千万円も計上されていました。
在庫は資産ですから、会社の価値=株価に影響します。計算してみると、自社株の評価額は、ほとんどゼロになりました。計算方法が違うウンヌンの話とは、次元が違うことになってしまったのです。
さて、ここからが、税務当局とのせめぎ合いです。あらためて算出した自社株の評価額を当てはめて申告書を作り直してみると、保険金の未記載分などと相殺しても、十分「おつり」が来る内容でした。修正申告すれば、追徴どころか、税の還付になるような状況だったのです。ただし、当時は実際の正確な在庫の金額を証明できなかったので、少々難しい状況でした。
そうした事実を税務署に堂々と提示して話し合った結果の、「お咎めなし」でした。言葉は悪いのですけど、ずさんな申告で追徴必至だった社長側と、正しく申告をやり直せば、下手をすると還付が求められかねない税務当局との「手打ち」です。税務当局は、税金を徴収するのが仕事ですから、「損」になるところまでは、基本的に踏み込んではこないんですね。
ともあれ、粉飾を見つけ出し、そのうえで正論を掲げて戦ったからこそ、勝ち取れた成果でした。さすがに、調査に入られ、保険金の記載漏れまで発覚したのに修正申告を免れた、というのは、後にも先にもあの一件だけです。
ちなみに、その会社は、新社長の下で順調に業績を伸ばし、今では粉飾など考える必要のない健全な経営が行われています。あの時、追徴課税で余計なお金を持っていかれなかったことも、会社の立ち直りに少しは貢献したのかな、と思ったりもします。
◆「名義預金」か「贈与」か。単純ではない“損得”の分かれ道
「名義預金」か「贈与」か。単純ではない“損得”の分かれ道
「名義預金」と「贈与」の違いについて、最初に簡単に述べておきましょう。被相続Aさんが、家族Bさんの名前で預金していたけれども、そのことをBさんが知らなかったら。「名義預金」。通帳に記された名前は「借りている」に過ぎず、実質的な所有者はAさんであるとみなされます。一方、Aさんに、「Bさんにお金を渡す」意志があり、Bさんにも「Aさんからお金をもらう」意志があったなら、それは「贈与」になります。 「名義預金」は、あくまでも被相続人の財産です。通帳の名義は家族であったとしても、そこに記載された金額は、相続税算定のベースになる相続財産に含めなければなりません。ところが、被相続人の名義ではないため、「漏れ」が起きやすく、税務調査で「申告されていませんよ」と指摘される預貯金のかなりの部分は、この名義預金が占める、ともいわれているんですよ。
ところで、こうしたケースにおいて、税務調査に入った税務署の担当者から、「これは贈与ではないですか?」と「確認」されたりすることがあります。名義預金と贈与のわけも分からずに「はい」と答えると、思わぬ“損”を被ることもありますから、注意が必要です。 相続税より贈与税のほうが、税率の高いケースが多いんですね。税務当局にしてみれば、名義預金を相続財産に加えて追徴課税するよりも、贈与税を課したほうが、“実入り”が多くなるわけです。なお、亡くなった日から3年以内に贈与された財産は相続財産に加算され相続税の対象となりますので、この点は注意が必要です。
私の担当した案件にも、調査に入った税務署から、被相続人から相続人への資金移動を「贈与ではないか」と指摘されたケースがありました。でも、贈与の場合には、さきほど述べたような「あげる」「もらう」という両者の意志がなければなりません。このケースでは、「意志が確認できないではないか」「あくまで名義預金の漏れである」という理屈を押し通した結果、我々の主張が認められました。
「贈与が有利」なこともある
ただ、すべての相続について、今のやり方が「公式」のように当てはまるかというと、さにあらず、だからややこしい。名義預金にすると、税金を多く払わなければならなくなることもあるんですよ。
今年1月以降、相続税の最高税率(相続財産6億円超の場合)は、55%まで引き上げられました。相続財産が多ければ、そこに加えられる名義預金にも、そうした高率の税金が課せられることになります。贈与税も、最高税率は55%ですが、例えば1000万円までだったら、税率は30%ですみます。
結論を言えば、名義預金と贈与のどちらが“得”なのかは、遺産総額や移動した資金の金額などにより、ケースバイケースなのです。税務当局は、案件ごとに両者を天秤にかけ、「指摘」を使い分けてくるわけです。 もちろん、「正しい申告」をしなければいけません。でも、少なくとも「無知」だったために、払わなくてもいい税金を払わされるのは、避けたいもの。ただし、このレベルの話になると、素人が「徴税のプロ」に立ち向かっても、勝ち目はないものと思ってください。やはり、相続に強い税理士の力を借りるべきでしょう。
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士は聞いた!お金の現場
- あなたの相続にも「税務調査」が入る!?

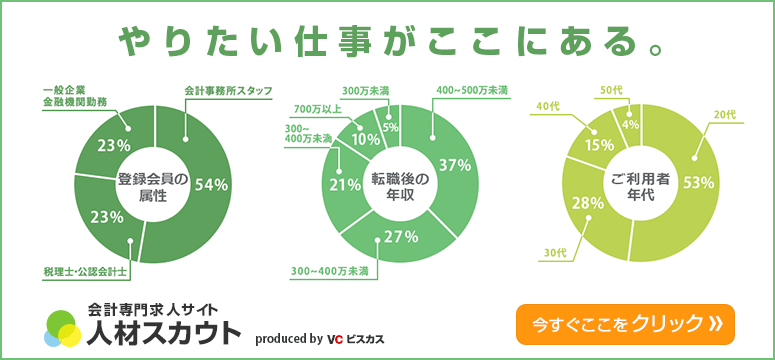
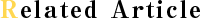 -あなたにおすすめの記事-
-あなたにおすすめの記事-
-あなたにおすすめの記事-
-
多様化する“愛の形”と相続

2015.2.18
-
みんなが敬遠する?農地の相続

2017.6.13
-
相続税の今後の動向と対策

2010.8.17
-
相続で子を争わせたくなかったら、 しっかり「遺言書」を
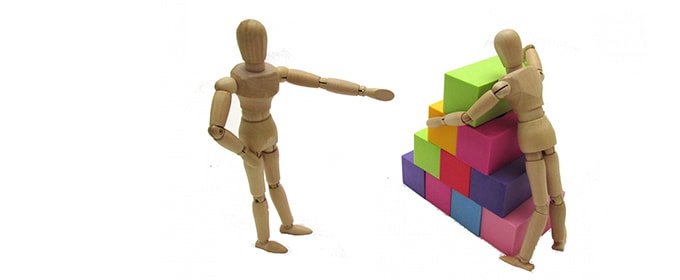
2017.6.13