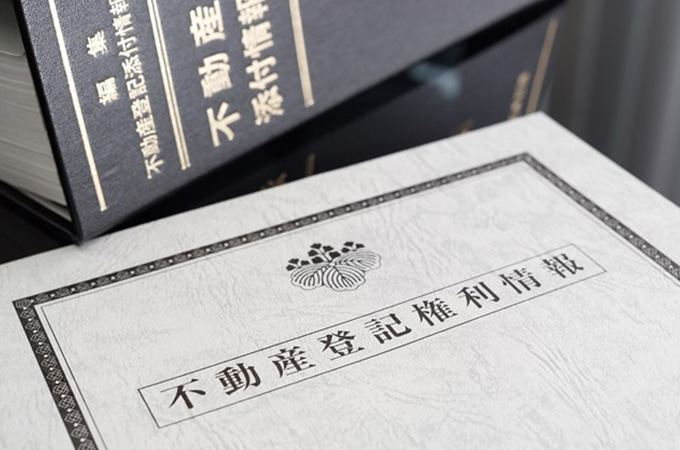昨年、「相続登記」の義務づけなどを内容とした「民法等の一部を改正する法律」「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が国会で成立しました。全国で増え続けている「所有者不明土地」対策を目的としたものですが、登記を怠ると10万円以下の過料の対象となることなどが、盛り込まれています。また、法改正以前の不動産も対象となる点にも、注意が必要。「不動産相続」のどこが変わるのか、注意点は何かについて解説します。
相続登記とは?
不動産を相続したら必要な手続き
今回の法改正のメインである「相続登記」とは、そもそもどういうものなのでしょうか?
被相続人(亡くなった人)から自宅、アパートなどの不動産を相続したら、その名義を相続人名に変更する必要があります。この名義変更登記手続きが「相続登記」です。
相続登記の申請は、対象不動産の所在地を管轄する法務局で行います。相続する不動産が複数の地域にある場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局ごとに申請しなければなりません。
相続登記しないデメリット
相続登記は“必要”ですが、現在のところ義務ではありません。24年4月1日から義務化されるのには、後述するように国や地方自治体、あるいは民間企業レベルでの土地の管理や利用上の問題が背景にあります。同時に、個人(相続人)にとっても、相続登記をしないと(過去の相続で相続登記が行われていないと)、次のようなデメリットが生じます。
デメリット1:売却できない
相続した不動産を売却して現金化するためには、相続登記が必要です。登記簿で相続人の名義であることが確認できない土地や家屋を購入する人は、まずいません。
デメリット2:不動産を担保に借金できない
土地を担保に金融機関から借り入れを行おうと思っても、同じ理由でNGです。例えば、相続対策で賃貸アパートを建設するため、土地を抵当に入れて借り入れを希望しても、以前の相続のときに正しい名義変更が行われていなかったために断られる、といったことも起こり得ます。
デメリット3:土地の利用も不可
賃貸物件を建てるときには、ハウスメーカーや不動産業者が土地の権利者を確認します。登記簿で正しい名義人が確認できないのでは、彼らも二の足を踏むでしょう。結局、土地は利用することができず、“宝の持ち腐れ”になってしまします。
裏を返せば、不動産の売却や利活用などが念頭になく、今のようなデメリットが実感できないケースで相続登記の「サボタージュ」が繰り返され、それが所有者不明土地の増加につながる結果を生んだといえるでしょう。
制度改正の中身を解説
それでは、今回の法改正で具体的に何が変わるのか、みていきましょう。ポイントは3つあります。
不動産登記制度の見直し(所有者不明土地の発生予防)
3年以内の相続登記の申請を義務化
相続で不動産を取得した人には、その取得を知った日から3年以内に相続登記申請を行うことが義務付けられます。もし正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料(国や公共団体が国民に課す金銭納付命令)の対象となってしまいます。相続人が遺言で財産を譲り受けた場合も同様です。
- 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本などの必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する
- 遺言の有効性や遺産の範囲などが争われている
- 申請義務を負う相続人自身に重病などの事情がある
※数次相続:被相続人の遺産相続が開始された後、遺産分割協議や相続登記を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されること。