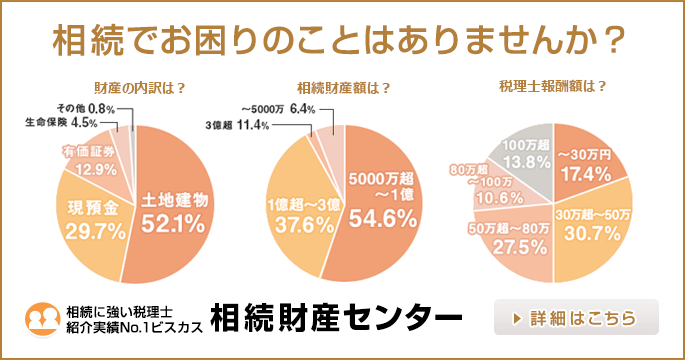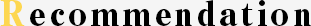特に問題のなかった兄弟仲が、親の相続で揉めたことが原因で、修復不可能なほど悪化してしまった――。残念ながら、それをフィクションとは言えない現実があります。相続をこじらせないために、注意すべきポイントは? 力になってくれる税理士は、どうやって選んだらいいのか? 相続に詳しい税理士法人アクトライズの松尾基宏先生にうかがいました。
数多くの相続を担当してきた先生からみて、「揉めない相続」のための秘訣はどこにあるのか、うかがっていきたいと思うのですが。
いろいろあるのですが、最初に「争った結果どうなるのか」について、お話ししておきたいんですよ。私の知る相続の中では、最長で7年間争ったケースがありました。お父さんが亡くなって、お母さんと子ども3人が相続人という事例だったのですが、長男が「跡取り」だからと、けっこうあった不動産などの大半をもらいたい、と主張したのが発端でした。
当人同士の話し合いではまとまらず、家庭裁判所での調停を申請。こうなると、もう税理士がどうこうできる話ではなくなります。それぞれが弁護士を立てて、争うことになりました。ちなみに、税理士は税金面のアドバイスを軸にして、遺産分割協議の全体をまとめていくことができますけど、弁護士は基本的に特定個人の「代理人」として働きます。
それぞれの利益を追求しようとしますから、事態はより悪くなりそうですね。
そうです。このケースも、結局調停ではケリがつかずに、裁判に持ち込まれました。ただ、長い時間をかけて裁判を戦っても、結果は法定相続分(※1)に沿ったかたちで分割せよ、という判決になることが多いんですよ。
しかも、単なる「痛み分け」では終わりません。長い時間弁護士を依頼すれば、報酬は馬鹿にならないでしょう。争った末に、トータルの取り分が減ってしまう。裁判までやったら、人間関係もガタガタになってしまうわけです。
※1法定相続分
被相続人(亡くなった人)の遺言書がない場合の、相続人それぞれの遺産の取り分。この事例では、配偶者が1/2、子どもは1/2を3人で案分し、1人1/6ずつとなる。
相続の際に、1人の相続人が「他の人よりもたくさん遺産をもらって当然だ」という態度を取るのは、揉める典型的なパターンです。今の事例では、長男がそういう誤りを犯したわけですが、実は背後には彼をけしかけた奥さんがいました。相続人ではないのに口を出す配偶者が相続をかき回すことも、珍しくないんですね。
今のように長男の嫁とか、ちょっと相続に詳しい旦那さんとか。
中には、堂々と遺産分割協議の場についてくる人もいるんですよ。当然、「あなたは、この遺産分割には関係ありません」とお引き取り願うのですが、たまに周囲も「まあ、いいじゃないか」という雰囲気になることもあります。しかし、これはNG。相続人以外の人物が協議に加わって全体のプラスになることは、何もないと考えてください。
私は、相続の際に、ことさら我慢する必要はないと思っています。ただし、主張の裏側には、他の相続人に納得してもらえるだけの行動、説得力が伴っていなくてはなりません。それを欠く「災いの芽」は、早い段階で摘んでおく必要があるのです。
理想的なのは、親族同士で常日頃から、ある程度のコミュニケーションが取れている状態。私のところに相談にいらっしゃる方は、相続のまとめ役の立場の場合が多いわけですが、その人が他の親族から信頼されている案件は、問題なくスムーズに進みます。
信頼されるためには、自分のことばかり考えていてはダメだということですね。
片方の親が亡くなる一次相続に比べて、残っていた親の二次相続は、揉めやすい傾向にあります。「目付け役」の親はおらず、子ども同士で遺産の分け方を決めることになりますから。問題を起こさないようにするには、一次相続の時に、二次相続まで見据えた遺産分割を行うことが大事になります。
一次相続では、配偶者控除(※2)が使えるわけですが、だからといってお母さんに遺産のほとんどを渡しても、そのお母さんが亡くなれば、結局子どもたちが相続することになります。一次、二次トータルの相続税は、かえって高額になる場合もあるのです。ですから、一次相続の時に、「目先の利益」だけにとらわれず、先々のことも考慮したシミュレーションを行う必要があるのです。加えて、私はその先のことも考えるべきだと思っているんですよ。
相続は、「二次相続」の後も続きます。例えば、遺産を受け取る子どもたちに家庭はあるのか、子どもはいるのか。そうしたことも踏まえて、将来のことを考えたら、「この人には不動産」「こちらには現金がいい」といったアドバイスが可能になる場合もあるわけですね。
なるほど。相続対策は決して税金の問題だけではないということが、よくわかります。
あえて付け加えておくと、普通はお父さんが先に亡くなるのですが、逆になることも、もちろんあります。私自身がそうだったのですが、母親の相続が先に来ると、いろいろと大変なのです。
さきほど配偶者控除の話をしましたけど、不動産などの資産の名義は父親になっている場合が多いですよね。お母さんは、控除してもらうような財産を、そもそも持っていないことが多い。配偶者控除による節税策が「使えない」のです。にもかかわらず、家計を管理するのは母親です。これが意外な盲点で、わが家ではすべての通帳を探し出すのに、とても苦労しました。
隠したつもりはなくても、他の家族に知らせていなければ、そうなりそうです。
恥ずかしながら、プロでもそんな目に遭いました。通帳や家の権利書の類は、ひとところにまとめておくとか、リストを作成しておくだとかの手立ては講じておくべきだと思います。
※2相続税の配偶者控除
配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものの額が1億6000万円まで、それを超えても法定相続分までは課税されない制度。
生前の対策も含めて、税理士にサポートを依頼したいという人はたくさんいます。ただ、みなさん迷うのが、「どの先生に頼むのがいいのか?」ということです。
ほとんどの税理士事務所は、無料相談に応じていますから、「これは」と思う先生がいたら、実際に会って話してみるのがいいのではないでしょうか。ポイントは、自分の家族のケースに見合った、的確なアドバイスがもらえそうかどうか。事務所のスタッフではなく、ちゃんと税理士が担当するのかどうかというのも、大事な点です。
そういうことを、実際に話をして確かめるわけですね。
最初に相談した先生に必ず頼まなくてはいけない、という決まりはありません。何人かに会ってみれば、自分に合う税理士に出会える確率も高まるはずです。


























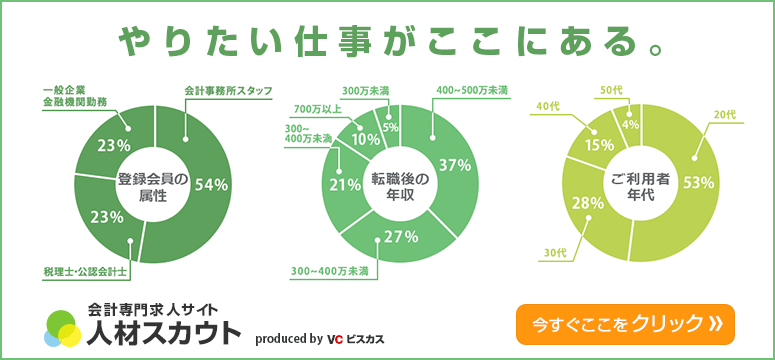
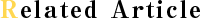 -あなたにおすすめの記事-
-あなたにおすすめの記事-