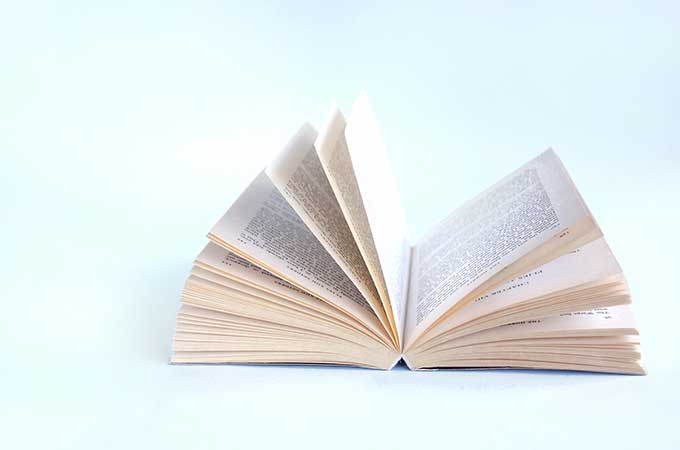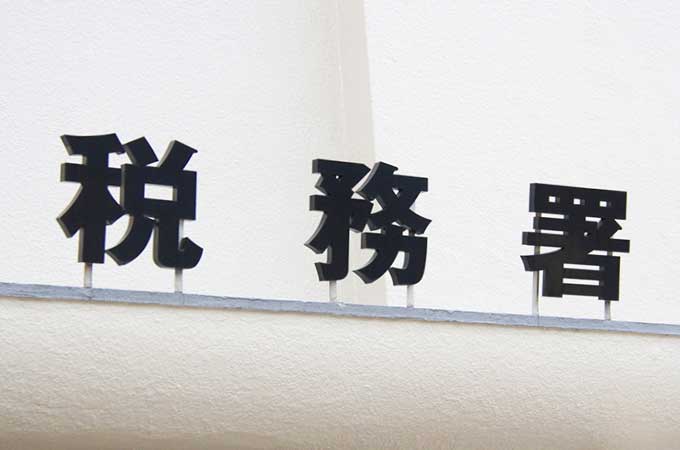法人から個人に戻りたい(個人成り)そのとき必要になることは?

「個人成り」を考える・考えたほうがいい状況とは?
法人にしておく意味がなくなった
一般的に、個人が法人成りする最大の理由は「節税」です。個人事業主のメインの税金は「所得税」ですが、これは所得が上がるにつれ、税率もアップしていく累進課税になっています。所得が一定のレベルを超えたら、事業に関しては税率が一定の法人税を支払いながら、自分は会社から給料をもらう形にしたほうが、納税額を抑えられることができるのです。
しかし、法人の所得が減少してくると、この話とは逆の現象が起きます。所得税にしたほうが、税金が安くなる状況が続きそうな場合には、個人成りを検討すべきでしょう。
この他にも、法人成りの大きな理由には「社会的信用度の向上」があります。例えば、法人のほうが仕事をもらいやすい、人材採用に有利だ、といった点です。こうしたことに重きを置く事業の場合には、節税効果と比較検討をして個人に戻るか・法人として継続するか決断すべきでしょう。
まだある「個人成り」のメリット
このほか、個人成りには、次のようなメリットがあります。
社会保険料の負担がなくなる
法人になると、たとえ社長1人の会社でも、厚生年金や健康保険などの社会保険への加入が義務づけられ、保険料の半分は会社が負担しなくてはなりません。保険自体はありがたいものですが、会社にとって保険料の支出は「痛手」で、それが原因で経営が危うくなるケースも珍しくありません。この負担がなくなるのは、経営者にとって大きなメリットです。
消費税の課税が2年間免除される
消費税が課税されている個人事業主が法人成りすると、最大2年間はその支払いが免除されます。個人成りの場合も同様で、再度2年間、消費税の支払いをしなくて済みます。
税務申告が楽になる
法人と個人の確定申告を比べれば、提出書類なども含めて、後者のほうがシンプルで作業は楽です。申告を税理士に依頼する場合でも、コスト削減が可能になるでしょう。
計画的な事業の縮小ができる
後継者難などを見越して、将来的には事業に見切りをつけたいというような場合にも、いきなり会社をたたむのではなく、個人成りして徐々に縮小させていくという方策を選ぶことができます。
「個人成り」のデメリットは?
個人成りのメリットを述べてきましたが、以下のようなデメリットもあります。
- 会社の解散・精算で手間と費用が発生する
- 法人の時のメリットをそのまま失う
- 法人の場合は有限責任だが、個人の場合は無限責任となる
- 役員報酬がなくなるので、自身への給与は払えなくなる
- 取引先に不信感を与えたり、取引そのものができなくなる可能性がある
- 許認可が必要な事業を営んでいる場合、再度個人で許認可を得る必要がある
- 法人の赤字を引き継ぐことができない
- 利益が出るほど、所得税等の徴収金額が上がる
- 法人では決算月を選ぶことができたが、個人では事業年度が1月1日~12月31日に限られる
- 法人の時の社会保険料より、国民年金や健康保険料のほうが高くなることもある
- 従業員がいる場合、個人成りに対する理解を得る必要がある
等々…
特に注意したいのが、以下の点です。
法人の場合は有限責任だが、個人の場合は無限責任となる
万が一、事業を清算せざるを得なくなった場合、法人(株式会社・合同会社)の出資者は、出資額以上のマイナスを背負うことはありません。例えば100万円出資していた場合、会社が倒産したらその100万円は返ってきませんが、それを超える債務があっても、債権者から返済を迫られることはないのです。一方で、個人事業では、債務があれば、その全てに弁済の義務が生じます。
取引先に不信感を与えたり、取引そのものができなったりする可能性がある
先述の通り、社会的信用度という点では、個人よりも法人が有利です。中には、“法人でなければ取引しない”という会社もありますので、注意が必要です。個人成りを考える場合には、現在の取引先との関係はもとより、将来的にそうした問題が生じるリスクはないかをよく検討すべきでしょう。
許認可が必要な事業を営んでいる場合、再度個人で許認可を得る必要がある
許認可を必要とする事業を営んでいる場合には、より慎重さが求められます。個人成りしたら、あらためて許認可を取得し直す必要があるからです。個人になったことで認められなくなる可能性などはないか、事前に十分調べるようにしましょう。
法人の赤字(繰越欠損金)を引き継ぐことができない
法人は、赤字を10年間繰越す(その間に出た黒字と相殺して所得を減らす=法人税を減額する)ことができます。逆に個人では、赤字を繰り越せるのは3年に短縮されてしまいます。個人成りにより、法人で出た赤字を個人事業に引き継ぐこともできません。
これらのデメリットを踏まえて、個人成りをするか法人のままで継続するかを考えましょう。
個人と法人の違いをおさらいしよう
個人成りの方法を述べる前に、個人事業と法人の違いをあらためて確認しておきましょう。
個人事業主とは
法人を設立せずに、個人で事業を営むのが「個人事業主」です。税務署に開業届を提出することで、基本的に誰でも個人事業主になることができます。脱サラして独立する場合などには、ここからスタートして「法人成り」を目指す、というパターンが多いでしょう。ちなみに、開業届を提出せずに個人で仕事をしている人もいます。
法人とは
「法人」は、法律により“人”と同じ権利・義務を認められた組織のことです。法人は、私法人と公法人(地方公共団体や社会福祉法人、一般社団法人など)に分かれ、さらに私法人には、株式会社をはじめとする会社(営利法人)と、NPO法人などの非営利法人があります。この記事でいう法人は、「会社」のことです。
それぞれかかる税が違う
両者の大きな違いは、冒頭で説明したように、課税されるメインの税金が異なることです。個人は「所得税」(税率は、所得が増えるほど税率も上がっていく「累進課税」)、法人は「法人税」(基本税率23.2%)が課税されます。法人のほうが、所得から差し引ける必要経費の幅が広く認められる、といった違いもあります。
個人事業の主なメリット・デメリット
個人事業のメリット
- コストをかけずに開業でき、手続きも楽
- 経理や税務申告の作業が楽
個人事業のデメリット
- 社会的信用力が低い
- 所得が増えると税負担が重くなる
法人の主なメリット・デメリット
法人のメリット
- 所得が一定以上になると、節税効果が大きい
- 社会的信用力が高い(人材を集めやすい、資金調達がしやすい)
法人のデメリット
- 会計、税務申告が煩雑になり、コストもかかる
- 赤字でも支払う税(法人住民税均等割額)がある
- 社会保険への加入が「強制」で、コストが発生する
「個人成り」に必要な手続き
個人成りの流れは、大まかに3つのステップに分かれています。
- 法人の廃止手続きを行い、税務署に書類を提出する
- 個人事業主として開業手続きを行う
- 開業した個人事業に、かつての会社の資産や権利を移転させる
法人の廃止手続きの方法は2つある
個人事業に戻るためには、まず法人の事業をストップさせなくてはなりません。それには、次の2つのやり方があります。
(1)会社を解散・清算する
1つは、会社を解散し、債権・債務などを清算して、事業活動を完全にやめる方法です。実は会社の解散については、会社法に事由(条件)が定められていて、勝手に「なくす」ことはできないのですが、いわゆるオーナー社長であれば、実質的に1人で決めることができます(株主総会の決議)。
ただし、解散しただけでは、会社は消滅しません。もし、会社に債権・債務があった場合には、その清算手続きが必要になりますので、この方法を考えるときには、注意しましょう。
なお、会社の解散には、「解散の登記」「清算人選任の登記」「清算完了の登記」が必要で、合わせて4万1,000円の登録免許税がかかるほか、官報公告費用として3~4万円のコストが発生します。複数回の確定申告なども必要になるので、これらの手続きを税理士や司法書士などの専門家に依頼した場合、会社の規模などにより10万円~数十万円程度必要になります。つまり、会社をたたむのにもお金がかかるわけです。
会社の解散・清算の流れ
会社の解散・清算の流れは、以下のようになっています。
- 株主総会の解散決議・清算人の選任
- 現状の業務(現務)の終了・清算事務の開始
- 解散及び清算人の登記
- 解散日現在の財産目録と貸借対照表の作成と株主総会の承認
- 債権申出の公告及び債権者への通知
- 債権取立て・財産換価処分・債務弁済
- 清算事務年度の株主総会
- 残余財産の確定・分配
- 決算報告の作成と株主総会の承認
- 清算結了登記
(2)会社を休業させる
2つ目は、会社自体は存続させたまま「休業」扱いにする方法です。登記が必要な(1)よりも手続きが簡単でコストもかからないため、実際の個人成りにおいては、こちらを選択するケースが多いようです。休業させておけば、再び法人に戻ることも容易である、というメリットもあります。
休業する際には、税務署や都道府県、市町村に「異動届出書」を提出する必要があります。また、従業員がいた場合には、「給与支払事務所の廃止届出書」も提出することになります。
休業中は利益が出ないはずですから、法人税を支払う必要はありません。ただし、地方法人税の均等割(赤字の会社にも課せられる地方税)年7万円の納付が義務づけられていて、これが休業のデメリットと言えるでしょう(自治体によっては減免措置を講じているところもあります)。
休業の流れや注意点
休業の流れや注意点は、以下の通りです。
- 事業の停止
※法人の事業活動を完全に停止させる必要がある。 - 税務署への「休業届(異動届出書)」「給与支払事務所等の廃止届出書」「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」(消費税課税事業者だった場合)の提出
- 都道府県税事務所、市区町村役場への「休業届」の提出
- 休業届の受理・休眠状態
登記簿上でのみ存在する会社として扱われるが、最後に登記を行った日から12年以上経過すると、解散したものとみなされる恐れがある。 - 税務申告
休業中も税務申告は必要。2年連続して期限内に税務申告を行わなかった場合、青色申告の承認が取り消される。また、休業中に税務申告のない年度があれば、繰越欠損金を適用できなくなる。 - 役員変更登記
会社の役員(取締役など)には任期が設定されているため、任期満了時には役員の改選および役員変更の登記を行う必要がある。 - 「異動届出書」の提出
休業届を提出した税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に対して、それぞれ事業を再開する旨の届出を行う。 - 休業中の会計処理・確定申告
休業中の売掛金の回収や買掛金の支払いなどを中心に会計処理を行い、過去の確定申告を行っていなければ、まとめて行う。青色申告が取り消されている場合には、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する。
―休業中―
―事業を再開させる場合―
個人事業主に戻るためには、個人事業主として開業の手続きを行う
個人で事業を始めるためには、業種や希望する特例(例えば青色申告)によっても異なりますが、基本的に次のような書類が必要になります。
- 個人事業の開業届出・廃業届出
- 所得税の青色申告承認申請
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
これらの書類はいずれも、管轄の税務署に提出しましょう。
個人事業主として開業する際の注意点
新たに個人で事業を行うわけですから、法人が行っていたこと、持っていたものは、すべてを受け継がなくてはなりません。
- 銀行口座は法人用を廃止し、個人用を開設する
- 法人名義の不動産や車両を買い取り、名義変更する
- 国民健康保険、国民年金への切り替え
などを忘れずに行いましょう。
法人時にあった借入金(債務・債権)の清算のしかた
会社を解散するのであれば、手続きに費用がかかるのはもちろんのこと、「解散=法人の消滅」ですから、会社が有している資産(債権)も会社が負っている債務も全て清算しなければなりません。法人から個人事業主になる際の借入金の清算方法、資産の引き継ぎ方法についても知っておきましょう。
借入金の清算方法
清算中の会社の業務執行や管理運営は「清算人」が行います(会社法第481条)。小規模法人であれば代表取締役(または役員)が清算人に就任することが多いでしょう。
解散時、金融機関等に借入金がある場合はまず融資担当者に相談しましょう。会社が持つ設備や不動産等の資産を全て売却し、借入金の返済にあてるのが通常ですが、それでも多額の負債が残り、返済が不可能なレベルであれば、民事再生手続を考えることになります。
もっとも、融資に関していわゆる「経営者保証契約」を金融機関と締結している場合であれば、法人の債務履行が、個人事業主となる経営者の保証債務履行へ移行するので、引き続き個人として残債務の返済を行っていくことになります。
資産の引き継ぎ方
法人の資産は全て売却しなければなりませんが、個人成りの場合、設備や建物などは、個人事業主となる元経営者が引き続き使用するとして購入し、代金を会社に支払うのが通常の形です。売却額は市場における時価が原則です。
解散手続関連の費用支払いや借入金の清算が終了し、なお残余財産があれば、株式会社であれば株主に、持株割合に応じて分配します。この時点でようやく、個人事業主に戻る経営者に対し、持株分の法人の資産が引き継がれることになります。
まとめ
法人から個人成りする場合には、会社を解散ないし休業させたうえで、個人事業主としての届出を行う必要があります。特に解散の場合の手続きは複雑です。ミスなく円滑に進めるためには、税理士などの専門家のサポートを検討すべきでしょう。
よくある質問
個人成りの手続きはどのように進めればよいですか?
個人成りには、まず法人の解散手続きを行い、その後、税務署に個人事業主としての開業届を提出します。法人解散には株主総会での決議と登記が必要です。必要に応じて許認可の再取得や取引先との契約見直しも行います。
個人成りのメリットは何ですか?
個人成りのメリットには、社会保険料の負担軽減、税務申告の簡素化、経営の柔軟性の向上などがあります。また、個人事業主としての税制優遇措置も受けられます。
個人成りのデメリットは何ですか?
個人成りのデメリットには、法人の信用力低下、法人税控除の損失、社会保険の加入義務がないことがあります。事業の拡大を考える場合、個人事業の枠組みでは限界があります。
個人成りに必要な書類は何ですか?
個人成りに必要な書類には、法人の解散登記書類、個人事業主としての開業届、廃業届、各種許認可の再取得書類などがあります。具体的には、定款、株主総会議事録、登記申請書類、税務署への届出書類が含まれます。
個人成りする際の税務上の注意点は何ですか?
個人成りする際の税務上の注意点には、法人から個人への資産移転による譲渡所得税の発生、個人事業主としての所得税申告、消費税の免税措置などがあります。適切な税務処理を行うために税理士に相談することが重要です。
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税金情報 >
- 法人から個人に戻りたい(個人成り)そのとき必要になることは?