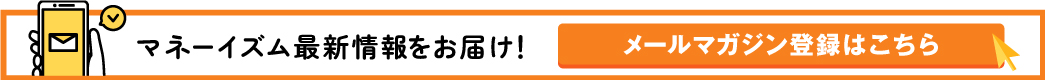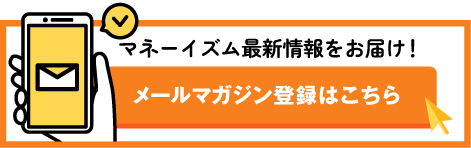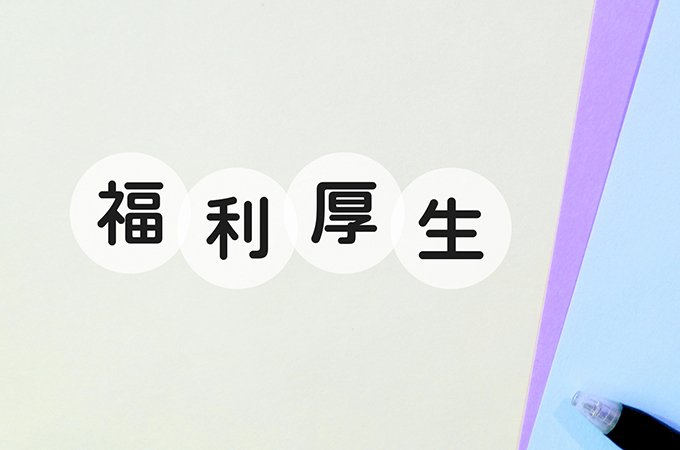勤めている会社を退職した場合は、退職の手続きを行い、失業保険を受け取ることができます。しかし、失業保険を受給した場合に気になるのが税金のことです。失業保険を受給したら税金は課されるか、確定申告が必要なのか気になる人も多いでしょう。
そこで、ここでは失業保険と確定申告の関係について詳しく解説します。
そもそも失業保険とは
失業保険とは、求職者が安定した生活を送りつつ、就職活動に専念できるようにサポートする保険のことです。
また、受給するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
- 離職日以前の2年間で雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある(会社都合退職などの場合は離職日以前の1年間で6カ月以上)
- 就労の意志と能力があり、前向きに求職活動をしている
失業保険は、退職したすべての人が受け取れるわけではありません。
そのため、失業保険の受給と確定申告について考える際は、まずは受給できる条件を確認し、「そもそも失業保険の対象外だった」とならないように気を付けてください。
なお、失業保険の給付日数も退職理由や被保険者期間によって90日から330日と幅広く設定されているため、気になる方は事前にハローワークに確認しておきましょう。
失業保険は税金がかからない
1年間に収入がある人は、サラリーマンを除いて原則、確定申告をして税金を納める必要があります。しかし、収入の中には、税金が課されないものもあります。税金が課されない主な収入(非課税所得)は、次の通りです。
・非課税所得の代表例
| 区 分 | 非課税所得の項目 |
|---|---|
| 利子・配当所得に関するもの | ・障害者等の少額預金の利子 ・勤労者財産形成住宅や勤労者財産形成年金貯蓄等の利子等 ・納税準備預金の利子 ・NISA、ジュニアNISAに係る配当等 |
| 給与所得・公的年金に関するもの | ・傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金等 ・給与所得者に支給される一定の旅費、限度額内の通勤手当など ・国外で勤務する者の受ける一定の在外手当 ・文化功労者年金法の規定による年金等 |
| 譲渡(山林)所得に関するもの | ・生活に通常必要な動産の譲渡による所得 ・NISA、ジュニアNISAに係る譲渡所得等 ・国や地方公共団体等に財産を寄附した場合の譲渡所得等 |
| 一時所得、雑所得に関するもの | ・学資金及び扶養義務を履行するために給付される金品 ・相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの ・心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料など ・生活支援定額給付金など |
| 他の法律で課税されないもの | ・失業保険、失業給付金(雇用保険法) ・宝くじの当選金(当せん金付証票法) |
さまざまある非課税所得の中に、失業保険や失業給付金も含まれています。そのため、失業保険には税金がかかりません。
確定申告をする場合は失業保険の申告は必要?
失業保険を受給した年の確定申告を自身で行う場合、失業保険の申告は基本的に不要です。
前述したとおり、失業保険で受け取った手当には税金がかかりません。税金がかからない失業保険を、税務署にわざわざ申告する必要はないのです。
年末調整をしてもらう場合は失業保険の申告は必要?
失業保険を受給した年に就職し、就職先の会社に年末調整をしてもらう場合も、失業保険の申告は不要です。
確定申告と同様に、年末調整においても税金のかからない収入は申請する必要はないため、失業保険を会社に伝える必要はありません。
ただし、退職から再就職するまでに雑所得などを得ていたり、副業で会社以外の収入があったりなど、その年の総所得が20万円を超えている場合は、年末調整とは別に確定申告が必要となりますので覚えておきましょう。
失業保険で確定申告をしたほうが良いケース
失業保険には、税金がかかりません。そのため、原則、確定申告は不要です。しかし、失業保険を受給している場合でも、確定申告をしたほうが良い場合もあります。それは税金の還付があるときです。
ここでは、失業保険で確定申告をしたほうが良い代表的なケースを見ていきましょう。
年内に再就職をしなかった場合
サラリーマンは、毎月の給料から所得税などが天引きされています。これを源泉徴収といいます。実は、源泉徴収されている所得税の金額は、通常であれば年末調整で追加の天引きがないような金額になっています。むしろ、年末調整で還付になる場合も多いです。
では、年の途中で退職した場合はどうかというと、退職時に年末調整はされません。再就職した勤務先で、退職前の給料と再就職先での給料を合算して年末調整されます。年内に再就職をしなかった場合は、年末調整が受けられません。
源泉徴収されている所得税の金額が大きい場合は、確定申告で還付を受けられる可能性があります。所得税の還付がある場合で、還付される金額と確定申告の手間を考え、所得税の還付を受けたほうが得と判断した場合は、確定申告をしたほうが良いでしょう。
失業中に支払った社会保険料がある場合は通常、社会保険料控除の金額が増加し、還付される税金の金額が増えるため、忘れずに社会保険料控除に含めましょう。
医療費控除などがある場合
1年間に一定金額の医療費を支払った場合は、医療費控除を受けることができます。ただし、医療費控除は年末調整で控除されません。医療費控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
年内に再就職をしなかった場合も、年内に再就職した場合も、医療費控除を受けて税金の還付を受ける場合は、確定申告を行いましょう。
失業中に収入がある場合
失業中、再就職先が見つかるまでの間に、アルバイトやパートなどをするケースも多いです。失業保険は税金がかかりませんが、アルバイトやパートなど給料は税金が課されます。また、副業で不動産収入がある場合なども、その収入には、税金が課されます。そのため、失業中に収入がある場合は、原則、確定申告をする必要があります。
失業保険の確定申告についてのよくある質問
失業保険を受給する方の中には、初めて受給する方もいるでしょう。安心して受給するためにも、事前によくある質問を確認しておいてください。
失業保険の確定申告についてのよくある質問は、以下のとおりです。
- 失業保険についての還付金はもらえるの?
- 失業保険と同時に退職金を受け取った場合は確定申告が必要?
- 失業保険の「再就職手当」は確定申告が必要?
- 失業保険は「年収」に含まれる?
失業保険についての還付金はもらえるの?
結論から言うと、失業保険についての還付金はありません。
ただし、退職した年に確定申告をすることで、退職した会社から源泉徴収されていた所得税額などが還付される場合があります。
会社などから給料が支払われる際、基本的に給料から源泉徴収が天引きされます。そして、給料所得の場合、源泉徴収税額は、扶養家族の人数によって異なります。
例えば、社会保険料などの控除が差し引かれた後の給料が「30万円」である場合、扶養親族がいない場合「8,420円」、扶養親族が1人の場合「6,740円」です。
このように、会社から毎月引かれている源泉徴収は、会社があなたの代わりに支払っている税金であるため、退職して所得が大幅に減少することで、払い過ぎた税金が確定申告で還付されるのです。
失業保険と同時に退職金を受け取った場合は確定申告が必要?
前述したとおり、失業保険を受け取っただけでは、わざわざ確定申告をする必要はありません。しかし、退職金を受け取った場合は、確定申告をして控除などを清算しましょう。
退職金を受け取って確定申告をしないと、退職金すべてに20.42%の所得税と復興税が課せられてしまいます。
例えば、勤続年数30年で2,500万円の退職金を「退職所得控除」を適用して受け取ると、以下のとおりです。
勤続年数30年分の退職金控除の計算式
課税退職所得金額の計算式
所得金額500万円の所得税の計算式
また、復興税2.1%を考慮すると、「58万4,522円」です。
ただし、退職金を受け取った会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、会社側が所得税や住民税の計算をしてくれるため、個人で確定申告をする必要はありません。
失業保険の「再就職手当」は確定申告が必要?
再就職手当も失業保険同様に確定申告は必要ありません。
再就職手当とは、失業保険の受給中に安定した勤務先に就職した人が受け取れる手当のことです。
ただし、再就職手当を受け取るには、いくつかの条件があります。
例えば、失業手当の支給残日数が3分の1以上であることや、再就職先での就業期間が1年を超えての勤務であることなどです。
再就職手当を受け取っても、確定申告をする必要はありませんので安心してください。
失業保険は「年収」に含まれる?
就職活動をしていると、応募先企業から「直近の年収」について聞かれることもあるでしょう。その際に、失業保険で受け取った手当も年収に入るのか疑問に感じる方もいるかと思います。
結論としては、失業保険は「年収」に含まれません。
そのため、前職や直近の年収を企業に聞かれた際は、その年に受け取った給料などの所得を合計した金額を答えましょう。
失業保険を年収に合わせてしまうと、就職後に源泉徴収票を提出した際に聞いていた年収と異なり、入社した企業に不信感を与えてしまう可能性があるため注意が必要です。
つまり、勤続年数30年で退職金2,500万円の場合、課税退職所得金額は500万円となります。

失業保険を受給した場合の確定申告の方法と手順
失業保険を受給した場合であっても、税金の還付を受ける場合や、失業中に収入がある場合は確定申告が必要です。
ここからは、失業保険を受給した場合の確定申告の方法と手順について見ていきましょう。
失業保険を受給した場合の確定申告の期間と手順
失業保険を受給した場合で確定申告を行う期間は通常、翌2月16日から3月15日までです。失業中に収入があって所得税の納付がある場合は、所得税の納付期限も同じ3月15日までです。所得税の還付がある場合は、翌1月1日から申告をすることができます。
次に、確定申告の手順について見ていきましょう。確定申告の手順は、次のようになります。
①必要書類の用意
確定申告書の書類は税務署の窓口や国税庁のホームページから入手します。生命保険料などの控除証明書は、保険会社から送付されてきます。
②確定申告書の作成
必要書類がそろったら、確定申告書を作成します。確定申告書に、住所・氏名などの納税者の情報、収入や所得金額、所得控除金額、納税額などの必要事項を記載します。
会計ソフトや国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーなどを利用して、確定申告書などを作成する場合は、必要事項を入力していくことで、所得金額や税額などが自動で計算され、確定申告書ができあがります。
③確定申告書の提出
確定申告書が作成できたら、税務署に提出します。税務署の窓口に持参、郵送、e-Taxの3つの提出方法があります。
- 税務署の窓口に持参
作成した確定申告書とその控えを、税務署の窓口に提出します。 - 郵送
所轄の税務署に、郵送で確定申告書などを提出します。郵送で提出する場合は、確定申告書などの控えや、切手を貼った返信用封筒も同封します。
郵送での提出期限は、提出期限の消印が有効となります。 - e-Tax
e-Taxを利用して、電子データのかたちで、確定申告書などを税務署に申告します。
e-Taxの利用には、事前に届出が必要です。
④所得税の納付や還付
確定申告を行い、納める税額がある場合は、所得税を納付します。所得税の還付がある場合は、確定申告書に記載した還付口座に、確定申告書の提出から1か月程度で還付されます。
失業保険を受給した場合の確定申告で必要な書類
失業保険を受給した場合の確定申告で必要な書類は、次の通りです。
・確定申告書A
確定申告書は、税務署の窓口や国税庁のホームページから入手できます。
確定申告書にはAとBの2種類がありますが、収入が給与のみ(アルバイト・パートも含む)の場合は、確定申告書Aを用います。
・その年のすべての勤務先の源泉徴収票(退職前、再就職先、失業中に行ったアルバイトやパート先)
・生命保険料などの所得控除証明書
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合)など
医療費控除の明細書や住宅ローン控除を受ける場合の住宅借入金等特別控除額の計算明細書など、状況によって必要書類が異なる場合があります。
YouTubeでポイントを解説中!
【知らないと危ない確定申告】もらった失業保険に税金はかかる?
ビスカス公式YouTubeチャンネルのご案内
ビスカス公式YouTubeチャンネル「3分でわかる税金」では、お金に関する疑問を分かりやすく簡単に紹介中!
チャンネル登録はこちら:3分でわかる税金
まとめ
失業保険には、所得税などの税金は課されません。そのため、原則、失業保険の受給に関する確定申告は不要です。
しかし、税金の還付がある場合や失業中に収入がある場合は、確定申告が必要です。特に、税金の納付がある場合は、申告・納付期限を遅れてしまうと、延滞税などのペナルティが発生することもあります。忘れずに期限内に申告しましょう。