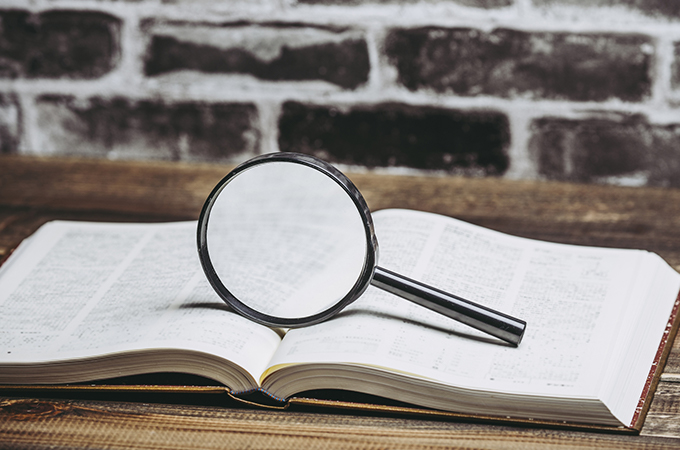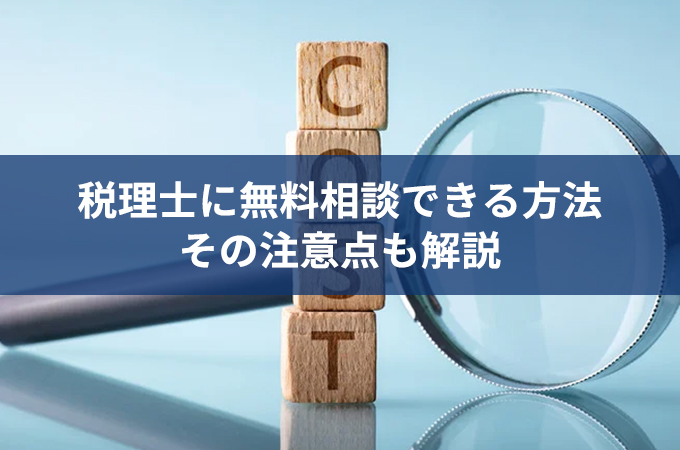資金調達で頼れる税理士とは?創業融資から補助金申請まで、資金不足を回避するには

- 最終更新日:
- 2025/08/26

- この記事の監修者
- Vmaster税理士事務所
所長 松田 光弘(税理士)
資金調達の基本知識と税理士サポートが効果的な方法
資金調達の基本的な仕組みから、税理士のサポートで成功率が向上する融資・補助金制度まで、企業が知っておくべき資金調達の全体像を解説します。
資金調達の基本と企業が検討すべきタイミング
資金調達とは、事業の運営や拡大に必要な資金を外部から集めることです。
設備投資や運転資金の確保、新規事業や研究開発など、企業は成長の節目ごとに多額の資金を必要とします。
では、どのようなタイミングで資金調達を検討すべきでしょうか?主なケースは以下の通りです。
- 成長期:売上急増による運転資金不足(例:大型受注で材料費が先行して必要になる場合)
- 拡大期:新規設備や店舗展開のための投資資金
- 季節変動期:繁閑の差が大きい業種での一時的な資金ショート
- 再建期:経営改善や事業転換に必要な運転資金
これらのタイミングを適切に見極め、計画的に資金調達を行うことが、持続可能な企業経営の基盤となります。
主な資金調達方法と成功事例の傾向
税理士の専門性を最も活かしやすい資金調達方法をご紹介します。
銀行融資
銀行融資や信用金庫などの金融機関への融資申請では、税理士が作成する精度の高い財務資料と事業計画書が審査通過の鍵となります。特に返済能力の根拠づけや資金使途の明確化において、財務の専門家である税理士の知見が威力を発揮します。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金(2025年8月時点)では、原則として無担保・無保証人での利用が可能で、利率は一律0.65%引下げ(雇用拡大時は0.9%引下げ)となっています。返済期間は以下の通りです。
- 設備資金:20年以内(据置5年以内)
- 運転資金:10年以内(据置5年以内)
従前の「自己資金1/10」要件は廃止されていますが、自己資金が多いほど審査上は有利になります。
関連:日本政策金融公庫(創業融資・利率等) 創業融資のご案内
補助金・助成金申請
税理士による申請書類の作成支援は、採択率向上に直結する傾向があります。補助金・助成金は申請書類が複雑で専門知識が必要なため、税理士のサポートが特に有効です。
中小企業新事業進出補助金(令和7年8月時点)の概要は以下の通りです。
- 対象要件:新事業進出要件、付加価値額要件、賃上げ要件、金融機関要件等
- 計画策定:補助事業実施にあたって金融機関からの融資を受ける場合は、融資元の金融機関から事業計画の確認を受けることが前提
- 補助上限:中小企業で従業員規模に応じて2,500万〜7,000万円(賃上げ特例の適用で上乗せあり)
- 補助率:1/2
- 採択率:約15%(事務局の事前想定)
関連:中小企業新事業進出補助金
補助金・助成金の違いと申請時の注意点・リスク
補助金と助成金の基本的な違い
補助金と助成金は、どちらも返済不要の資金調達手段ですが、重要な違いがあります。
- 補助金:経済産業省や中小企業庁、地方自治体などが管轄し、事業の革新性や成長性を競争審査で評価。採択率は20〜30%程度と限定的
- 助成金:厚生労働省が管轄し、雇用創出や労働環境改善を目的として要件を満たせば原則受給可能
申請時の重要な注意点
税理士のサポートを受ける際も、以下のリスクを理解しておくことが重要です。
- 後払い制:多くの制度で費用を先に支出し、後から交付される仕組み
- 用途限定:対象経費が厳格に定められており、目的外使用は返還対象
- 税務上の取扱い:補助金収入は法人税・所得税(事業所得)の課税対象となり、適切な会計処理が必要
- 実績報告義務:交付後も定期的な報告や検査が求められる場合がある
税理士は申請から事後処理まで一貫してサポートできるため、これらのリスクについて対策を検討しながら効率的に活用できます。
その他の調達手段と税理士の関わり方
ベンチャーキャピタル出資、ファクタリング(売掛債権売却)、クラウドファンディングなどの手法もあります。これらの場合、税理士は主に税務・会計面でのアドバイスを担当し、法的な契約条項については弁護士との連携が重要となります。
資金調達における税理士の具体的な役割とメリット
税理士が資金調達プロセスでどのような役割を果たし、どんなメリットを企業にもたらすのか、具体的な業務内容と注意点を詳しく解説します。
税理士がサポートできる資金調達の具体的場面と業務範囲
税理士は資金調達のあらゆる段階で専門的なサポートを提供できます。書類作成から金融機関との交渉、事後フォローまで、幅広い業務に対応可能です。
書類作成・財務分析
事業計画書、損益計画、資金繰り予測などの作成において、金融機関の審査基準を熟知した税理士ならではの精度の高い書類を作成できます。
金融機関との面談・交渉同席
審査担当者との面談に税理士が同席することで、専門的な観点から説明を補足し、金融機関からの信頼獲得につながります。決算内容や返済計画について、第三者の専門家として客観的な説明を行います。
補助金申請から事後フォロー
申請書類の作成から採択後の実績報告書作成まで、一貫したサポートを提供します。顧問税理士であれば、企業の財務状況を日常的に把握しているため、最適な調達タイミングや手法についてアドバイスできます。
税理士活用で得られる主なメリットと成功事例の傾向
税理士に資金調達の支援を依頼することで、企業は様々なメリットを享受できます。特に審査通過率の向上と時間効率の改善は、多くの企業が実感する効果です。
審査通過率の向上
金融機関の審査基準や必要資料を熟知した税理士の確認を経て作成された書類は、審査担当者にとって理解しやすく、結果として融資や補助金の審査通過率向上につながる傾向があります。
時間効率の大幅改善
膨大な書類作成や手続きについて税理士の支援を得ることで、経営者は本業に専念できます。複数の金融機関の特徴を把握している税理士なら、企業に最適な調達先を効率的に提案できます。
税務リスクの事前回避
資金調達後の資金使途や税務処理について適切なアドバイスを受けることで、税務調査でのトラブルを未然に防げます。
金融機関との継続的関係構築
顧問契約により定期的な業績・資金繰り情報をタイムリーに整備・共有できるため、結果として金融機関とのコミュニケーションが円滑になります。将来的な追加融資や条件変更の相談もスムーズに進められます。
税理士依頼時の注意点とリスク管理のポイント
税理士への依頼は多くのメリットがありますが、事前に理解しておくべきリスクや注意点もあります。適切な判断のために重要なポイントを確認しましょう。
- 費用対効果の慎重な検討:
着手金や成功報酬など相応の費用が発生するため、特に小規模な資金調達では費用対効果を慎重に検討する必要があります。 - 税理士の専門分野の見極め:
すべての税理士が資金調達に精通しているわけではありません。記帳代行中心の事務所と資金調達を得意とする事務所では、提供できるサービスレベルに大きな差があります。 - 過度な期待の禁物:
税理士に依頼しても必ず資金調達が成功するとは限りません。無理な売上予測を立てた結果、融資後の返済計画が破綻するケースも見られます。現実的な計画策定と企業体質の改善が前提となります。
資金調達に強い税理士の選び方と実績の見極め方
資金調達を成功に導く税理士を見つけるための具体的な選定基準と、税理士紹介サービスの効率的な活用方法をご紹介します。
優秀な税理士を見分けるポイントと評価基準
最も重要なのは過去の実績です。自社と同じ業種・規模での成功事例があるか、過去3年間の支援件数や調達総額などを具体的に確認しましょう。業界特有の事情を理解している税理士なら、より実践的なサポートが期待できます。
よくある失敗パターンと対策
資金調達で税理士選びに失敗するケースは珍しくありません。実際の失敗例をご紹介します。
失敗例1:記帳代行メインの税理士への依頼
「顧問税理士に融資相談をしたところ、金融機関に提出する事業計画書の精度が低く、審査で指摘が多発。結果的に融資が否決され、他の税理士に相談し直すことになった」
失敗例2:補助金申請の経験不足
「ものづくり補助金の申請の支援を依頼したが、十分な精度の申請書が出来上がらず不採択。後で分かったことだが、その税理士は補助金申請支援の経験がほとんどなかった」
失敗例3:金融機関とのコミュニケーションスキル不足
「創業融資の支援を依頼したが、担当税理士が日本政策金融公庫からの融資を支援した経験が少なく、審査のポイントを把握していなかった。面談でも的確なフォローが得られず、希望額を大幅に下回る結果となった」
ミスマッチを避けるための質問例
契約前に以下の質問をすることで、税理士の実力を見極められます。
- 過去3年間で、どのような規模・業種の資金調達を何件サポートしましたか?
- 私の業界での融資・補助金申請の支援の経験はありますか?
- 主に取引を支援している金融機関はどちらですか?
- 認定支援機関の資格はお持ちですか?
- 不採択・否決となった場合のフォロー体制はありますか?
これらの質問に具体的に答えられない税理士は避けるべきです。
また、認定支援機関の活用という選択肢もあります。
認定支援機関(中小企業支援の専門知識を国が認定した機関)の税理士は、公的支援制度を活用できます。中小企業経営力強化資金計画策定や伴走支援を要件とし、結果として一般融資より低い利率を利用できる制度があります。
資金調達に強い税理士を選ぶには?

松田 光弘
監修税理士からのワンポイントアドバイス
経営者が資金調達に強い税理士選びに失敗しないためには、①補助金や金融機関対応の支援実績、②財務・会計に関する専門性、③コミュニケーションスキルの3点を最低限確認すべきです。
①事業計画の策定を要する補助金の申請や、新規借入、追加融資及びリスケジュールに関する金融機関対応を支援した実績を詳しく確認しましょう。
②会計及び財務、特に業種特有の資金繰り、つまり売上入金と仕入支出のサイクルに対する理解度を確認しましょう。
③金融機関や行政など融資や補助金を審査する側の視点や考えを分かりやすく説明してくれるかどうかを確認しましょう。
経営者が資金調達に強い税理士を選ぶ際は、初回面談で以上の3点をご確認いただくことが重要です。
税理士紹介サービスの効率的な活用方法
税理士紹介サービスを活用することで、効率的に最適な税理士を見つけられます。
税理士紹介センタービスカスのような専門サービスでは、全国4,200所以上の登録税理士事務所から企業のニーズに適した税理士を厳選紹介します。
専任コーディネーターが企業の状況を詳しくヒアリングし、資金調達の目的や希望条件に合った税理士をマッチングします。
利用の流れ
1. 電話・ウェブフォームでの問い合わせ
2. コーディネーターへの詳細ヒアリング
3. 候補税理士の選定・面談日程調整
4. 実際の面談・相性確認
5. 納得できれば契約
重要なのは、財務状況が厳しい場合でも正直に伝えることです。経営改善や事業再生に強い税理士を紹介してもらえる可能性があります。
契約前の確認事項とチェックリスト
税理士との契約前に必ず確認すべき項目をリストアップしました。
実績関連の確認事項
・過去3年間の融資支援件数と成功事例
・自社と同業種での実績有無
・得意とする金融機関・制度
・補助金申請の採択実績
費用・契約関連
・着手金の有無と金額
・成功報酬の割合
・追加費用発生の可能性
・サポート範囲(書類作成のみか、同行・交渉まで含むか)
・融資実行後のフォロー体制
準備すべき資料一覧
基本的な資料として以下を事前に準備しておきましょう。
・決算書3期分
・直近の試算表・資金繰り表
・事業計画書(ドラフト可)
・会社案内・登記簿謄本
・納税証明書(その1・その2)
・主要取引先一覧(回収・支払条件含む)
・許認可証の写し(該当業種)
・見積書・注文書(設備資金・運転資金の裏づけ)
これらを準備することで、初回面談がスムーズに進みます。
税理士に依頼すべきか迷った時の判断基準
小規模・単純な融資や補助金申請は自力でも可能ですが、初めての申請や高額調達、複雑な制度利用時は専門家の支援が推奨されます。以下の判断基準を参考にしてください。
以下のチェックリストで3つ以上該当する場合は、税理士への依頼を強く推奨します。
- □ 初回の資金調達である
- □ 調達希望額が1,000万円以上
- □ 補助金・助成金への申請を検討している
- □ 金融機関との取引実績が少ない
- □ 財務資料の作成に不安がある
- □ 本業が忙しく申請作業に時間を割けない
- □ 過去に融資で否決された経験がある
- □ 業績が下降気味または赤字である
調達方法別の推奨度
| 資金調達方法 | 自分で申請 | 税理士推奨 |
|---|---|---|
| 少額融資(500万円未満) | △ | ○ |
| 創業融資 | × | ◎ |
| 大型融資(1,000万円以上) | × | ◎ |
| 補助金・助成金 | × | ◎ |
| 緊急の資金調達 | × | ◎ |
税理士報酬が高く感じても、以下の観点で総合判断することが重要です。
- 審査通過率の向上による機会損失の回避
- 申請作業にかかる時間コストの削減
- 金融機関との継続的な関係構築による将来メリット
- 税務リスク回避による長期的な安心感
費用相場と契約形態別のメリット・デメリット
税理士に資金調達を依頼する際の費用体系と相場感、スポット契約と顧問契約それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。
資金調達支援の費用体系と相場感
税理士に資金調達を依頼する際の費用は、事務所や依頼内容によって大きく異なります。主な費用体系を理解して、適切な予算計画を立てましょう。
着手金型
・相場:10万〜50万円程度
・成功の可否に関わらず事前支払い
・事業計画書作成や財務分析などの基礎作業が対象
成功報酬型
・融資:調達額の2〜5%程度
・補助金:採択額の10〜20%程度
・資金調達成功時のみ支払い
組み合わせ型
・着手金+成功報酬(成功報酬率は5〜15%に下がることが多い)
※補助金の交付対象経費に申請支援費用は含まれないのが一般的です(自己負担)。公募要領で要確認。
契約形態別の相場
・スポット契約:事業計画書のみ10〜30万円、同行・交渉込みで30〜80万円
・顧問契約:月額顧問料+資金調達支援費(顧問料の2〜3か月分程度)
ただし、業務範囲や事務所ごとに大きく異なるため、複数の税理士から見積もりを取ることをお勧めします。
スポット契約vs顧問契約のメリット・デメリット比較
税理士との契約形態は大きく分けてスポット契約と顧問契約があります。それぞれの特徴を理解して、自社に最適な契約形態を選択しましょう。
スポット契約のメリット・デメリット
メリット
- 必要な時だけの依頼で継続費用負担なし
- 資金調達を得意とする税理士に依頼可能
- 高い専門性を期待できる
デメリット
- 企業の財務状況を一から説明する必要
- 税理士側も詳細把握に時間を要する
- 単発依頼のため関係構築に限界
顧問契約のメリット・デメリット
メリット
- 日常的な財務状況把握によりスムーズな準備
- 資金調達後の継続的な資金管理・税務サポート
- 金融機関からの信頼獲得
デメリット
- 顧問税理士が必ずしも資金調達に強いとは限らない
- 顧問料+追加料金でトータルコスト増
- 記帳中心の事務所では専門性に限界
単発の資金調達ならスポット契約が効率的ですが、継続的な成長を目指す企業なら資金調達に強い税理士との顧問契約も検討する価値があります。
事業フェーズ別の最適な資金調達戦略と税理士活用事例
企業の成長段階に応じた効果的な資金調達手法と、それぞれの局面で税理士がどのようにサポートできるかを具体的に解説します。
創業時の資金調達と税理士サポートの具体例
創業期では実績が不足している分、説得力ある計画書の作成が成否を分けます。
創業時の主な資金調達手段と税理士サポート
・日本政策金融公庫の創業融資:税理士が創業計画書作成・自己資金要件のアドバイスを提供
・自治体の制度融資:税理士が保証制度の選定・申請書類の精緻化をサポート
・創業関連補助金・助成金:税理士が事業の新規性・収益性を数値で裏づけ・申請書の作成を支援
よくある創業時の相談例と解決策
「飲食店開業で1,500万円が必要だが、自己資金が500万円しかない」というケースでは、税理士は以下のようにサポートします。
・日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の活用提案
・売上予測の根拠となる商圏分析データの整理
・月次資金繰り計画の精緻化
・自治体の制度融資との組み合わせ提案
創業時によくある失敗パターン
・過度に楽観的な売上予測を立てて審査で指摘される
・運転資金の見積もりが甘く、開業後すぐに資金ショートする
・必要書類の準備不足で審査が長期化する
税理士のサポートにより、これらのリスクを事前に回避できます。
税理士にサポートを依頼する最大のメリットは?

松田 光弘
監修税理士からのワンポイントアドバイス
創業融資や創業補助金の申請で税理士に依頼する最大のメリットは、事業計画書や申請書類の精度が向上することです。財務や会計の専門家である税理士は、説得力のある事業計画や資金繰り予測の作成をサポートしたり、創業者のアイデアを審査側の視点で信頼性の高い文章表現や数値計画に落とし込むためのアドバイスを提供したりできます。
創業者がよく陥る失敗は、売上計画の根拠不足、費用予測の甘さ、自己資金の根拠不足です。逆に言えば、成功のポイントはこれらの課題を丁寧にクリアすることです。具体的には、販路、販売先及び販売の時期と金額を明確に示すこと、購買から物流、納品に至るまでの売上原価と販売管理費を網羅して計算に入れること、自己資金として用意できる預金や金融資産を整理してリスト化することです。
成長・拡大期の資金調達戦略と税理士の貢献
成長期では大規模な資金需要への対応が求められます。
成長期の主な資金調達手段と税理士サポート
・中小企業新事業進出補助金:
税理士が投資効果の定量化・事業計画の数値根拠の作成を支援
・ベンチャーキャピタル:
税理士が投資家向け財務資料・企業価値算定をサポート
・大型融資(設備投資):
税理士が複数金融機関への戦略的申請・投資回収計画の策定をサポート
成長期の典型的な相談例
「製造業で設備投資に5,000万円が必要。売上は順調だが、大型投資の経験がない」というケースでは、税理士は以下をサポートします。
・設備投資効果を定量化した事業計画書の作成
・複数金融機関への分散申請戦略の立案
・ものづくり補助金との併用提案
・投資回収期間とキャッシュフローの精密なシミュレーション
成長期の注意点
・急成長による運転資金不足の見落とし
・過度な楽観論による返済計画の甘さ
・複数案件の同時進行による管理不足
税理士は財務の専門家として、これらの盲点を指摘し、現実的な計画策定をサポートします。
経営難・資金繰り悪化時の緊急対応と税理士サポート
経営が厳しい局面では、迅速かつ適切な対応が生命線となります。
経営難時の主な資金調達手段と税理士サポート
・セーフティネット保証
:税理士が要件確認・経営改善計画の策定・迅速な申請をサポート
・ファクタリング
:税理士が資金繰り表作成・手数料率の妥当性検証・会計処理をアドバイス
・リスケジュール
:税理士が現実的な返済計画・金融機関への説明資料を作成
たとえば、「コロナ禍で売上が50%減少。運転資金が3か月で底をつく予定」というケースでは、税理士は緊急的に以下をサポートすることがあります。
- セーフティネット保証の要件確認と迅速な申請
- 既存借入のリスケジュール交渉
- 雇用調整助成金の申請サポート
- 現実的な経営改善計画の策定
経営難時の資金調達で重要なポイントは下記です。
- 現状を隠さず正直に金融機関に相談する
- 一時的な困窮なのか構造的な問題なのかを明確にする
- 具体的で実現可能な改善策を示す
- 複数の支援制度を組み合わせて活用する
税理士は企業の窮状を客観的に分析し、金融機関が納得できる現実的な改善計画の策定をサポートします。
セーフティネット保証(4号・5号等)は状況に応じて活用できます。危機関連保証は、国が危機認定を行った場合に限り発動する時限制度で、2025年8月時点では「現在の認定案件はなし」です。
ファクタリングによる売掛債権の早期資金化を検討する場合、二者間・三者間の違い、手数料・買取率・債権譲渡登記の有無、早期償還条項や不適切業者のトラブル事例等を確認のうえ、総支払額と資金繰りへの影響を税理士とシミュレーションすることを推奨します。
関連:セーフティネット/危機関連保証(現状) 危機関連保証制度
まとめ
資金調達は企業の成長段階や経営状況に応じて避けて通れない重要な課題です。本記事でご紹介したように、税理士の専門性を活用することで資金調達の成功率を大幅に高めることができます。
税理士活用の主なメリットをまとめると、金融機関の審査基準を熟知した精度の高い書類作成、専門家としての信頼性による金融機関との関係構築、そして経営者が本業に専念できる時間効率の向上が挙げられます。特に日本政策金融公庫の融資や補助金申請では、税理士のサポートが採択率向上に直結する傾向があります。
一方で、税理士選びは慎重に行う必要があります。すべての税理士が資金調達に精通しているわけではないため、過去の実績、認定支援機関の登録有無、金融機関との関係性などを総合的に判断することが重要です。費用面でも着手金や成功報酬の相場を理解し、複数の税理士から見積もりを取って比較検討しましょう。
事業フェーズに応じた戦略的なアプローチも欠かせません。創業期は実績がない分、説得力ある計画書の作成が鍵となり、成長期は過去の実績を基にした将来性のアピールが重要です。経営が厳しい局面では、現実的な経営改善計画の策定と複数の支援制度の組み合わせが効果的です。
資金調達でお悩みの経営者の方は、まず税理士紹介センタービスカスの無料相談をご活用ください。専任コーディネーターが貴社の状況に最適な税理士をご紹介し、資金調達成功への第一歩をサポートいたします。
税理士紹介センタービスカスでは、資金調達に強い税理士を無料でご紹介しています。お急ぎの方もまずはお気軽にご相談ください。
お電話ご相談はこちら → 0120-610-386(受付:平日9時~19時/土日祝9時~18時)
お電話ご相談はこちら→0120-610-386
電話受付:平日9時~19時/土日祝9時~18時
資金調達の税理士活用でよくある質問
Q. 税理士のサポート範囲はどこまでですか?
A. 事業計画書・資金繰り表の作成から金融機関との面談同席、交渉サポート、融資実行後の資金管理アドバイスまで対応できます。ただし、税理士事務所によってサービス内容は異なるため、事前確認が重要です。
Q. 費用はどの程度かかりますか?
A. 一般的には融資額の2〜5%の成功報酬、または10〜50万円程度の着手金の事例が多く見られます。補助金申請では採択額の10〜20%程度が一般的です。企業の状況や依頼内容によって変動するため、複数の税理士から見積もりを取ることをお勧めします。
Q. 複数の税理士に相談してもよいですか?
A. 問題ありません。それぞれの専門性や提案内容を比較検討することで、より適切な選択ができます。税理士紹介センタービスカスなら複数の税理士との面談をスムーズに設定できます。
Q. 税理士の得意分野を見極める方法は?
A. 過去の実績を具体的に確認することが最も確実です。どのような業種・規模の資金調達を成功させたか、成功事例の内容、得意とする金融機関など、具体的な質問でその税理士の強みが明確になります。
Q. 顧問税理士がいる場合でも他の税理士に相談できますか?
A. 資金調達専門の税理士にセカンドオピニオンを求めることは一般的です。顧問税理士が資金調達に不慣れな場合は、専門性の高い税理士と連携することで、より良い結果が期待できます。
Q. 資金調達に不慣れな税理士に依頼して失敗した場合の対処法は?
A. まずは現在の状況を客観的に分析し、資金調達専門の税理士に相談することをお勧めします。必要に応じて税理士を変更し、適切な戦略の立て直しを図ることが重要です。時間的制約がある場合は、迅速な対応が求められます。
Q. 資金調達に失敗した場合の費用はどうなりますか?
A. 成功報酬型の場合、資金調達に失敗すれば報酬は発生しません。ただし、着手金がある場合は返金されないのが一般的です。契約前に必ず確認しておきましょう。
Q. 税理士への資料提出のタイミングはいつが最適ですか?
A. 資金調達を検討し始めた時点で早めに相談することをお勧めします。申請の1〜2か月前には必要書類を揃えておくと、余裕を持って準備できます。
Q. 審査に落ちた場合、税理士はどのようなフォローをしてくれますか?
A. 多くの税理士は否決理由の分析、改善点の整理、再申請戦略の立案などをサポートします。契約前にアフターフォローの内容を確認しておきましょう。
Q. 税理士を変更したい場合の注意点はありますか?
A. 進行中の申請がある場合は、引き継ぎのタイミングや責任の所在を明確にする必要があります。新しい税理士には経緯を詳しく説明し、スムーズな移行を心がけましょう。
関連リンク
本記事で紹介した制度の最新情報は、各公式サイトでご確認ください。
制度内容は予告なく変更される場合があります。
関連:日本政策金融公庫(創業融資・利率等) 創業融資のご案内
関連:中小企業新事業進出補助金
関連:セーフティネット/危機関連保証(現状):危機関連保証制度
関連:中小企業経営力強化資金
各制度の最新情報は、上記公式ページにて随時ご確認ください。

- この記事の監修者
- Vmaster税理士事務所
所長 松田 光弘(税理士)
事務所公式ホームページはこちら
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税理士・税理士探し >
- 資金調達で頼れる税理士とは?創業融資から補助金申請まで、資金不足を回避するには