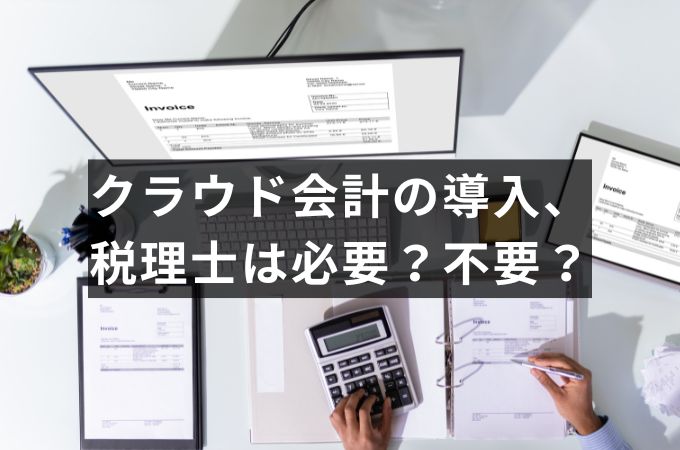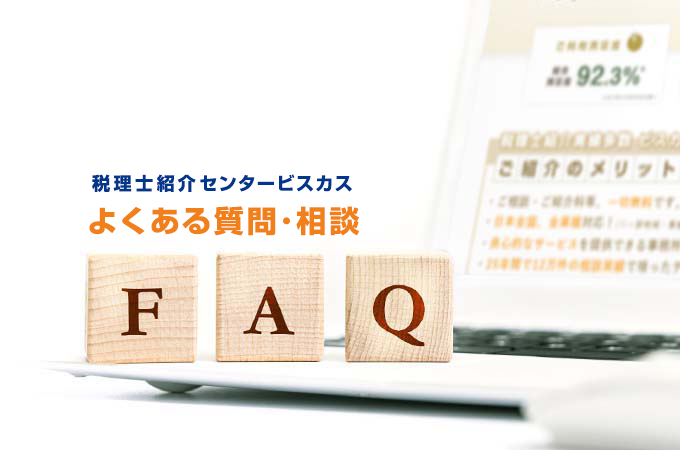【2025年版】税理士に無料で相談できる5つの方法をまとめました!その注意点も解説
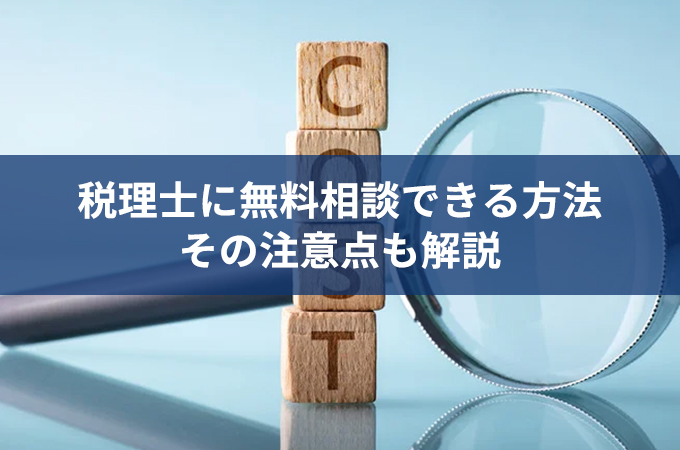
- 最終更新日:
- 2025/07/09

- この記事の監修者
- ご紹介実績40万件以上、税理士紹介のパイオニア
株式会社ビスカス 代表取締役 八木美代子
この記事のアドバイザー

おだね税理士事務所 代表
小田根 大輔
業界歴15年間で、法人・個人事業主の顧問業務、申告(法人税、消費税、所得税、相続税)業務のほか、財務・税務のデューデリジェンス業務、公益法人の顧問業務、M&Aや事業承継業務など、幅広い業務に携わってまりました。これらの経験を通じて、企業の成長と発展には、税務・会計の専門家としてのサポートが不可欠であることを確信しております。また、企業経営には、常に様々な課題がつきものです。税務・会計に関するお悩みはもとより事業に関することまで、どうぞお気軽にご相談ください。お客様の立場に寄り添い、最善のサポートをさせていただきます。
無料で税金について税理士に相談する方法5選
では、税理士に無料で相談するのには、具体的にどういった方法があるのでしょうか?
今回は
- 税理士会が開設している無料相談を利用する
- 国税庁が開設している無料相談窓口を利用する
- 自治体の無料相談窓口を利用する
- 税理士事務所、会計事務所の無料相談サービスを利用する
- 税理士紹介会社を利用する
の5つの方法を解説します。
1. 税理士会が開設している無料相談を利用する
すべての税理士が加入する「税理士会」(特別法人)はその名の通り、税理士で構成される組織であり、税理士自身を指導監督することが主な活動で定期的に無料税務相談会を開催しています。全国で15ある各税理士会の支部ごとに税金に関する相談窓口を開設していますので、最寄りの税理士会に申し込みをすれば無料で相談に応じてもらえます。
税理士会の相談会に行ってみる - 日本税理士会連合会 (nichizeiren.or.jp)
全国の税理士会の管轄するエリアは次のとおりです。
| 税理士会 | 管轄エリア |
|---|---|
| 東京税理士会 | 東京都 |
| 東京地方税理士会 | 神奈川県、山梨県 |
| 千葉県税理士会 | 千葉県 |
| 関東信越税理士会 | 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県 |
| 近畿税理士会 | 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県 |
| 北海道税理士会 | 北海道 |
| 東北税理士会 | 宮城県、岩手県、福島県、秋田県、青森県、山形県 |
| 名古屋税理士会 | 愛知県のうち名古屋市、清須市、北名古屋市、半田市、常滑市、東海市、 大府市、知多市、豊明市、日進市、長久手市、西春日井郡、愛知郡、及び知多郡並びに岐阜県 |
| 東海税理士会 | 愛知県(名古屋税理士会に係る区域を除く。)静岡県、三重県 |
| 北陸税理士会 | 石川県、福井県、富山県 |
| 中国税理士会 | 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県 |
| 九州北部税理士会 | 福岡県、佐賀県、長崎県 |
| 南九州税理士会 | 熊本県、大分県、鹿児島県、宮崎県 |
| 沖縄税理士会 | 沖縄県 |
さらに各税理士会の中でもエリアごとに支部が設けられています。例えば東京理士会の場合は第1ブロックから第8ブロックに区分けされています。ご自身のお住まいのエリアの窓口を確認してみてください。
東京税理士会の納税者支援センターでは、東京税理士会館で常設(祝日等を除く月~金)の無料相談を受け付けており、同会に所属する税理士に直接応じてもらえます。相談は、面接でも電話でも可能ですが、相談時間はいずれも30分以内となっています。
相談への回答はあくまで一般的な範囲のものとなります。複雑な内容であったり、「節税」を目的とした相談には応じてもらえないと考えるべきでしょう。
また、相談内容によっては予約が必要なこともあります。相談会を利用したい場合は、必ず近くの税理士会のウェブサイトにアクセスして詳細を確認しましょう。
2. 国税庁が開設している無料相談窓口を利用する
事前予約をすれば税務署に直接相談に行くことも可能ですが、税務署に赴く時間が取れない方は以下のような窓口で税金に関する各種無料相談を受けられます。
電話相談センター
電話対応による相談窓口であり、平日午前8時30分時から午後5時まで税金に関する相談ができます。また、国税局の職員等が直接回答してくれますので、確実性が高いのもメリットとして挙げられます。
チャットボット
「チャットボット」はAIによる自動回答システムであり、国税庁でも税金に関する質問に対しチャットボットが24時間365日対応するサービスを提供しています。利用できる税目や相談内容が限定されているというデメリットはありますが、生じた疑問について迅速に回答が得られるというメリットがあります。
チャットボット(ふたば)に質問する|国税庁 (nta.go.jp)
タックスアンサー
税金についての取り扱いや税務判断に対する回答をまとめてデータベース化したものが「タックスアンサー」です。検索機能を使って、知りたい情報をいつでも取り出せます。
タックスアンサー(よくある税の質問)|国税庁 (nta.go.jp)
3. 自治体の無料相談窓口を利用する
全国の各自治体でも、税金に関する無料相談窓口を開設しているところがあります。自治体の相談窓口で直接相談する「窓口相談」をはじめ、電話やウェブカメラを使った「オンライン相談」を提供しているところもありますので、ご自身のスケジュールに合わせた税務相談ができます。
4. 税理士事務所、会計事務所の無料相談サービスを利用する
税理士事務所や会計事務所が開催する無料相談サービスを利用する方法です。税理士事務所等に直接赴いたりオンラインを使ったりして、税に関する疑問点等を相談できます。ただし、税理士にとっては行った回答に対して職務上の責任が生じるため、2回目以降の相談を有料にする事務所が一般的です。
5. 税理士紹介会社を利用する
税理士紹介会社を通して、無料で税務相談に応じてくれる税理士や公認会計士を探す方法です。スポットでも利用できることから、税務申告までに発生するコストを抑えられます。ただし、一般的には無料で対応してもらえるのは初回だけであり、2回目以降は有料になるケースがほとんどです。
実際のところ、どこに相談するのが最適なの?

小田根 大輔
税理士からのワンポイントアドバイス
個人の方の相続・贈与・不動産の譲渡に関する税金の相談であれば、まず1.税理士会、2.国税庁、3・自治体での窓口が無料でお気軽にご利用いただけます。ただし、事前予約が必要となる場合や、相談時間(東京税理士会であれば25分以内)が限られ、回答内容も一般的なものになってしまいます。
もし、具体的な内容について、申告等をご自身や確定申告期の確定申告会場で解決できないのであれば、4.税理士事務所、5.税理士紹介会社を利用して税理士に相談いただくことをお勧めいたします。税理士にご相談いただけますと、個別の事情に合わせた具体的なアドバイスを受けられ、税務申告や税務調査の対応をご依頼でき、長期的なサポートを受けられます。ただし、相談は有償となります。
個人事業主、法人の税金相談であれば、事業の関する具体的な内容の相談になるかと思いますので、初めから4.税理士事務所、5.税理士紹介会社で、複数の税理士と無料相談を行い、自分に合った税理士と有償の顧問契約をすることをお勧めいたします。
【税理士紹介センタービスカスの税理士無料紹介&無料面談のご案内】
税理士紹介センタービスカスでは、確定申告・税務顧問・相続などに対応できる税理士を無料でお探しするサービスを提供しています。お電話かメールでお問い合わせいただいた後、専任コーディネーターが税理士を選定・ご紹介し、ご面談(無料)を設定いたします。もちろん、ご面談後に「この税理士に依頼したい!」となりましたら、その税理士とご契約に進んでいただけます。
まずは以下のボタンより、お気軽にお問い合わせください。
- 税理士紹介センタービスカスでは、税理士と契約する前に必ず税理士との面談を行っています。実際にお会いすることで、相性面などもご判断いただけます。
- 無料ご面談は、ご対面だけでなくオンライン(ZOOM)でも実施可能です。
無料でどこまで相談できる?
決算時期
法人の決算時期は、適切な決算書類の作成と税務申告が必要になる重要な時期です。決算業務は複雑で、利益の計上方法や経費の計上方法、減価償却など専門知識が求められます。
無料で相談できる範囲:
- 決算書類の作成手順や一般的な流れについて
- 基本的な会計処理方法や仕訳の考え方
- 減価償却の基本的な計算方法
- 経費計上の一般的なルールや考え方
- 申告書の提出期限や必要書類について
無料では難しい範囲:
- 実際の決算書類の作成代行
- 個別の会計処理の詳細な検討と判断
- 具体的な節税対策の提案
- 複雑な取引の会計処理
- 税務申告書の作成と提出
資金調達や経営戦略の見直し時
事業拡大や新規プロジェクトの立ち上げ、経営環境の変化に伴う経営戦略の見直しでは、財務面での専門的なアドバイスが必要になります。
無料で相談できる範囲:
- 資金調達方法の一般的な種類と特徴
- 金融機関からの借入に必要な基本的な書類
- 財務諸表の基本的な見方
- 税務上考慮すべき一般的なポイント
- 補助金や助成金の概要について
無料では難しい範囲:
- 詳細な財務分析と具体的な改善提案
- 資金繰り計画の作成
- 金融機関向けの事業計画書作成支援
- 個別の経営戦略に応じた税務対策
- M&Aや事業承継に関する具体的なスキーム提案
確定申告前
個人事業主やフリーランスにとって、毎年の確定申告は重要な手続きです。申告書の内容に誤りがあれば税務署からの指摘を受ける可能性があり、逆に経費を計上し忘れれば税金を払い過ぎるリスクもあります。
無料で相談できる範囲:
- 確定申告書の基本的な書き方と記入方法
- 所得の種類と基本的な計算方法
- 経費として認められる項目の一般的な基準
- 各種控除制度の概要と適用条件
- 申告期限や提出方法について
無料では難しい範囲:
- 個別の事情に応じた具体的な節税対策
- 複雑な取引の所得計算
- 確定申告書の作成代行
- 税務調査対応を想定した申告書作成
- 将来の税務リスクを考慮した申告戦略
個人事業主として開業する時
個人事業主として独立する際は、会社員と違って自ら所得・納税額を計算し、確定申告を行う必要があります。節税メリットが期待できる「青色申告」を選択する場合は、日々の記帳も重要になります。
無料で相談できる範囲:
- 開業届の記入方法と提出手続き
- 青色申告承認申請書の基本的な書き方
- 個人事業主の基本的な税務上の義務
- 帳簿の種類と記帳方法の概要
- 必要な届出書類の種類と提出期限
無料では難しい範囲:
- 事業形態に応じた最適な税務戦略の提案
- 継続的な記帳指導と会計処理のサポート
- 法人成りのタイミングと手続きの詳細検討
- 個別の事業内容に応じた経費処理の判断
- 開業後の継続的な税務相談
相続が発生した時
相続が発生した場合、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると相続税の課税対象となります。不動産などがあると判断が複雑になり、「古い家だから大した価値はない」と思って申告しないでいたら、後から税務署に指摘を受けることもあります。
無料で相談できる範囲:
- 相続税の基礎控除額の計算方法
- 相続税申告の必要性の基本的な判断基準
- 相続税の申告期限と一般的な手続きの流れ
- 相続財産の評価方法の概要
- 各種特例制度の存在と適用条件の概要
無料では難しい範囲:
- 具体的な相続財産の詳細な評価
- 相続税申告書の作成
- 節税を目的とした具体的な相続対策
- 複雑な財産構成の場合の申告戦略
- 税務調査対応や不服申立て手続き
税務調査が入る場合
税務署から税務調査の通知があった場合、適切な対応が求められます。税務調査では過去の申告内容や帳簿の適正性がチェックされ、誤りが見つかると追徴課税が発生することもあります。
無料で相談できる範囲:
- 税務調査の一般的な流れと手続き
- 調査官への基本的な対応方法
- 準備すべき書類の種類
- 納税者の権利と義務の概要
- 調査後の一般的な手続きについて
無料では難しい範囲:
- 調査官との具体的な交渉や立会い
- 個別の論点に対する詳細な検討と対応策
- 修正申告書の作成
- 不服申立てや異議申立ての手続き
- 将来の税務調査対策の具体的な提案
無料で税理士に相談する時に注意したいポイント
無料相談は多くの人にとって手軽で便利なサービスですが、誰でも気軽に利用できる反面、利用には特有の制約や注意点があります。専門家である税理士に無料で相談できるのは大きなメリットですが、無制限にどんなことでも相談できるわけではありません。事前に注意点を理解しておくことで、より効果的に無料相談を活用できます。
相談時間に制限がある
無料相談の多くは1回20~40分程度と短時間に設定されています。これは税理士側の負担軽減や他の相談者との公平性を保つためです。
具体的な影響:
- 複雑な相続や法人税の相談では時間内に十分な説明が受けられない
- 複数の論点がある場合、すべてを聞ききれずに終わることがある
- 詳細な検討が必要な場合は、後日有料相談を勧められるケースが多い
対策:
限られた時間の中で的確なアドバイスをもらうためには、「聞きたいこと」を予め整理し、必要な資料などをきちんと用意して臨むことが重要になります。優先順位を付けて、最も重要な質問から順番に相談しましょう。
相談回数に制限がある
多くの無料相談サービスでは、初回のみ無料で2回目以降は有料となるケースが一般的です。これは継続的なサポートを有料サービスとして提供するためです。
具体的な影響:
- 初回相談で解決しなかった場合、追加の相談は有料になる
- 税理士事務所の場合、2回目以降は正式な契約を前提とした相談になることが多い
- 継続的なフォローアップは期待できない
対策:
初回の無料相談で最大限の成果を得るために、事前準備を徹底し、複数の税理士に相談して比較検討することをお勧めします。
一般的なアドバイスに留まることが多い
無料相談では、例えば申告書の書き方や、税法上正しい税務処理の助言など「一般的なアドバイス」はもらえますが、特定分野(例えば不動産)についての専門的な知識を必要とするような、踏み込んだ税金・節税のアドバイスは期待できません。
理由:
- 限られた時間や情報の中で個別性の高いアドバイスをすれば、間違いも起きやすく税理士側がリスクを負うため
- 無料で専門的なサービスを提供していては「商売にならない」ため
- 責任を伴う具体的なアドバイスには、十分な情報収集と検討時間が必要なため
期待できる範囲:
- 確定申告書の基本的な書き方
- 税法上の一般的な処理方法
- 各種控除制度の概要
- 申告期限や提出方法
期待できない範囲:
- 個別の事情に応じた具体的な節税対策
- 複雑な税務計算や詳細な財務分析
- 将来の税務リスクを考慮した戦略的アドバイス
- 継続的なサポートや定期的な相談
有料サービスへの勧誘がある場合もある
そもそも税理士や税理士会などが無料相談窓口を設けているのは、有料の仕事(顧問契約など)に結びつく可能性があるためです。
具体的な状況:
- 相談内容によっては、確定申告のスポット契約を勧められる
- 継続的なサポートが必要な場合は、顧問契約を提案される
- 複雑な案件では、有料相談での詳細検討を勧められる
対応方法:
相談する側もその点を理解したうえで「料金に見合うサポートが受けられる」と判断できる場合には、その道を選択するのもアリでしょう。無料相談を、本格的に税理士に依頼する判断の場と考えることもできるはずです。
もちろん、不要な勧誘は断ればOKです。無料相談を受けたから…と気にする必要はありません。
次のアクションを検討しよう
無料相談で解決しない場合や、より詳細なアドバイスが必要な場合は、以下のような次のステップを検討しましょう:
- 有料相談の利用:より具体的で個別性の高いアドバイスを受ける
- 複数の税理士との面談:相性や専門性を比較検討する
- 顧問契約の検討:継続的なサポートが必要な場合
- スポット契約の利用:特定の業務(確定申告など)のみ依頼する
無料相談は「税理士のサービス内容や相性を確認する機会」として活用し、必要に応じて有料サービスに移行することで、最適な税務サポートを受けることができます。
無料相談に向けて準備すべきものとは?

小田根 大輔
税理士からのワンポイントアドバイス
無料相談は時間が限られ、一般的な内容となるため、相談をスムーズに効果的に行うためにも、以下の準備と注意をご確認ください。
1.相談内容を簡潔に、疑問点を明確して、質問リストを作成
「不動産の譲渡に税金は発生するのか?」「扶養控除の対象になるか?」など、具体的な疑問点を明確にしましょう。事前に質問をリスト化しておくと、相談中の確認漏れを防ぐことができます。以前に、不動産譲渡の申告について教えてほしい、と相談され申告方法についてご説明しましたが、詳しい話を伺うと、明らかに譲渡所得がマイナスで申告が不要であった(特例を適用するためにマイナスでも申告が必要となる場合もあります)ことがありました。
2.関係書類を準備する
相談内容に関する書類(不動産売買等の契約書、確定申告書、など)を事前にご準備いただくと、相談内容について正確に把握し、より適切なアドバイスが可能となります。以前に、個人事業主の方の初回面談時に書類(確定申告書、決算書など)がなく、具体的な所得や控除の状況が把握できず、一般的なご説明しかできないことがありました。
有料で税理士に相談することのメリット
無料相談は一般的な税務知識や基本的な手続きについての相談が中心ですが、有料相談では個別の事情に踏み込んだ具体的で実用的なアドバイスが受けられます。節税方法や資金繰りに関するアドバイスなど、もう一歩踏み込んだ具体的な相談をしたい場合は、有料相談を利用することをおすすめします。
有料相談で受けられる具体的なサービス
有料相談では、無料相談では対応できない以下のような専門的なサービスを受けることができます:
個別具体的な税務アドバイス:
- 個人の事情に応じた具体的な節税対策の提案
- 複雑な取引や特殊な事情に対する税務処理方法
- 将来の税務リスクを考慮した戦略的アドバイス
- 事業形態変更(法人成りなど)のタイミングと手続き
具体的な計算とシミュレーション:
- 詳細な税額シミュレーションと比較検討
- 複数の選択肢による税負担の違いの計算
- 将来の税務負担の予測と対策
- 資金繰り計画と税務の関連性の分析
書類作成とチェック:
- 申告書の作成代行や内容チェック
- 各種届出書類の作成と提出サポート
- 契約書や取引内容の税務的な検証
- 過去の申告書の見直しと修正提案
経営戦略と税務の連携:
- 事業拡大や投資計画における税務上の留意点
- M&Aや事業承継における税務戦略
- 金融機関対応における税務面でのサポート
- 補助金・助成金申請時の税務処理
信頼できるパートナー選びとしての価値
有料相談は、継続的な顧問契約を結ぶ前に「信頼できる税理士かどうかをしっかり見極められる」貴重な機会でもあります。実際に有料でサービスを受けることで、税理士の専門性、対応の質、説明の分かりやすさ、相性などを総合的に判断できます。
無料相談では短時間で一般的な内容に留まるため、税理士の真の実力や人柄を把握するのは困難です。しかし有料相談では、時間をかけて具体的な問題解決に取り組むため、税理士のコミュニケーション能力や提案力、問題解決能力を実際に体験できます。将来の長期的なパートナーシップを考える際の重要な判断材料となるでしょう。
有料相談が特に有効な場面
個別判断が必要な複雑な相談
例えば「プライベートと事業の両方で使用している車に関する費用をどのくらい経費で落とすことができるのか」といった個別判断が必要な内容や、「将来の相続に向けて準備を始めたいが節税対策として今からできることはないか」といった長期的な戦略相談などは、有料相談でなければ十分な回答が得られません。
投資や事業戦略に関する相談
また、不動産投資を検討している場合の税務上最も有利な購入方法の検討や、複数の事業を展開している場合の税務上最適な事業構造の提案なども、有料相談ならではの専門的なアドバイスが受けられる分野です。
有料相談を検討すべきタイミング
有料相談を積極的に検討すべきタイミングは、主に以下のケースです。
- 無料相談では時間が足りなかった場合 - 十分な説明が受けられず、もう少し詳しく聞きたい
- 複雑な事情がある場合 - 専門的な検討が必要で、一般的なアドバイスでは解決できない
- 具体的な数字が必要な場合 - シミュレーションに基づいた判断をしたい
- 税理士の能力を確認したい場合 - 継続的な税務サポートを検討する前の見極め
無料相談との違いと位置づけ
サービス内容の違い
無料相談:一般的な税務知識・基本的な手続き・初歩的な確認
有料相談:個別最適な実務サポート・具体的な解決策・継続的な関係構築
投資としての価値
有料相談は単なる出費ではなく「投資」として捉えることが重要です。適切な節税対策により相談料以上の効果が期待できる場合が多く、税務リスクの回避により将来の追徴課税や加算税を防ぐことができます。より質の高い税務サポートを受けることで、結果的に税負担の軽減や事業の発展につながる価値のあるサービスといえるでしょう。
有料相談・正式依頼時の費用相場
税理士の有料相談や正式依頼を検討する際に、実際にどのくらいの費用がかかるのかを把握しておくことは重要です。
有料相談の費用目安
有料相談は一般的に1時間あたり1万円~2万円を目安に設定している事務所が多いです。相談内容や税理士の経験、地域によって料金は変動します。
正式依頼時の基本料金
顧問契約の月額費用
税理士と顧問契約を結ぶ場合、月額30,000円が一般的な目安となります。事業規模によって以下のような相場があります。
- 法人(年商1,000万円未満):月額10,000円~+決算申告料
- 法人(年商1,000万円~3,000万円):月額15,000円~20,000円+決算申告料
- 個人事業主(年商500万円未満):確定申告のみ70,000円~80,000円/年
- 個人事業主(年商500万円~1,000万円):月額10,000円~+確定申告料
決算申告料
決算申告料は月額顧問料の4~6ヶ月分が目安となり、年額100,000円~が相場です。顧問契約がない場合のスポット契約では、法人100,000円~300,000円/年、個人事業主70,000円~200,000円/年程度となります。
追加費用が発生する業務
基本の顧問料に加えて、以下のような追加業務には別途料金が発生します:
- 記帳代行:15,000円~35,000円/月(仕訳数により変動)
- 給与計算・年末調整:事務所により設定が異なる
- 相続税申告:遺産総額の0.5%~1%
支払いタイミング
- 顧問契約:月額顧問料は毎月、決算申告料は申告書完成時
- スポット契約:申告書完成時に一括支払い
- 有料相談:相談当日または翌月初旬
費用を抑える方法
- 訪問回数を減らす(毎月→2-3ヶ月に1回)
- 記帳を自社で行う
- クラウド会計を活用する
- 同県内の税理士に依頼する
税理士費用は適切な税務処理により節税効果や税務リスクの回避が期待できる投資として考えることが重要です。まずは有料相談から始めて、税理士との相性やサービス内容を確認した上で、正式な契約を検討することをお勧めします。
まとめ
税理士会・国税庁の窓口や税理士紹介サービスなどを利用することで、税金のことを税理士に無料で相談することができます。申告などに関して不明な点や困ったことがある場合などには、気軽に活用してみてはいかがでしょうか。ただし、相談には時間制限や回数制限が設けられていることもあり、具体的な節税対策などについて明確な答えをもらうことは期待薄です。無料相談を受けたうえで、必要であれば有料のサポートを依頼するのがいいでしょう。
よくある質問と回答
無料相談を利用する際に必要な準備は何ですか?
無料相談を効果的に活用するためには、事前の準備が重要です。まず、相談内容を明確にし、質問リストを作成しておきましょう。相談に関連する書類(過去の確定申告書、決算書、契約書、経費の明細など)を揃えて持参することで、より具体的で正確なアドバイスを受けることができます。また、相談時間は限られているため、優先順位を付けて質問を整理しておくことが大切です。
無料相談でどこまで詳しいアドバイスがもらえますか?
無料相談では、一般的な税務に関するアドバイスや基本的な質問への回答が得られます。例えば、確定申告書の書き方や税法上の処理方法などについて説明を受けることができます。ただし、個別の事情に応じた具体的な節税対策や複雑な税務計算、詳細な財務分析などは、無料相談の範囲を超えることが多いです。より専門的なサポートが必要な場合は、有料の相談や顧問契約を検討することをお勧めします。
無料相談の時間や回数に制限はありますか?
はい、無料相談には通常、時間と回数に制限があります。税理士会の相談窓口では一般的に20~40分程度、税理士事務所の初回無料相談では30分~1時間程度が目安となっています。回数についても、多くの場合は初回のみ無料で、2回目以降は有料となることが一般的です。国税庁の電話相談センターは時間制限がありませんが、複雑な相談には対応しきれない場合があります。詳細は各相談窓口にお問い合わせください。
無料相談を受けた後、必ずその税理士に依頼しなければいけませんか?
いいえ、無料相談を受けたからといって、必ずその税理士に依頼する義務はありません。無料相談は、税理士のサービス内容や相性を確認するための機会でもあります。相談後に勧誘を受けることがあるかもしれませんが、不要であれば遠慮なく断って構いません。複数の税理士から無料相談を受けて比較検討し、最も適した税理士を選ぶことが大切です。気に入った税理士がいれば、そのまま有料サービスの契約に進むことも可能です。
電話やオンラインで無料相談はできますか?
はい、多くの相談窓口で電話やオンラインでの無料相談が可能です。国税庁の電話相談センターでは平日8時30分から17時まで電話での相談を受け付けています。また、一部の自治体や税理士事務所では、ZoomやSkype等を使用したオンライン相談も提供しています。ただし、相談内容によっては実際に書類を確認する必要がある場合もあるため、事前に対応可能な相談方法を確認することをお勧めします。チャットボットによる24時間対応のサービスもあります。
税理士以外にも無料で相談できる窓口はありますか?
はい、税理士以外にも無料で税務相談できる窓口があります。国税庁の税務署では直接相談が可能で、電話相談センターやチャットボット、タックスアンサーなどのサービスも提供しています。また、全国の市区町村の多くが税務相談窓口を設けており、確定申告時期には臨時の相談会場も設置されます。商工会議所や青色申告会でも会員向けに無料相談を実施しています。ただし、これらの窓口では一般的な質問への回答が中心となり、複雑な事案には対応できない場合があります。
無料相談で断られるケースや注意点はありますか?
無料相談で断られる可能性があるケースとして、以下のようなものがあります。過度に複雑な事案や専門的な知識を要する相談、具体的な節税スキームの提案を求める相談、訴訟に関わる案件、既に税務調査が開始されている案件などです。また、相談内容が税理士の専門分野外の場合や、明らかに営利目的の相談も断られることがあります。注意点として、無料相談では一般的なアドバイスに留まることが多く、個別の事情に応じた具体的な対策は期待できません。相談時間も限られているため、事前の準備が重要です。
無料相談の後、有料相談や依頼に進む場合の流れは?
無料相談の結果、より詳しいサポートが必要と判断された場合、有料相談や正式な依頼に進むことができます。一般的な流れとしては、まず有料相談(通常1時間あたり1万円~)を受けて、具体的な課題や解決策を詳しく検討します。その後、継続的なサポートが必要であれば、顧問契約や単発の業務委託契約を結ぶことになります。契約前には、料金体系、サービス内容、対応範囲などを明確に確認し、契約書を取り交わします。複数の税理士から見積もりを取って比較検討することも重要です。

- この記事の監修者
- ご紹介実績40万件以上、税理士紹介のパイオニア
株式会社ビスカス 代表取締役 八木美代子
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税理士・税理士探し >
- 【2025年版】税理士に無料で相談できる5つの方法をまとめました!その注意点も解説