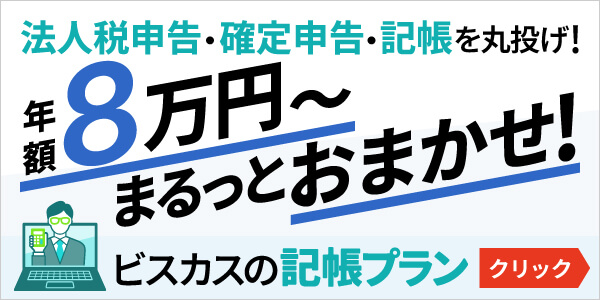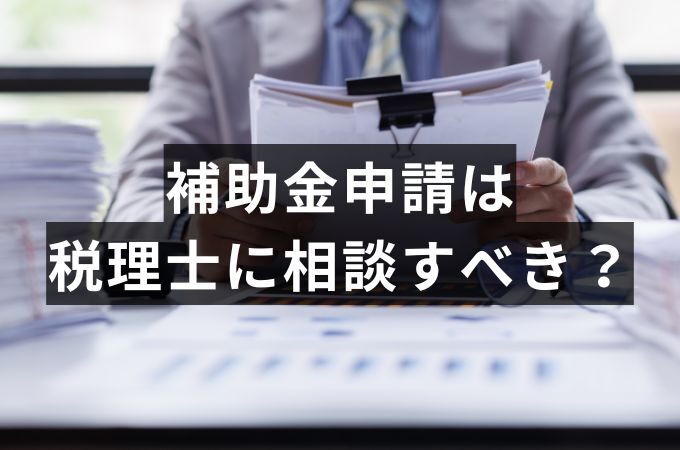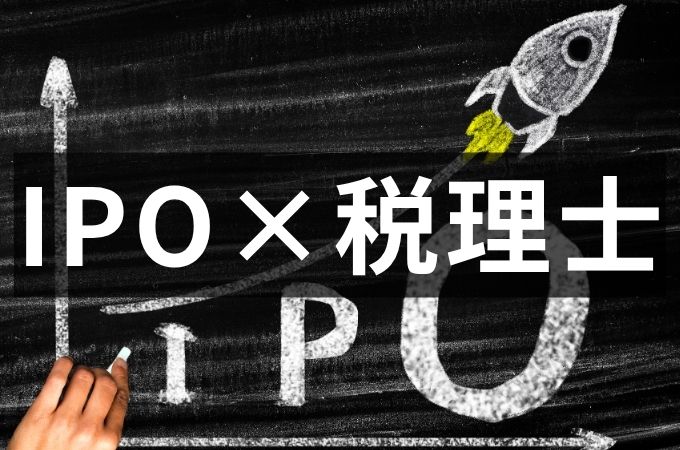製造業に強い税理士とは?製造業税務の特徴や税理士の選び方を解説

- 最終更新日:
- 2025/10/27

- この記事の監修者
- おだね税理士事務所
代表 小田根 大輔(税理士)
製造業における税理士の役割
製造業では仕入→製造→検査→出荷という複数工程があり、各段階で適切な会計処理と税務判断が求められます。以下では配賦・在庫・設備の3論点を中心に、税理士の関与ポイントを整理します。
製造業の会計・税務の特徴と課題
製造業特有の会計・税務論点は、原価配賦・在庫評価・設備投資の3点に集約されます。それぞれ税務リスクと実務上の注意点を押さえておきましょう。
原価計算と配賦の設計
製造原価は材料費・労務費・製造経費の三要素から構成されます。工場光熱費・機械減価償却費などの間接製造経費は、機械稼働時間・直接作業時間・床面積比・材料消費量・電力使用量などの合理的で説明可能な基準で配賦します。
配賦基準は実態適合+継続適用が原則です。変更時は理由・開始期と影響範囲を明記し、証憑を保存してください。これらを社内規程へ明文化し、継続適用を徹底します。
個別原価計算(受注生産向け)、総合原価計算(量産向け)、標準原価計算(差異分析重視)の使い分け方針を期首に決定し、差異分析は初月から回して担当・期限を割り付けてください。
在庫評価の論点とリスク
原材料・仕掛品・製品という三段階の在庫があり、それぞれ適切な評価方法(先入先出法・総平均法・移動平均法・最終仕入原価法など)を選択します。
| 【重要な注意点】 税務上は最終仕入原価法が認められていますが、会計基準(特にIFRS)では後入先出法(LIFO)は認められていません。会計と税務で評価法が異なる場合は注記が必要です。評価法の変更には税務署への届出と継続適用が必須です。 |
根拠のない評価減や過度な圧縮は税務調査で否認されるリスクがあります。評価損を計上する場合は、陳腐化・劣化の証憑(写真・検査票・型落ち通知等)を添付し、計上基準を社内規程に明文化してください。棚卸立会記録・評価法届出書の控・差異分析表・実地棚卸と帳簿の突合記録は必ず保管します。
製造業が注意すべき実務上のポイントとは?

小田根 大輔
税理士からのワンポイントアドバイス
在庫評価法の選択は、自社が製造する製品の特性(例:流行品、生鮮品、受注生産品など)や「事務負担」「原価管理の精度」「損益への影響」のバランスで決めるのが鍵です。
例えば、食品やアパレルなどモノの流れ(先入れ先出し)が重要な製品は「先入先出法」が実態に合います。一方、機械などの個別受注生産品は「個別法」が最も正確な原価を把握できます。
計算が簡単な「最終仕入原価法」は事務負担を減らせますが、原価管理の精度は低下しがちです。
特に注意すべきは、設立時に届出がない場合、自動的に「最終仕入原価法」が適用される点です。後から変更するには「正当な理由」に加え、「変更したい事業年度の開始の日の前日まで」に変更届出書の提出が必要です。
自社の製品と管理体制に最適な方法を勘案して戦略的に選択してください。
設備投資の税制活用
中小企業経営強化税制は2027年3月31日までの期限付き制度で、即時償却または税額控除10%(資本金3,000万円超は7%)が選択できます。取得前に工業会等証明書・経済産業大臣の確認書を取得し、経営力向上計画の認定を受けることが必須です。取得後の申請は認められません。
投資前に
- 対象類型(A類型/B類型/D類型等)への適合性確認
- 取得前手続きの完了
- 事業年度内の稼働見込みと時期設計
を確認してください。検収日・稼働開始日・請負契約書は税制・償却資産税・補助金で整合させ、原始証憑を保存します。
税理士が果たす具体的な役割
税理士は会計・税務申告、経営分析と資金調達、補助金支援の3領域で製造業をサポートします。それぞれの実務ポイントを確認しましょう。
会計処理・税務申告支援
月次→決算→申告を通じ、配賦・在庫・税務調整の整合を点検します。評価法届・配賦設計・差異分析・棚卸記録を月次更新し、変更は期首適用+理由記録を徹底します。
経営分析と資金繰り支援
製品別・部門別の粗利分析や差異分析により、収益構造を見える化します。投資案は回収期間・IRR・損益分岐点を示し、3〜6か月CFで資金影響を即提示します。
銀行は月次信頼性×CF予測を重視するため、自己資本比率・営業CF・在庫回転をそろえ、ストレスケース(売上下振れ/回収遅延)も同封すると説得力が高まります。
補助金・助成金支援
ものづくり補助金は公募期ごと、事業再構築補助金は第13回で新規応募が終了しています(交付候補向け手続き等は継続)。公募は期限定であり、採択後は実績報告と返還リスクがあります。中小企業診断士/行政書士との連携体制を確認してください。
ただし、税制や補助金制度は改正されるため、アドバイス通りにすれば必ず成果が出るとは限りません。現場の工程改善・技術判断は技術専門家の領域であり、税理士は財務面の設計と手続きに専念します。
製造業に強い税理士へ依頼するメリット
税理士に依頼することで、税務リスクの低減・経理コストの削減・経営判断の質向上という3つの価値が得られます。それぞれ具体的なメリットを見ていきましょう。
税務調査・節税・資金調達のサポート
製造業における税理士の支援は、税務調査対応・節税策の提案・資金調達支援の3つが中心です。いずれも専門知識と実務経験が必要な領域であり、税理士の関与により大きな効果が期待できます。
税務調査への対応
製造業では在庫評価と配賦の妥当性が調査の焦点となります。税理士が関与していれば、評価法の継続適用と配賦の合理性を証憑で日常的に証明できるため、追徴課税を抑制しやすくなります(説明資料が整っている前提)。
実際に調査が入った際には、税理士が立ち会い、専門用語や税法解釈について適切に説明し、不当な追徴を防ぎます。
節税対策
中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)では、要件充足と適切な手続により、即時償却または税額控除10%(資本金3,000万円超は7%)による節税効果が見込めます。試験研究費の税額控除なども含め、取得前手続×時期設計で最適化します。
資金調達支援
税理士が作成する銀行目線の月次パック(試算表・資金繰り表・在庫回転分析)があれば、融資審査がスムーズに進み、金利・期間の条件を有利化できる可能性が高まります。
経理業務の効率化・コスト削減
製造業の経理担当者は、日々の記帳に加えて原価計算や在庫管理を抱えています。税理士に記帳代行や月次決算を依頼すれば、経理担当者は本来業務に集中でき、業務効率が向上します。
経理専任者の人件費は地域・規模によりますが、参考例として年間300〜500万円前後かかります。税理士への顧問料は参考例として月3〜5万円程度ですが、事業規模・業務範囲で変動します。
税理士に外注する際の注意点
記帳代行を税理士に依頼する場合、内部統制が弱まるリスクがあります。承認フローの明確化(記帳→承認→確定の責任分界)、定期的な突合(銀行残高・現金実査・在庫確認)、会計ソフトや証憑保管のアクセス権限管理、税理士との連携ルール(報告頻度・連絡手段)を明文化しておきましょう。
月次決算を早く締めることと実地棚卸の標準化により、決算完了までの期間を短縮できれば、経営判断のスピードも上がります。記帳の"安さ"だけで判断せず、原価と在庫の正確性に報酬を紐づける考え方が合理的です。
経営の相談・パートナーシップ
税理士は財務数値の面から客観的なアドバイスを提供できる存在です。ただし、相談範囲は定量的な分析(収益性・資金繰り・投資判断)が中心であり、人事制度・品質管理・設備の技術的選定などは専門外となります。
事業承継の支援も税理士の重要な役割です。株式の承継方法、相続税対策、事業承継税制(法人版特例は特例承継計画の提出期限が2026年3月31日まで)の活用などを総合的にアドバイスします。最新制度の期限・要件は必ず確認してください。
製造業に強い税理士の特徴
製造業に精通した税理士を見極めるには、原価計算の実務経験・業界理解・最新制度への対応力・コミュニケーションの4点を確認します。
原価計算・キャッシュフロー管理への精通
個別・総合・標準の各原価計算に対応し、初回面談で配賦設計と差異分析フローを提示できることが必須です。製品別・部門別の収益性分析で利益源泉とムダを明確に示し、3〜6か月先のキャッシュフロー影響を即時試算できる税理士を選びましょう。
【面談時に確認する3つの質問】
- 当社の評価法運用のリスクを1分で要約してください
- 中小企業経営強化税制の「取得前手続」と当社設備の適用可否は?
- 3か月先CFを赤字にしない運転資金策は?(在庫・回収・与信の観点で)
【持参すべき資料】
- 配賦設計書
- 評価法届出書の控
- 差異分析表(直近3か月分)
- 在庫回転率の推移
- 資金繰り表
製造業の実務経験・業界理解
製造業クライアントの担当実績が豊富で、製造現場を見学しライン停滞分析に関与した経験がある税理士が望ましいです。金属加工・食品製造など業種特性は大きく異なるため、同業×同規模のクライアントを持つ税理士を選んでください。
下請取引特有の手形決済・長期サイト・発注キャンセルリスクを理解し、資金繰り対策や取引条件改善を提案できるかが重要です。
【面談で確認すべき3点】
- 同業種×同規模の担当年数と社数
- 原価改善の実例(配賦変更・差異削減・在庫圧縮の具体的な数値)
- 下請・手形・長サイト前提での資金繰り提案経験の有無
法改正・補助金対応力
税制は毎年改正されます。最新情報をタイムリーに提案できる税理士を選びましょう。
| 中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで) 即時償却または税額控除10%(資本金3,000万円超は7%)。取得前に工業会等証明書・経産相確認書取得+経営力向上計画の認定が必須です。制度を知らずに投資すると適用を受けられません。 |
| 補助金対応 ものづくり補助金は公募期ごと、事業再構築補助金は第13回で新規応募終了(交付候補向け手続等は継続)。申請サポート実績(成功率・返還対応経験)を確認してください。 |
電子帳簿保存法とインボイス制度への対応
| 電子帳簿保存法 2024年1月1日以降、電子取引データの保存は原則義務化(猶予措置終了)。検索要件(年月日・金額・取引先)、訂正削除の履歴保持、ダウンロード応答体制、ファイル命名規則、ERP連携が必要です。製造業では発注→製造→出荷→請求の複数段階データをトレーサビリティを保って保存する体制が求められます。 |
| インボイス制度 適格請求書類似書類の交付・虚偽記載には刑事罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。登録番号の真偽確認・記載要件の定期点検を行える税理士を選びましょう。 |
対応のスピード・コミュニケーション力
レスポンスが遅い税理士では経営サポートが機能しません。対応チャネル(電話・メール・チャット)と対応速度、専門用語を経営者目線で説明できるか、初回面談後48時間以内に見積・改善提案メモが届くかを確認してください。
月1回程度の訪問で試算表説明や経営課題を話し合える税理士が理想です。遠方の税理士は訪問頻度が減るため、物理的距離も考慮しましょう。
製造業に詳しい税理士とは?

小田根 大輔
税理士からのワンポイントアドバイス
製造業に詳しい税理士とそうでない税理士の最大の違いは、「事前関与」の有無と「原価への解像度」です。
詳しい税理士は、設備投資の「計画段階」で中小企業経営強化税制などの「取得前」手続きを提案・支援します。そうでない税理士は決算時での対応となりがちで、多額の税制優遇(即時償却や税額控除)の機会を逃しがちです。
また、税務調査の焦点となる在庫評価や原価配賦について、詳しい税理士は製造実態に即した「合理的な根拠」を設計段階から文書化し、否認リスクを減らします。
依頼時は、「投資計画(取得前手続きを知っているか)」「現在の配賦基準(現場確認の姿勢があるか)」「同業他社の実績」を確認し、上流工程から関与できる専門家かを見極めることが重要です。
製造業向け税理士の選び方
税理士選びは、実績確認・契約内容の精査・面談での相性確認の3ステップで進めます。自社に最適な税理士を効率的に見つける方法を解説します。
実績・専門性の確認方法
税理士事務所のホームページで、製造業の支援実績(同業種×同規模)と原価/在庫の支援事例が数値つきで紹介されているかを確認します。同業種の担当社数・支援年数、製造業特有の論点(配賦・評価法・設備投資税制)への言及、顧客の声の具体性をチェックしましょう。
【面談で確認する3つの質問】
- 当社の評価法の現況リスクを1分でどう整理できますか?
- 中小企業経営強化税制の取得前手続と適用可否は?(当社の設備想定で)
- 3か月先のCFを赤字にしない運転資金策は?
具体的な事例を交えて答えられる税理士は実務経験が豊富です。あいまいな回答のみの場合は、製造業への対応実績が少ない可能性があります。
紹介サービスの活用
税理士紹介サービスを利用する場合は、料金の透明性・上乗せ有無・マッチング料の有無を確認してください。株式会社ビスカスが運営する税理士紹介センターでは、専任コーディネーターが製造業に精通した税理士を無料でご紹介しています。
契約内容・料金の確認ポイント
契約書には、業務範囲・月次訪問頻度・別料金が発生する業務(税務調査立会い・年末調整・補助金申請・制度対応・工数増)・解約条件(通常1〜3ヶ月前通知)・守秘義務を明記します。
顧問料は売上規模・取引量・訪問頻度で変動します。参考例として、年商5,000万円以下で月額3〜5万円程度、年商1億円規模で月額5〜10万円程度が目安ですが、記帳代行や給与計算の有無で変わります。極端に安い税理士は訪問頻度や対応速度に問題があるケースがあるため、料金だけでなく月次の信頼性×意思決定材料の質で総合判断してください。
面談・コミュニケーションで見るべき点
初回面談では、こちらの話をしっかり聞き30分以内に課題を要約し改善方向を示せるか、専門用語を経営者目線で言い換えられるか、具体的な提案をしてくれるか、面談後すぐに見積・提案書が届くかを確認します。
連絡手段(電話・メール・チャット)と担当窓口、初回訪問の実施時期、契約開始までのスケジュールも明確にしておきましょう。最後に、直感的な相性も大切にしてください。「この人になら相談しやすい」と感じられる税理士を選ぶことが、長期的な良好関係につながります。
まとめ
製造業の経営では、原価計算・在庫管理・設備投資といった複雑な会計処理と税務判断が求められます。これらに適切に対応するためには、製造業の実務に精通した税理士のサポートが不可欠です。
税理士に依頼することで、税務調査対応・節税策・資金調達支援といった直接的メリットに加え、経理業務効率化・経営数値に基づく戦略的意思決定が可能になります。単なるコストではなく、企業成長への投資として捉えましょう。
製造業に強い税理士を選ぶ際は、原価計算・キャッシュフロー管理への精通、製造業での実務経験、最新税制・補助金への対応力、迅速なコミュニケーション力を重視してください。制度改正や個社条件により結論が変わる場合がありますので、常に最新情報を確認する姿勢を持つ税理士を選びましょう。
ビスカスが運営する税理士紹介センターでは、専任の税理士コーディネーターが、お客様の業種や課題に合わせて最適な税理士を無料でご紹介しています。
よくある質問
Q.税理士変更の最適なタイミングは?
決算直後が基本です。解約予告期間(契約書記載の1〜3ヶ月前)を守り、会計データ・評価法届出・棚卸差異を新旧で突合し、期首から継続適用を徹底します。引き継ぎ中の記帳ミス・帳簿不整合リスクを防ぐため、残高確認と評価法の整合性チェックを必ず行ってください。
Q.初回相談の持参物は?
決算書2〜3期分/月次推移、評価法届出書、主要設備と耐用年数リスト、製造工程フロー図、資金繰り表を準備してください。これらがあれば、税理士は具体的な改善提案を即座に行えます。現在の顧問料・契約内容も把握しておくと比較検討しやすくなります。
Q.税理士の得意分野の見極め方は?
ホームページの支援事例を確認し、面談時に「製造業クライアントは何社担当していますか」「原価改善の実例を数値で教えてください」と直接質問します。具体的な数値を伴った説明ができる税理士は実務経験が豊富です。簡易課題(原価計算例・在庫評価例)を出して反応を見る実技テスト的質問も効果的です。
Q.紹介サービス利用のメリットと注意点は?
メリットは、自社の業種・課題に合った税理士を効率的に見つけられる点です。専任コーディネーターが製造業の実務経験・得意分野・料金面を考慮してマッチングするため、ミスマッチリスクが軽減されます。注意点として、マッチング料の有無・顧問料への上乗せ条件を事前確認し、透明性の高いサービスを選びましょう。紹介は無料で、面談後の契約判断は自由です。
製造業の成長を支える最適な税理士をお探しなら、ぜひ税理士紹介センターにご相談ください。お客様のビジネスを深く理解し、長期的なパートナーとなる税理士との出会いをサポートいたします。

- この記事の監修者
- おだね税理士事務所
代表 小田根 大輔(税理士)
事務所公式ホームページはこちら
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税理士・税理士探し >
- 製造業に強い税理士とは?製造業税務の特徴や税理士の選び方を解説