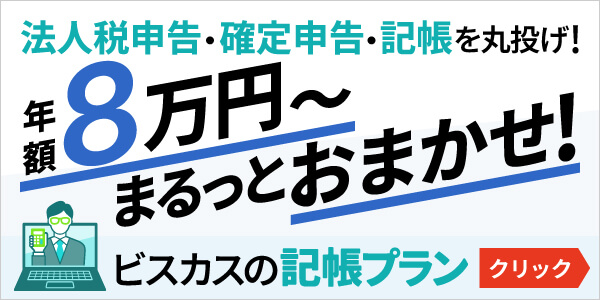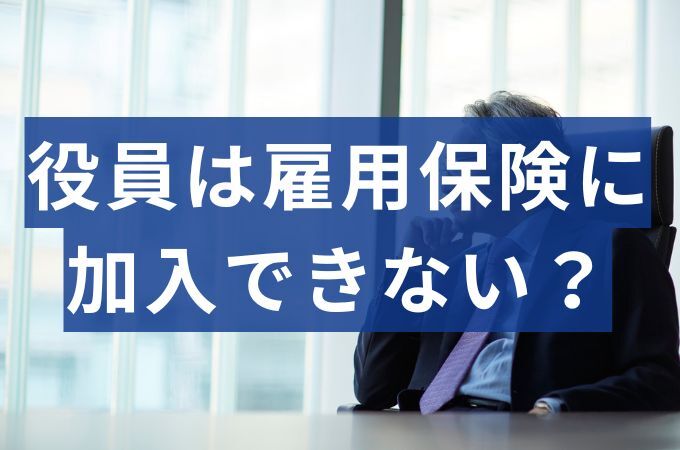賞与にかかる社会保険料の計算方法と法改正による最新の注意点とは?

- 最終更新日:
- 2025/11/25

- この記事の監修者
- Vmaster税理士事務所
所長 松田 光弘(税理士)
賞与と社会保険料の基礎知識
賞与とは労働の対価として支給される報酬のうち、毎月の給与とは別に支給されるものを指します。社会保険制度では賞与も報酬の一部として扱われ、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料の計算対象となります。ここでは賞与の法的な定義と、なぜ賞与にも社会保険料がかかるのかを明確にします。
賞与とは?社会保険上の定義と一般的なボーナスとの違い
社会保険上の「賞与」とは、臨時的または一時的に支給される報酬を指し、名称は問いません。支給回数が年3回以下のものは原則として賞与に該当し、同一の性質で年4回以上定期的・継続的に支給される場合は「賞与にかかる報酬」として給与と同様に扱われます。
つまり、「ボーナス」「賞与」「一時金」「インセンティブ」「決算賞与」など呼び方が違っても、臨時的・一時的な支給で年3回以内であれば賞与として扱われます。一方、年4回以上支給されるものは原則「報酬」として扱われ、標準報酬月額の算定基礎に含まれます。年4回以上の定期支給は「報酬」として支払月の報酬に算入され、標準報酬月額の定時決定・随時改定に反映されます。
また、現物支給(商品券や株式など)も金銭換算した価額が賞与の対象となります。社会保険料の対象となる根拠は、健康保険法および厚生年金保険法において、賞与も被保険者の報酬として保険料計算の基礎に含めることが規定されているためです。
社会保険料とは?賞与にもかかる理由
社会保険料には、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(40歳以上)、雇用保険料の4種類があります(厳密に言えば雇用保険料は労働保険料の一部ですが、ここでは賞与から控除されるものとして社会保険料と同じ区分で扱います)。健康保険料は医療費の給付財源、厚生年金保険料は将来の年金給付の原資、介護保険料は介護サービスの財源、雇用保険料は失業給付などの財源となります。
賞与にも社会保険料がかかる背景には、平成15年4月に導入された「総報酬制」があります。それまでは月々の給与(標準報酬月額)のみが保険料計算の対象でしたが、総報酬制の導入により賞与も含めた年間の総報酬額に応じて保険料を負担する仕組みに変わりました。これにより、給与と賞与の支給バランスに関わらず、年収が同じであれば保険料負担も同等になるという公平性が確保されています。
社会保険料は原則労使折半(雇用保険のみ負担割合が異なる)で、一般的には賞与額の15%程度が社会保険料として控除されます(地域や年齢により異なります)。手取りへの影響も大きいため、賞与の支給設計時に十分考慮が必要です。
賞与にかかる社会保険料の具体的な計算方法
賞与の社会保険料を正確に計算するには、標準賞与額の算出方法と各保険ごとの料率を理解する必要があります。健康保険と厚生年金では上限額の設定や適用期間が異なるため、特に高額賞与を支給する場合は注意が必要です。ここでは実務で使える具体的な計算手順と、間違いやすいポイントを詳しく解説します。
標準賞与額とは?計算の流れと上限額の仕組み
標準賞与額とは、実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことです。例えば、賞与支給額が498,600円の場合、標準賞与額は498,000円となります。この標準賞与額に保険料率を乗じて社会保険料を計算します。
厚生年金保険では1回の支給ごとに150万円が上限です。仮に1回で200万円の賞与を支給しても、150万円が標準賞与額の上限となります。この上限額は同一月内に複数回賞与を支給した場合はその賞与の月間合計額に適用されますが、異なる月であれば各月ごとに150万円まで適用されます。
健康保険・介護保険では年度累計(4月1日〜翌年3月31日)で573万円が上限です。例えば、夏季賞与300万円、冬季賞与300万円を支給した場合、合計600万円のうち573万円までが標準賞与額の対象となり、27万円分は保険料計算の対象外となります。
複数の事業所で勤務している従業員に、各事業所で個別に賞与を支給する場合は、それぞれで(従業員が主たる事業所として選択した事業所が加入する健康保険組合の料率を用いて)標準賞与額を算出し保険料を計算します。年金事務所では合算管理されるため、上限額の判定には注意が必要です。
各社会保険料の計算方法(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)
各社会保険料の計算式は以下のとおりです。料率は年度や都道府県により変動するため、最新の料率を確認する必要があります。
健康保険料・介護保険料の計算
健康保険料=標準賞与額×健康保険料率÷2(従業員負担分)
健康保険料率は都道府県ごとに異なります。例えば、令和7年度の協会けんぽの料率は各都道府県により9.44%~10.78%と差があります。(自社に適用される料率は協会けんぽのサイトで確認してください)。例えば東京都の協会けんぽでは標準賞与額が50万円の場合、健康保険料の従業員負担は50万円×9.91%÷2=24,775円となります。
介護保険料は40歳以上65歳未満の方のみ対象で、標準賞与額×介護保険料率÷2で計算します。令和7年度の料率は全国一律1.59%です。
厚生年金保険料の計算
厚生年金保険料=標準賞与額×厚生年金保険料率÷2(従業員負担分)
厚生年金保険料率は全国一律で18.3%です。標準賞与額が50万円の場合、厚生年金保険料の従業員負担は50万円×18.3%÷2=45,750円となります。
雇用保険料の計算
雇用保険料=賞与支給額(1円単位)×雇用保険料率
雇用保険料は標準賞与額ではなく、賞与支給額そのままに料率を乗じます。令和7年度の一般の事業の労働者負担率は0.55%です。賞与支給額が498,600円の場合、雇用保険料は498,600円×0.6%=2,742円(1円未満切り捨て)となります。
具体的な計算例
【計算例】東京都在住、40歳未満、賞与額50万円の場合
- 標準賞与額:500,000円
- 健康保険料:500,000円×9.91%÷2=24,775円
- 厚生年金保険料:500,000円×18.3%÷2=45,750円
- 雇用保険料:500,000円×0.55%=2,750円
- 社会保険料合計:73,275円
- 手取り額:426,725円(所得税控除前)
最新の料率は厚生労働省のサイトや日本年金機構のサイトで確認できます。
賞与の社会保険料計算について気をつける点や落とし穴は?

松田 光弘
税理士からのワンポイントアドバイス
賞与の社会保険料計算において注意すべきことはまず、標準賞与額の上限です。健康保険は年度(4月~翌3月)の累計で573万円、厚生年金は1回(同月内複数回支給は合算)あたり150万円が上限です。これを超えた分には保険料がかかりません。高額賞与の場合は、この上限超過を見落としがちです。
次に、保険料計算の基礎となる標準賞与額は、支給額から1,000円未満を切り捨てて決定します。この端数処理を忘れると、計算が合いません。
最後に、適用する保険料率は、必ず賞与を支給した月のものを使用します。料率改定をまたぐ場合は特に注意してください。これらを誤ると徴収不足や過払いが生じ、後の精算手続きが煩雑になります。
給与計算システムを導入して正しく条件を設定すれば、社会保険料の計算を自動化できます。事業主が給与計算を誤れば従業員からの信頼度低下にも繋がりますので、給与計算システムをご利用いただくことをお勧めします。
賞与に社会保険料がかからないケースと例外規定
賞与から社会保険料を控除しないケースは、退職時期や休業の種類・期間によって細かく定められています。月の途中で退職した場合の賞与は保険料控除が不要となり、産前産後休業や育児休業中も一定要件を満たせば免除対象です。また、高額賞与を支給する際は厚生年金150万円(単月)、健康保険573万円(年度累計)の上限を超えた部分には保険料がかかりません。ここでは実務で判断に迷いやすい免除・不要ケースを具体的に解説します。
退職・資格喪失月・休業中の場合の取扱い
賞与の社会保険料が控除不要または免除となるのは、退職日が月の途中である場合、産前産後休業中の場合、育児休業中で一定要件を満たす場合です。退職時は資格喪失日が月の何日かによって判断が分かれ、休業中は申出の有無や休業期間の長さが重要になります。それぞれのケースで取扱いが異なるため、正確な判断が必要です。
月の途中退職の場合は社会保険料を控除しない
退職日が月末以外の場合、その月に支給された賞与からは社会保険料を控除しません。社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となり、資格喪失日が属する月は保険料徴収の対象外となるためです。
例えば、6月20日退職で6月25日に賞与を支給する場合、資格喪失日は6月21日となり、6月分の保険料は発生しないため、賞与からの社会保険料控除は不要です。一方、6月30日退職の場合は資格喪失日が7月1日となり、6月分の保険料が発生するため、6月支給の賞与からも社会保険料を控除します。
月末退職か月中退職かで取扱いが大きく変わるため、退職日の確認は慎重に行う必要があります。
産前産後休業中の賞与の保険料は申出により免除
産前産後休業中の賞与は、事業主の申出により社会保険料が免除されます。産前産後休業期間中(産前42日・産後56日)に賞与を支給した場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所に提出することで、従業員・事業主ともに保険料負担が生じません。
免除を受けるには届出が必須であり、届出を行わない場合は通常どおり保険料が発生します。産前産後休業中に賞与支給がある場合は、提出期間(産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間)内に速やかに申出書を提出しましょう。
育児休業中の賞与の保険料免除は「月末を含む1か月超」が条件
育児休業中の賞与は、賞与支給月の末日を含む連続1か月超の休業がある場合にのみ保険料が免除されます(令和4年10月改正後)。この要件は非常に厳格で、月末を含む休業であっても1か月以内の場合は免除対象外となります。
例えば、6月末に賞与を支給し、6月15日〜7月20日まで育児休業を取得していた場合、6月末を含む連続1か月超の休業があるため免除対象です。しかし、6月25日〜7月5日の育児休業では、6月末を含むものの連続1か月超の要件を満たさないため免除されません。
この改正により、月末に短期間だけ育児休業を取得して賞与の社会保険料を免除するという運用は不可能になりました。実務では育児休業の開始日と終了日を正確に把握し、免除要件を満たすかどうかを慎重に判断する必要があります。※要件の詳細は厚生労働省の通達をご確認ください。
育児休業中の賞与免除を受ける場合においても、事業主側は「育児休業等取得者申出書」の届出が必須です。提出期限は被保険者の育児休業等期間中または育児休業等終了日から起算して1か月以内ですから、漏れのないように手続きをしましょう。
標準賞与額の上限超過時の対応と手続き
厚生年金の標準賞与額が単月累計150万円を超える場合、または健康保険の標準賞与額が年度累計573万円を超える場合、上限額を超えた部分には保険料がかかりません。
例えば、健康保険で年度内の賞与累計が600万円に達した場合、573万円までが保険料計算の対象となり、超過分27万円には保険料が発生しません。従業員への説明資料などでは「上限額に達したため、この部分の保険料は控除されません」と明記すると理解が得られやすいでしょう。
上限額に達した場合でも、被保険者賞与支払届には実際に支給した賞与額を記載します。届出書の備考欄などに上限超過である旨を記載し、保険料計算は上限額に基づいて行います。年金事務所や健康保険組合では累計管理を行っているため、届出漏れがあると後日調査や追徴の対象となる可能性があります。
例外規定について起こりがちな問題や対策は?

松田 光弘
税理士からのワンポイントアドバイス
賞与の社会保険料控除が不要なケース(月中退職・産休育休中)における注意点としてはまず、月中退職者を月末退職者と混同し、不要な保険料を控除してしまうことです。社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)が賞与支給月に含まれる場合は、社会保険料を控除する必要がありません。必ず退職日(資格喪失日)を確認することが重要です。
また、産休・育休中の保険料免除は自動で適用されるものではなく、事業主による「産前産後休業取得者申出書」又は「育児休業等取得者申出書」の提出が必須です。この提出を失念したり、給与計算への反映を漏らしたりすれば、社会保険料が誤って控除されてしまいます。これらの届出の提出と給与計算システムへの反映を確認する体制を整えておく必要があります。
賞与支給時に必要な手続きとその他の控除項目
賞与支給時には、社会保険料の計算・控除だけでなく、行政機関への届出や所得税の源泉徴収など、複数の手続きが必要です。期限を守らないと督促の対象となる場合もあるため、手続きの流れと期限を正確に把握しておくことが重要です。
被保険者賞与支払届の提出と納付期限
賞与支給後は、被保険者賞与支払届の提出と保険料の納付という2つの重要な手続きが必要です。それぞれ期限が定められており、遅延すると督促や延滞金の対象となるため、計画的な対応が求められます。
被保険者賞与支払届の提出手続き
賞与を支給した場合、原則として支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を年金事務所へ提出する必要があります。提出先は、協会けんぽ加入事業所の場合は管轄の年金事務所、健康保険組合加入事業所の場合は健康保険組合および年金事務所です。
届出書には、従業員ごとの賞与支給額、標準賞与額、保険料額などを記載します。日本年金機構の様式を参考に、正確に記入しましょう。電子申請(e-Gov)での提出も可能で、大量の従業員がいる場合は電子申請の方が効率的です。
提出期限の5日間は非常に短いため、賞与支給日が確定した時点で早めに準備を始めることが大切です。提出が遅れると年金事務所から督促や指導の対象となり、保険料の納付スケジュールにも影響するため、期限管理が重要です。
保険料の納付期限と納付方法
保険料の納付期限は、賞与支給月の翌月末日です。例えば6月に賞与を支給した場合、7月末日までに納付します。納付が遅れると延滞金が発生するため、資金繰りも含めて計画的に対応しましょう。
協会けんぽの場合は日本年金機構から納入告知書が送付され、指定金融機関で納付します。口座振替の場合は自動引き落としとなりますが、残高不足に注意が必要です。健康保険組合加入の場合は、組合ごとに納付方法が異なるため、各組合の規定を確認してください。
提出漏れ・遅延のリスクと対応策
賞与支払届の提出漏れは、将来受け取る年金額に影響し従業員の不利益となります。遅延が続く場合は年金事務所から指導を受けることもあるため、期限管理が重要です。
提出漏れを防ぐには、賞与支給予定日をカレンダーに登録し、支給の都度チェックリストで確認するなど、組織的な管理体制を整えることが有効です。給与計算システムと連携して自動的に届出データを作成できる仕組みがあれば、ミスのリスクを大幅に減らせます。
賞与支給時に社会保険料以外で控除される項目
賞与からは社会保険料以外に、源泉所得税も控除されます。賞与の源泉所得税は、前月の給与額(社会保険料等控除後)と扶養親族等の数に応じた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算します。
具体的には、前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を基に算出率を求め、「(賞与額-賞与の社会保険料)×算出率」で税額を計算します(例外あり)。給与とは異なり、算出率を用いて計算する点が特徴です。賞与の支給額が大きい場合、源泉所得税の負担も大きくなるため、賞与支給額の設計時には社会保険料と源泉所得税の両方を考慮した手取り額のシミュレーションが重要です。
また、事業主のみが負担する社会保険料として子ども・子育て拠出金があります。これは標準賞与額に一定の率(令和7年度は0.36%)を乗じた額を事業主のみが負担するもので、従業員の賞与からの控除はありません。ただし、賞与支払届の提出時には事業主負担分も含めて計算・納付する必要があります。
その他、労使協定がある場合には、社宅費や食事代、財形貯蓄、組合費などが賞与から控除されることもあります。控除項目が多い場合は、給与明細に控除の内訳を明記し、従業員が内容を理解できるようにすることが大切です。
まとめ
賞与にかかる社会保険料は、標準賞与額をベースに健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険のそれぞれで計算され、給与とは異なる計算ルールが適用されます。特に上限額や退職時や育児休業中の取扱い、法改正による免除要件の変更など、実務上の注意点は多岐にわたります。社会保険労務士にサポートを依頼したり、給与計算システムを利用したりして正確な計算と期限内の届出を行うことで、従業員の信頼を守り、行政からの指摘や追徴を避けることができます。
賞与の社会保険料計算に不安がある場合や、複雑なケースへの対応に迷った際は、社会保険労務士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。税理士紹介センターでは、給与計算や社会保険実務に精通した税理士を無料でご紹介しています。経験豊富なコーディネーターがお客様の状況に合わせて最適な専門家をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問
Q:インセンティブや業績手当は賞与に該当しますか?
支給回数が年3回以内で臨時的・一時的なものであれば、名称に関わらず社会保険上は賞与として扱われます。「インセンティブ」「業績連動手当」「決算賞与」などの名称でも、年3回以内の支給であれば標準賞与額として社会保険料の計算対象です。同一の性質で年4回以上支給される場合は原則報酬扱いとなり、標準報酬月額の算定に含まれます。
Q:賞与支給時に社会保険料が0円になるのはどんなときですか?
主に以下のケースで社会保険料が0円になります。
(1)月の途中で退職し、資格喪失後に賞与が支給される場合
(2)産前産後休業中で免除申出が受理されている場合
(3)育児休業中で「賞与支給月の末日を含む連続1か月超の休業」要件を満たし、免除申出が受理されている場合
(4)標準賞与額が上限額に達しており、それを超える部分の賞与を支給する場合(超過分のみ)
などです。
Q:賞与の支給回数が年4回以上になった場合はどうなりますか?
同一の性質で年4回以上の賞与は社会保険上「報酬」として扱われ、標準賞与額ではなく標準報酬月額の算定対象となります。この場合、年間の賞与支給額を12で割った額が毎月の標準報酬月額に加算され、月々の社会保険料が高くなります。賞与支払時には賞与としての保険料控除は行わず、毎月の給与から控除される保険料に含まれます。ただし、「今年は会社の業績が良かった」など、事業者の都合でたまたま賞与を年4回支給することになった場合は「報酬」扱いとせず、「賞与支払届」を提出することで事足りる場合もあります。そのような場合は念のため、社会保険労務士や年金事務所などに事業所の規程と事実を正確に伝えて、賞与か報酬のいずれに該当するか、ご確認いただくことをおすすめします。
Q:賞与支給後に計算ミスが発覚した場合はどう対応すればよいですか?
過大控除・過少控除いずれの場合も、速やかに訂正手続きが必要です。過大控除の場合は従業員に還付し、過少控除の場合は不足分を徴収します。被保険者賞与支払届の訂正届を年金事務所に提出し、保険料の過不足を精算します。訂正が年度をまたぐ場合や金額が大きい場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
Q:標準賞与額の上限管理はどのように行えばよいですか?
厚生年金の1回150万円、健康保険の年度累計573万円の上限管理は、賞与支給の都度、累計額を記録・確認することが基本です。給与計算システムに累計管理機能がある場合は活用し、手作業の場合は賞与支給台帳に年度累計を記載します。特に高額賞与を支給する企業では、支給前に上限到達の有無を確認するチェックリストを作成すると安心です。
Q:複数の事業所で勤務している従業員の賞与はどう扱いますか?
各事業所で個別に賞与を支給する場合は、それぞれで(従業員が主たる事業所として選択した事業所が加入する健康保険組合の料率を用いて)標準賞与額を算出し社会保険料を計算・控除します。年金事務所では合算して上限額の判定を行うため、複数事業所の賞与合計が上限を超える場合には按分計算などの調整が必要になることがあります。複雑なケースでは年金事務所や社会保険労務士への確認をおすすめします。

- この記事の監修者
- Vmaster税理士事務所
所長 松田 光弘(税理士)
事務所公式ホームページはこちら
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 労務 >
- 賞与にかかる社会保険料の計算方法と法改正による最新の注意点とは?