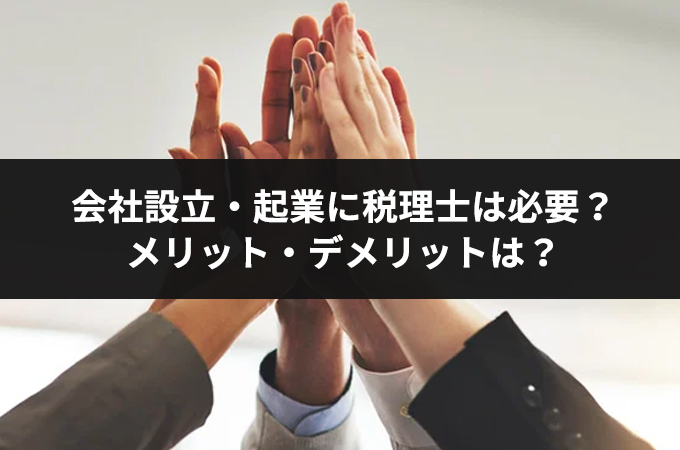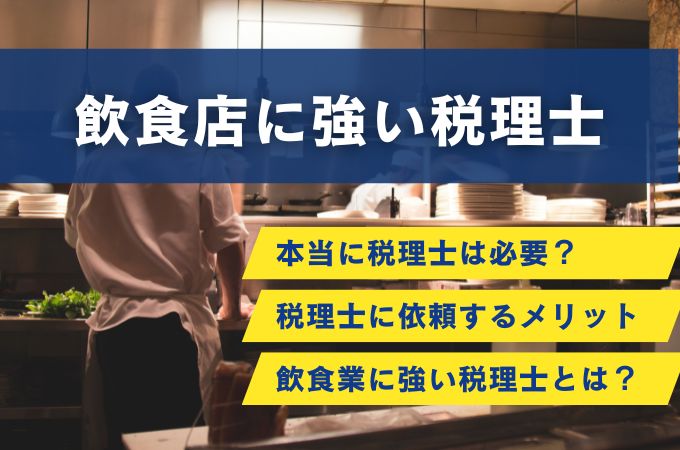会社を設立するにあたって、「会社設立時に税理士は本当に必要なのか」「税理士に依頼することでどんなメリット・デメリットがあるのか」「費用はどれくらいかかるのか」「タイミングはいつが最適か」などの悩みを抱える人も少なくないのではないでしょうか?
結論として、会社設立時に税理士が必要か?という疑問に対しては、"必須ではありませんが多くのメリットを得られるのでおすすめします!"という回答になります。
本記事では、こ会社設立時に税理士を頼むメリットから具体的な費用相場、最適な選び方まで、網羅的に解説しています。
目 次
税理士の仕事と役割について
税務申告等の税務代理業務
会社の税務や会計業務は、会社の規模が拡大していくにつれて次第に複雑化していきます。
これらの仕事に割かれる時間は本業へも影響するため、税務を代行してくれる税理士は頼りになる存在です。税理士が主に担う役割は税理士法に明記されており、以下の3つは税理士資格を持つ者しかできない、独占業務と位置づけられています。
1.税務代理
確定申告や青色申告など、税金に関わる申告や申請の業務を代行する役割です。これに加えて税務調査への立会いや、税務署の決定への不服申立ても行うことができます。
2.税務書類の作成
確定申告や相続税申告書、青色申告承認書など、税務署に提出する書類の作成を代わって行います。一般的に、税務代理の業務の流れで行われることが多いです。
3.税務相談
実際にかかる税額や、節税の方法といった税務に関わる相談がある際、税理士が相談に対応します。分かりやすく言うと、事業をしていくうえで必要な事務である申告書や届出書等の書類作成から、提出まで税理士に任せることができ、かつ、税金の相談もできる、ということです。
以上の3つ の独占業務に加えて、税理士は会社の経理や財務面において、多岐にわたるサポートを付随業務として行うことができます。以下で、税理士に依頼できることを会社の成長に合わせて説明していきます。
会社設立時・起業時に税理士に依頼するメリット
「起業」とは、独立して「事業を起こす」ことを言います。会社(法人)を設立するのも、個人事業でスタートするのも「起業」です。
個人事業の場合は、開業時は売上も少なく、所得税の確定申告などは、会計ソフトを使って自分でやるという人も多いでしょう。確定申告の時期になると、税理士が無料相談会を開いたりしますから、そうした場を活用するのもおすすめです。
一方、会社を設立するとなると、個人事業主のように税務署に開業届を提出すればOK、というわけにはいきません。設立登記をはじめとするさまざまな手続きが必要になるうえ、例えば会社の基本的な事項を記す「定款」の中身が不十分だったりすれば、起業後の事業がスムーズに進まないような事態も起こり得ます。そうならないよう、設立前から起業に詳しい税理士などのサポートを受けるのがおすすめです。「自社に合った先生だ」と感じれば、会社設立後も顧問税理士として契約を結ぶことも検討しましょう。
税理士に期待される役割の一つが「節税」の実行です。会社設立間もない経営者が、税務申告直前に予想を超える納税額を聞かされて資金集めに苦労する、といった例は珍しくありません。そのようなことを防ぐためにも、節税や資金繰りに詳しく、適切なアドバイスをしてくれる税理士を選ぶ必要があります。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 例えば、会社設立後に支出したものしか経費にならないと思い、領収書を保管していないという方も多いと思いますが、実際には設立日前の費用も、「創立費」として経費にすることができますし、設立後も開業準備費用を「開業費」として経費にすることができます。早めに税理士に相談すると何か気づきがあるかもしれません。
- 徳門税理士事務所 所長 徳門仁来(税理士・行政書士)
同時に、税理士の仕事は「税金まわり」だけではありません。例えば、会社設立において重要な事業計画は、金融機関へのアピールにもなる重要な書類でもあります。税理士は融資の獲得に有利となるような、事業計画の作成に関わる経営コンサルティング業務を行っていることもあります。会社設立時に、財務的な見通しを持った税理士に相談することは非常に有効だと言えるでしょう。
会社の設立時に税理士に依頼する7つのメリット
税理士は「会社を設立した後」に頼むこともできます。ただ、設立時から依頼すると、次のようなメリットがあります。
1.会社の設立手続きを代行してくれる
会社設立に必要な定款認証の代行や法務局への登記申請は、税理士自身が行うことはできません。ただ、「会社設立代行」をうたう税理士事務所は、行政書士や司法書士と提携しており、会社設立の手続きも受け付けてくれます。
2.会社の決算期の決め方について、的確なアドバイスがもらえる
決算が12月と決まっている個人事業主と違い、法人は決算期を自由に決めることができます。とはいえ、決算月を安易に決めてしまうと、後々で思わぬデメリットを被ることもあります。
例えば、売上に季節性がある場合、「ピークの近くを決算期にしない」というのが鉄則です。決算ギリギリまで収益予想が立てづらく、節税対策も講じにくくなるためです。決算に詳しい税理士ならば、決算期の設定について、的確なアドバイスをしてくれるでしょう。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 決算後、税務申告期限は原則2カ月以内です。そのため、決算月のみが忙しいのではなく、その後の1~2カ月も資料集めや決算打ち合わせなどで通常月より事務に時間を割くことが増えるでしょう。そこも踏まえて決算月を決める必要があります。
- 徳門税理士事務所 所長 徳門仁来(税理士・行政書士)
3.インボイス制度をはじめ、消費税についてのアドバイスがもらえる
決算期は、消費税の納税に影響することもあります。資本金1,000万円未満の場合、会社設立後2年間は、原則として消費税は課税されません(免税事業者となります)。しかし、例外もあります。事業開始から決算までが12カ月の場合、上半期で売上が1,000万円かつ給与支給額が合計1,000万円を超えると、2期目(設立2年目)から消費税課税事業者となるのです。
ただし、設立初年度が7カ月以下の場合は前期の特定期間の適用を受けずに、最初の6カ月以内で売上、給与支給額が1,000万円を超えた場合でも、2期目も免税事業者となります。つまり、設立後、最初の6カ月で売上、給与支給額が1,000万円を超えることが見込まれる場合、決算期を設立日から7カ月以内にすることで、2期目に課税事業者とはなりません。
なお、2023年10月に消費税のインボイス制度が導入されたため、このスキームを使うかどうかには、判断が必要になります。免税事業者はインボイスを発行できません。そのため、取引先が消費税の税額控除を受けられないという事態が発生し、それを理由に、例えば取引を打ち切られる(課税事業者に乗り換えられる)などのデメリットが生じる可能性があるのです。
このように消費税の考え方は難解です。どのような対応を取るべきか税理士に相談することで、事業の実態などを考慮したうえで具体的な説明・アドバイスを受けることもできます。
4.顧問契約前提ならば、無料(安価)で設立準備をサポートしてくれる
設立時には、税理士への依頼は「マスト」ではありません。しかし、設立後は顧問税理士をつける必要が出てきます。個人に比べ、申告業務は煩雑で、適切な節税の有無が最終利益に大きく影響するからです。どうせ顧問税理士をつけるのならば、会社設立時から「相性がいい先生」を見つけて、サポートを受けるというのも一つの考え方です。
5.利用できる補助金や助成金について相談できる
税理士は多くのクライアントと顧問契約を結んでおり、クライアントに役立つ補助金や助成金に関する情報やノウハウを持っていることがあります。自社が受けられる補助金や助成金がないか税理士に相談ができます。
6.起業直後の融資・資金繰りについて相談できる
起業直後に運転資金が十分に確保できず、金融機関からの融資が必要になる場合があります。資金繰り計画の作成や、それに基づく融資相談などを税理士に相談することで、必要な資金をよりスムーズに調達できるでしょう。
7.起業直後の経営について相談できる
初めて起業するケースでは、会社の経営を今後どのように進めていけばよいのか不安に感じる方もいるでしょう。税理士はさまざまなクライアントとの関わりのなかで、経営に関する多種多様なノウハウを持っています。積極的に相談することで自社に有益なアドバイスを受けられるでしょう。
会社の設立時から税理士に依頼するデメリット
一方、これは起業後の以下の各ステージにも共通するのですが、税理士に仕事を依頼することには、次のようなデメリットもあります。
・コストがかかる
・税理士によっては、自分が求める「節税や経営に関するアドバイス」をもらえないこともある
これらについては、後ほど詳しく述べます。
税理士を雇わない場合の選択肢とリスク
税理士を雇わない場合のリスク
逆に、起業後から税理士に依頼しない場合、以下のようなリスクが発生する可能性があります。
書類不備によるリスク
青色申告承認申請書の提出遅れや記載ミス、法人設立届出書などの必要書類の提出漏れ、消費税課税事業者選択届出書の提出タイミングのミス、給与支払事務所等の開設届出書の未提出といった問題が起こりがちです。これらの書類不備は、後々大きな損失につながる可能性があります。
税務調査リスク
申告書の記載ミスによる追徴課税のリスク、税務調査時に適切な対応ができない可能性、経費の計上根拠が不十分で否認されるリスク、法人税・消費税の計算ミスによる過少申告加算税などが発生する恐れがあります。特に税務調査では、専門知識がないと不利な状況に追い込まれやすくなります。
時間的負担・機会損失
税務学習や申告書作成に膨大な時間を要し、本業に集中できず事業成長の機会を失う可能性があります。経理業務に追われて営業活動の時間が削られたり、税制改正への対応遅れによる不利益を被ったりするケースも少なくありません。
起こりがちな失敗例・損失事例
また、税理士に相談せずに会社設立を進めた場合、思わぬ損失を被るケースも少なくありません。以下は実際に起こりがちな具体的な失敗事例です。
資本金設定ミスによる消費税免税期間の損失
事例:資本金1,050万円で設立したケース
本来であれば資本金を999万円に設定すれば設立1期目から消費税が免税となるところ、「きりの良い数字にしたい」という理由で1,050万円に設定。結果として設立1期目から消費税課税事業者となり、年間売上3,000万円の場合、約30万円の消費税を納税することになった事例があります。
青色申告承認申請書の提出遅れによる損失
事例:設立から3カ月以内の申請を忘れたケース
青色申告承認申請書は設立から3カ月以内(または事業年度終了日のいずれか早い日)に提出する必要があります。この申請を怠った結果、青色申告特別控除や欠損金の繰越控除などの特典を受けられず、年間で数十万円から数百万円の節税機会を失う場合があります。
決算期設定の失敗による資金繰りの悪化
事例:売上のピーク月を決算期にしたケース
飲食業で12月の売上がピークとなる会社が、12月決算を選択。決算業務で忙しい時期に本業の繁忙期が重なり、適切な決算予測ができずに想定外の法人税額が発生。資金繰りに苦労し、追加融資を受ける羽目になったケースもあります。
創立費・開業費の計上漏れ
事例:設立前費用を経費にできることを知らなかったケース
会社設立前に支出した市場調査費用50万円、事務所の敷金100万円、開業準備のための人件費80万円などを「会社設立前だから経費にならない」と判断し、個人負担として処理。実際にはこれらは創立費や開業費として経費計上でき、合計230万円分の節税機会を失った事例があります。
起業時、税理士に質問しておきたいリスト
資本金はいくらにするのが妥当か
起業前に決定しておかなければならない項目の1つに「資本金」があります。「資本金」を決定する際には、次の2点に注意しましょう。
- 資本金を1,000万円以上にすると、設立1期目から消費税の納税義務が生じる
- 資本金に応じて都道府県民税や市町村民税の均等割(赤字でも納税しなければならない税金)が多くなる
資本金は会社の信用力の1つではありますが、あまり多すぎると上記のようなデメリットが生じます。自社に見合う適切な資本金はいくらか税理士に相談しましょう。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 株式会社にするのか合同会社にするのか、そもそもそれらの違いは何なのか、などもあわせて税理士に相談するのもよいかと思います。
- 徳門税理士事務所 所長 徳門仁来(税理士・行政書士)
役員報酬はいくらに設定するのが妥当か
設立1期目の役員報酬をいくらにするかも重要な項目です。設立当初は得意先も少なく、売上高や利益が思うように上がらないケースも想定されます。多額の役員報酬で経営を圧迫しないよう、事業計画に基づいた適切な役員報酬の金額を相談しましょう。
創業時に活用できる補助金・助成金はあるか
創業時に必要な運転資金をサポートする目的で、国や地方公共団体が創業時の補助・助成制度を実施していることがあります。創業時に活用できる制度がないか質問してみましょう。
インボイス制度への対応
会社設立時に注意しなければならない項目の1つに「消費税のインボイス制度」への対応があります。設立時の資本金額が1,000万円以上であったり、特定期間の課税売上高(又は給与の支給額)が1,000万円超だったりした場合を除き、原則として設立1期目と2期目は消費税の納税義務が免除されます。
しかし、消費税の免税事業者はインボイス制度の請求書(適格請求書)を発行できません。取引先から適格請求書の発行を求められても対応できず、結果として取引を断られるリスクがあります。ご自身の会社が、設立後「2年間の消費税納税義務免除」という大きなメリットを諦めてでも、消費税課税事業者となるべきか相談しましょう。
起業時に依頼すべきは税理士?行政書士?司法書士?
行政書士が行う業務とは?
行政書士が行う業務として、国や都道府県、市区町村など、官公庁に提出する書類の作成・提出及び手続き内容の相談等が挙げられます。作成する書類は許認可に関するものが多く、手続きが煩雑な場合があります。専門的な知識を持つ行政書士に依頼すれば許認可の取得もスムーズに行えるでしょう。起業時に提出する「法人設立届出書」や個人の「開業届」など、税務関連の書類作成は税理士に、各種許認可等に関する書類作成は行政書士に依頼するケースが一般的です。
司法書士が行う業務とは?
司法書士が行う業務として、法務局や裁判所、検察庁などに提出する書類の作成・提出及び手続き内容の相談等が挙げられます。その他にも家庭裁判所から選任され成年後見人や破産管財人に関する業務を行うこともあります。法人を起業する際の資本金額や役員数などをどうすればよいかといった相談業務は税理士に、定款の作成・認証や設立登記などは司法書士に依頼するケースが一般的です。
会社設立を税理士以外に依頼するメリットはある?
先述のように、会社設立の手続きそのものは税理士にはできません。それらは、行政書士・司法書士の仕事です。
- 行政書士:会社設立に必要な書類の作成、許認可取得の代行
- 司法書士:法人登記の手続きの代行
上記は、それぞれの独占業務で、他の士業が代行することは認められないのです。
そのため、会社設立にプロの力を借りようと思ったら、本来は、書類作成は行政書士、登記は司法書士、税務関係の書類作成などは税理士というように、別々に依頼することになります。ただし、これら士業のネットワークを持つ税理士事務所に頼めば、ワンストップで税務、決算関連も含めた設立手続きをしてもらうことが可能です。
逆に言えば、税理士事務所に依頼する場合には、そのようなネットワークを持ったところを選ぶ必要があるでしょう。
会社を支えてくれる税理士の選び方
ここでは、会社を支えてくれる税理士の選び方についていくつかのポイントを挙げていきましょう。
税理士選びで失敗しないために押さえておくべきポイントは?
税理士選びで失敗しないために押さえておくべきポイントとして、以下の3点があります。
・信頼性
・スキル
・レスポンス
それぞれのポイントについて、見ていきましょう。
・信頼性
税理士に仕事を依頼するということは、会社のお金に関する情報を渡すということです。そのため、税理士を選ぶ際の基準としては、その人が「信頼できるか」「相性が合うか」が最も重要です。
・スキル
会社設立時に、信頼できて、かつ「スキルの高い」税理士と出会うことができれば、間違いなく会社は費用以上の恩恵を得られるでしょう。税理士のスキルについては、ホームページに書かれている実績や口コミなどでも判断することができます。
・レスポンス
税理士の能力とは別に、税理士に対する不満として多いものの一つに「レスポンスの遅さ」が挙げられます。
実は、税金に関する質問や資金繰りに関する質問のメールを送っても、何日経っても返信が来ない…といったことが頻繁に起こっています。レスポンスが遅いと素早い経営判断ができず、会社の成長に支障が出る可能性もあります。そのため、レスポンスの速い税理士を選びます。
レスポンスの速さを判断するには、見積書が送られてくるスピードや、質問に対する返答までの時間などをチェックしてみましょう。
業種や事業規模に適した税理士の選び方
自社の業種や事業規模に適した税理士を選ぶことも重要です。
自社の業種の顧問経験が多い税理士であれば、より適切なアドバイスを受けられます。
また、事業規模によって会社が税理士に望むことも違ってきます。例えば、中小企業では節税を重視する会社が多いですが、中堅から大企業では節税よりも上場を目指す会社も多いです。
実は税理士の中には、節税対策に消極的な人もいます。法律上、税理士の役目は適切な納税を支援することとなっているため、その「適切な納税」の範囲をどう捉えるのかによって節税に対するスタンスが変わってきます。節税を望む会社が、このような税理士に依頼するとミスマッチになります。
そこで依頼した税理士が「自分が求めているサービスをしてくれているのか」どうかは、常に検討する必要があります。
上場を目指している場合は上場に精通した税理士、節税を重視したい場合は節税に強い税理士…といったように、自らの会社が求める税理士像を明確にすることが、税理士選びのコツといえるでしょう。
税理士選びのチェックリスト・失敗例
税理士選びで後悔しないために、契約前に確認すべき重要なポイントと、実際によくある失敗事例を解説します。以下のチェックリストを参考に、自社に最適な税理士を見極めましょう。
契約前に必ず確認すべきチェックリスト
サービス内容の確認
- 記帳代行は月額料金に含まれているか
- 月次面談の頻度と方法(対面・オンライン・電話)
- 税務相談の回数制限はあるか
- 年末調整や給与計算は対応可能か
- 税務調査への立会いは可能か
料金体系の確認
- 月額顧問料に含まれるサービス範囲の詳細
- 決算申告料の金額
- オプション料金が発生する業務の一覧
- 追加相談時の料金設定
- 契約期間の縛りや解約条件
デジタル対応の確認
- クラウド会計ソフトへの対応状況
- オンライン面談の可否
- 電子帳簿保存法への対応
- 資料の電子化やペーパーレス対応
- メールやチャットでの迅速な連絡体制
専門性・実績の確認
- 自社の業種での顧問実績の有無
- 同規模企業の対応経験
- 資格者の人数と経験年数
- 得意分野(節税、融資、上場支援など)
- 最新の税制改正への対応力
よくある失敗例
税理士と顧問契約したからといってすべてがうまくいくわけではありません。
下記のようなケースも参考に、慎重に選定しましょう。
失敗例1:記帳代行が別料金で高額になった
月額顧問料3万円という税理士事務所と契約したA社の事例。契約後に記帳代行は別料金(月額2万円)と判明し、さらに給与計算(月額1.5万円)、年末調整(15万円)も追加費用として請求された。結果的に年間で100万円以上の費用となり、予算を大幅に超過してしまった。事前に「月額料金に何が含まれているか」の詳細確認が不十分だったことが原因です。
失敗例2:レスポンスが遅くデジタル非対応で不便
B社が依頼した税理士は、メールの返信が1週間以上かかることが常態化していた。さらにクラウド会計ソフトに対応しておらず、毎月紙の資料を郵送で送る必要があった。急ぎの税務相談があっても迅速な対応が得られず、重要な経営判断が遅れる事態が頻発。現代のビジネススピードに対応できない税理士との契約は、経営の足枷となる可能性があります。
税理士に依頼する場合の費用はどれくらい?
顧問契約を頼んだ場合の月額顧問料の相場
税理士と顧問契約を結ぶ前には、費用やサービス内容を確認します。なぜなら、税理士によって費用とサービス内容が異なるからです。
ただし、多くの会計事務所が競争している状況ですから、目安としての「報酬相場」は存在します。開業したての零細企業で売上もそこまで多くない場合であれば、月額の費用は2万円~5万円程度と考えればいいでしょう(別途、決算申告料もかかります)。
一般的に記帳代行だけ依頼するのか、コンサル的なサポートも頼むのか、といった依頼内容によって、金額は変わってきます。
月額顧問料以外に発生する費用について
しかし、ある税理士では、提示された費用の中に、ここまでのサービスが含まれていても、別の税理士では含まれていないということがあります。例えば、顧問契約の中にコンサル的なサポートが含まれている税理士も含まれていない税理士もいます。
ホームページなどで、上述した目安よりも安い価格を提示している会計事務所もありますが、必要なサポートを受けようとすると、さまざまなオプション料金が加算される可能性も十分にあるので、注意しなければなりません。
一般的には、記帳代行から申告、定期的な面談など通常の税理士業務を行う場合には、会社の年間売上のおおよそ3%~8%の顧問料が設定されるといわれています。しかし、実際には会社の規模や業種などによって顧問料は変動するので、一応の目安と考えて、会計事務所と相談のうえで納得できる依頼内容や顧問料を決めるようにしましょう。
会社設立の方法別費用比較
会社設立にかかる費用は、どの方法で手続きを進めるかによって大きく異なります。以下は株式会社設立時の費用相場例です(参考・目安)。
自分で設立する場合
- 定款認証手数料:約5万円
- 登録免許税:15万円
- 印紙代:4万円(電子定款でない場合)
- その他実費:約1万円
合計:約25万円
司法書士に依頼する場合
- 上記実費:約21万円(電子定款対応)
- 司法書士報酬:8~15万円程度
合計:約29~36万円
税理士に依頼する場合(顧問契約前提)
- 上記実費:約21万円(電子定款対応)
- 税理士報酬:無料~10万円程度(顧問契約前提の場合)
- 提携士業への支払い:5~10万円程度
合計:約26~31万円
費用を抑える制度について
「特定創業支援等事業」の認定を受けた場合、株式会社設立時の登録免許税が15万円から7.5万円に軽減される制度があります。この制度は市区町村が認定する創業支援事業を受けることで利用でき、約7.5万円の節約につながります。税理士に相談することで、このような制度の活用方法についてもアドバイスを受けることができるでしょう。
会社設立後のステージ別税理士に依頼するメリット【参考】
ここまでは会社設立時に税理士に依頼するメリットなどを見てきましたが、会社設立が無事に完了し、事業が始まった後から税理士に依頼するメリットも見ていきましょう。
税理士に依頼するメリット(創業初期、急成長期)
個人事業の場合は、売上1,000万円超というのが、税理士を頼む1つの目安になるでしょう。その水準からは消費税がかかってきますし、法人化(法人成り)も視野に入ってくるからです。
会社を設立したばかりの時期は、多くの場合で慣れない会計業務に苦心することとなります。そのような場合は、税理士に会計指導を依頼するのがいいでしょう。税理士は、会社の業務形態に適した会計処理や会計ソフトの選択などを丁寧に指導してくれます。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 近年、会計ソフトは日々の領収書等を入力し記帳していくだけではなく、請求書や人事管理も一体となったものがあります。そのようなERP(Enterprise Resource Planning=業務統合パッケージ)を導入して、最初から事務の効率化をしていくといいでしょう。
- 徳門税理士事務所 所長 徳門仁来(税理士・行政書士)
また、そもそも本業以外に時間を割きたくない、会計業務を税理士に委託したいという場合には、「記帳代行」という形で依頼することが可能です。毎月の領収書や請求書などの書類を税理士に渡せば、これらを整理して会計ソフトへの入力まで行ってもらえます。人手の足りない場合が多い創業初期には非常に便利で、人件費削減の観点からも有効と言えるでしょう。
そして事業が軌道に乗り、売上が増えて人も多く雇うようになると、税理士に依頼できることも増えてきます。
給与の計算
毎月の従業員給与の計算も、所得税法を熟知している税理士であれば代行可能です。毎月の勤怠表を税理士に渡すだけで、面倒な源泉所得税や年末調整、社会保険料などを一括して計算してくれます。こういったプライベートな情報は信頼のおける税理士に委託することで、情報が意図せず外部に漏洩するリスクが低減されますし、最初から税理士に相談しておくことで、時期になって焦ることなく年末調整を終えることができるでしょう。
節税対策
例えば、“自らが受け取る役員報酬を適正な水準にする”や“自社の事業拡大に結びつく宣伝広告費を増やして経費にする”など、税理士の持つノウハウを駆使することで、大きな節税効果が期待できます。先ほども述べたように、これらは経営に対するコンサルティング的なサポートと表裏一体です。そういったサポート力を持った税理士に依頼しましょう。
税理士に依頼するメリット(安定成長期)
安定成長期に税理士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。
税務調査対策
「税務調査」は、申告内容に間違いがないかを税務署が調べる任意調査のことです(悪質な脱税に対する強制調査もあります)。その対象にならないように、税理士に適正な申告を依頼するのはもちろんですが、特に法人の場合は正しく申告を行っていても、調査に入られることがあります。任意調査には、税理士の同席が認められますが、対応を誤ると余計な税金を取られることもありますので、経験のある税理士のフォローを受けられると安心です。
内部管理体制の見直し
経営が軌道に乗ってきたら、経営の合理化を図ることで業績の拡大を目指すことになるでしょう。そのために営業に力を注ぐことは重要ですが、一方で内部管理体制に不備があると、事業の足を引っ張ったり、思わぬ形で会社の信用を落としたりしかねません。内部管理体制は、株式を上場する際にも特に重要視されます。それぞれの会社の業態に合わせた内部管理体制にできるように、コンサルティングサービスを行っている税理士もいます。
事業再生
事業を行っている以上、過剰債務や業績悪化などが原因で資金繰りに行き詰る可能性もゼロではありません。そんな場合でも、事業再生のサポートを行ってくれる税理士がいます。再生計画の立案から、業務の効率化を通じた会社の収益構造の見直し、事業再生後のフォローアップまでアドバイスをもらうことができます。
事業承継対策
会社がある程度成熟した場合、最終的には次世代へ会社をバトンタッチすること、すなわち事業承継を考えなくてはなりません。事業承継では、相続が発生した場合の相続税の試算や、事業承継税制のような制度の利用の検討などにおいて、専門知識のある税理士に相談することでスムーズに進めることができます。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 税理士は会社の状況や、社長個人の財産などを把握していることが多いです。人に相談しにくい相続の問題も、税理士だから相談しやすいこともあると思います。
- 徳門税理士事務所 所長 徳門仁来(税理士・行政書士)
会社設立で税理士への依頼を検討中の方へ
優秀な税理士と出会うことは、会社の成長の大きな助けになります。今回解説したような税理士のサービスを踏まえて、自分の会社が必要とする税理士を見つけましょう。
記事監修者 徳門税理士からのアドバイス
会社を設立する際、多くの方は倒産することを考えていません。長く事業を続ける前提で取り組んでいます。しかし、会社の継続のためには、決算や税務申告など数字や税金に関わる作業は避けて通れません。自分で全てをやろうとする方もいるかもしれませんが、どの程度の知識やスキルが必要なのかを把握するためにも、一度税理士に相談するのも良いでしょう。
また、税理士は会計指導もできます。例えば会社設立時からERPシステムを導入することで、日々の帳簿管理や請求書作成、在庫管理、支払い管理などを効率的に行うことも可能です。
会社設立を検討している方は、早い段階で税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
よくある質問
Q:会社設立時に税理士は必ず必要ですか?
A:法的には「必須」ではありませんが、専門家のサポートを受けることで設立手続きや節税対策、資金繰りといった経営の要となる部分をスムーズに進められます。特に、会社設立前後は経営者ご自身が本業に集中できる環境を整えることが大切です。税理士を活用すれば、書類作成や税務対応の負担を軽減できるため、結果的にコスト以上のメリットを得られるケースが多いと言えます。
Q:起業前に税理士へ相談するメリットは何でしょうか?
A:起業前から税理士に相談することで、定款の作成や資本金の設定、決算期の選定など、設立後に影響する重要事項を戦略的に決めやすくなります。また、開業準備費用など「設立前の支出」を経費に計上できるケースがあり、節税メリットを見落としにくい点も大きな利点です。早めの相談で、経営や資金繰りに関するリスクを把握・対策できるのもメリットの一つです。
Q:税理士に依頼する場合の費用はどのくらいかかりますか?
A:依頼内容や会社の事業規模によって異なりますが、開業直後の小規模法人であれば、月額顧問料はおおよそ2万円~5万円程度が目安です。さらに決算申告料などが別途発生します。ただし、顧問契約にどこまでのサービスが含まれるかは事務所によって異なるので、事前に「月額報酬に何が含まれるのか」「オプション料金はあるのか」をしっかり確認することをおすすめします。
Q:設立手続きを税理士にまるごと代行してもらえますか?
A:税理士自体が会社の定款認証や登記申請を直接代行することはできません。これらは行政書士や司法書士の独占業務にあたるからです。ただし、多くの税理士事務所は行政書士・司法書士と提携し、ワンストップで書類作成や登記をサポートしている場合があります。複数の専門家を個別に手配する手間を省きたいなら、提携先のある税理士事務所を探すとよいでしょう。
Q:会社設立後に税理士に依頼するタイミングを逃した場合はどうすればいいですか?
A:会社設立後、しばらく自力で税務対応していた方でも、必要性を感じたタイミングで税理士に依頼すれば問題ありません。特に、売上が1,000万円を超えてくると消費税の納税義務や会計処理が複雑化するため、経理負担を大きく感じるようになります。その段階からでも遅くはありませんが、対応が後手に回ると税務リスクが高まるため、早めの依頼が安心です。
Q:たくさんの税理士がいる中で、どうやって自分に合った税理士を選べばいいですか?
A:まずは「信頼性」「スキル」「レスポンスの速さ」という3つの基準で比較検討することをおすすめします。具体的には、実績や得意分野をしっかりと確認したうえで、初回の問い合わせや見積り依頼時の対応速度を見て判断しましょう。また、業種や事業規模に合った経験を持つ税理士かどうかも重要です。節税を重視したいなら節税案件に強い税理士、上場を目指すなら上場支援の実績がある税理士と、目的に合った専門家を選ぶことがポイントです。