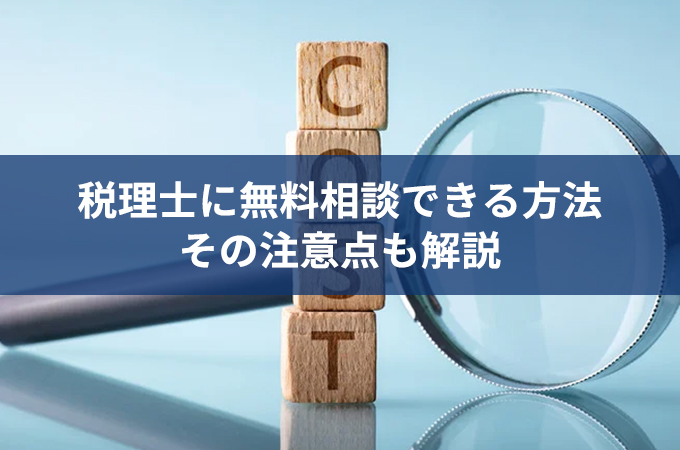中小企業に最適な税理士とは?選び方のポイントを解説
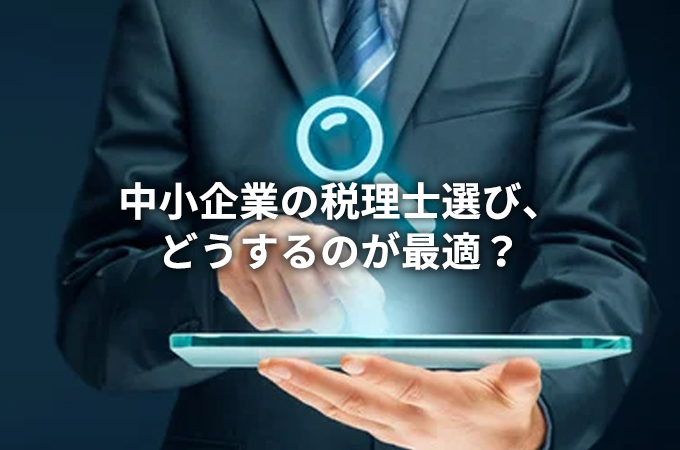
- 最終更新日:
- 2025/05/14

- この記事の監修者
- 税理士紹介業界で30年・44万件超の現場を知るパイオニア
株式会社ビスカス 代表取締役 八木美代子
この記事のアドバイザー

徳永税理士事務所 所長
徳永 圭
大学で財務会計ゼミに入ったことがきっかけとなり税理士資格を取得。総合不動産会社、不動産証券化(SPC)特化型事務所、総合会計事務所を経て令和へ年号が変わるとともに開業。これまでの職歴から不動産周りの税務会計、資産税(相続)に強みがあります。
中小企業に税理士のサポートは必要?
「うちは家族経営の小規模企業だし、確定申告も会計ソフトで自分たちで済ませている。だから税理士までは必要ないのでは?」──そう考える経営者も少なくありません。
確かに、仕訳数が少なく 電子申告にも慣れている 企業であれば、日常的な帳簿づけや決算書作成までは自社で完結できるケースがあります。
ただし税理士の役割は申告代理だけではありません。
中小企業に精通した税理士は、利益の最大化・適切な節税・資金繰り・経営分析など、経営者とは異なる視点でサポートできます。とくに近年はインボイス制度や電子帳簿保存法など新制度が相次ぎ、「経営」と「法令対応」を両立させるハードルが急速に上がっています。
そのため、税理士のサポートは「絶対に必要」ではないものの、会社の成長フェーズや業務負荷によっては大きなメリットをもたらします。では、もし税理士を利用しなかった場合、どのようなリスクや限界があるのでしょうか。
税理士を利用しない場合のリスクと限界
1. 申告ミスによる追徴課税リスク
自社で記帳・申告を行うと、消費税区分や交際費損金算入額など専門的な論点で誤りが出やすくなります。ある飲食店では仕入控除税額を誤計算して150万円の追徴課税を受けました。税理士チェックが入れば防げたミスです。
2. 節税機会の逸失
税制改正をフォローしきれないまま設備投資を行い、即時償却の特例を逃した製造業A社は約90万円の追加納税を余儀なくされました。時限措置や優遇税制を活かすには専門家の知識が不可欠です。
3. 時間コスト増大と経営判断の遅延
月末・決算期の仕訳入力や申告書作成に追われ、本来注力すべき新規顧客開拓が後回しに。数字把握の遅れは資金繰り悪化や投資判断の遅延に直結します。
4. 融資・補助金審査での信用力不足
税理士の署名がない決算書は信頼性が低く見なされ、融資枠縮小や金利上乗せの要因に。ITスタートアップB社は希望額の80%しか借入できず、開発計画が半年遅延しました。
5. 法改正対応の遅れ
電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が遅れると、経費否認・社内業務停滞を招くリスクがあります。専門家の伴走がない場合、ペナルティや追加コストが発生しやすい点は要注意です。
結論:コスト削減のために税理士を使わない選択をすると、見えにくいコスト(追徴課税・機会損失・時間ロス)が膨らむ恐れがあります。税理士活用は「経営リスクを抑制しながら成長を加速させる投資」と捉えるのが賢明です。
中小企業経営者は税理士に頼むべき?そのメリットは?
ここまで述べたことを踏まえたうえで、中小企業経営者が税理士に依頼できることには、次のようなものがあります。
税務署への確定申告や会計処理
税務申告にミスは許されません。意図的ではなくても“申告漏れ”があれば、「加算税」などのペナルティで、より多くの税金を支払うことになる可能性があります。税理士に税務書類の作成や申告を頼めば、そうしたリスクを軽減することができるでしょう。税理士が申告書を作成していても税務調査が行われることはありますが、その際にも税理士の立ち会いが認められています。
会社が確定申告を行う際には、財務諸表などの決算書類も併せて提出しなくてはなりません。税理士には、これらの書類の作成や会計帳簿の記帳((帳簿付け))も併せて依頼できます。そうすることで経営者は本業に集中することができ、会社の規模などによっては、社内で人を雇うよりもコストダウンが図れます。
節税対策の実行
今述べたように「過少申告」は問題ですが、反対に適切な節税が行われずに税負担が膨らむことも、経営の圧迫要因になります。随時更新される中小企業税制などに通じた税理士に依頼すれば、それらも活用した有効な節税策を実行してくれるはずです。
経営に対するアドバイス
正確な税務申告や有効な節税のためには、税理士に「会社の実情」を理解してもらう必要があります。そういう立場にある税理士からは、数字に基づく経営のアドバイスを受けることも可能でしょう。というのも最近は、税務関連オンリーではなく、コンサルタント的な機能を重視する会計事務所も増えているためです。ただし、そういった経営のアドバイスが得意でない税理士もいますので、税理士選びの際には注意が必要です。
資金調達のサポート
金融機関から融資を受ける際には、原則として「事業計画書」などの提出を求められます。経験のある税理士ならば、貸し手が納得できる説得力のある計画書作りをサポートしてくれます。中には、金融機関の担当者とパイプを持つ税理士もいますので、そういった“繋がり”を活用することもできるでしょう。中小企業向けには様々な補助金や助成金も用意されていますが、それに気づかない経営者も数多くいます。中小企業税制に詳しい税理士に依頼すれば、自社に適した制度の活用を提案してくれるでしょう。
経営者個人の相続、事業承継
上場大企業と違い、自社株を社長が持つ中小企業では、会社の利益・資産と経営者のそれは密接不可分と言っても過言ではありません。税理士には、経営者個人の所得税の申告や、資産の管理なども任せることができます。経営者が特に考える必要があるのは「相続対策」です。次期経営者に自社株をうまく引き継げなければ、事業の承継は難しくなってしまいます。相続の実績のある税理士に相談し、早めに準備をスタートさせるべきでしょう。
税理士に依頼する場合の注意点
一方で、税理士に依頼する場合は以下のデメリット・注意点があります。
コストがかかる
税理士に業務を頼めば、当然ですが税理士報酬が発生します。依頼する業務の内容や量によって、金額は変わってきます。また、同じ依頼内容でも、事務所によって差の生じることもあるのです。報酬が高いわりに節税効果はたいしたことがなかった…というのでは、あまり意味がありません。税理士に依頼する場合には、その費用対効果を検討するとともに、複数の事務所の比較をしてみることが大事です。
費用の相場は、例えば主に税務関係の業務委託と相談対応の顧問契約であれば以下の表のとおりです。
| 年商 | 月額費用 |
|---|---|
| ~1,000万円 | 1万円~2万5,000円 |
| ~3,000万円 | 1万5,000円~3万5,000円 |
| ~5,000万円 | 2万5,000円~4万5,000円 |
| ~1億円 | 3万円~6万円 |
| 1億円以上 | 6万円~10万円 |
また、主に経営方針や資金調達などのアドバイスや指導を依頼する、いわゆるコンサルティング業務の場合の費用は、着手金+成果報酬型となることが多いです。例えば融資・助成金など資金調達業務であれば、着手金は数万~20万円、成果報酬は得られた調達額の2~5%程が相場と言われています。
※税理士は自由報酬制ですので、金額はあくまでも目安となります。
法人税や経営を知らない税理士だと満足は得られない
税理士にも得意分野があります。中には「相続税には強いけれど、法人税の申告は一度もやったことがない」というような税理士もいるのです。そういう税理士に依頼した場合、法人税の節税などは難しいと考えるべきでしょう。
また、先ほど「経営のアドバイスがもらえる」と言いましたが、会社経営や業界事情に不慣れなのにも関わらず、やたらと経営に口出ししてくるようなタイプの税理士は考えものです。場合によってはミスリードされてしまう危険性さえありますので、十分な実績のある税理士を選ぶように注意しましょう。
税理士に依頼するタイミング・きっかけは?
メリット・デメリットと見てきましたが、会社経営のどのタイミングで税理士に依頼すべきかをフェーズごとに見ていきましょう。
1. 会社設立時:スタートダッシュを切りたい創業フェーズ
会社設立後は、税務署への各種届出(青色申告承認申請・消費税課税事業者選択届など)を原則2か月以内に提出する必要があります。開業直後は事業計画や顧客開拓に注力したい時期でもあるため、帳簿づけや届出の準備を税理士に任せることで「手続き漏れの防止」と「本業への専念」を同時に実現できます。また、創業融資を検討している場合には、金融機関向けの事業計画書や資金繰り表を税理士がサポートすることで、資金調達の成功率を高められます。
2. 売上が伸び始めた頃:成長フェーズで資金繰りを最適化したいとき
売上が上がると、納税額や資金繰りの難易度も比例して高まります。月次試算表の早期化や四半期ごとの節税シミュレーションを税理士に依頼すれば、キャッシュフローを見える化しながら先手の資金計画が立てられます。決算対策や利益計画を踏まえた設備投資・採用の判断もスムーズになり、経営スピードを落とさずに次の成長ステージへ移行できます。
3. 手続き・帳簿が煩雑になったとき:本業に集中するためのアウトソーシング
領収書や請求書が増え、経理処理に追われ始めたら「専門家に任せるべきサイン」です。自社で記帳を続けると、締め切り直前の入力ミスや消費税区分の誤りが発生しやすく、修正申告や追徴課税のリスクが高まります。税理士にアウトソーシングすれば、クラウド会計と連携した効率化・チェック体制が整い、社内工数をコア業務に再配分できます。
4. 融資・補助金を検討するとき:金融機関・行政への信用力を高める
金融機関は試算表の正確性や納税の適正性を重視します。税理士が監修した決算書を提出することで審査の評価が上がり、融資枠や金利条件の優遇につながるケースも多く見られます。また、ものづくり補助金・事業再構築補助金などの申請でも事業計画の数値根拠をプロが作成・サポートすることで採択率が向上します。
5. 税制改正への対応や節税を検討するとき
毎年の税制改正で中小企業投資促進税制・所得拡大促進税制などの優遇措置が更新されます。最新制度を漏れなく活用するには、税制改正に精通した税理士のサポートが欠かせません。試算段階から節税メリットを数値化し、「適用要件を満たすための行動計画」まで落とし込むことで、税負担を最小限に抑えられます。
6. 事業承継・M&Aを視野に入れるとき
後継者への自社株評価やM&Aスキームの税負担は複雑で、早期に専門家と連携するほど選択肢が広がります。税理士が事業承継税制や株価引下げ策を活用しつつ、財務デューデリジェンスもサポートすることで、スムーズかつ節税メリットを最大化した承継が可能になります。
中小企業に最適な税理士を選ぶチェックポイント
ここからは、「税理士に何を期待するか」「どう見極めるか」という2つの観点で中小企業経営者が押さえておきたいポイントを解説します。
面談時に確認すべき質問例や、契約前にチェックできる客観的な指標も盛り込みましたので、面談メモや比較表づくりの参考にしてください。
中小企業の税制に詳しく、経験があるか
中小企業特有の優遇税制(中小企業投資促進税制・所得拡大促進税制・交際費課税の特例など)は、制度改正のたびに適用要件が細かく変わります。
面談では、
「最近サポートした顧問先で、どの制度をどのように活用しましたか?」
「インボイス制度で免税から課税へ切り替えた顧問先は、どの手順で対応しましたか?」
といった具体的事例を尋ね、最新情報を実務レベルで語れるかを確認しましょう。
顧問先数や業種構成を質問し、同規模・同業態の企業を複数支援した実績があれば安心感が増します。
中小企業の経営に詳しく、適切なアドバイスがもらえるか
税理士を「決算・申告の外注先」ではなく、経営伴走者として活用したい場合は、数字を経営指標へ翻訳できる力が必須です。
面談では、
「月次試算表をどのようなフォーマットで共有し、経営分析をどこまで行ってくれますか?」
「粗利率や資金繰りの改善提案を行った事例はありますか?」
と質問し、提案内容を口頭で“即答”できるかを確認しましょう。
顧問先の黒字化率や資金調達成功率など、定量的な成果指標を示せる税理士は信頼度が高いです。
業界知識があるか
飲食・IT・製造など、業種によっては原価計算の方法、許認可の更新スケジュール、経費計上の慣行が大きく異なります。
面談時に「同業種の顧問先で気を付けているポイントは何ですか?」と投げかけ、業界特有の指標や監督官庁のガイドラインを踏まえた回答が返ってくるかを確認しましょう。
日本政策金融公庫の業種別財務データなどを引用しながら話せる税理士は、実務経験が豊富である可能性が高いです。
融資に強いか
融資面談で決算書の見せ方をアドバイスできる税理士は、金融機関との交渉を円滑にします。
「最近サポートした融資案件で、どのようなストラクチャーを提案しましたか?」
「政策金融公庫・保証協会付き融資・事業再構築補助金との併用事例はありますか?」
などと聞くことで、実際の支援プロセスを把握できます。
金融機関からの紹介実績や、定期的に行う資金繰り予測(CF計算書や資金繰り表)の提供方法も確認ポイントです。
レスポンスは早いか
経営判断はタイミングが命です。相談の返答が翌日以降になる税理士だと、資金繰りや取引条件の変更に対応しきれません。
契約前に平均レスポンス時間を数値で示してもらい、「チャットツール・電話・メールの優先順位」「決算期の繁忙期でも守れるか」など具体的に確認しましょう。
“36時間以内に一次回答”など、SLA(サービスレベルアグリーメント)を明示している事務所は安心です。
経営者との相性・親身な対応
数字のアドバイスが的確でも、コミュニケーションが噛み合わなければ実行に移せません。
初回面談では「専門用語をかみ砕いて説明してくれるか」「意見を遮らずヒアリングしてくれるか」を観察し、感覚的に“話しやすい”かどうかも判断してください。
また、経営計画の共有や月次ミーティングの頻度を確認し、「先回りの提案」が期待できるフォロー体制かを見極めましょう。
サービス内容、料金が明確である
税理士報酬は「記帳」「決算・申告」「経営相談」「年末調整・給与計算」など業務ごとに区切って提示されるのが一般的です。
見積書やパンフレットで「何が基本料金に含まれ、どこからがオプションか」を明示し、追加料金の発生条件(訪問回数・部門別管理の導入など)を説明できる税理士を選びましょう。
クラウド会計の導入支援や経営ダッシュボードの提供など、付加価値サービスの内容と価格を比較することで、単純な費用対効果ではなく“投資対効果”の視点で判断できます。
中小企業に最適な税理士の探し方
税理士は、ネットで事務所のホームページなどを検索し、比較することで選ぶことが可能です。知り合いや同業者などの紹介や、口コミを参考にすることもできるでしょう。
また、当社のような実績のある税理士紹介会社を利用するという方法もあります。
地域や業種、依頼したい中身などを伝えれば、第三者の視点からニーズに見合った税理士を無料で探してもらえますから、効率的に最適の税理士に出会える確率が高まります。
中小企業の税理士選定で注意すべきことは?

徳永 圭
税理士からのワンポイントアドバイス
税理士に依頼するに当たって最初に検討すべき事項は2点です。
①予算はいくらを想定しているか?
②どのような目的で税理士に依頼するか?の2点です。
ニーズは個々人で異なり、ある人にとっては「良い税理士」であっても、読者の皆様にとって「良い税理士」とは限りません。例えば、グレーゾーンの取り扱いを巡り税務署と見解の相違が発生するリスクを負っても良いと考えているにもかかわらず顧問税理士がその処理を認めないならば求めていた税理士とは異なるでしょう。逆のパターンもしかりで、税務署とは一切揉めたくないというお客様もいます。本当に価値観はひとそれぞれなのです。
よって、皆様は必ず契約前に税理士と直接話をする機会を設けご自身のニーズを税理士に打ち明けて頂き、対応できる税理士を選ぶと良いでしょう。
複数の候補者で迷ったならば、最後は「相性」になるかと思います。税理士とお客様の関係においても日常生活の中での人付き合い(人間関係)と何ら変わるものではないからです。
よくある質問
税理士の選び方のポイントは何ですか?
税理士を選ぶ際は、中小企業の税制に詳しいこと、経営に対するアドバイスができること、業界知識があること、融資に強いこと、対応が早く親身になってくれること、サービス内容と料金が明確であることが重要です。
税理士に依頼するメリットは何ですか?
税理士に依頼することで、税務申告や会計処理のミスを防ぎ、節税対策を実行でき、経営に対する適切なアドバイスを受けられます。また、資金調達のサポートや経営者個人の相続・事業承継の助言も期待できます。
税理士に依頼する際の注意点は何ですか?
税理士に依頼する際の注意点として、コストがかかること、法人税や経営に詳しくない税理士だと満足できない可能性があることが挙げられます。費用対効果を検討し、複数の事務所を比較することが大切です。
中小企業に最適な税理士を探す方法は?
税理士は、ネットで事務所のホームページを検索し、比較することで選ぶことが可能です。また、知り合いや同業者からの紹介や、税理士紹介会社を利用することも効果的です。
税理士に依頼する業務の費用相場はどれくらいですか?
税理士に依頼する業務の費用相場は、例えば税務関係の業務委託では年間20万~50万円、相談対応の顧問契約では月額2万~5万円程度です。経営コンサルティング業務の場合は、着手金と成果報酬型となり、融資・助成金の資金調達業務では、着手金数万~20万円、成果報酬は調達額の2~5%が相場です。
まとめ|中小企業が税理士を“経営パートナー”にするための要点
税理士の活用は単なる申告代行ではなく、「経営リスクを抑え、成長スピードを上げる投資」です。
▼ 自社対応の限界 ─ 追徴課税や節税機会の逸失、資金繰り判断の遅延など“見えにくいコスト”が膨らむリスク。
▼ 依頼すべきタイミング ─ 創業時・売上拡大期・帳簿煩雑化・融資/補助金申請・節税検討・事業承継など、ステージごとに専門家の伴走が不可欠。
▼ 選定チェックポイント ─ 中小企業税制への精通・経営提案力・業界知識・融資支援実績・レスポンス速度・相性・明朗な料金体系は必須条件。
おすすめアクション
1. 上記チェックリストを使い最低2~3事務所と面談して比較。
2. 迷ったら無料の税理士紹介サービスで業種・地域・ニーズに合う候補を絞り込み、時間コストを最小化。
3. 契約前に目的・予算・コミュニケーション方法を共有し、SLA(回答時間など)を明確化。
経営者が本業に集中し、「数字の安心」と「攻めの経営」を両立させるために、信頼できる税理士を“経営パートナー”として迎え入れましょう。

- この記事の監修者
- 税理士紹介業界で30年・44万件超の現場を知るパイオニア
株式会社ビスカス 代表取締役 八木美代子
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税理士・税理士探し >
- 中小企業に最適な税理士とは?選び方のポイントを解説