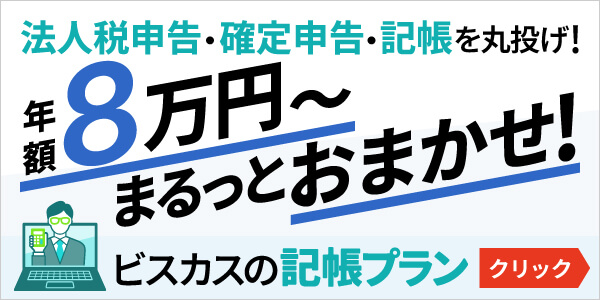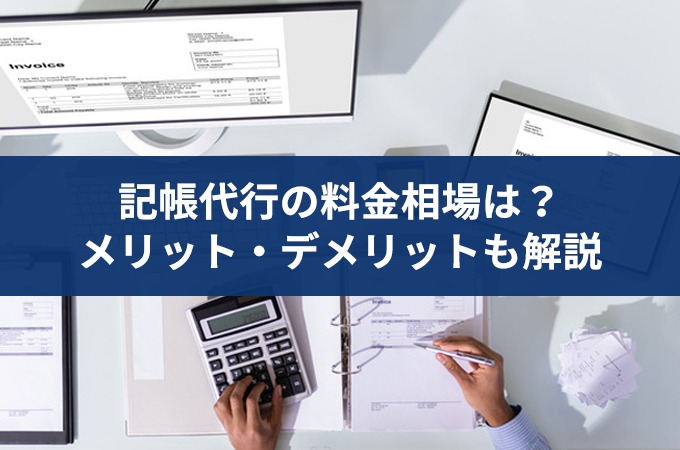退職者も年末調整の対象者になる?例外・実務対応まで徹底解説


- この記事の監修者
- おだね税理士事務所
代表 小田根 大輔(税理士)
退職者の年末調整とは?基本ルールと原則
年末調整は、給与所得者の1年間の所得税を精算する手続きです。毎月の給与から源泉徴収された所得税額と、各種控除を適用した後の正確な年税額を比較し、過不足を調整します。この手続きにより、従業員は原則として確定申告をする必要がなくなります。
退職者は原則として年末調整の対象外となります。なぜなら、年末調整は12月31日時点で在籍している従業員を対象とする制度だからです。退職者は年の途中で会社を離れるため、その時点では1年間の所得が確定しておらず、再就職先での給与も含めた年間所得全体を精算する必要があります。
※その年の給与収入が2,000万円超の人は在籍中でも年末調整の対象外となり、自ら確定申告を行います。
ただし、一定の条件を満たす場合には例外的に退職者でも年末調整の対象となります。これらの例外ケースを正確に理解し、適切に対応することが人事労務担当者には求められます。
年末調整の対象となる人・ならない人
年末調整の対象者は、12月31日時点で会社に在籍し、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している従業員です。正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、この条件を満たせば年末調整の対象となります。
退職者が原則として対象外となる理由は、年末調整が「その年の12月31日現在の状況」を基準に行われるためです。退職後に再就職した場合、新しい勤務先で前職分も含めて年末調整を行うことになります。このため、退職時点では会社側で年末調整を行わず、源泉徴収票を発行して退職者に渡すのが基本的な対応です。
なお、扶養控除等申告書の提出がない場合は、在籍中の従業員であっても年末調整の対象外となり、乙欄徴収(税率が高い)となります。退職者についても、この申告書の提出有無は例外的に年末調整を行う際の重要な判断材料となります。
退職者が年末調整の対象になる例外パターン
退職者でも以下の5つのパターンに該当する場合は、例外的に会社側で年末調整を行う必要があります。
死亡退職の場合
従業員が死亡により退職した場合は、死亡時点で年末調整を行います。死亡後に相続人が確定申告を行うこともできますが、通常は会社側で年末調整を実施し、過不足税額を精算します。死亡退職の場合は再就職の可能性がないため、その時点での所得確定が可能です。遺族への源泉徴収票交付と丁寧な説明が求められます。
著しい心身の障害により退職し、再就職の見込みがない場合
重度の病気や障害により退職し、その年中に再就職が見込めないケースでは、退職時に年末調整を行います。この場合、医師の診断書など再就職が困難であることを示す資料の確認が必要です。単なる病気療養による休職とは異なり、就労が著しく困難な状態であることが要件となります。
12月中に給与の支払いを受けて退職した場合
12月に給与支給を受けて退職する場合は、その年の給与が確定するため年末調整の対象となります。ただし、12月分の給与が翌年1月に支払われる場合は対象外となります。年末調整は支給日基準で判定するため、給与規程や実際の振込予定日を正確に確認する必要があります。国税庁タックスアンサーNo.2668(年末調整の対象となる人)で詳細が確認できます。
パート・アルバイト等で年間給与が123万円以下、かつ再就職の見込みがない場合
退職時までの本年中の給与総額が123万円以下(日額2万850円以下)で、かつその年に他社から給与の支払見込みがない場合のみ、退職時に年末調整を行います。この2つの要件を両方満たすことが必要です。短期間のパート勤務者などがこのケースに該当することが多く、本人への確認が必要です。再就職予定について書面で確認を取ることが実務上推奨されます。国税庁タックスアンサーNo.2665(年末調整の対象となる人の範囲)で詳細が確認できます。
海外転勤等により非居住者となった場合
海外支店への転勤などで日本の非居住者となる場合は、出国時点で年末調整を行います。非居住者となった後の所得は日本の所得税の対象外となるため、出国前までの所得について精算します。出国後も日本国内で給与が支払われる場合の取り扱いなど、国際税務の知識も必要となるケースです。
年末調整をしない退職者の対応(確定申告)
例外パターンに該当せず会社で年末調整を行わなかった退職者は、原則として自分で確定申告を行う必要があります。確定申告により、1年間の所得税額を正確に計算し、源泉徴収された税額との過不足を精算します。
再就職した場合は、転職先の会社で前職分も含めて年末調整を行うことができます。この場合、退職した会社から発行された源泉徴収票を転職先に提出する必要があります。転職先での年末調整で前職分を含めて精算できれば、退職者本人が確定申告をする必要はありません。
一方、年内に再就職しなかった場合や、転職先で前職分の年末調整を行わなかった場合は、翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行います。源泉徴収票は確定申告の際に必要となるため、退職時に必ず受け取り、大切に保管しておく必要があります。退職者への説明として、この点を丁寧に伝えることが会社側の配慮として重要です。
退職者の年末調整 実務の流れ・必要書類と注意点
退職者対応では、年末調整の要否判断から書類発行まで、正確かつ迅速な事務処理が求められます。退職時期によって対応が異なるため、時系列に沿った実務フローを理解しておく必要があります。
会社側の基本的な対応は、退職時の源泉徴収票発行、給与支払報告書の提出、そして例外ケースに該当する場合の年末調整実施です。特に源泉徴収票は法定の交付期限があり、遅延すると退職者の確定申告や転職先での年末調整に支障をきたします。
退職時期や給与の支給タイミングによって判断が分かれるケースもあるため、個別の状況を正確に把握し、適切な実務対応を行うことが重要です。
退職時に会社が必ず行う対応・書類発行
源泉徴収票の発行は法律で義務付けられており、退職後1か月以内に交付する必要があります。退職日が確定し、最終給与額が決まった時点で速やかに作成・交付しましょう。源泉徴収票には、その年の1月1日から退職日までの給与総額、源泉徴収税額、社会保険料控除額などを記載します。源泉徴収票は書面交付のほか、従業員の承諾があれば電子交付も可能です。国税庁タックスアンサーNo.7411(源泉徴収票の電子交付)で詳細が確認できます。
給与支払報告書は、退職者が1月1日時点で居住していた市区町村に提出する書類です。退職年の翌年1月31日までに提出することが義務付けられています。退職年の給与支払額が30万円以下の退職者は原則提出不要ですが、自治体運用で提出を求められることもあるため、所轄市区町村へ確認して運用を統一しましょう。
退職者への説明では、源泉徴収票の重要性を伝えることが大切です。転職先での年末調整や確定申告で必要となること、紛失した場合は再発行を依頼できることなどを丁寧に案内します。特に、転職予定がある場合は新しい勤務先に必ず提出するよう伝えておくと、後のトラブルを防げます。
例外ケースで年末調整を行う際の手続き・書類
例外パターンに該当し退職時に年末調整を行う場合は、通常の年末調整と同様の書類を回収する必要があります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」
の3つが基本となります。
死亡退職や著しい心身の障害による退職の場合は、それを証明する書類の確認も必要です。死亡退職では死亡診断書の写し、障害による退職では医師の診断書などで再就職見込みがないことを確認します。これらの書類は税務調査時の証拠資料となるため、適切に保管しておきます。
再就職の見込みがないことを要件とするケース(パート退職者など)では、本人からの申告に基づいて判断します。口頭確認だけでなく、書面で確認書を取得しておくと後日のトラブル防止に有効です。退職理由や今後の予定について、退職届や面談記録に残しておくことも実務上重要な対応となります。
退職時期・給与支給タイミング別の実務注意点
11月退職の場合は、原則として年末調整の対象外です。ただし、例外パターン(再就職見込みなしのパート等)に該当する場合は年末調整を実施します。判断に迷う場合は、本人に再就職予定を確認することが重要です。
12月退職の場合は、給与支給のタイミングが判断の分かれ目となります。12月分給与を12月中に支給して退職する場合は年末調整の対象ですが、12月分給与の支給日が翌年1月の場合は対象外となります。年末調整は支給日基準で判定するため、給与規程や実際の振込日を正確に確認する必要があります。
パート・アルバイトの退職者については、本年中の給与総額が123万円以下かつその年に他社から給与の支払見込みがないという2つの要件を両方満たすかどうかが重要な判断基準です。退職時点での給与総額を計算し、再就職の見込みを本人に確認した上で年末調整の要否を決定します。短期間勤務のパート従業員が多い職場では、この判断フローをマニュアル化しておくと実務がスムーズに進みます。
実務上、特に担当者が注意しておくべきポイントは?

小田根 大輔
税理士からのワンポイントアドバイス
1.「再就職の見込みがない」の判断は慎重に:
税法上の例外規定を適用する以上、その要件を満たす客観的な根拠が必要です。特に「見込みがない」という将来の不確実な事実については、担当者が安易に判断せず、本人からの書面での申告や客観資料(診断書など)の提示を義務付けるといいでしょう。
2.源泉徴収票の交付期限の厳守:
退職者への源泉徴収票は退職後1か月以内、または退職者が海外へ転勤する場合はその出国の日までに交付が義務付けられています。遅延は、退職者(の確定申告や転職先での手続き)に影響を与えるだけでなく、税法上の義務違反となるため、最終給与が確定次第、最優先で発行するよう実務フローを構築してください。
3.12月退職の支給日判定の徹底:
「12月中に給与の支払いを受けて退職した場合」が年末調整の対象となるかの判断は、実際に給与が支給された日(銀行振込日など)が12月中であるか否かで決まります。給与規程上の締め日や計算期間ではなく、支給日ベースで判断することを担当者に徹底させることが重要です。
退職者向けにおさえておきたい対策
退職者から年末調整に関してよく寄せられる実務的な質問と、その対応方法を整理します。
転職先の入社が翌年1月なので、退職時に年末調整をしてほしいと言われた場合
転職先の入社が翌年1月の場合、退職時点では年末調整の対象外となります。年末調整は12月31日時点で在籍している従業員を対象とする制度であり、年内に再就職しない退職者は、翌年に自分で確定申告を行うか、転職先で前職分を含めて年末調整を受ける必要があります。
会社側としては、源泉徴収票を退職後1か月以内に交付し、「転職先に源泉徴収票を提出すれば、1月入社でも前年分を含めて年末調整してもらえる可能性がある」「それができない場合は翌年2月16日から3月15日の間に確定申告が必要」という2つの選択肢を丁寧に説明することが重要です。
確定申告をすれば多くの場合は還付金が発生するため、退職者の不利益にはなりません。ただし、手続きの手間がかかることは事実なので、転職先の人事担当者に前年分の年末調整対応について事前に確認するよう助言すると親切です。
心身の不調で退職し、再就職しないため年末調整をしてほしいと言われた場合
心身の不調による退職で年末調整を希望される場合、「著しい心身の障害により退職し、その年中に再就職が見込めない」という要件に該当するかどうかを慎重に判断する必要があります。この特例が適用されるのは、就労が著しく困難な重度の状態に限られます。
具体的には、医師の診断書などで再就職が困難であることを客観的に確認できる場合に限り、退職時に年末調整を行うことができます。単なる体調不良や休養目的での退職では、この特例の対象とはなりません。
会社側としては、本人の状況を丁寧に聞き取り、診断書等の提出を依頼した上で判断します。特例の要件を満たさない場合は、翌年の確定申告で対応してもらうことになります。その際、「確定申告をすれば還付金が受け取れる可能性が高い」「国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxで比較的簡単に手続きができる」といった情報提供を行うと、退職者の不安を軽減できます。
年末調整の書類を提出し忘れて退職してしまった場合
年末調整の対象となる退職者(12月給与支給後の退職等)が、必要な申告書を提出せずに退職してしまった場合、会社側から連絡を取り、郵送やメールで書類を提出してもらう必要があります。扶養控除等申告書、保険料控除申告書などの必要書類を速やかに送付してもらいましょう。
期限までに書類が揃わない場合は、控除を適用せずに年末調整を行い、源泉徴収票を交付します。この場合、退職者本人が確定申告で各種控除を申告することで、正確な税額精算が可能です。
会社側としては、退職手続きの際に年末調整の要否を事前に確認し、対象者には必要書類と提出期限を明確に伝えておくことが、こうしたトラブルの予防につながります。退職者向けのチェックリストを作成し、漏れのない案内を心がけましょう。
転職先で前職の源泉徴収票提出を求められたが、まだ受け取っていない場合
転職先から前職の源泉徴収票提出を求められたにもかかわらず、まだ受け取っていない場合は、退職した会社に速やかに連絡して交付を依頼する必要があります。源泉徴収票は退職後1か月以内の交付が義務付けられているため、期限を過ぎている場合は早急な対応を求めましょう。
転職先の年末調整には原本の提出を求められるのが一般的です(会社方針により電子データ可のケースもあります)。紛失時は退職後1か月以内交付の原則と合わせ、早めに再発行を依頼しましょう。前職の会社に連絡がつかない、倒産しているなどの特殊なケースでは、所轄税務署に相談することで対応方法を教えてもらえます。
転職先の年末調整の締め切りに間に合わない場合は、自分で確定申告を行うことになります。その旨を転職先の人事担当者に早めに伝え、確定申告の準備を進めることが重要です。
退職者との間に起こりがちなトラブルとは?

小田根 大輔
税理士からのワンポイントアドバイス
退職者の年末調整に関するトラブルは、主に「誤解と不満」、および「書類の不備・遅延」から生じることが多いです。
最も多いのは、退職者による年末調整の必要性に関する誤解です。退職者は「毎月の源泉徴収が多かったから、退職時に会社が精算・還付すべき」と考えがちですが、原則は確定申告か転職先での年末調整となります。会社が原則どおり(年末調整をせずに)源泉徴収票を交付すると、「手続きを押し付けられた」と不満につながることもあります。
また、源泉徴収票の住所不備や送付遅延も頻発します。特に退職後の住所変更は連絡漏れが多く、書類が届かないことで、転職先の年末調整に間に合わないという緊急トラブルに発展しますので、退職後の住所変更については確認されてほうがいいでしょう。
例外的に退職時年末調整を行う際の「再就職の見込みなし」の判断を、書面確認なしで安易に行った場合、税務調査で否認されるリスクもあるので実務上注意すべき点です。
担当者は、源泉徴収票の確実な交付と、原則(確定申告)を丁寧に説明して退職者とのトラブルを未然に防ぐようにしてください。
まとめ
退職者の年末調整は原則として対象外ですが、
- 死亡退職
- 障害による退職
- 12月給与支給後の退職
- 年間給与123万円以下かつ他社給与見込みなし
- 非居住者
となる場合の5つのパターンでは例外的に会社側で年末調整を行います。特に12月退職は支給日基準で判定し、パート退職者は2つの要件を両方満たす必要があるなど、判断に注意が必要です。
会社側は退職後1か月以内に源泉徴収票を発行し、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。退職者への丁寧な説明も求められます。年末調整の対象外となった退職者は、転職先での年末調整または自身での確定申告により所得税を精算します。
退職者対応では、税務上のルールだけでなく、退職者の不安に寄り添った説明と適切な書類発行が信頼関係の維持につながります。年末調整や給与計算などの労務業務は専門知識が必要で、判断に迷うケースも少なくありません。税理士紹介センターでは、年末調整対応や労務業務にも精通した税理士を無料でご紹介しています。創業30年、30万件以上の相談実績に基づき、貴社の状況に最適な税理士をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q:退職者の源泉徴収票を紛失した場合はどうすればいいですか?
退職した会社に連絡して再発行を依頼できます。会社側には源泉徴収票の再発行義務があり、通常は無料で対応してもらえます。確定申告や転職先での年末調整に間に合うよう、余裕を持って依頼することが大切です。電話やメールで依頼し、数日から1週間程度で郵送してもらえます。前職の会社に連絡がつかない場合は、所轄税務署に相談しましょう。
Q:12月末に退職する場合、年末調整の対象になりますか?
12月分の給与を12月中に受け取って退職する場合は年末調整の対象となります。ただし、12月分給与の支給日が翌年1月の場合は対象外です。年末調整は支給日基準で判定されるため、給与規程や実際の振込予定日を確認することが重要です。対象となる場合は、控除申告書などの必要書類を会社に提出する必要があります。
Q:再就職が翌年になる場合、税金の手続きはどうなりますか?
年内に再就職しない場合は、翌年2月16日から3月15日までに自分で確定申告を行う必要があります。退職した会社から受け取った源泉徴収票を使用し、1年間の所得税を正確に計算します。多くの場合は還付金が発生するため、生命保険料控除や医療費控除なども忘れずに申告しましょう。翌年再就職した際は、新しい勤務先に前年の源泉徴収票を提出すれば、前年分を含めて年末調整してもらえる可能性があります。
Q:パートやアルバイトの退職者も年末調整が必要ですか?
パート・アルバイトでも、退職時までの本年中の給与総額が123万円以下で、かつその年に他社から給与の支払見込みがない場合は、会社で年末調整を行います。この2つの要件を両方満たす必要があります。それ以外の場合は原則として対象外となり、本人が確定申告を行うか、転職先で年末調整を受けることになります。年間給与が103万円以下の場合は所得税が発生しないため、確定申告により源泉徴収税額が全額還付される可能性があります。
Q:退職後の住民税はどのように納付しますか?
1月から5月に退職した場合は、退職月から5月分までの住民税が最終給与から一括徴収されます。6月から12月に退職した場合は、退職後は自宅に送られる納付書で自分で納付(普通徴収)する形に切り替わります。転職先が決まっている場合は、特別徴収の継続手続きにより引き続き給与天引きでの納付も可能です。納付書が届いたら期限を守って納付することが重要です。
Q:会社側が年末調整を忘れた場合、罰則やリスクはありますか?
年末調整漏れ自体は本人の確定申告で是正可能ですが、源泉徴収票の遅延交付や給与支払報告書の未提出は法令違反となり、行政指導や加算税等のリスクがあります。源泉徴収票の交付遅延は所得税法違反となる可能性もあります。社内フローを整え、交付・提出期限(退職後1か月・翌年1月31日)の厳守が重要です。適切な実務対応を行うため、退職者対応のマニュアル整備や専門家への相談をおすすめします。

- この記事の監修者
- おだね税理士事務所
代表 小田根 大輔(税理士)
事務所公式ホームページはこちら
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 経理/帳簿 >
- 退職者も年末調整の対象者になる?例外・実務対応まで徹底解説