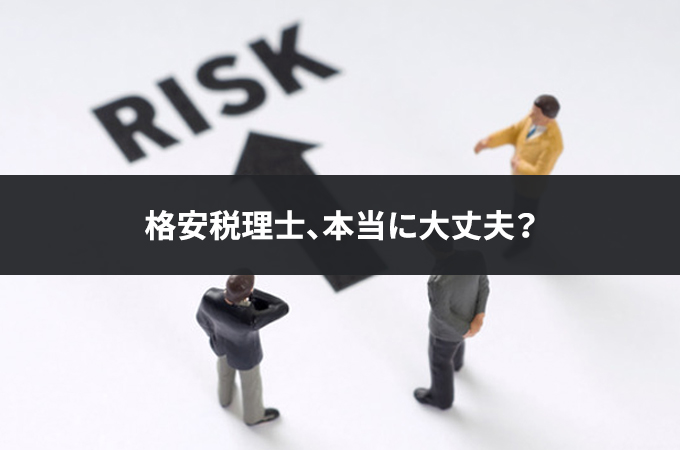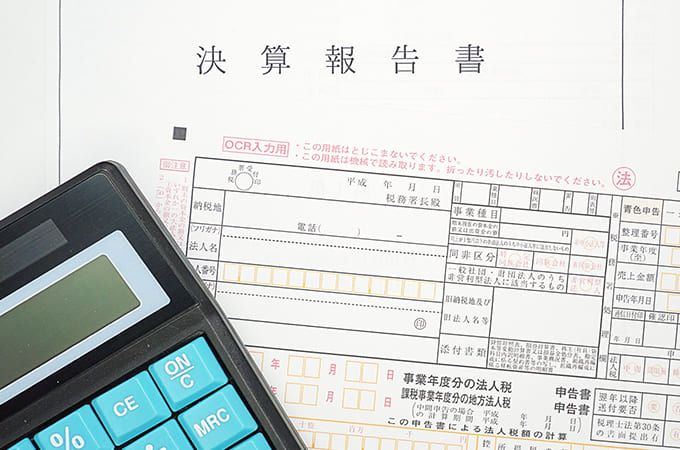不動産の売買や投資では、高額な税金が発生するため、専門知識を持つ税理士のサポートが不可欠です。しかし、すべての税理士が不動産税務に精通しているわけではありません。本記事では、不動産に強い税理士の選び方から依頼するメリット、費用相場まで詳しく解説します。正しい税理士選びで、税務リスクを回避し、効果的な節税を実現しましょう。
目 次
幅広い専門知識が要求される「不動産の税金」
不動産は、売買にせよ投資にせよ、「大きなお金」が動きます。当然、そこにかかってくる税金も、高額になりがち。しかも、不動産特有のものも含めて、さまざまな税が関係してくるのも、その特徴と言えるでしょう。
主なものを列挙してみます。
不動産を取得するとき
〈購入・新築の場合〉
- 所得税
- 住民税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 印紙税
- 固定資産税・都市計画税
- 消費税
〈贈与の場合〉
- 贈与税
- 登録免許税
- 不動産取得税
〈相続の場合〉
- 相続税
- 登録免許税
不動産を保有しているとき
- 固定資産税・都市計画税
- 所得税(賃貸時)
- 住民税(賃貸時)
不動産を譲渡(売却)したとき
- 所得税
- 住民税
- 印紙税
- 消費税
不動産投資をしたとき
〈アパートなどの不動産購入時〉
- 不動産取得税
- 印紙税
- 登録免許税
〈管理・運営時〉
- 固定資産税・都市計画税
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
〈売却時〉
- 所得税
- 住民税
- 印紙税
- 消費税
申告を正しく行わなかった場合にはペナルティがある
注意すべきことは、上記のうち、不動産を売却して「譲渡所得」があった場合には、サラリーマンでも自ら確定申告を行い、納税する必要があることです。「譲渡所得」というのは、譲渡価格(売却額)から、取得費(購入額)と仲介手数料などの譲渡費用を差し引いた金額です。そのため、例えば不動産の売却額が購入額よりも低ければ、所得はマイナスとなり、申告の必要はありません。
一方、譲渡所得が発生し、確定申告の必要があるのにしなかったら、どうなるのでしょうか? 所得税に限らず、そのような税金の「申告漏れ」が発覚した場合には、次のようなペナルティが課せられることになっています。
無申告加算税
申告しなくてはならない所得があるにもかかわらず、所定の申告期限を過ぎてもそれをしない状態を「無申告」と言います。その場合には、原則として本税(本来納めるべきであった税額)に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額が、本来の税額に加算されます。
重加算税
多額の譲渡所得を故意に隠そうとしたりしたような場合(悪質な隠蔽)には、さらに重い「重加算税」の対象になる可能性があります。税率は、ケースにより本税に対して35%ないし40%となっています。
延滞税
これらとは別に、確定申告(納付)の期限を過ぎて納税した場合には、超過日数分の「延滞税」、いわば利息を支払わなくてはなりません。税額は、本税に対して納税期限から2ヵ月は約7%、2ヵ月以降は約14%で計算されます。
売却の金額に比例してペナルティの税金も高くなる
最初に「不動産にかかる税金は高額になりがち」と言いましたが、それだけに、万一そうしたペナルティが課せられた場合の出費も、非常に大きなものになります。当然のことながら、「申告しなかった所得」が大きいほど、一定の税率を掛けて算出される加算税や延滞税の金額も上がっていきます。事業を行っている場合には、その継続に影響を与えるようなこともあり得ますから、「正しい申告」を心掛ける必要があるのです。
なお、不動産の売却を行なった際には、法務局で所有権移転登記を行いますが、その記録はすべて税務署に通知されています。不動産の売買は隠せません。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- サラリーマンの方も不動産の売却をする方は多いはずです。普段は会社の年末調整で済んでいて、譲渡所得の確定申告をうっかり忘れていた場合は早急に行いましょう。そのまま放置していても時間は解決してくれず、税務署にはすべて筒抜けです。
- 河鍋公認会計士・税理士事務所
代表 河鍋 優寛
課税だけでなく、減税措置も一緒に考える
「不動産と税金」という切り口からみると、考えるべきことは「課税」だけではありません。保有している建物を耐震や省エネを目的に改修したときには、さまざまな税の減額措置などが受けられます。
また、居住用の不動産を譲渡すると、その所得から3000万円を控除して(差し引いて)もらえるという特例があります。今挙げたのはほんの一例で、こうした税金の減免措置も、数多く用意されているのです。
加えて、これらにかかわる税法は、毎年のように変わります。幅広く、かつ最新の知識を備えているかどうかで、「不動産にかかる税の取られ方」には、大きな差が出ることになります。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 減税措置(特例)を適用できれば納税額を抑えることができますが、特例適用のためには様々な要件があります。本来は適用できないのに誤って申告をした場合は追徴課税がされますので、事前に詳細な検討や専門家に相談することが大切です。
- 河鍋公認会計士・税理士事務所
代表 河鍋 優寛
税理士の中でも「不動産に詳しい税理士」を選ぶのがおすすめ
そこで頼りになるのが、税金のプロである税理士。そのサポートを受けることで、素人の知識では困難な節税の可能性が広がります。特例などに気付かず、みすみす高額な税金を支払っていた、というような失敗も防げるはずです。
しかし、気を付けなければならないのは、税理士の資格を持っていても、みんなが「不動産の税」に詳しいわけではない、ということ。税理士にも、得意分野があります。一般的には、法人税や個人の所得税をメインとする事務所が多数で、固定資産税や相続税といった資産税関連に強い税理士は限られる、と理解してください。
一般的な税理士と何が違う?
不動産は「土地」や「建物」を指しますが、不動産に強い税理士とは土地や建物の売買取引に伴い生じる課税関係について、一般の税理士より経験と知識を持つ税理士をいいます。譲渡所得や相続税、贈与税など、不動産の売買は高額になることが多く、課税される税額も大きくなる傾向にあります。法人・個人を問わず不動産の賃貸借や売買、贈与などがある際、納税者にとって税制面で最も有利な選択を提示できる「不動産特化型」の税理士は心強いものです。
不動産に強い税理士を選ぶメリットと5つのポイント
「不動産に強い税理士」とは、どのような税理士なのか? 選ぶメリットとともに、重要なポイントを整理してみます。
不動産に強い税理士を選ぶ5つのポイント
☑ 不動産分野を専門領域として掲げているか – 他の分野と掛け持ちせず「不動産専門」を公言している税理士なら信頼度アップ
☑ 不動産関連業務の豊富な実績があるか – 過去にどのような不動産案件(売買・賃貸・相続など)をどれだけ扱ったか確認する。可能であれば自ら不動産投資の経験がある税理士だと実体験に基づくアドバイスも期待できる
☑ 最新の税制改正や不動産業界動向に詳しいか – 空き家対策や税法改正など最新情報へのアンテナは重要。常にアップデートしている税理士なら誤りのない最適な提案が受けられる
☑ 他士業(司法書士・弁護士・不動産鑑定士等)とのネットワークがあるか – 不動産取引は登記や法務、評価の専門家との連携が不可欠。協力体制がある税理士ならワンストップで問題解決できる
資産税(相続税・固定資産税等)に精通している
資産税関連というのは、税の世界ではやや特殊な領域だと言えます。そこをしっかり勉強して、専門知識を持っているというのは、不動産案件を依頼する際の「必要条件」になります。資産税分野は特殊で専門知識が必要なため、ここに詳しいことが不動産に強い税理士を見極める重要なポイントです。
不動産分野を専門領域として掲げている
「特殊領域」だけに、他の分野との"かけもち"は難しい面があります。「不動産専門」を掲げる税理士は、選択肢に加えていいでしょう。他の分野と掛け持ちせず「不動産専門」を公言している税理士なら信頼度がアップします。
不動産関連業務の豊富な実績がある
知識と同時に、実績も大事です。どのような案件をどれくらい担当してきたのかは、選択の際の基準の1つになるでしょう。過去にどのような不動産案件(売買・賃貸・相続など)をどれだけ扱ったか確認することが重要です。税理士の中には、自ら不動産投資を行っている人もいます。その生きた経験を生かしてもらうことには、大きなメリットがあるはずです。
最新の税制改正や不動産業界動向に詳しい
不動産も、「社会的存在」です。例えば、耐震、省エネ建築に対するニーズが高まったり、「空き家対策」が強く意識されたりします。そのような社会、経済情勢も反映して、関連する税制も頻繁に改定されているわけです。そうした情報に対して敏感であることも、不動産に強い税理士の大事な要件だと言えるでしょう。常にアップデートしている税理士なら誤りのない最適な提案が受けられます。
他士業(司法書士・弁護士・不動産鑑定士等)とのネットワークがある
不動産取引は登記や法律トラブルなど税務以外の課題も発生することが多々あります。司法書士や弁護士、不動産鑑定士ともネットワークを持ち連携できる税理士であれば、複雑な不動産案件でも各分野の専門家が協力することで、より確実で効率的な問題解決が可能になります。協力体制がある税理士ならワンストップで問題解決できるため、依頼者にとって大きなメリットとなります。
不動産に強い税理士に依頼するメリット
専門性の高い節税対策が受けられる
3000万円特別控除や不動産取得税の特例など節税スキームの提案力は重要です。物件の耐用年数を考慮した減価償却の工夫や、修繕費を必要経費にする判断など、専門家ならではの節税策を提示してもらえます。一般の税理士では見落としがちな特例や控除も、不動産に強い税理士なら確実に適用してくれるでしょう。
確定申告が格段に楽になる
さきほど説明した譲渡所得の確定申告を行うためには、取得費を証明する売買契約書など数多くの書類を揃えるのと同時に、経費として認められる売却時の不動産仲介料、印紙代、測量代などを細かく調べる必要があります(そうしないと、納税額が膨らみます)。加えて、建物に関しては、「減価償却費」の計算といった作業も必要になります。自分で申告を行うのは、かなりハードルが高いと考えてください。
苦労して申告を行っても、やり方を「間違える」と、税理士費用をはるかに超える「損」をする可能性があります。例えば、親が買った不動産の売買契約書が見当たらない、などということは珍しくありません。そのようなときには、取得費に「売却額×5%」の「概算取得費」を当てはめて計算することができるのですが、この方法だと譲渡所得は非常に高額になる公算大。そうした事態への対処法も、不動産取引に強い税理士は持っています。
ワンストップで総合的なサポートが受けられる
不動産取引は登記や法律トラブルなど税務以外の課題も発生します。不動産に強い税理士は司法書士や弁護士、不動産鑑定士ともネットワークを持ち連携できるため、ワンストップで安心です。複雑な不動産案件では、各分野の専門家が協力することで、より確実で効率的な問題解決が可能になります。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 資料がすべて揃っていても計算が非常に難解なのが譲渡所得です。
実際に当事務所も譲渡所得のご相談は増えています。計算には非常に複雑な知識と経験が要求されますので、よほど単純なケースを除いては報酬を支払っても専門家に任せた方がかえって総支出額を抑えることができるケースが多いです。 - 河鍋公認会計士・税理士事務所
代表 河鍋 優寛
税理士に依頼するデメリットと注意点
不動産に強い税理士に依頼することで多くのメリットがありますが、一方でデメリットや注意すべき点もあります。税理士選びを失敗しないために、以下の点を理解しておきましょう。
税理士に依頼する主なデメリット
費用がかかる
税理士に依頼する最大のデメリットは、当然ながらコストが発生することです。確定申告だけでも数十万円、継続的な顧問契約では月額数万円の費用がかかります。自分で申告を行えば、これらの費用は発生しません。
専門外の税理士を選んだ場合のリスク
万が一「専門外」の税理士だった場合、コストがかかったうえに、期待していた節税効果も得られないという最悪の結果になる可能性があります。費用を支払ったにも関わらず、自分で申告した場合と変わらない、または税理士費用の分だけ損をするケースもあり得ます。
税理士選びで注意すべきポイント
「安さ」のアピールには要注意
誰しも、税理士に支払う報酬をできるだけ抑えたいと考えます。しかし、低価格で差別化しようという姿勢の税理士には(不動産に限らずですが)注意が必要です。「安かろう悪かろう」で肝心の節税策がおざなりなものだったら、元も子もありません。
実績と専門性を必ず確認する
税理士の資格を持っていても、すべての税理士が不動産税務に精通しているわけではありません。不動産関連の税務申告の実績や、自分の案件に合った経験があるかを事前に確認することが重要です。税理士は慎重に選ぶことをおすすめします。
不動産の税務を税理士に依頼した際にかかる費用の目安
不動産の税務を税理士に依頼する際の費用は、依頼内容によって大きく異なります。以下に主要なケース別の料金相場をまとめました。
■料金相場一覧表
| 業務内容 | 料金目安(相場) |
|---|---|
| 税務相談(スポット) | 数千円~数万円程度 ※初回無料の税理士も多い |
| 確定申告代行(単発) | 約10万円~数十万円程度 |
| 継続顧問契約 | 月額1~5万円程度 (内容・規模により変動) |
| 相続税申告(参考) | 財産評価額の0.5~1.5%が目安 |
税務相談を依頼するケース
相続税や贈与税など、将来起こり得る資産課税について税務相談を依頼するケースです。相続や贈与について、適用が可能な税法上の特例についてのアドバイスを生前に受けることで、将来発生する納税についてのシミュレーションができます。
費用目安:数千円~数万円程度(初回無料の税理士も多い)
資産税の税務申告にかかる費用は、対象資産の評価額に応じて高くなるのが一般的ですが(評価額の0.5%~1.5%)、税務相談のみであれば相談料程度の比較的安い料金で依頼できるケースもあります。
確定申告のみ依頼するケース
不動産にかかる確定申告のみを税理士に依頼するケースです。土地や建物の譲渡(所得税)や贈与(贈与税)、相続(相続税)などの確定申告をスポットで税理士に頼むケースがこれに当たります。
費用目安:約10万円~数十万円程度
いずれのケースも対象となる不動産の「評価」を行い、譲渡や贈与、相続で不動産を手に入れた側がどれくらい儲けたかを計算する必要がありますので、単純な申告手続きだけの費用とはなりません。費用の目安としては対象資産の評価額の「0.5%~1.5%」が一般的ですが、評価の難易度、申告期限までの時間などに応じて費用が変わってきます。
契約を結ぶケース
土地建物の売買や不動産賃貸を行っている法人や個人事業主の方が、税理士と顧問契約を結んで継続的なコンサルティングを受けるケースです。
費用目安:月額1~5万円程度(内容・規模により変動)
一般的な会計監査業務にとどまらず、中長期的な視点から不動産の売買や賃貸借に関するアドバイスを受けられるメリットがあります。顧問契約の場合、費用は月額(あるいは年額)で発生しますが、日常的に行う軽微な相談であれば月額報酬の範囲内でやってくれる税理士が多いでしょう。月額報酬の目安は月次監査や決算監査の難易度やボリュームにもよりますが、一般的な法人や個人事業主で発生する金額と大きな違いはないようです。
どうやって選ぶ?
最後に、具体的にどのようにして探したらいいのか、代表的な方法を各々のメリットとデメリットとともにまとめておきましょう。
ホームページを検索する
メリット:手軽に情報にアクセスでき、事務所の強み、料金などもわかる
デメリット:実際に会ってみたら様子が違う、ということがありうる
知人の紹介を受ける
メリット:実績や仕事の中身などが具体的にわかり、安心できる
デメリット:問題があったときに、断りにくい
税理士紹介会社を使う
メリット:登録している多くの税理士の中から、客観的な目で適する人を選んでもらえる
デメリット:不十分な紹介の仕方をするところもある
まとめ
不動産に関する税金は複雑で金額も大きくなりがちです。取得から保有、譲渡まで様々な税が関係し、申告を誤れば重いペナルティが課される可能性もあります。一方で、適切な節税対策を行えば大幅な税負担軽減も期待できます。
その解決には不動産に強い税理士の力が不可欠です。本記事で挙げた5つのポイント(資産税への精通、専門領域としての不動産、豊富な実績、最新情報への対応、他士業との連携)を参考に信頼できる税理士を選び、安心して不動産取引に臨みましょう。
費用はかかりますが、専門家のサポートを受けることで、税務リスクの回避と効果的な節税の両方を実現できます。特に高額な不動産取引では、税理士費用を上回る節税効果が期待できるケースも多くあります。
不動産業に詳しい税理士をお探しの方へ
不動産に関わる税金は、多種多様。専門知識や経験のある税理士のサポートを受けることが重要です。ホームページ検索や、実績のある税理士紹介会社の活用で、間違いのない税理士選びをしましょう。
よくある質問
不動産に強い税理士を選ぶメリットは何ですか?
不動産に詳しい税理士を選ぶことで、正確な申告や節税対策が可能となり、税務リスクを軽減できます。また、最新の税制改正にも対応してもらえるため、安心して依頼できます。
不動産に強い税理士の探し方は?
知人からの紹介、インターネット検索、税理士紹介会社の利用が一般的です。特に、実績のある税理士紹介会社を活用すると良いでしょう。
不動産に強い税理士に依頼する際の注意点は?
税理士の専門分野や実績を確認し、具体的な相談内容に対応できるかを事前に確認することが重要です。安さだけで選ばず、実績や信頼性を重視しましょう。
不動産の税務相談はどのくらいの費用がかかりますか?
初回の税務相談は無料の場合が多いですが、確定申告や継続的な顧問契約には別途費用がかかります。確定申告のみで10万円程度から数十万円程度、継続的な顧問契約では月額1~数万円が相場です。
不動産の税務申告を自分で行う場合のリスクは?
税務知識が不十分だと申告ミスや節税漏れが発生し、結果的に余計な税金を支払うことになるリスクがあります。専門知識を持つ税理士に依頼することで、これらのリスクを軽減できます。
記事監修者 河鍋税理士からのワンポイントアドバイス
今回は不動産に強い税理士について解説をしました。
不動産に関する税金、いわゆる「資産税」を専門としている税理士は数が限られており、特に地方に行くほどその傾向は顕著です。
その理由は、「税理士としても業務を請け負うリスクが高い」ことにあります。当記事でも解説したとおり、不動産売買は高額な取引でそれ故に税金も多額になりやすいです。それに加えて特例適用の要件が複雑であるため正確な判断が求められます。
本来の難易度が高い上に、もし誤った申告をして依頼者に損害を与えてしまった場合は損害賠償リスクも抱えています。そのため、参入障壁が非常に高い税の分野です。
私もこの「資産税」を専門としておりますが、それも大きな税理士法人で資産税専門の部署で業務を専任した経験があるからこそであり、自分で1から始めようとは思わなかったでしょう。
このように、税のプロである税理士の中でも難易度が高いとされている領域ですので、高額な売買をする不動産取引の際には、不動産に強い税理士を見つけてご相談されることをお勧めします。