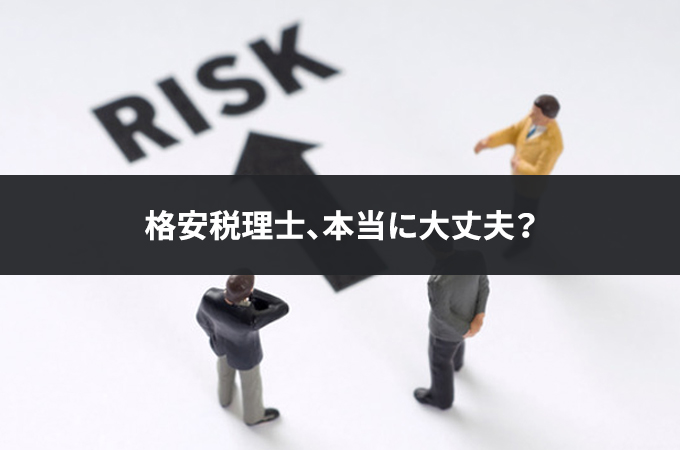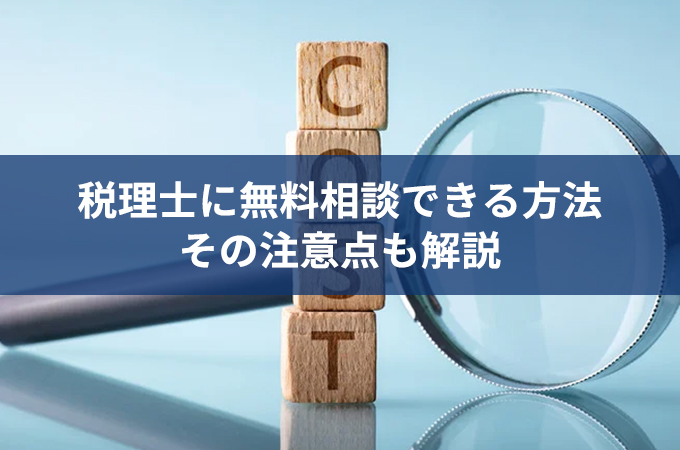『税理士費用を安く抑えたいけれど、安い税理士に任せて大丈夫?』と不安に思っていませんか?
本記事では、税理士報酬の相場や格安税理士のメリット・デメリットを詳しく解説します。安い税理士だからといってサービスの質が必ずしも低いわけではありませんが、安いなりの理由があります。どのような事業者に格安税理士が向いているかや、失敗しない税理士の選び方も併せて紹介します。
目 次
格安税理士とは?
格安の定義はいくらから?
以前は、税理士費用は税理士報酬規定で一律に決まっていたのですが、今は撤廃されそれぞれの事務所が自由に設定できるようになりました。そんな現在、そもそも「格安税理士」とは、いくらぐらいの報酬で頼める税理士のことをいうのでしょうか?
例えば、売上高1,000万円未満の法人・個人事業主が、税理士と顧問契約をして3~4ヵ月に1回訪問してもらうとします。その場合、決算申告料(確定申告料)を除く月額報酬の相場は、一般的に1万円が「底値」となっています。それを下回る月額数千円の価格設定をしている場合、相場より安い=格安ということができるでしょう。
以下に税理士に支払う料金の相場の目安を示しています。これを下回る価格を提示しているのが、この記事で述べる格安税理士だと考えてください。
税理士に依頼する場合の料金の相場は?
ここに載せたのは、税理士と顧問契約を結んだ場合の料金相場です。当然、法人と個人事業主では、税理士顧問料の相場は異なります。また、売上高や訪問回数(税理士事務所の税理士やスタッフが顧問先を訪問する回数)などによっても金額は違ってくるため、その点は注意が必要です。
■法人の場合の金額相場
| 年商・年間売上高 | 税理士の訪問回数 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 年商1,000万円未満 | 決算のみ | 100,000円~/年 |
| 年商1,000万円以上3,000万円未満 | 決算のみ | 150,000円~/年 |
| 年商3,000万円以上5,000万円未満 | 3-4ヶ月に1回 | 15,000円~/月 + 決算申告料 |
| 年商5,000万円以上1億円未満 | 3-4ヶ月に1回 | 20,000円~/月 + 決算申告料 |
| 年商1億円以上3億円未満 | 要相談 | 30,000~50,000円/月 + 決算申告料 |
| 年商3億円以上5億円未満 | 要相談 | 35,000円~/月 + 決算申告料 |
| 年商5億円以上10億円未満 | 要相談 | 45,000円~/月 + 決算申告料 |
| 年商10億円以上 | 要相談 | 50,000円~/月 + 決算申告料 |
■個人の場合の金額相場
| 年商・年間売上高 | 税理士の訪問回数 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 年商500万円未満 | 確定申告のみ | 70,000~80,000円/年 |
| 年商500万円以上1,000万円未満 | 確定申告のみ | 100,000円~/年 |
| 年商1,000万円以上3,000万円未満 | 確定申告のみ | 150,000円~/年 |
| 年商3,000万円以上5,000万円未満 | 3-4ヶ月に1回 | 15,000円~/月 + 確定申告料 |
| 年商5,000万円以上1億円未満 | 3-4ヶ月に1回 | 20,000円~/月 + 確定申告料 |
| 年商1億円以上 | 要相談 | 30,000円~/月 + 確定申告料 |
※詳細な金額は税理士顧問料・報酬・料金・価格の適正価格 で確認できます。
なぜ格安で依頼できるのか?
どんなモノやサービスでも、相場よりも安い場合には必ず理由があります。安い税理士でもサービス品質が低いとは必ずしもいえず違う理由も存在します。
格安税理士については、次のようなことが考えられるでしょう。
- 税理士やスタッフのスキル・対応レベルが低い
- 採算を考えずに集客優先で料金設定している
- 人件費を過度に削減している
- 訪問などの直接面談の頻度を減らしている
- 提供サービスや税理士の業務範囲を限定している
- 創業時の特別割引を適用している
- IT化によるコストダウンを実現している
"安かろう、悪かろう"の税理士事務所
税理士やスタッフのレベルが低い(例えば勉強不足で税務の知識が不十分など)、対応が悪い、といった理由で顧客に敬遠されるため、低料金でないと仕事がもらえない…というパターンです。
"ドンブリ勘定"の税理士事務所
税理士事務所でありながら、集客第一で採算を十分考えずに料金設定がされているケースもあります。当然、レベルの高いサービスを提供していたのでは儲けになりませんから、安さが魅力で契約した顧客が結局しわ寄せを食うことになります。
仕事の割に従業員の数が少ない、給料が安い
普通の事業でもいえることですが、人件費の無駄を抑えることは経営の基本です。とはいえ、仕事量が過大だったり、給料が標準レベルに届かなかったりすれば、従業員のモチベーションは上がらず、離職にもつながります。そういう事務所に依頼しても、やはり満足のいくサービスが受けられない可能性があります。
訪問など直接面談の頻度を減らしている
税理士にとって訪問は移動時間を含めて大きなコストとなります。格安税理士の多くは、訪問回数を減らしたり、オンライン面談に切り替えることで人件費や時間コストを削減しています。訪問頻度が少ない分、料金を安く設定できる仕組みです。
サービスが限定されている
同じ顧問契約でも、提供されるサービスは事務所によって違いがあり、例えば「決算に関わる業務のみ」のように限定されていることがあります。また、税理士の業務範囲を記帳代行や申告書作成など特定の業務に絞ることで、効率化とコスト削減を図っているケースもあります。このような場合には、他の業務も依頼しようとすると、別途オプション料金を請求されることになります。必要なサービスだけを選ぶことができるという利点がある半面、あれこれ頼んだらむしろ割高になってしまった…ということも十分にあり得るため、契約時にしっかり確認する必要があるでしょう。
創業時の「特別割引」
後でも述べますが、創業支援を行う事務所では、創業時(初年度)の料金を安く設定している場合があります。通常料金や、それで受けられるサービス内容については、やはり契約時に確認しておきましょう。
IT化によるコストダウン
もちろん様々な経営努力により、税理士報酬を大幅に引き下げている事務所もあります。特に近年は、ITを活用した申告業務の簡略化などを積極的に進め、コストダウンを図る傾向が強まりました。ただ、目に見えるコストダウンのためには、顧客の側もそうしたIT化に対応する必要があります。

髙谷 武司
監修税理士からのワンポイントアドバイス
実は、税理士が格安で業務を受けるのは、お客様の環境が変化してきたという側面もあります。例えば、会計ソフトの自動化です。金融機関等とのAPI連携をはじめ、請求書など紙資料についてもAI-OCRでデータ化が可能になり、仕訳が自動で生成されるようになってきました。また、簡単な疑問なら、ブログや動画、最近ではAIで解決できることも多くなってきています。そのため、事業がシンプルだったり、取引数が少ないお客様は、受けるサービスを限定する代わりに、報酬を安くしてほしいというニーズが高まってきています。
このようなニーズを受けて、ITツールを利用し、サービスを限定することで、格安で業務を受けるというのが、最近の傾向と言えるでしょう。
法人ではなく個人の税理士は料金が安い?
税理士法人と個人の税理士で料金に違いはどれくらいあるのでしょうか。
先ほどの料金表をご覧いただくとわかりますが、結論から言えば、税理士法人か個人税理士かといった事業形態による料金の違いはありません。
税理士報酬はクライアントとの契約形態(スポット契約か顧問契約か)と、クライアントの事業規模(年間売上高など)によって決めるのが一般的です。税理士としては、一時的なスポット契約より継続して取引ができる顧問契約の方が報酬を低く設定しやすいでしょう。また、事業規模が大きければ税理士が負うべき責任も大きくなりますので、報酬も比例して大きくなる傾向にあります。
格安税理士を選択するメリット・デメリット
格安税理士のメリット
格安税理士を選ぶことで得られる主なメリットは以下の通りです。コスト削減だけでなく、自社の状況に応じたサービス選択や税務知識の向上も期待できます。
- 税理士報酬を大幅に削減できる
- 必要なサービスだけを選択して無駄を省ける
- クラウド会計ソフトとの連携で税務知識が身につく
メリット① : 税理士報酬が安い
格安税理士のメリットの代表格は税理士報酬の絶対額が安いことでしょう。たとえば、年商2,000万円の法人の場合、税理士報酬の相場である月額1万5,000円から2万円より、はるかに低い料金で税理士に依頼することができます。また、税理士報酬が相場より低いのは、創業支援サービスの一環の可能性があります(料金の内訳は事務所により異なりますので、契約前に確認しておくのがおすすめです)。
メリット② : 必要最低限のサービスだけを選択できる
格安税理士の中には、顧問契約を結ぶことを前提としないケースがあります。そのため、さまざまなサービスメニューの中から決算書の作成のみ依頼できるなど、必要最小限のサービスだけを選択することができます。「顧問契約」の場合は、税理士と"月額○○円+決算申告料金"をベースに契約を結びます。基本的に、法人であれば月次決算を出してもらい、年に数回は会社に来てもらって経理や税務、あるいは経営などについて相談し、アドバイスを受けることができます。期末には、年度の決算と、それに基づく法人税の申告を依頼します。先述のように、通常この決算申告は別料金となっており、売上2,000万円の会社が2ヵ月に1度訪問を受ける場合には、顧問料が月2万円~、決算申告料金がその4~6ヵ月分です。一方、「決算申告のみ依頼」する場合は、同規模の会社で料金は年額15万円~というのが相場です。具体的には、「記帳(税務申告に必要な帳簿の作成)」「決算書作成」「申告書作成」「申告」などを税理士に代行してもらうことができ、このうち必要な業務だけチョイスすることも可能なのです。
メリット③ : クラウド会計ソフトとの連携で税務知識が身につく
格安税理士を利用する際、クラウド会計ソフトを活用して日常的な記帳を自社で行い、重要な申告業務のみを税理士に依頼するケースが多くあります。この方法により、経理処理の流れや税務の基本的な考え方を実践的に学ぶことができ、将来的に自社の税務レベル向上につながります。また、会計ソフトの自動化機能を使いこなすことで、効率的な経理体制を構築できるメリットもあります。
格安税理士のデメリット
格安税理士にはコスト面でのメリットがある一方で、サービス内容や対応面でのデメリットも存在します。契約前にリスクを把握しておくことが重要です。
- 訪問サービスが制限される可能性が高い
- 積極的な節税アドバイスが受けにくい
- 自社に一定の経理知識が必要になる
- オプション料金で結果的に割高になるリスクがある
- 経営相談の機会が限定される
- 無資格者である可能性がゼロではない
デメリット① : 訪問サービスが受けられない可能性が高い
税理士にとってのコストは業務に投入する時間であり、訪問する移動時間もコストにカウントされます。そのため、格安税理士は訪問サービスの回数を減らすことで、業務に投入する時間を減らしコスト削減を図ります。その結果、格安税理士に依頼すると訪問サービスが受けられない可能性が高くなります。
デメリット② : 積極的な節税のアドバイスが受けられない
訪問サービスを受けることによって積極的な節税のアドバイスが受けられる機会がより多くなります。そのため、訪問サービスが受けられないと節税のアドバイスも受けづらくなります。
デメリット③ : 経理の知識が求められる
格安税理士は業務に投入する時間を短縮するために、会計ソフトにデータを入力する時間を削減する傾向にあります。そのため、自計化(自社で会計ソフトにデータを入力すること)が前提になるケースがあり、自社のスタッフに経理の知識が求められます。
デメリット④ : 付随するサービスがオプション料金として加算される
格安税理士の中には、サービスメニューごとに細かく料金設定をしている所が存在します。そのため、記帳代行や経営分析などのサービスがオプション料金で加算され、結果的に割高になる可能性があります。
デメリット⑤ : 経営相談がしづらい
格安税理士は訪問サービスに投入する時間はできるだけ削減したいと考えている可能性があります。そのため、最低額の訪問サービスを実施するとしても、所長税理士や経験豊富なスタッフではなく、年収の低い比較的経験が浅いスタッフが訪問する傾向にあります。そのため、経営相談をしたい相手に相談しづらいといえます。
デメリット⑥ : あまりに安すぎると無資格者(にせ税理士)である可能性も?
格安税理士に依頼する最大のリスクは、実は「頼んだ相手が税理士の資格を持っていなかった」という状況です。まさかと思うかもしれませんが、"にせ税理士"が脱税を指南して逮捕される、といった事件が実際に起こっているのです。
税理士には、
税務代理(税務申告や、税務署などの税務調査への対応)
税務書類の作成(申告書類の作成)
税務相談(税金に関する相談への対応)
という「独占業務」があります。これらの業務は、税理士、税理士法人以外は許されておらず、納税者に代わって申告を行ったりすれば、税理士法違反に問われます。一方で、依頼したほうも、申告書のミスで「申告漏れ」になる・全く節税ができない・税理士の署名のない信頼度の低い申告書になってしまう…といった被害をこうむる可能性が高くなります。
税理士は、日本税理士会連合会の発行する「税理士証票」(税理士にとっての身分証明書)と「税理士バッジ」を保有していますので、バッジを付けていない場合などには念のため確認するようにしましょう。
格安税理士がおすすめの法人・個人事業主とは?
前述の通り、格安税理士のメリット・デメリットを挙げましたが、それでも税理士報酬を削減したいと考えている法人・個人事業主は多いでしょう。そこで、格安税理士がおすすめのケースについて紹介します。
創業間もない法人・個人事業主
創業間もない法人・個人事業主は売上が少ないのが一般的であり、事業が軌道に乗るまでは料金重視で税理士を選ぶことが現実的といえます。また、「売り上げが伸びたら税理士報酬をきちんと支払う」など低料金が軌道に乗るまでの間の期間限定なら、多くの税理士は料金重視を理解してくれるでしょう。
取引量が極端に少ない法人・個人事業主
取引量が極端に少ない法人・個人事業主なら格安税理士がおすすめです。取引量が少なければ、会計処理も簡単であり、税理士の品質によって納める税金に差が出ることは少ないでしょう。
知識の豊富な経理スタッフがいる法人・個人事業主
知識の豊富な経理スタッフがいる法人・個人事業主なら、決算のみを依頼するなどの工夫で、月額料金を節約でき、税理士報酬の削減につながります。知識の豊富な経理スタッフとは、たとえば「税理士事務所でクライアントの申告書まで作成した経験がある」など、税金の知識が豊富な人のことを指します。
格安税理士がおすすめできない法人・個人事業主
では、逆に、格安税理士との契約がおすすめできない法人・個人事業主について説明します。
税務調査で損をしたくない法人・個人事業主
税務調査対策は訪問サービスを受けることで可能となる傾向にあります。そのため、訪問サービスを受けられなければ、事前対策のアドバイスも受けられず、税務調査で損しやすくなります。たとえば、不良在庫にかかる仕入金額を経費に計上することを検討するとします。税務調査では本当に破棄したどうかが争点になりますが、事前対策により「きちんと廃棄処分をすべき」というアドバイスが受けられます。
積極的な節税のアドバイスを受けたい法人・個人事業主
格安税理士以外の税理士なら訪問サービスを実施する所は多いでしょう。そのため、積極的な節税のアドバイスを受けやすくなります。たとえば、法人の利益が予測より多額になる可能性が高くなった場合、決算賞与などの節税対策のアドバイスが受けられます。
事業拡大を見据える法人・個人事業主
事業拡大を見据える法人・個人事業主は格安税理士以外の税理士がおすすめです。取引量が多くなり、税務が複雑になる可能性が高くなります。そのため、格安税理士以外の税理士のほうが親身に対応してくれます。格安税理士は業務に投入する時間を短縮する傾向にあるのに対し、格安税理士以外の税理士は品質重視の傾向にあるためです。
経理スタッフの人件費を削減したい法人・個人事業主
知識の豊富な経理スタッフを雇用するのにはある程度の人件費(給料など)が必要になります。しかし、経理スタッフに支払う人件費を削減したい場合は、サービスが充実している格安税理士以外の税理士に依頼すべきでしょう。それでも、一般的には経理スタッフに支払う人件費よりも税理士報酬のほうが低くなる傾向にあります。
安い税理士を選ぶ際のポイントと注意点
安い税理士を使うにしても、トラブルが少なく必要最低限のサービス提供を受けられる税理士を選びたいものです。次に、安い税理士を選ぶ際のポイントについて解説します。
口コミや評判を調べてトラブルがないか確認する方法
安い税理士と契約する前にネットにあがっている口コミや評判を調べて、その税理士に問題がないか、先に確認しておく方法があります。「安かろう悪かろう」の税理士である場合、実際にその税理士を使ったことのあるクライアントの評判は、契約を結ぶか判断する際の貴重な情報源となります。ただし、口コミや評判に具体的な指摘がなく、単に悪口が書かれているだけの投稿も少なからずあります。情報自体にある程度の信憑性があることを確認しながら読むようにしましょう。
費用が安くても税務調査対応が可能か?リスク管理の重要性
税理士が行う「税務代理」には、税務調査の立ち合いや税務署との折衝なども含まれます。税務調査の際には税務署とクライアントの間に入り、質問への答弁や税務署が要求する資料の提示などを行います。スムーズに調査が進むようサポートしつつ、納税者の主張を税務署サイドに正しく説明してくれますので、納税者も安心して調査を受けられます。
しかし、費用が安い税理士の場合、税務調査対応をしてもらえないケースや、対応が不十分なケースが見受けられます。調査で不利益を被るリスクを回避するためにも、税務調査に対応してもらえるか事前に確認しておきましょう。
報酬が安くとも契約前に面談はしましょう
税理士を選ぶ際のポイントの1つに、税理士の人柄があります。クライアントのために熱意を持って誠実に仕事に取り組む税理士かどうか、その人柄を判断するためには直接会って話してみるのが一番です。会社の業績や経営方針などを親身になって聞いてくれるか?何でも相談できる雰囲気か?など、面談を通して判断することをお勧めします。いくら報酬が安いとはいえ、面談もなしに契約するのは避けた方がよいでしょう。
金額だけで決めるのは要注意

髙谷 武司
監修税理士からのワンポイントアドバイス
格安税理士は、格安スマホや格安航空会社と同様、サービスを限定したり、オペレーションコストを削減することで、低価格を実現しています。そのため、サービスの範囲および品質に注意する必要があります。
まず、サービスの範囲ですが、決算書類の作成や確定申告の代行など、最低限の業務に絞っている傾向があります。そのため、受けたいサービスの有無や追加した場合の料金を確認しておくことが重要です。
また、実際の担当者が経験の浅い(=人件費の安い)スタッフである場合があります。この場合、税理士が担当するよりも、サービスの質が低下することが多いでしょう。したがって、一定程度の会計・税務に関する知識がない場合は、慎重に検討することをお勧めします。
創業支援サービスにより格安税理士を上手に活用する
前述の通り、創業支援サービスの一環として税理士報酬を安く設定している税理士は多い傾向にあります。また、創業間もない法人・個人事業主にとっても、税理士報酬は削減したいでしょう。そこで、創業支援サービスにより格安税理士を上手に活用するポイントについて紹介します。
創業支援サービスは税理士にもメリットあり
税理士業も営利目的です。そのため、税理士報酬は利益の最大化を図る視点から料金設定をしています。具体的には、創業支援サービスによる低価格の料金設定は法人・個人事業主が創業後に事業が軌道に乗り、税理士報酬の支払い能力が増すまでの間の投資と考えています。
経営相談にも積極的に乗ってくれる可能性がある
格安税理士でも創業支援サービスの場合、経営相談に積極的に乗ってくれる可能性があります。前述の通り、低価格の料金設定は税理士報酬の支払い能力が増すまでの投資であるため、法人・個人事業主にはできるだけ早く軌道に乗ってほしいと考えているためです。そのため、節税対策はもちろん、労務関係などについても積極的に相談することをおすすめします。たとえ税理士自身がアドバイスできなくても、社会保険労務士など他の専門家を紹介するなどコーディネートしてくれる可能性があります。
安い税理士を探す方法
格安税理士を見つけるには複数の方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合った探し方を選ぶことが重要です。
知人からの紹介
経営者仲間や同業者からの紹介は、実際の利用経験に基づいた情報が得られる方法です。紹介者から税理士の人柄やサービス内容を事前に聞けるため安心感があります。ただし、紹介者の主観も入るため、自分の事業規模や求めるサービスに合うかは客観的に判断する必要があります。
インターネット検索
「地域名+格安税理士」「月額○円以下+税理士」など、具体的な条件を入れて検索すると効率的に候補を見つけられます。各事務所のホームページで料金体系やサービス内容を比較検討できるメリットがあります。一方で、情報が多すぎて選択に迷ったり、実際のサービス品質は面談してみないと分からないデメリットもあります。
税理士紹介サービスの活用
税理士紹介サービスを利用すると、自分で探す手間なく条件に合う税理士を無料で紹介してもらえる利点があります。専門のコーディネーターが要望をヒアリングして最適な税理士をマッチングするため、効率的に理想の税理士と出会えます。また、紹介後のフォローもあるため安心です。
税理士無料相談や初回お試しを活用して比較検討する
安い税理士を選ぶ際には、実際に面会しながら料金やサービス等の相談をするのが一番です。そのためには、税理士の無料相談や初回お試しなどを積極的に活用しながら比較検討してはいかがでしょうか。
税理士無料相談の活用
税理士会が開催する無料相談会を通じて顧問料を比較検討する方法です。会計や税務に関する相談をしながら、その税理士と顧問契約を結ぶ際の費用相場を確認してみるのもよいでしょう。税理士と直接面談して人柄を確認しつつ、費用を比較できるというメリットがあります。
初回お試しを活用してみる
税理士事務所によっては、初回の相談料を無料にしているところがあります。無料相談会と同様に、税理士本人に直接面談して話せるので、熱意のある誠実な人柄かを確認することができます。また、直接事務所を訪問することで、事務所の規模や所内の雰囲気なども併せて確認できるメリットがあります。
料金重視で税理士をお探しの方へ
税理士に依頼するとき、料金重視にすべきかどうかは法人・個人事業主の状況によって決まってきます。創業間もない場合は創業支援サービスにより格安税理士を上手に活用することができます。一方、充実したサービスの提供を受けたい場合は、ある程度の税理士報酬を負担する必要があります。どちらの選択にしろ、自分の現状や将来像に見合った税理士を選ぶことが重要です。
- 料金重視で税理士を探したい
- 金額はそのままで、よりサービスの良い税理士に変更したい
- 顧問料の相場を知りたい
など、料金に関するご相談を多数いただいています。
まずはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
よくある質問
格安税理士を選ぶ際のポイントは何ですか?
格安税理士を選ぶ際には、サービスの内容や提供される範囲を確認することが重要です。また、訪問回数や対応の質、税理士の資格を持っているかどうかもチェックしてください。特に、料金が安すぎる場合は注意が必要です。
格安税理士に依頼するメリットは何ですか?
メリットとしては、税理士報酬が低いため、コスト削減が可能です。また、必要最低限のサービスだけを選択できるため、無駄な支出を抑えられる点も利点です。
格安税理士に依頼するデメリットは何ですか?
デメリットとしては、訪問サービスが受けられない可能性が高いことや、積極的な節税アドバイスが受けにくいことが挙げられます。また、自社での経理作業が増える可能性があるため、経理知識が求められます。
どのような法人・個人事業主に格安税理士が適していますか?
創業間もない法人や、取引量が少ない法人、知識の豊富な経理スタッフがいる法人には格安税理士が適しています。これらのケースでは、低料金で十分なサービスを受けることができます。
格安税理士のリスクを回避する方法はありますか?
税理士の資格を確認し、契約前にサービス内容を詳細に確認することがリスク回避のポイントです。また、実績や評判を調べることも大切です。信頼できる税理士を選ぶことで、トラブルを未然に防ぐことができます。