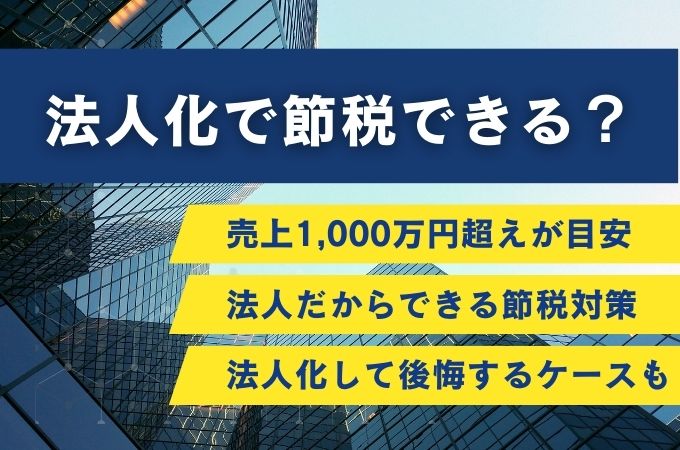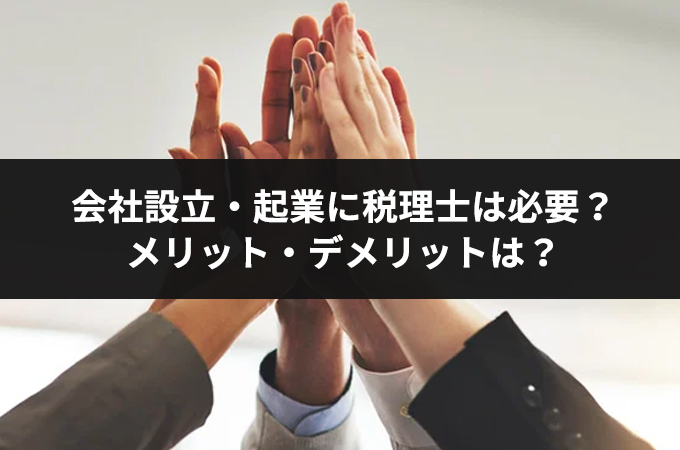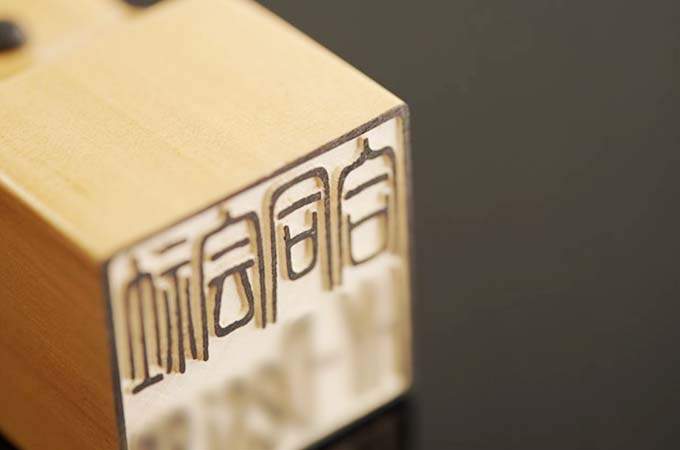個人事業主として活動を続けるうちに、「そろそろ法人化したほうが節税になるのでは?」と迷うタイミングは必ず訪れます。結論からいうと、年間売上が1,000万円を超えたあたりが法人化の大きなメリットを享受できる一つの目安です。消費税の免税期間を有効活用できるほか、法人税率の低さによって税負担が軽くなるからです。
ただし、設立費用や社会保険料の負担などデメリットもあるため、タイミングを誤ると予想外の損が出ることも。本記事では、「いつ法人化するのがベストか」「どんなメリット・デメリットがあるのか」を具体的な数値例や専門家の知見を交えて解説します。
目 次
法人化とは?
法人化とは、個人事業主が会社を設立し、その設立した会社に自身の事業を引き継いで経営を行うことをいいます。
法人のうち、商業登記により設立するものがいわゆる「会社」です。会社には以下の4つの種類があります。
・株式会社…最もポピュラーな会社形態です。出資者から資本を集めて設立し、出資者は払い込んだ金額に応じて株主=「会社の所有者」となり、取締役ら役員を選任します。経営を行うのは取締役で、株主は会社の債務について出資額以上の責任を負うことは原則的にありません(会社法第104条)。これを「株主有限責任」といいます。
・合同会社…2006年の会社法施行に合わせて誕生した新しい会社形態です。出資者はそのまま社員となり、経営を行います。所有者兼経営者という状態ではあるものの、株式会社同様、自身の出資額以上の責任は負わない有限責任となります。
・合資会社…無限責任社員と有限責任社員で組織される会社形態です。法人化の場面では、個人事業主が第三者から資金提供を受けて会社を設立する際に用いられやすい形です。資金提供者は有限責任社員として会社の利益の分配を受けます。
・合名会社…出資者全員が会社債務に対し無限責任を負う形態の会社です。設立の手軽さがメリットですが、出資者全員が「無限責任社員」となり、各人が個人事業主として働くイメージに近くなります。
法人化のメリット7点
個人事業と比較した場合、法人化すると次のようなメリットが期待できます。
メリット1:利益が大きい場合には、節税になる
個人事業主が支払う所得税は、課税所得金額195万円未満は5%、195万円以上~330万円未満は10%、330万円以上~695万円未満は20%と所得が大きくなるほど税率も上がり(累進課税)、最高税率は4000万円以上の45%に上ります。これに対して、法人税の税率は、15%ないし19%(年800万円を超える部分は23.2%)に固定。利益が一定額を超えたら、法人化して法人税を払ったほうが得、ということになるのです。ただし、法人になると、後で述べるような社会保険料の負担などが生じてくるため、「損益分岐点」を利益のみの指標で設定することはできません。
メリット2:信用力が高まる
個人に比べ、法人は社会的信用度が高く、そもそも取引先を法人に限定している企業もあります。金融機関から融資を受ける際にも、有利です。
メリット3:無限責任から有限責任にできる
個人事業の場合、万が一事業が傾いたような場合には、その経済的な責任(仕入先への未払金、借入金など)をすべて背負わなければなりません(=無限責任)。しかし、法人化している場合には、個人保証している借入金以外は、「負うべき責任は出資の範囲内」ということで先述した合名会社以外は、全部もしくは一部を有限責任にすることができます。
メリット4:事業承継がしやすい
個人事業のまま後継者に引き継ごうとすると、経営権・従業員・資産の3つそれぞれで移転手続きが必要になります。経営権に関しては、現経営者が廃業し、後継者が開業することで移転ができ、従業員の引継ぎは新規で雇用契約を締結する必要があります。資産に関しては、無償譲渡か有償譲渡かを選びます。
一方、法人は経営者からは独立した存在であるため、経営者が引退してもそのまま営業を継続でき、後継者への引き継ぎも個人事業に比べればスムーズに行えます。
メリット5:優秀な人材が集まりやすくなる
一般的に、従業員を募集する際、個人事業主と会社であれば、会社のほうが応募者も多くなり、その分優秀な人材を雇える可能性が高くなります。
前述した通り、法人の方が信用力が高まるので、応募する側にとって、勤務先が「会社」であることは安心感に繋がります。また、法人は厚生年金保険、健康保険の加入義務があるので、その点も、求職者のメリットとなります。
メリット6:決算月を自由に決めることができる
個人事業主の場合、事業年度は1月1日からその年の12月31日までと決められており、原則3月15日までに確定申告をしなければなりません。
しかし、法人であれば、定款に定めることで事業年度を自身に都合の良い期間に定められます。また、定款を変更すれば事業年度を途中で変えることも可能です。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 決算月は自由に決めることができますが、売上が多い時期を決算月にしてしまうと、年間売上の着地の予測が難しくなり、節税対策も難しくなってしまいます。 そのため、売上に季節変動がある事業の場合は、少ない時期を決算月にすることをおすすめします。
- 白兼公認会計士・税理士事務所 代表 白兼道夫
メリット7:生命保険料の一部が経費になる
個人事業主の場合、生命保険料の支払いに応じて、確定申告時に一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3種類の合計で12万円を限度として「生命保険料控除」が利用できます。
法人だと、生命保険料で支払った金額は、最高解約返戻率が50%以下の定期保険など、保険の種類によっては保険料全額の損金計上が可能になります。
法人化のデメリット4点
法人化のメリットを紹介してきましたが、もちろん、良いことばかりではありません。ここからはデメリットを解説していきます。
デメリット1:赤字でも負担しなければならない税金がある
個人事業は、赤字になれば所得税や住民税の支払い義務はありません。しかし、法人の場合は、法人住民税の均等割部分の負担(小規模法人で7万円くらい)が、たとえ赤字になっても発生します。
デメリット2:社会保険への加入(社会保険料の負担)が必要になる
健康保険や厚生年金の加入義務は従業員にとってはメリットになりますが、会社がその保険料を従業員と折半しなくてはならないという意味では負担となり、デメリットにもなり得ます。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 社会保険料の支払いが想像よりもきつく、会社を廃業するケースもあります。従業員数が多い場合や高額の所得者がいる場合は、給与に加えて会社が負担する社会保険料も高くなるため注意が必要です。
- 白兼公認会計士・税理士事務所 代表 白兼道夫
デメリット3:交際費を全額経費にすることができなくなる
個人事業では、交際費は全額損金として計上する(所得から差し引ける=税金が安くなる)ことができましたが、法人になると原則として「交際費のうちの飲食代に限って、50%相当額を上限として経費計上できる」と限定されます(ただし資本金1億円以下の企業は、50%相当額を上限として経費計上するか、飲食代に限らず交際費を年間800万円まで経費計上するか、任意で選ぶことができます)。
デメリット4:会計処理が複雑化、事務作業も増加する
個人事業主には、自分で確定申告を済ませる人も少なくありません。しかし、法人化すると会計処理や申告内容が複雑になるため、税理士に頼むのが一般的です。事務作業も増えるため、そのためのスタッフも必要になるかもしれません。
デメリット5:設立コストがかかる
法人化を行うには、個人事業のままでは不要だった**設立費用**が発生します。
たとえば株式会社を設立する場合、公証人役場での定款認証手数料(約5万円)や登録免許税(最低15万円)などを含めて、最低でも20万円以上の費用がかかるのが一般的です。さらに、専門家に手続きを依頼すると報酬も必要になります。 また、設立登記の手配だけでなく、銀行口座の開設や社会保険の手続きなど、法人化後に伴う事務コストも増えるため、結果的に初期出費がかさむことに注意が必要です。
デメリット6:プライベートで使えるお金が制限される
個人事業主のときは、事業資金とプライベート資金を比較的柔軟にやりくりできました。しかし法人化すると、会社のお金と個人のお金を厳格に分けなければならないため、以前のように経費や売上を自由に引き出すことはできません。
具体的には、役員報酬として支払われる額が自分の「使えるお金」の上限になり、それ以上のプライベートな引き出しは「役員貸付金」として扱われるなど会計上の手間も増えます。経費として計上できる範囲もルールが細かく定められているため、事業と私生活を完全に分ける管理能力が求められる点は、個人事業主時代とは大きく異なる部分といえます。
法人化のタイミングはいつがベスト?
ここからは、個人事業主が法人化するタイミングについて見ていきましょう。
売上がどれくらいになったら法人化すべき?
法人化するタイミングは、売上が1,000万円を超えた時がひとつの目安です。
売上が1,000万円を超えると、その2年後からは消費税の課税事業者として消費税を納める義務が生じます。しかし、法人化すれば、2年後に消費税の発生義務は生じません。なぜなら、個人と法人は別のものと考えるからです。
さらに、課税所得(利益)が800万~900万円を超えてくると、累進課税が適用される個人事業よりも法人税率の方が有利になるケースが多いといわれており、所得税・住民税の合計よりも法人税のほうが低く抑えられる可能性が高まります。
ただし、法人設立時の資本金が1,000万円を超える場合や、インボイス制度を導入する場合には、法人化の初年度から消費税が発生するので、注意が必要です。
事業の成長フェーズごとの法人化のメリット
事業の成長フェーズごとの法人化のメリットは、以下のとおりです。
事業が成長しているとき
事業が成長しているときに法人化するメリットとして、節税効果が得られることや人材の確保が挙げられます。
所得が800万円から900万円を超えると、所得税の税率よりも法人税の税率が高くなるため、法人化したほうが節税になります。
また、法人化することで、従業員の数に関わらず社会保険の加入義務が発生したり、個人事業よりも社会的な信用が高くなったりします。そのことで、人材の確保がしやすくなり、さらなる事業の成長が見込めます。
事業の成熟期や新規事業を始める時
行っている事業が成熟すると、そこからの成長が見込めにくくなります。そこで法人化を考えます。企業の中には、法人としか取引しないところもあります。法人化すると、個人事業よりも社会的な信用が高くなるため、新たな販路を開拓できる可能性があります。
また、行っている事業が成熟したため、新規事業を始めるときも同様に、法人化することで社会的な信用が高くなり、新たな取引先を見つけやすくなります。
法人化を急ぐべきではないケースとは?
行っている個人事業が、個人のままでも成長を見込めるケースでは、法人化を急ぐ必要はありません。
法人になると、法人設立の費用や領収書や請求書を個人のものから法人のものに変更する費用がかかるほか、法人化したことを顧客や取引先に知らせる手間もかかります。
また、法人になると社会保険の加入が必須となることや、赤字でも税金の支払いが発生するなど、法人設立時だけでなく、毎期の費用も多くなります。
費用が増加するため、成長事業への投資額も減少し、成長が見込めていた事業の成長が鈍くなる危険性もでてきます。
節税だけでなく長期的な経営戦略として法人化を考える
法人化をするタイミングとして、節税のことから考えることが多いですが、節税だけでなく長期的な経営戦略として、法人化を考えなくてはなりません。節税のために法人化したら、かえってデメリットが多く、事業が成長しなかったということもあります。
長期的な戦略として、どのタイミングで法人化したほうが良いのかを考えましょう。
法人化のタイミングで税理士相談を挟んだ方がいい理由
法人化のタイミングで税理士相談を挟んだ方がいい理由として、経営戦略が立てやすくなることと節税対策がしやすくなることが挙げられます。
法人化して事業の成長を促すには、タイムリーに会社の経営状況などを把握し、場合によっては経営戦略の見直しなどをしなければなりません。そのためには、税理士に記帳業務や月次監査などを依頼し、毎月の経営状況の報告を受けたほうが良いでしょう。
また、法人では、決算時だけ節税対策を行っても効果は薄く、節税対策の効果を上げるためには長期的に対策を行う必要があります。そこで、普段から税理士と相談しながら節税対策を進めましょう。
個人事業主と法人の違い 早見表
紹介してきたポイントを中心に、個人事業主と法人の対比表として整理しました。複数の軸でお互いのメリット・デメリットを理解した上で、法人化が自分にとって必要なのかを判断することが大切です。
| 個人事業主 | 法人 | |
|---|---|---|
| 社会的信用 | 低い | 高い |
| 手続き | 開業届を出す | 定款の作成や設立登記が必要 |
| 経費 税金 |
経費計上の範囲が狭い | 経費計上の範囲が広い |
| 会計 経理 |
確定申告
自力でも可能だが、
場合によっては税理士に依頼するのがおすすめ |
法人決算書・申告
会計処理や申告内容が複雑なため、
税理士に依頼するケースがほとんど |
| 赤字の場合 | 所得税や住民税の負担が無くなる | 法人住民税均等割 |
| 社会保険 | 従業員数に応じて加入保険が変わる | 加入が必須 |
| 生命保険 | 所得控除(上限12万円) | 返戻率に応じて経費計上 |
| 責任範囲 | 無限責任 | 有限責任 |
| 事業承継 | 移転手続きが面倒 | 個人事業主より手間は少ない |
| 廃業 | 届出を出す | 解散登記や公告が必要 |
法人化して後悔するケースはある?
メリット・デメリットを理解した上で法人化したけれどやっぱりしなければよかった…と後悔することになってしまう原因は様々なものがあり得ますが、ここでは2点、解説していきます。
思ったより費用負担が大きい
会社を設立するコストは意外とかかります。
株式会社の場合、作成した定款に公証人の認証が必要だったり、設立申請時の登録免許税が最低でも15万円かかったりするため、設立の実費だけでもおよそ18万円以上になります。設立手続きを司法書士などの専門家に依頼すれば、その分の報酬も必要です。
また、別途資本金の払い込みも必要です。会社法上、資本金は1円でも問題ありませんが、取引先や融資の際の信用を得るには、資本金額も重要な要素の一つになるため、慎重に考えるべき事項なのです。
法人化することで増えた事務作業を税理士などの専門家に依頼する場合の費用も忘れてはいけません。
思ったよりも節税にならなかった
節税効果は、必ず出るというものではありません。そのため、節税効果を得るためにだけ法人化しても、思ったよりも節税にならなかった。ということは当然あります。
法人化をするときには、あくまでも「ある程度の利益があがれば法人税のほうが安くなるケースがある」といった認識でいてください。
個人事業主より精神的に大変
法人に移行する際、事業拡大を見据えて出資者を募り株式会社にすると、会社の所有者は全株主(出資者)となります。自分以外の出資者の株主保有率が一定以上になると、会社の重要事項の決定に関して影響力を持つため、調整が大変かもしれません。また、取締役会設置会社にすると、今度は役員間での経営方針が一致しないことも起こり得ます。
このように、個人事業主であればせずに済んだ苦労をする可能性があります。
また、事業拡大のため融資を受けやすくする目的で法人化した場合、未来への希望と同時にプレッシャーも大きくなります。
これらのプレッシャーを、一人で抱え込み過ぎないようにすることが大切です。
法人と個人で支払う税金の違いとは
一部、前述しましたが、ここでは、法人と個人事業主で支払う税金の違いについて解説していきます。
個人が支払うのは所得税
個人事業主には、毎年1月1日~12月31日の間に稼いだ所得に対して「所得税」が課税されます。
所得税の税率は、所得の金額に応じて段階的に高くなる累進課税制度を採用しています。
| 課税される所得金額 | 所得税率 | 所得税の控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
法人が支払うのは法人税
上記の通り、個人事業主のときは「所得税」を支払わなければなりませんが、会社設立以降は所得税に代わって「法人税」を支払う必要があります。
法人税は、「事業年度(設立月から1年間)の利益」、つまり法人税法が定める「課税所得」に課税されます。そのため、事業年度終了の翌日から2か月以内に申告及び納税を行います。
法人税の税率は会社の規模により税率が決まるため、個人事業主としてある程度利益が出て、所得が800万~900万円程度(所得税率23%または33%)になれば、法人化してしまった方が税金を抑えることが可能です(資本金1億円以下の中小企業の場合…法人税率は、所得金額が年800万円以下の部分は15%、所得金額が年800万円超の部分は23.2%)。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 継続的に利益をキープできる見通しが立っているかどうかも、法人化判断ポイントの一つです。短期間だけ利益が増える場合には、法人化しない方がよかったということもあります。
- 白兼公認会計士・税理士事務所 代表 白兼道夫
法人では法人税以外にも支払わなければならない税金・費用が複数ある
会社設立を行った場合には、上記の法人税以外にも、以下のような出費も織り込んでおかなければなりません。
社会保険料
法人化をした場合は、会社の従業員数に関わらず社会保険(健康保険や厚生年金保険など)への加入が義務付けられます。社会保険料の半分は会社負担となり、たとえ会社が赤字になったとしても社会保険料の負担は免除されませんので、注意が必要です。
一方で、個人事業主の場合は、常時雇用の従業員が5人以上いる場合は社会保険への加入が必要ですが、5人未満の場合は任意です。ただし、従業員が1名以上いれば労災保険は必ず加入、雇用保険は条件を満たすならば加入しなければならないので、注意してください。
法人住民税
個人事業主の時と同様、法人も住民税(法人住民税)を支払う必要があります。
法人事業税
個人事業主の時と同様、法人も会社・事業所が所在している都道府県・地方自治体に事業税を支払う必要があります。
消費税
個人事業主の時と同様、2期前の売上が1,000万円を超える場合やインボイス制度に登録している場合は、法人も消費税を支払う必要があります。
源泉所得税
源泉徴収とは、従業員の給与を支払う会社が、社員の代わりに所得税(源泉所得税)を徴収して、まとめて納税する制度です。個人事業主の時と同様、従業員を雇って給与を支払う場合には必ず源泉徴収を行わなければなりません。
法人化による節税メリット
個人事業の利益が一定水準を超えた場合には、法人化して支払う主な税金を所得税→法人税とすることで節税になる、という話をしました。
同時に、法人化することで、次のような節税メリットも生まれます。
(1)事業所得者→給与所得者に
個人事業主は、利益(事業所得)から自分の生活費などを捻出します。生活費などプライベートに関わる費用は、経費にはなりません。
一方で、法人化して社長になると、会社から役員報酬(給与)をもらう形になります。この役員報酬は、会社の経費になりますので、会社の利益から差し引く=法人税を減額することができます。さらに、受け取る報酬には所得税がかかるのですが、「給与所得控除(所得税の計算の際に差し引ける金額)」が適用されるため、個人ベースでも節税になるのです。
(2)事業主や家族従業員への退職金が損金になる
個人事業でも、要件を満たせば、家族従業員に対する給与を経費扱いにすることは可能ですが、退職金はNGです。
逆に、法人になると、事業主や家族の従業員に支払う退職金も経費(損金)にすることができ、節税効果があります。
(3)「欠損金の繰越控除」が3年→10年に
欠損(赤字)が出た場合、それを翌年以降に黒字と相殺して所得を減らす(またはゼロにする)ことができる「繰越控除」という仕組みがあります。個人事業の場合、繰越せるのは3年ですが、法人では10年認められます。大きな赤字が出た場合には、法人のほうがメリット大と言えるでしょう。
(4)消費税の免除期間を利用できる
消費税は、原則として前々年(法人は前々事業年度)の課税売上高(※)が1,000万円を超えた場合に課税されます。要するに、2年(年度)前の売上高が、課税事業者になるかどうかの判定対象期間になります。言い方を変えると、この2年間については、消費税が免除されるのです。(ただし課税売上高が1,000万円未満でも、インボイス制度に登録するなど課税事業者になっている場合は除きます)
個人と法人は別人格なので、仮に個人事業主として課税事業者であったとしても、法人化して免税事業者を選んだ場合は、やはり2年間は消費税の支払いが免除されます。
ただし、資本金が1,000万円を超えた場合は、会社設立1年目から課税事業者になります。
また、1年目に、前半6カ月の課税売上高が1,000万円を超えた場合などには、翌年から課税事業者(免税は1年間)です。
法人ができる節税対策
法人としてできる節税対策としては、たとえば次のようなものがあります。会社の状況によって最適な節税対策は異なるため、しっかりと税理士などの専門家のアドバイスを聞きながら、判断することが大切です。
役員報酬の最適化を図る
先述のように、社長になると会社から役員報酬を受け取ることになります。多ければ多いほど、会社の経費が増えて、法人税を減額することができます。一方で、報酬が高額になるほど、個人として支払う所得税は増えていきます。つまり、このバランスを調整することで、節税が可能になるわけです。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 「会社の法人税」・「個人の所得税」の納税額と会社負担となる社会保険料のトータルを考えながら、役員報酬と役員賞与の金額を毎期考える必要がありますので、注意が必要です。
- 白兼公認会計士・税理士事務所 代表 白兼道夫
自家用車を社用車にする
個人所有の自家用車がある場合、社用車とすることで、自動車の取得費用を経費計上できるほか、燃料費や自動車保険料、高速料金なども経費にできます。
社員旅行の実施
社員旅行は、旅行期間や参加人数の割合などの条件を満たせば、費用を福利厚生費として経費計上できます。会社の出費になりますが、節税しながら社員のコミュニケーションやモチベーション強化などが図れるでしょう。
健康診断の実施
人間ドックや健康診断の費用も、福利厚生費になります。ただし全社員を対象とする必要があります。
団体定期保険への加入
企業が契約者となり従業員も加入できる団体定期保険に加入すると、保険料を損金計上できます。
共済制度への加入
廃業した際などに退職金を受け取れる「小規模企業共済」に加入すれば、掛け金を支払った分だけ節税できます。
社宅を用意する
会社が住宅を借り、社長や従業員に社宅として貸し付けた場合、会社が支払った賃料と社員から受け取った賃料の差額を、会社の損金とすることができます。
法人化するとどのくらい節税できる?シミュレーション
あくまでも簡易的なシミュレーションになりますが、年間利益ごとに見ていきましょう。
年間利益500万円の場合
個人事業主のまま
所得税・住民税などを合計すると、おおよそ75万〜85万円前後の税負担になる可能性があります(控除や家族構成で変動)。
法人化した場合
役員報酬を適切に設定したうえで法人税・住民税などを支払うと、同等の利益でも65万〜75万円程度で収まるケースが多いです。
ただし、社会保険料の負担増や設立費用も考慮が必要になります。
年間利益800万円の場合
個人事業主のまま
累進課税が効いてくるため、所得税・住民税で140万〜160万円程度の負担になるケースも(その他の経費控除状況により差あり)。
法人化した場合
法人税率が一定水準であるため、所得分散や役員報酬の設定次第で、上記より数十万円以上税負担を抑えられる可能性が高まります。
ただし社会保険料は利益が大きいほど負担額も増えるため、全体でどの程度の節税になるかはシミュレーションが不可欠です。
法人化で税率が下がるメリットは大きいものの、役員報酬の設計や社会保険料、設立費用を含むトータルコストを見落とすと「思ったより節税できなかった」ということにもなりかねません。したがって、実際には税理士等の専門家と相談しながら、「利益」「役員報酬」「社会保険料」などを総合的に考慮したうえでシミュレーションを行い、法人化のメリットを最大化できるタイミングを見極めることが重要です。
法人化で税理士への依頼を検討中の方へ
節税や信用度のアップなど、メリットの多い法人化ですが、必要な手続きなどは多岐にわたります。失敗しないために、法人化に詳しい税理士など、専門家のアドバイスを受けるのもいいでしょう。
記事監修者 白兼税理士からのワンポイントアドバイス
節税や信用度のアップなど、メリットの多い法人化ですが、必要な手続きなどは多岐にわたります。失敗しないために、法人化に詳しい税理士など、専門家のアドバイスを受けるのもいいでしょう。
法人設立はご自身で行うことも可能ですが、手間がかかりますし、よく分からないまま設立して不安が残るということもあります。設立後に後悔しないためには、まずは法人化するメリットとデメリットを法人化に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。設立登記の申請を行う司法書士などの専門家への依頼もワンストップで行うことができますし、自分で調べただけでは思いつかないアドバイスがもらえるはずです。メリットとデメリットの両方をしっかりと理解したうえで、数年先の売上や利益まで見通して、メリットがデメリットを上回る場合には、自信をもって法人化をしましょう。