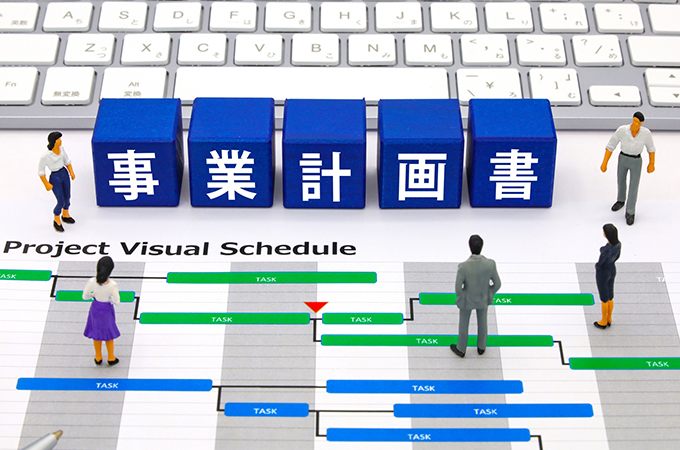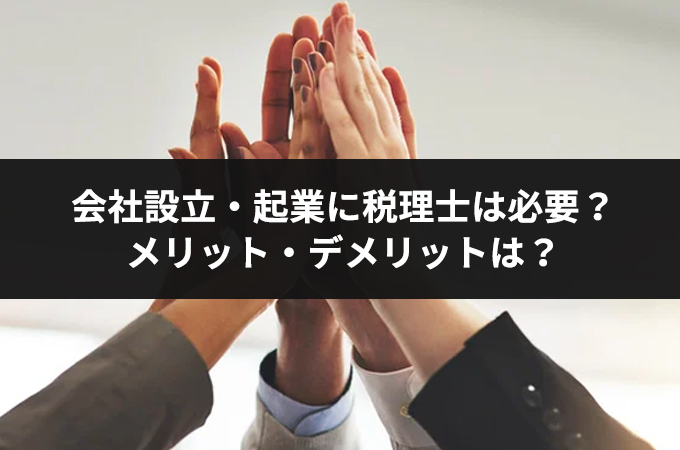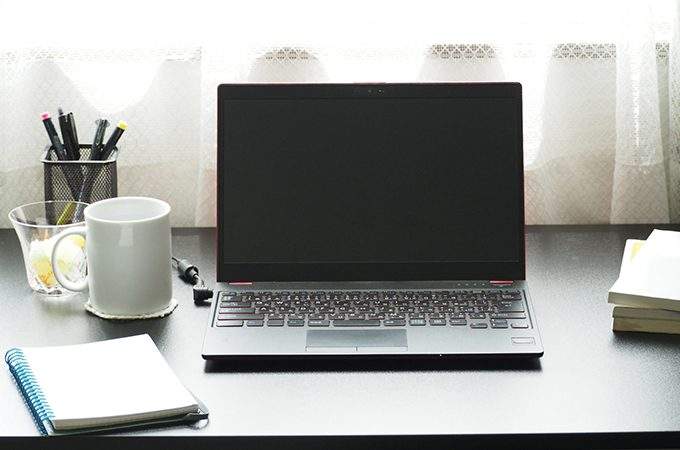会社設立や起業後にかかる税金は?節税のポイントもまとめて解説
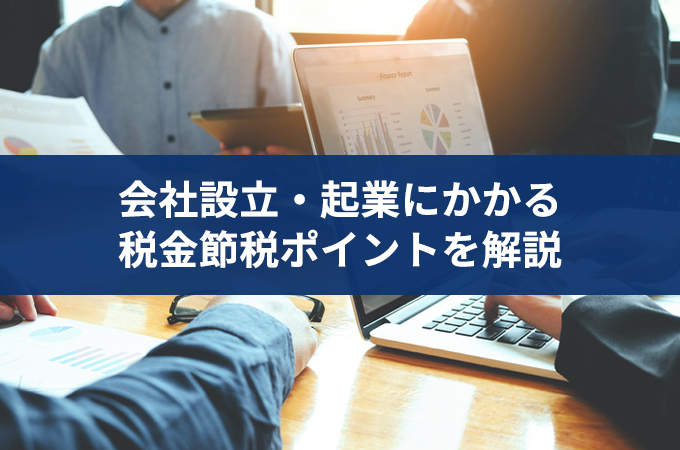

- この記事の監修者
- 税理士法人資産経営パートナーズ 代表 加瀬 直樹(税理士・公認会計士)
会社設立時に必要な税金は?
会社設立の際に必要な税金は、次の2つです。
定款の印紙税
「定款」とは、事業の目的などを定めた、いわば「会社のルールブック」です。会社をつくるときには、その作成が必須になりますが、それには4万円の印紙税がかかります。
ただし、紙ではなくPDFによる電子定款にした場合には、課税されません。
登録免許税
設立登記も、会社設立の必要条件です。その際に課税されるのが「登録免許税」で、株式会社は15万円(資本金の0.7%が15万円を超える場合には、その金額)、株式会社より設立が容易な合同会社は6万円(同)となっています。
会社設立後にかかる税金は?
会社設立以降に支払う必要があるのは、次のような税金になります。
法人税
「法人税」は、個人事業主の「所得税」に当たる税金で、事業年度(設立月から決算月)の利益=法人税法が定める「課税所得」に課税されます。事業年度終了の翌日から2ヵ月以内に申告・納税を済ませる必要があります。
税率は、資本金1億円以下の中小企業の場合、課税所得金額が800万円以下は15%、それを超える金額は23.2%となっています。起業促進の"国是"もあって、法人税率は引き下げのトレンドにあります。
| 区分 | 対象 | 課税所得区分 | 適用関係(開始事業年度) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | 令4.4.1以後 | |||
| 普通法人 | 資本金1億円以下の法人など(注1) | 年800万円以下 (適用除外事業者以外) |
15% | 15% | 15% | 15% |
| 年800万円以下 (適用除外事業者(注2)) |
15% | 15% | 19%(注3) | 19%(注3) | ||
| 年800万円超 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||
| 上記以外の普通法人 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||
- (注1) 資本金または出資金が1億円以下の普通法人(ただし特定の医療法人6を除く)。相互会社や完全支配関係にある大法人などは対象外。
-
(注2) 「適用除外事業者」はグループ通算制度における除外事業者を含む。詳細は
国税庁 Q&A 問83 を参照。 - (注3) 平成31年4月1日以後開始事業年度から、年平均所得が15億円超の法人等(注2)の年800万円以下部分に19%を適用。
令和4年4月1日以降に開業した普通法人では23.30%が最大の税率となっています。
普通法人ではない区分の法人は出典元の国税庁のウェブページをご参照ください。
また、法人税の計算式は以下のようになっています。
課税所得 × 税率 - 税額控除額 = 法人税額
事業年度開始日:令和4年4月1日以後
資本金 1 億円以下の普通法人(中小法人扱い)
課税所得:8,000,000 円(800 万円) の場合、
8,000,000 × 15% = 1,200,000(円)

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 法人税の申告・納付期限は、事業年度が終了した日の翌日から2か月以内と決まっています。個人事業の「所得税」の確定申告とは異なるため、注意しましょう。
- 税理士法人資産経営パートナーズ 代表 加瀬 直樹
法人住民税
法人住民税は「都道府県民税+市町村民税」を合わせた地方税で、法人税額に比例する「法人税割」と、赤字でも一定額を負担する「均等割」の 2 本立てです。
■ 法人税割……法人税額 × おおむね 6〜7%(東京都 23 区は 7% など)
■ 均等割……資本金と従業員数で区分され、年 7 万〜30 万円超まで幅あり(東京 23 区の場合)
たとえば資本金 1,000 万円以下・従業員 50 人以下の中小法人が課税所得 800 万円の場合、法人税 120 万円 × 7% = 84,000 円(法人税割)と、均等割 70,000 円を合わせ、年間の法人住民税は154,000 円が目安となります。
法人事業税
さまざまな公共サービスの経費の一部を徴収する目的で、法人の事業所得に対して地方自治体(都道府県)が課す税金が「法人事業税」です。税率などは各都道府県によって異なるため、事前に確認しておくのがいいでしょう。
消費税
やはり個人事業と同様に、法人の消費活動にも「消費税」がかかってきます。実際には、顧客から支払われた消費税から、仕入れなどで自らが支払った消費税を差し引いた金額を納付することになります。
納税の義務が生じるのは、基本的に課税売上高が1,000万円を超えた2年(2期)後から。ただし、注意すべき点は、資本金を1,000万円以上に設定するとその期から課税業者になることです。
特別な理由がない場合には、会社設立時の資本金は、1,000万円未満にするのが得策と言えるでしょう。
源泉所得税
従業員を雇う場合には、源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収とは、「給与・報酬などの特定の所得の支払者が、その所得の支払をする際に、所定の方法により所得税(源泉所得税)の金額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付すること」を言います(これは個人事業主の場合も同じです)。
社会保険料
常時従業員を使用する法人事業所は、「社会保険」(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用医保険)に加入しなくてはなりません。会社の設立に当たっては、そのための出費も織り込んでおく必要があります。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 給料が出ていない場合や、非常勤の従業員しかいない場合には社会保険適用の対象にはなりません。
- 税理士法人資産経営パートナーズ 代表 加瀬 直樹
設立時に陥りやすい税務リスクとその回避方法
会社設立後は非常にすることが多く大変ですが、税務関連手続きも忘れず行いましょう。
税金の未納や申告漏れによる罰金のリスク
設立直後は資金繰り・営業・採用など多くのタスクに追われがちで、記帳や申告が後回しになるケースが少なくありません。
しかし申告漏れ=高利の借金と同じで、放置するとコストだけでなく信用も失います。
- 延滞税 … 納期限翌日~2か月年7.3%/2か月超年14.6%
- 無申告加算税 … 法人税額に原則15%(50万円超部分は20%)
- 重加算税 … 仮装・隠ぺいが認定されると35%
- 信用失墜・融資不可 … 滞納を続けると金融機関からの信用を失い、新規融資やリスケが困難になるリスク
- 税務調査リスク … 未納・遅延が続く法人は重点的に税務調査を受けやすくなる
支払わなければ督促状 → 差押え → 競売と進行し、口座凍結や取引停止に発展する場合もあります。
「忙しい時期こそ専門家と記帳・申告体制を構築」し、罰金と信用失墜のダブルリスクを未然に防ぎましょう。
消費税の課税業者となるタイミングとその対応策
資本金1,000万円未満の新設法人は原則設立1・2期目の消費税が免除されます(前々期課税売上高ゼロ)。
ただしインボイス制度(2023年10月開始)により、取引先が仕入税額控除を受けるためインボイス発行を求めるケースが増えています。
- 課税事業者になるには課税事業者選択届出書と適格請求書発行事業者登録申請を期末日までに提出
- 期限内に届出すると期首に遡って課税事業者として扱われる
- 一度選択すると原則2年間(届出後3年間)は免税に戻れない
また資本金1,000万円以上や「特定期間」売上高1,000万円超の場合は自動で課税事業者となるため要注意です。決算直前は書類が集中しやすいので、設立時の手続きと同時にインボイス関連届出も済ませるとスムーズです。
会社設立で節税する方法
会社を設立すると法人ならではの税制を活用でき、個人事業よりも大きな節税効果を狙えるケースがあります。ここでは5つの代表的な方法をまとめました。
役員報酬を適切に設定する
役員報酬は期首に金額を決定し、その額を1年間固定で支給することで法人の損金に算入できます。
法人と個人に所得を分散させ、累進課税を緩和することでトータルの税負担を抑えられます。
会社設立後も所得税がかかることに要注意
個人の所得税は、所得が増えるほど税率も高くなる「累進課税」という仕組みになっています。法人税のほうは、税率が一定で、さきほど説明したように「減税」の方向にもあります。
そのため、事業が拡大して所得が一定の水準を超えた場合には、会社にして、支払う税を所得税から法人税に切り替えた方が有利になるというわけです。
ただし、法人化をすると社会保険の負担が生じますし、さらに盲点になりやすいのが、自らの報酬に課税される税金です。
個人事業の場合には、生活も事業も、会計上は混然一体で済みました。しかし、会社をつくるとそうはいきません。生活費を含めた「自分のお金」は、会社から報酬のかたちで受け取ることになるのです。従業員がもらう給与と同じように、その金額には所得税がかかってきます。当然、都道府県民税や市町村民税などの地方税も課税されます。
つまり、会社経営者には、「会社の法人税など」と「個人の所得税など」を両にらみにした節税プランが求められることになるわけです。「自分の会社なのだから」と報酬を多くもらいすぎたりするとトータルの納税額が膨らむことになりますので、注意が必要です。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 「自分の会社だから」と報酬を多くもらいすぎてしまうと、トータルの納税額が膨らむことになりますので、注意が必要です。
- 税理士法人資産経営パートナーズ 代表 加瀬 直樹
退職金を支給する
退職金は法人にとって損金、受取人にとっては退職所得控除+1/2 課税となるため大きな節税効果があります。
会社の財務状況に合わせて支給額や支払い時期を設計できる点もメリットです。
- 5 年以上勤務した役員・従業員が対象
- 退職所得は他の所得と分離課税されるため所得税が軽減
- 小規模企業共済・iDeCo との比較検討が必要
家族を役員にする
親族に給与を支払い所得を分散することで累進課税の負担を抑える方法です。
たとえば親が代表取締役、子どもを役員とし、それぞれに適正額の給与を支給すると法人税+所得税の合計負担をトータルで軽減できます。
- 税務上適正給与の範囲内で設定することが必須
- 社会保険料の増減も加味しトータルコストを試算
保険に加入する
個人契約の保険料は控除が 年間 12 万円 までですが、法人保険は商品により全額または一定割合を損金算入できます。これにより当期課税所得を圧縮し法人税を抑えることが可能です。
- 解約返戻金や満期金は益金計上されるため将来課税に備える
- 退職金・設備投資へ充当すると課税タイミングをコントロールできる
消費税の納税義務免除を活用する
資本金1,000 万円未満の新設法人は、原則として設立 1・2 期目の消費税が免除されます(前々期課税売上高ゼロ扱い)。
免除分を運転資金に回せるため、キャッシュフロー改善策として有効です。
- 売上高が 1,000 万円を超えるまでは免税事業者を維持可能
- ただし インボイス制度下では取引先から発行を求められると課税事業者選択届出が必要
- 一度課税事業者を選択すると原則 2 年間は免税に戻れないため要検討
法人化は結局トクなの?税理士に依頼すべきタイミングは?
結論:年間利益が600万~800万円を超えるなら、法人化した方が手取りベースで有利になるケースが多い――これが税務シミュレーションの一般的な結果です。
- 個人の最高税率(所得45%+住民10%)に比べ、法人なら15%+約7%で頭打ち(800万円以下部分)
- 役員報酬・退職金・法人保険など損金算入の幅が広く、節税メニューが増える
- 社会的信用が高まり、口座開設や融資がスムーズになる
もちろん赤字でも均等割(7万円~)がかかる、社会保険が強制加入になる、経理事務の手間が増える――といったデメリットもあります。利益が小さいうちは個人事業のまま小規模企業共済などを活用した方が有利な場合もあるため、必ず試算が必要です。
また、税理士へ依頼するベストタイミングは「設立書類の準備を始める前」。会社設立届、青色申告承認、インボイス登録、役員報酬額の設計までワンストップで任せれば、設立初年度から最適な節税プランを走らせることができます。
よくある質問
会社設立時に必ずかかる税金は何ですか?
定款の印紙税 4 万円と、設立登記時の登録免許税(株式会社 15 万円/合同会社 6 万円※資本金に応じて変動)の 2 つです。電子定款にすれば印紙税は不要です。
会社にすると、個人事業よりどんな税金が増えますか?
法人税・法人住民税・法人事業税・(条件により)消費税が発生します。赤字でも法人住民税の均等割は最低 7 万円~かかる点に注意が必要です。
資本金を 1,000 万円未満に抑えるメリットは?
課税売上高がゼロの新設法人は、資本金が1,000 万円未満なら設立 1・2 期目の消費税が免除されます。インボイス発行を求められる場合は課税事業者選択届の提出が必要です。
赤字でも支払う税金はありますか?
はい。法人住民税の均等割(7 万~30 万円超)は所得ゼロでも課されます。また従業員を雇えば社会保険料の会社負担分が発生します。
法人化すると結局どれくらい得になりますか?
利益が年間 600~800 万円を超えると、個人の最高税率より法人+役員報酬の組み合わせの方が手取りで有利になるケースが多いです。ただし社会保険料や事務コストも加味してシミュレーションが必要です。
会社設立は税理士に依頼した方がいいですか?
設立届・青色申告承認・インボイス登録・役員報酬設計をワンストップで任せられるため、初年度から最適な節税プランを走らせたい場合は税理士に依頼するメリットが大きいです。
記事監修者 加瀬税理士からのワンポイントアドバイス
会社をつくるときにも、設立後にも、個人の場合とは異なる税金がかかってきます。設立後の個人の報酬には、所得税が課税されることにも要注意です。
また、会社設立時から税理士などの専門家にサポートを依頼しておくことで、事業に集中することもできます。ご自身の状況に照らし合わせて検討してみてください。

- この記事の監修者
- 税理士法人資産経営パートナーズ 代表 加瀬 直樹(税理士・公認会計士)
事務所詳細はこちら
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 会社設立 >
- 会社設立や起業後にかかる税金は?節税のポイントもまとめて解説