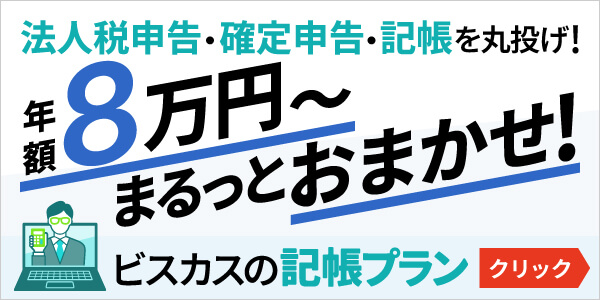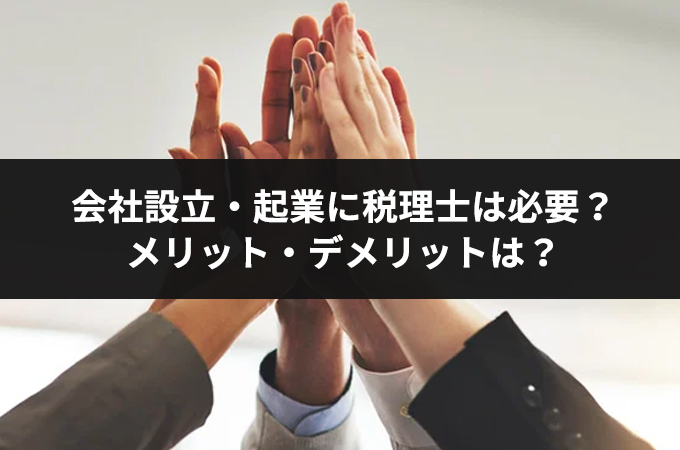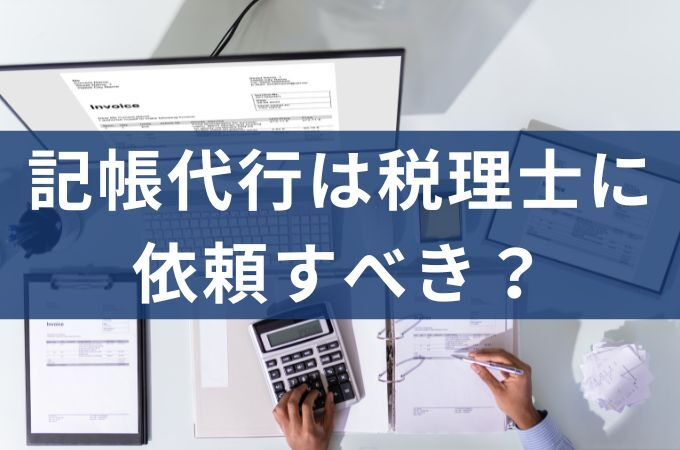補助金申請は税理士に依頼すべき?メリット・デメリットと税理士選びのポイント
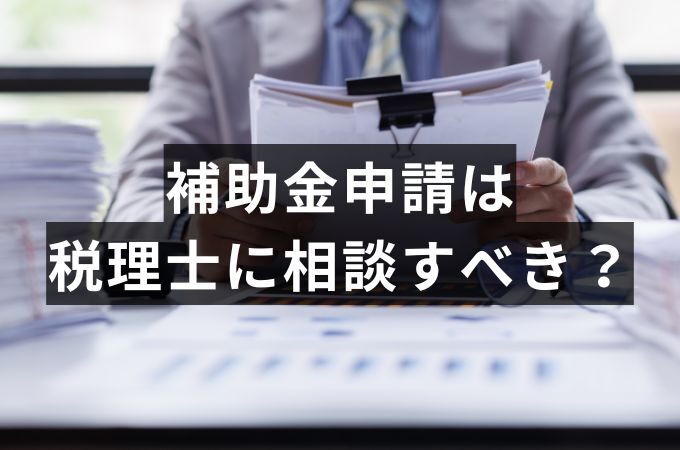
- 最終更新日:
- 2025/04/24

- この記事の監修者
- 澤村明浩税理士事務所
代表 澤村 明浩(税理士)
補助金申請サポートを税理士に依頼する前に知っておきたい基礎知識
補助金や助成金は事業拡大や新規事業立ち上げに欠かせない資金源ですが、申請手続きの複雑さや採択のハードルの高さから、多くの経営者が頭を悩ませています。そこで注目したいのが、税理士による補助金申請サポートです。しかし依頼する前に、どのような支援が受けられるのか、また税理士と社労士の役割の違いなど、基本的な知識を押さえておく必要があります。
補助金・助成金の申請サポート(申請代行)とは?
補助金・助成金の申請サポートとは、専門家が事業者の補助金申請をサポートするサービスのことです。具体的には以下のような業務が含まれます。
- 公募要領の確認と申請条件の整理
- 申請書類の作成支援や添削
- 事業計画書の作成アドバイス
- 必要書類の準備と提出サポート
- 審査対応のアドバイス
ただし重要なのは、事業計画の根幹となる部分(何をどのように実現したいのか)は事業者自身が考える必要があり、専門家は主に「計画を書類として形にする」ことをサポートする点です。つまり、丸投げではなく、事業者と専門家の協力関係が成功の鍵となります。
税理士と社労士・行政書士の違いと補助金申請での役割分担
補助金・助成金を申請する際に依頼できる専門家には、主に税理士と社会保険労務士(社労士)、さらに行政書士がいます。それぞれの専門分野と役割は以下のように分かれています。
税理士の専門分野・役割
- 経済産業省系の補助金申請支援(ものづくり補助金、事業再構築補助金など)
- 事業計画の財務面の構築サポート
- 税務・会計面からの事業計画アドバイス
社労士の専門分野・役割
- 厚生労働省管轄の助成金申請代行(雇用関係の助成金など)
- 労務管理に関する助成金の申請支援
- 従業員の雇用に関連する助成金活用のアドバイス
社労士の専門分野・役割
- 官公署に提出する書類の作成・提出代行
- 各種補助金・助成金の申請書類作成支援
- 事業計画書の作成サポート
- 許認可が必要な補助金申請のサポート
例えば、新たな設備投資を行うためのものづくり補助金を検討しているなら税理士に、従業員の処遇改善や雇用拡大に関する助成金を検討しているなら社労士に、複雑な申請書類の作成や官公署への提出を伴う補助金なら行政書士に相談するのが適切です。制度によって申請代行できる専門家が法律で定められているケースもあるため、自社が活用したい補助金・助成金の種類に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。
補助金の種類や内容によっては、複数の専門家が連携して対応するケースもあります。大型の補助金申請では税理士(財務面)、行政書士(申請書類作成)、社労士(労務関連)が役割分担して総合的なサポートを行うことも珍しくありません。
また、税理士や社労士が行政書士資格も同時に保有していることも多く見られます。このような複数資格保有者に依頼すれば、異なる専門分野からのアドバイスを一括して受けられるため、依頼前に保有資格を確認しておくと効率的です。
税理士に依頼できること・できないこと
税理士に補助金申請で依頼できる主な業務と、依頼できない業務を整理しておきましょう。
税理士に依頼できること
- 経済産業省系補助金の申請書類作成支援
- 事業計画の財務数値の策定支援
- 補助金制度の紹介や適切な制度の提案
- 受給後の会計処理・税務申告のサポート
- 補助金活用を含めた中長期的な資金計画の助言
税理士に依頼できないこと
- 社労士法で規定された労務系助成金の申請代行
- 事業計画の構想そのものの策定(企業側の本質的な意思決定部分)
- 許認可が必要な行政書士業務
- 補助金採択の確約(結果を保証するものではない)
税理士は補助金申請において強力なサポート役となりますが、法律上の制限や業務範囲があることを理解しておくことで、適切な期待値を持って依頼することができます。特に労務系の助成金については社労士との連携が必要となるケースもあるため、税理士に相談する際は「どのような補助金・助成金を検討しているか」を明確に伝えましょう。
税理士に補助金相談をする際に注意すべき点とは?

澤村 明浩
監修税理士からのワンポイントアドバイス
税理士は税金に関する専門家ではありますが、補助金の知識が必ずあるとは限りません。税理士試験では補助金の知識まで担保されないため、過去の実績を聞くことをお勧めします。また、ものづくり補助金は購入予定先のメーカー側が無料又は低廉な料金により代理申請してもらえる場合も多くあります。税理士は会社の財務状況がわかるという点が、補助金の代理申請のパートナーとして優れている点だと考えますので、補助金申請時に必要になることが多い、財務状況を記載する部分についてどのように書けばいいか聞く、ワンポイントリリーフのような使い方も検討していいかと考えます。補助金代理申請の音頭をとっていただく税理士であればお任せしてしまうことも一つですが、料金は割高になる可能性があります。
補助金申請を税理士に依頼するメリット
中小企業やフリーランスが補助金申請を税理士に依頼することで得られるメリットは多岐にわたります。ここでは主な5つのメリットを詳しく解説します。
メリット① 書類作成の手間を大幅削減し本業に集中できる
補助金申請書類の作成は、公募要領の読み込みから始まり、申請書の記入、必要書類の収集、提出まで多くの時間と労力を要します。特に初めて申請する場合は、どのように書けばよいのか試行錯誤する時間も必要です。
税理士に依頼することで、こうした手続きの大部分をプロに任せることができ、経営者は本業に集中できるようになります。例えば、ものづくり補助金の申請書類は30ページ以上になることもあり、自力で作成すると数週間かかることもありますが、税理士に依頼すれば必要な情報を提供するだけで済みます。
本業が忙しい中小企業経営者にとって、この時間の節約は非常に大きな価値があります。自社の強みを活かした事業運営に注力できることで、結果的に事業全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
メリット② 申請書の品質向上とノウハウ活用で採択率アップが期待できる
補助金申請では採択されるかどうかが最も重要ですが、採択されるためには申請書の質が決め手となります。税理士、特に補助金申請のサポート実績が豊富な税理士は、審査員の視点を理解し、採択されやすい申請書の作成ノウハウを持っています。
具体的には以下のような点で申請書の品質向上が期待できます。
- 審査項目に沿った効果的なアピールポイントの整理
- 説得力のある数値計画の作成
- 事業の社会的意義や革新性の明確な表現
- 過去の採択事例から学んだ成功パターンの活用
例えば、事業再構築補助金では「新規性」や「市場性」が重視されますが、これらを効果的に表現するためには専門的な知識と経験が必要です。税理士のノウハウを活用することで、自力での申請に比べて採択される可能性が高まると言えるでしょう。
メリット③ 自社に適した補助金の提案や最新情報の入手ができる
補助金・助成金の制度は非常に多岐にわたり、常に新しい制度が登場したり、既存の制度が変更されたりします。個人事業主や中小企業の経営者が全ての情報を把握するのは困難です。
税理士は日頃から最新の補助金情報を収集しており、クライアントの事業内容や財務状況を踏まえて、最適な補助金を提案してくれます。例えば、設備投資を検討している企業には「ものづくり補助金」を、新規事業への挑戦を考えている企業には「事業再構築補助金」というように、目的に合わせた制度を紹介してくれるでしょう。
また、補助金以外にも低利融資や税制優遇措置など、様々な資金調達・支援策についても情報提供を受けられるため、経営者の選択肢が広がります。自社の状況に合った支援策を総合的に活用できることは、大きなメリットと言えます。
メリット④ 受給後の会計処理や税務対応まで安心して任せられる
補助金を受給した後の会計処理や税務申告も重要なポイントです。補助金は原則として益金(収益)として計上する必要があり、法人税等の課税対象となります。また、補助金で取得した資産の減価償却方法など、特有の会計処理が必要になるケースもあります。
税理士に依頼していれば、これらの処理を正確に行えるため、申告ミスによるペナルティのリスクを回避できます。具体的には以下のような対応が期待できます。
- 補助金の適切な会計処理方法のアドバイス
- 補助金関連の経費計上や資産計上の指導
- 税務申告時の正確な処理
- 補助金受給に伴う税金対策の提案
特に顧問税理士に依頼している場合は、申請から受給後の対応まで一貫してサポートを受けられるため、安心感が大きいでしょう。
メリット⑤ 事業計画のブラッシュアップや経営アドバイスも受けられる
補助金申請の過程では、事業計画を練り上げる必要があります。この作業を税理士と共に行うことで、単に補助金を獲得するだけでなく、事業そのものの将来性や収益性を高めるための貴重なアドバイスを得ることができます。
税理士は数多くの企業の財務状況を見てきた経験から、事業の強みや弱み、成長の可能性などを客観的に分析できます。補助金申請をきっかけに以下のようなアドバイスも期待できるでしょう。
- 収益構造の改善ポイントの提案
- 資金繰り計画の最適化
- 中長期的な事業戦略の検討
- 業界の動向を踏まえた経営判断のサポート
このように、補助金申請の先にある「事業の成長」というゴールに向けて、税理士の知見を活用できることは大きなメリットです。特に顧問契約を結んでいる場合は、継続的なアドバイスを受けることで、補助金をきっかけとした事業発展につなげることができます。
補助金申請を税理士に依頼するデメリット・注意点
税理士に補助金申請を依頼することで多くのメリットを得られますが、一方でいくつかのデメリットや注意点も存在します。ここでは主な3つのデメリット・注意点を解説します。
デメリット① 専門家への依頼コストがかかる
税理士に補助金申請を依頼する際には、一定の費用が発生します。一般的な料金体系としては、「着手金(初期費用)」と「成功報酬」の組み合わせが多く見られます。
例えば、ものづくり補助金の場合、着手金として5〜15万円程度、成功報酬として補助金額の10〜15%程度を支払うケースが一般的です。仮に1,000万円の補助金を受け取れた場合、成功報酬だけで100〜150万円の費用が発生することになります。
中小企業やスタートアップにとって、この費用負担は決して小さくありません。特に着手金は補助金が不採択となった場合でも返金されないため、リスクととらえる経営者もいるでしょう。
ただし、この費用を「投資」と考えることも重要です。専門家のサポートによって採択率が向上し、結果的に大きな資金を獲得できれば、費用対効果としては十分に見合うものとなります。依頼を検討する際は、単に費用の額だけでなく、期待できるリターンとのバランスで判断することが大切です。
デメリット② 社労士法違反など法的リスクへの注意
補助金・助成金の種類によっては、税理士に依頼できないケースがあることに注意が必要です。特に厚生労働省管轄の雇用関連助成金については、社会保険労務士法により申請代行は社労士の専管業務とされています。
このような助成金を誤って税理士に依頼してしまうと、社労士法違反となる可能性があり、税理士側も依頼を受けられません。また、知らずに法令違反の依頼をした場合でも、依頼者側にも責任が及ぶ可能性があります。
このリスクを避けるためには、依頼前に以下の点を確認しておくことが重要です。
- 申請したい補助金・助成金が税理士の業務範囲に含まれるかどうか
- 税理士が社労士と連携して対応可能かどうか
- 複合的な申請の場合、役割分担はどうなるか
良心的な税理士であれば、自分の業務範囲外の助成金については社労士を紹介してくれるはずです。依頼前に十分なコミュニケーションを取り、法的リスクを回避することが大切です。
デメリット③ 事業計画策定など自社で対応すべき部分は残る
税理士に補助金申請を依頼しても、全てを任せられるわけではありません。特に事業計画の根幹となる部分、例えば「どのような事業を展開したいのか」「なぜその事業に取り組むのか」といった本質的な部分は、事業者自身が考える必要があります。
税理士は提供された情報をもとに申請書を作成・ブラッシュアップすることはできますが、事業のビジョンや具体的な実施内容については、経営者からの情報提供が不可欠です。つまり、「丸投げすれば採択される」というものではなく、依頼者側にも一定の準備と協力が求められるのです。
具体的には以下のような作業が依頼者側に必要となります。
- 事業の基本コンセプトの明確化
- 市場分析や競合調査のための情報提供
- 設備投資内容や導入技術の詳細説明
- 財務データや過去の実績資料の準備
これらの準備が不十分だと、せっかく専門家に依頼しても十分な成果が得られない可能性があります。税理士との密なコミュニケーションを通じて、双方が協力して申請を進める姿勢が重要です。
補助金申請サポートを税理士に依頼する際の費用相場
税理士に補助金申請のサポートを依頼する際には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは一般的な料金体系と相場について解説します。
着手金(依頼時に支払う費用)の相場と意味
着手金とは、補助金申請の依頼を受けた時点で税理士に支払う初期費用のことです。この費用は申請書類の作成や準備作業の対価として発生し、補助金が採択されるかどうかに関わらず支払う必要があります。
着手金の一般的な相場:
- 小規模な補助金申請(小規模事業者持続化補助金など):3〜8万円程度
- 中規模な補助金申請(ものづくり補助金など):8〜15万円程度
- 大規模な補助金申請(事業再構築補助金など):10〜20万円程度
着手金の金額は、申請する補助金の種類や申請内容の複雑さ、税理士事務所の規模などによって異なります。一部の税理士事務所では着手金なしで成功報酬のみの契約形態を提案する場合もありますが、これは採択されなかった場合のリスクを税理士側が負うことになるため、成功報酬の率が高くなる傾向があります。
着手金は「採択されなければ無駄になる」と考えるかもしれませんが、申請書類の作成には専門的な知識と時間が必要であり、その労力に対する正当な対価という側面もあります。複数の税理士事務所から見積もりを取り、着手金と成功報酬のバランスを比較検討することをおすすめします。
成功報酬(採択・受給時に支払う費用)の相場と注意点
成功報酬とは、補助金が採択され実際に交付されたタイミングで支払う報酬です。多くの場合、受給した補助金額に対する一定の割合で設定されています。
成功報酬の一般的な相場:
- 小〜中規模な補助金:補助金額の10〜15%程度
- 大規模な補助金:補助金額の8〜12%程度
- 特殊な補助金(難易度が高いもの):補助金額の15〜20%程度
例えば、1,000万円の補助金が採択された場合、成功報酬として100〜150万円程度を支払うことになります。成功報酬は補助金額に比例するため、大型の補助金ほど報酬額も大きくなりますが、割合(パーセンテージ)は補助金額が大きくなるほど低く設定されるケースが多いです。
成功報酬型の契約には以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
- 不採択の場合は成功報酬が発生しないため、リスクが限定的
- 税理士側も採択を目指して全力でサポートするインセンティブがある
デメリット
- 採択された場合の手取り額(補助金から報酬を引いた額)が減少する
- 補助金額が大きいほど支払う報酬も高額になる
契約時には成功報酬の計算方法や支払いタイミングについても明確にしておくことが重要です。また、一部の補助金では交付決定後に分割して支払われるケースもあるため、そのような場合の成功報酬の支払い条件についても事前に確認しておきましょう。
顧問税理士契約を活用した継続的な補助金サポートのススメ
補助金申請を単発で依頼するスポット契約と、顧問税理士として継続的にサポートを受ける顧問契約では、受けられるサービスの質や範囲が大きく異なります。ここでは両者の違いと、継続的なサポートを受けるメリットについて解説します。
スポット契約 vs 顧問契約:サポート内容と費用の違い
スポット契約の特徴:
- 補助金申請だけを目的とした単発の契約
- 必要な時だけ依頼するため、固定費が発生しない
- 着手金と成功報酬の組み合わせで費用が発生
- 経営状況や事業内容の理解から始める必要がある
- 依頼ごとに新たな関係構築が必要
顧問契約の特徴:
- 月額顧問料が発生する継続的な契約
- 税務・会計業務全般のサポートを受けられる
- 補助金申請も顧問業務の一環として対応(追加費用は事務所によって異なる)
- 経営状況を常に把握してもらえるため、的確なアドバイスが期待できる
- 密なコミュニケーションにより信頼関係が構築されている
費用面の比較
- スポット契約:着手金5〜20万円+成功報酬(補助金額の8〜15%程度)
- 顧問契約:月額顧問料(3〜10万円程度)+補助金申請の追加費用(事務所により異なる、顧問料に含まれる場合や、スポット契約より低額な場合が多い)
顧問税理士がいる場合、補助金申請をサポートしてもらう大きなメリットは「事業内容や財務状況を熟知した専門家」による支援が受けられる点です。既に自社の強みや課題を把握している税理士であれば、補助金申請においても的確なアドバイスがもらえます。
また、顧問税理士は定期的に新しい補助金情報をチェックしているため、「この補助金が出たので申請してみませんか」といった提案を受けられることも大きなメリットです。事業者自身が情報収集する手間が省け、チャンスを逃さずに済みます。
継続的な事業拡大や成長を目指す企業にとっては、単発の補助金申請だけでなく、中長期的な視点での資金調達戦略が重要です。その意味でも、顧問税理士との継続的な関係構築は、補助金活用の成功確率を高めるうえで有効な選択と言えるでしょう。
税理士に補助金申請を依頼するベストタイミングとは
補助金申請のサポートを税理士に依頼する際には、タイミングが非常に重要です。締切直前では十分な準備ができず、採択率が下がる可能性もあります。ここでは効果的な依頼タイミングについて解説します。
申請準備は早め早めに!公募前からの相談が鍵
補助金申請において最も重要なのは「早め早めの準備」です。理想的なタイミングは以下の通りです。
最適な依頼タイミング:
- 公募要領発表前:事業計画の構想段階から相談
- 公募要領発表直後:要件確認と申請準備の開始
- 公募開始から締切の1/3程度の期間内:本格的な申請書作成
特に競争率の高い人気補助金(ものづくり補助金や事業再構築補助金など)では、公募開始と同時に多くの企業が準備を始めます。締切間際になると税理士側も案件が集中し、十分な時間を確保できなくなる可能性があります。
早めに準備を始めるメリットとしては以下の点が挙げられます。
- 事業計画を十分に練り上げる時間が確保できる
- 必要書類を余裕を持って準備できる
- 税理士からの改善提案を反映させる時間がある
- 不測の事態が生じても対応できる
例えば、「来年度は設備投資を考えているので、使える補助金があれば活用したい」という段階から税理士に相談しておけば、公募情報が出た時点ですぐに準備に取りかかることができます。
反対に、締切直前の依頼では以下のようなリスクがあります。
- 税理士が多忙で十分なサポートが受けられない
- 事業計画の練り込みが不十分になる
- 申請書の質が低下し採択率が下がる
- 必要書類の準備が間に合わない可能性がある
「思い立ったら即行動」を心がけ、補助金活用を検討した時点で早めに税理士への相談を始めることが、採択への近道と言えるでしょう。
補助金申請を依頼する税理士の選び方ポイント
補助金申請の依頼先として適切な税理士を選ぶことは、採択の可能性を大きく左右します。ここでは失敗しない税理士選びの3つのポイントを紹介します。
ポイント① 補助金申請代行の実績や専門分野で選ぶ
税理士の中でも、補助金申請のサポート実績には大きな差があります。実績豊富な税理士を選ぶことで、ノウハウを活かした質の高い申請書作成が期待できます。
チェックすべきポイントは以下の通りです。
- 申請サポートの実績数(過去に何件の補助金申請をサポートしたか)
- 採択率(サポートした案件のうち何%が採択されているか)
- 対応実績のある補助金の種類(ものづくり補助金、事業再構築補助金など)
- 自社と同業種の企業への支援実績
例えば、製造業の設備投資に関する補助金を申請したい場合は、ものづくり補助金の支援実績が豊富で、製造業のクライアントを多く持つ税理士を選ぶことが望ましいでしょう。
また、補助金申請に強い税理士事務所では、中小企業診断士の資格を持つスタッフがいたり、補助金専門の部署を設けていたりする場合もあります。そのような事務所は専門性が高く、採択率も高い傾向にあります。
実績や専門分野を確認する方法としては、税理士事務所のホームページでの実績紹介を確認する、初回相談時に直接質問する、あるいは税理士紹介サービスを利用して補助金申請に強い税理士を紹介してもらうといった方法があります。
ポイント② 提示された料金体系・報酬条件で選ぶ
税理士選びでは、料金体系も重要な判断材料となります。同じサービスでも事務所によって料金設定は大きく異なるため、複数の事務所から見積もりを取り比較することが大切です。
確認すべき料金条件は以下の通りです。
- 着手金の有無と金額
- 成功報酬の率(補助金額に対する何%か)
- 追加料金が発生する条件(例:修正対応、フォローアップなど)
- 顧問契約の場合の特典や割引
例えば、「着手金10万円+成功報酬10%」と「着手金なし+成功報酬15%」では、補助金額や採択の見込みによってどちらがお得になるかが変わってきます。補助金額が大きい場合は着手金があっても成功報酬率が低い方が総額では安くなる可能性が高いです。
また、料金だけでなく、サービス内容との兼ね合いも重要です。例えば、安価ではあっても最低限の申請書作成しかサポートしない税理士と、料金は高めでも事業計画の練り直しから丁寧にサポートする税理士では、後者の方が採択される可能性は高くなるでしょう。
契約前には必ず以下の点を確認しておくことをおすすめします。
- 料金に含まれる具体的なサービス内容
- 不採択だった場合の再申請対応の有無と費用
- 支払いのタイミングと方法
- キャンセル時の取り扱い
料金体系は透明で、サービス内容と費用のバランスが取れている税理士を選ぶことが、後々のトラブル防止にもつながります。
ポイント③ 相性や対応力(コミュニケーションのしやすさ)で選ぶ
補助金申請は税理士との緊密な連携が必要なプロセスです。そのため、コミュニケーションがスムーズに取れる税理士を選ぶことが重要になります。
チェックすべきポイントは以下の通りです。
- 質問への回答が迅速かつ丁寧か
- 専門用語を分かりやすく説明してくれるか
- こちらの事業内容や状況を理解しようとする姿勢があるか
- 対応がスピーディーで約束を守るか
- 電話やメールなど希望する連絡手段に対応してくれるか
例えば、初回相談時の対応が遅い、質問に明確に答えてくれない、専門用語ばかりで理解しづらいといった場合は、実際の申請プロセスでもコミュニケーションに支障が出る可能性があります。補助金申請では締切までの限られた時間内に効率よく準備を進める必要があるため、円滑なコミュニケーションは不可欠です。
また、税理士との相性も重要です。頻繁にやり取りする中で、人間関係の相性が合わないと、ストレスや誤解が生じやすくなります。初回相談時の印象や話しやすさも、選定の重要な判断材料と言えるでしょう。
信頼できる税理士との良好な関係構築は、補助金申請の成功だけでなく、今後の事業発展にも大きく寄与します。相性や対応力を重視して、長期的なパートナーとなる税理士を選びましょう。
税理士に補助金申請を依頼する際のアドバイス

澤村 明浩
監修税理士からのワンポイントアドバイス
厳密には補助金申請のエキスパートという職種は何かしらに定まっているわけではありません。「良い補助金とかあったら教えてください。」と言われることが時々ありますが、よほど補助金関係のニュースに目を光らせていない限り、税理士がお伝えできる補助金というものはメジャーなもの限定になります。ものづくり補助金、事業再構築補助金、コロナ時であれば持続化給付金や飲食店の緊急事態宣言による休業補助金などです。補助金申請の際に税理士が思い浮かぶ方が多いのは、前述のとおり会社の財務状況を読む能力は一定程度担保されているからだと考えます。補助金が入ってきて、それを税務会計上どのように処理するか、資金繰りはどうするかなど、税務会計に繋げるのが税理士の大きな役割と考えますので、補助金のみを税理士にスポットで依頼するのは、よほどそれ専門と謳っている税理士に頼むのでない限り、再検討することをお勧めします。
まとめ:補助金活用には税理士の力を賢く借りて事業成長につなげよう
補助金は事業拡大や新規事業展開の貴重な資金源となりますが、申請の複雑さや競争の激しさから、専門家のサポートなしでは採択の可能性を高めることが難しい場合があります。税理士による申請サポートを活用することで、採択率の向上や手続きの負担軽減など、多くのメリットが得られることが分かりました。
特に重要なポイントをあらためて整理すると、以下の通りです。
1. 適切な専門家選び:
補助金の種類によって税理士か社労士かを適切に選択し、特に税理士に依頼する場合は補助金申請の実績豊富な専門家を選ぶことが大切です。
2. 早めの準備開始:
締切直前ではなく、公募前や公募開始直後から準備を始めることで、質の高い申請書作成が可能になります。
3. 顧問税理士の活用:
継続的なサポートを受けられる顧問税理士契約は、単発の申請支援だけでなく、事業全体の成長戦略にも寄与します。
4. 費用対効果の検討:
税理士に依頼する際は費用が発生しますが、採択率向上や手間削減のメリットと比較して判断することが重要です。
5. 自社の積極的な関与:
税理士任せにするのではなく、事業計画の核となる部分は自社で考え、税理士とのコミュニケーションを密に取ることが成功の鍵となります。
補助金申請はハードルが高いと感じるかもしれませんが、専門家のサポートを上手に活用することで、採択の可能性を大きく高めることができます。また、申請プロセスそのものが自社の事業を見つめ直し、成長戦略を練り直す貴重な機会にもなります。
「この補助金に挑戦してみたい」「自社の事業拡大に補助金を活用できないか」といった思いがあれば、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。当サイトの税理士紹介サービスでは、補助金申請に強い税理士を無料でご紹介しています。経験豊富な税理士コーディネーターが、お客様のご要望や状況に合わせて最適な税理士をマッチングいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

- この記事の監修者
- 澤村明浩税理士事務所
代表 澤村 明浩(税理士)
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税理士・税理士探し >
- 補助金申請は税理士に依頼すべき?メリット・デメリットと税理士選びのポイント