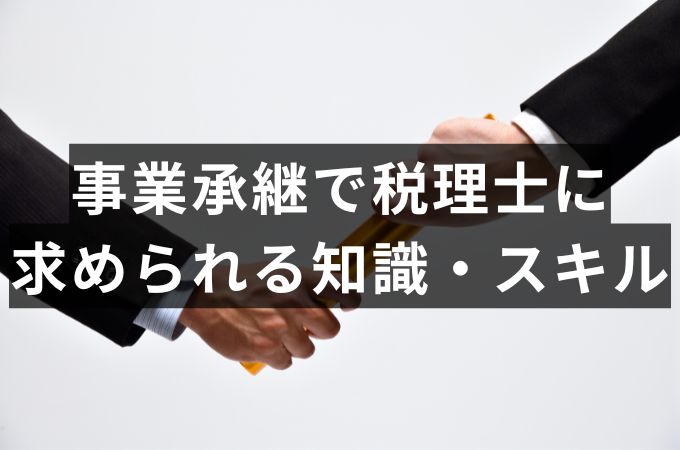介護事業に強い税理士の選び方と依頼メリットや費用相場を解説

- 最終更新日:
- 2025/09/25

- この記事の監修者
- Vmaster税理士事務所
所長 松田 光弘(税理士)
介護事業・社会福祉法人に税理士が必要な理由
介護・福祉業界の会計処理の特殊性と、専門税理士がなぜ必要なのかを解説します。一般的な税理士では対応困難な業界特有の課題と、専門家による解決策をご紹介します。
介護事業と社会福祉法人の違い・共通点のポイント
まず、介護事業と社会福祉法人の基本的な違いと、両者に共通する課題について整理します。運営形態の違いを理解することで、自社に適した税理士選びの基準が明確になります。
運営形態と適用される会計基準の違い
介護事業は株式会社・合同会社等の営利法人のほか、個人事業や医療法人、NPO等でも運営されます。営利法人等は企業会計基準、中小会計指針又は中小会計要領に則った会計処理と法人税法に基づく法人税申告が必要です。一方、社会福祉法人は非営利法人として社会福祉法人会計基準に従い、拠点区分・サービス区分による区分経理や、主要3表(資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表)に加え、注記や内訳表の作成・整合性確認も必要です。
なお、社会福祉法人は収益事業を営まない限り法人税申告は不要ですが、消費税については、非課税売上が中心でも課税仕入の取扱いや按分計算が生じ得るため、課税仕入の課税対応・非課税対応、共通対応の判定を含め仕入税額控除の適正化が重要です。
両者に共通する主要課題
両者に共通する課題として、介護報酬請求の複雑さ、処遇改善加算などの行政による金銭的支援制度、人件費比率の高さ、実地指導への対応があります。特に介護報酬制度は制度改正が頻繁で、加算・減算の計算も複雑なため、専門知識がない一般の税理士では適切な対応が困難です。最新の制度改正やDX化にも対応できる税理士を選ぶことが今後ますます重要になっています。
業界特有の複雑な会計処理の特徴
介護・福祉業界で発生する特殊な会計処理について、具体的な内容と難しさを見ていきます。一般の税理士では対応が困難な理由が掴めます。
介護事業特有の会計処理
介護事業の会計処理では、国保連への介護給付費請求とその後の入金、返戻、過誤などを会計に正しく反映すること、利用者負担金の管理、介護報酬の資金繰り予測など、一般企業にはない独特の管理が必要です。介護給付費請求データと実際の入金額の照合により、請求漏れや返戻、過誤などの早期発見に税理士が貢献できます。なお、加算の算定・請求そのものは事業者側の実務(専用ソフト等)であり、税理士は会計・財務面からの突合・検証を担います。
社会福祉法人の高度な専門性
社会福祉法人の場合、さらに高度な専門知識が求められます。収益事業・非収益事業の区分、拠点・サービス間の振替や内部取引の相殺等、区分間の整合性確保、基本金の取り扱い、充実残額の算定など、社会福祉法人会計基準特有の処理を正確に行う必要があります。また、情報開示義務や監査への対応、社会福祉充実計画の策定など、ガバナンス面での要求も厳格です。
これらの処理を介護・福祉業界に明るくない税理士に依頼すると、処理ミスや法令違反のリスクが高まり、実地指導での指摘事項増加や信頼失墜につながる可能性があります。
介護事業・社会福祉法人の会計実務で重要なポイントは?

松田 光弘
監修税理士からのワンポイントアドバイス
介護事業や社会福祉法人の会計実務で最も重要なのは、事業や拠点の区分ごとの正確な会計処理と採算管理です。介護保険収入の入金サイクルを考慮して資金繰り予測を作成したり、事業や拠点ごとの採算に注意しながらコスト管理することが不可欠となります。ミスを防止するには、請求システムと会計ソフトを連携させ、経理を効率化して月次決算を早期化することが有効でしょう。
現場で注意すべき点は、利用者様からの預り金と利用者様に対する立替金の管理、職員の処遇改善加算に関する人件費計算などが、特に煩雑になりやすいことです。これらは規程を整備し、業務管理システムを導入して、管理部署全体で確認する体制を構築することで、ミスや不正のリスクを大幅に軽減できます。
専門税理士による課題解決と経営改善の効果
専門税理士がどのような解決策を提供し、どの程度の効果が期待できるのでしょうか。
包括的な解決策の提供
介護・福祉業界に強い税理士は、これらの課題に対して包括的な解決策を提供します。会計処理の代行により経営者と管理部の事務負担を大幅に軽減し、介護給付費請求の正確な会計処理、請求データと入金額の突合確認により適正な収益計上を図ります。
経営数値の分析と改善提案
特に処遇改善加算などの各種加算制度については、加算収入が適切に会計処理されているかの確認や、経営数値への影響分析を行います。ある社会福祉法人では、処遇改善加算の適切な会計処理と突合により、年間約2,000万円規模の収入実績を適正に把握・可視化できたというケースも。
経営面では、クラウド会計システムの導入による業務効率化、補助金・助成金に関する経営数値の整備、資金調達のための事業計画書作成など、多角的な支援を提供します。また、実地指導への対応準備や法令改正情報の提供により、コンプライアンス面でのリスクも最小限に抑えることができます。実地指導は主に指定・運営・請求実務の監査であり会計監査とは軸が異なりますが、会計記録の整合性や根拠資料の整備は間接的に有効です。
介護事業・社会福祉法人に強い税理士を選ぶポイント
専門性の高い税理士を見極めるための具体的なチェックポイントは何でしょうか。業界経験、サポート範囲、コミュニケーション体制の3つの観点から選び方をご紹介します。
業界経験と専門知識の確認ポイント
税理士の専門性を見極めるために、どのような質問をすべきか、どのような実績を確認すべきかを具体的に説明します。面談時に役立つチェックリストとしてご活用ください。
実績と経験の具体的な確認事項
税理士選びで最も重要なのは、介護・福祉分野での実績と専門知識の有無です。具体的に何件の介護事業者や社会福祉法人を顧問先として持っているか、自社と同じサービス種別での経験があるかを確認しましょう。デイサービス、訪問介護、グループホーム、特別養護老人ホームなど、サービス種別により会計処理や加算の取り扱いが異なるため、同種の業態での経験は重要な判断基準です。
専門性を見極める質問例
介護報酬制度への理解度も必須確認事項です。
「社会福祉法人会計基準の特徴について説明してください」「充実残額の算定方法は?」といった具体的な質問をしてみましょう。社会福祉法人の場合は、社会福祉法人会計基準への精通度、社会福祉充実計画の策定支援経験、法人監査への対応実績も重要な判断材料となります。
サポート範囲とワンストップ対応力のポイント
税理士に求められるサービスの範囲と、一つの窓口ですべて対応してもらうメリットについて、どのような連携体制があると安心かも含めてご紹介します。
理想的なサービス範囲
介護・福祉事業の課題は多岐にわたるため、会計・税務だけでなく幅広いサポートが可能な税理士を選ぶことが重要です。基本的な税務申告・記帳代行に加え、給与計算、社会保険手続き、補助金申請に必要な経営数値の整備、資金調達のための事業計画書作成まで一つの窓口で対応できれば、業務効率が大幅に向上します。申請書類の作成・提出は、制度により行政書士・社会保険労務士等の職域となる場合があるため、必要に応じて連携します。
他専門家との連携体制
社会保険労務士、行政書士、弁護士などとのネットワークがあれば、労務トラブル、指定申請、利用者とのトラブルなど、より専門的な課題にも迅速に対応できます。また、ITツールの活用支援能力も重要で、クラウド会計システムの導入支援、介護ソフトとの連携、電子申請への対応などにより、業務のデジタル化を推進できる税理士を選ぶことで、経理業務の効率化が実現できます。
コミュニケーションと費用体系の確認ポイント
長期間の付き合いとなる税理士選びでは、コミュニケーションの質と費用の透明性が重要です。事前に確認すべきポイントを整理してお伝えします。
コミュニケーション面のチェック事項
円滑なコミュニケーションは適切な経営判断に不可欠です。専門用語を使わず平易な言葉で説明してくれるか、質問に対して丁寧に回答してくれるかを確認しましょう。レスポンスの速さも重要で、メールや電話での問い合わせに迅速に対応してくれる税理士を選ぶことで、緊急時の対応も安心です。
費用体系の透明性の確認
費用体系の透明性も重要な判断基準です。基本顧問料に何が含まれているのか、オプション料金の発生条件、決算料の設定など、詳細な料金表の提示を求めましょう。単純に料金が安いだけでなく、提供されるサービスの質と量を総合的に判断し、コストパフォーマンスの高い税理士を選ぶことが大切です。
社会福祉法人に特化した税理士サポートのポイント
社会福祉法人特有の会計基準や監査対応、経営支援について、専門税理士が提供するサービス内容を詳しく解説します。
社会福祉法人会計基準・監査対応のポイント
社会福祉法人が遵守すべき特殊な会計基準と、避けて通れない監査への対応について説明します。
特殊な会計処理への対応
社会福祉法人は一般企業とは異なる特殊な会計基準への対応が求められます。拠点区分・サービス区分による区分経理を正確に行い、主要3表(資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表)に加え、注記や内訳表の作成・整合性確認も必要です。基本金の組入れと取崩し、国庫補助金等特別積立金の処理など、専門知識なしには適切な処理が困難な業務について、専門税理士が正確な処理を実施します。
監査対応と充実残額の算定
監査対応は社会福祉法人の重要な責務の一つです。法人監査、会計監査人監査への準備と立会い、指摘事項への改善計画策定など、包括的なサポートを提供します。なお、会計監査人による監査は一定規模以上の法人が対象です(監事監査は全法人で必要)。充実残額の算定と社会福祉充実計画の策定についても、控除対象財産の適切な計上、将来必要経費の合理的な算定を行い、地域貢献事業として評価される効果的な計画策定を支援します。
経営・財務サポートと業務効率化のポイント
社会福祉法人の持続的な運営に必要な財務管理と業務効率化について、補助金活用から人材の有効活用まで、幅広いサポート内容をご紹介します。
助成金・補助金に関する経営数値の整備
社会福祉法人の持続的運営には適切な財務管理が不可欠です。助成金・補助金の活用支援では、施設整備費補助金、処遇改善加算、ICT導入支援事業補助金などの申請に必要な経営数値や資金繰り表の作成をサポートします。資金繰り管理では資金繰り表の作成とモニタリングを通じて資金ショートリスクを事前に察知し、福祉医療機構からの借入れなど、社会福祉法人特有の資金調達のための事業計画書作成についてもアドバイスを提供します。
業務効率化による成功事例
業務効率化による人材の有効活用も重要なサポート内容です。経理アウトソーシングにより職員が本来の福祉サービスに専念できる環境を整え、給与計算から社会保険手続きまでの一括委託により大幅な業務効率化を実現します。実際に複数拠点を運営する法人でクラウド会計システムを導入し、経理時間を大幅に短縮したケースもあるようです。
介護事業・社会福祉法人の税理士費用・顧問料の相場
事業形態や規模別の費用相場例と、コストを抑えるための実践的なポイントをご紹介します。
事業形態別の費用相場例
介護事業と社会福祉法人それぞれの費用相場例を、年商規模別に参考として解説します。実際の費用は地域差・事務所規模差が大きいため、予算計画の目安としてご活用ください。
介護事業の顧問料相場例
介護事業の顧問料は、業務内容の複雑さにより設定される傾向があります。以下は相場例として参考にしてください。
年商1,000万円から3,000万円未満の場合、2ヶ月に1回の訪問で月額2万円程度から、3-4ヶ月に1回の訪問で月額1万5,000円程度から、決算のみの場合は年額15万円程度からが目安となります。
年商3,000万円から5,000万円未満では、毎月訪問で月額2万5,000円程度から、年商5,000万円から1億円未満では毎月訪問で月額3万円程度からが相場例です。
社会福祉法人の顧問料相場例
社会福祉法人の場合、社会福祉法人会計基準への対応が必要なため、業務内容により料金が決まります。以下は相場例として参考にしてください。
年商1,000万円から5,000万円未満の場合、2ヶ月に1回の訪問で月額2万5,000円程度から、会計処理のみの場合は年額25万円程度からが目安となります。
年商5,000万円から1億円未満では毎月訪問で月額3万5,000円程度から、1億円以上では月額4万円から6万円程度が相場例となっています。
実際の報酬は、拠点数・サービス区分数・仕訳量・月次関与度・監査対応範囲・人件費計算の有無等で大きく変動します。
オプションサービス・費用削減のコツ
追加で発生する可能性があるオプション費用と、賢く費用を抑えるための具体的な方法をお伝えします。コストパフォーマンスを最大化するためのヒントが満載です。
追加サービスの費用相場例
記帳代行の料金は仕訳数により決まり、200枚まで月額1万5,000円程度、300枚まで2万円程度、400枚まで2万5,000円程度が相場例です。給与計算は従業員数により変動し、年末調整や各種申請に必要な経営数値の作成などの追加サービスも費用が発生します。
効果的な費用削減方法
費用を抑えるコツとして、以下の点が効果的です。
- 複数の税理士事務所から見積もりを取り、サービス内容と料金を詳細に比較
- 面談をオンライン中心にして移動コストを削減
- 領収書や請求書を整理し、オンラインで受け渡して税理士の作業時間を短縮
- 記帳は自社で行い、チェックと決算処理のみを依頼
また、自社の事業内容や取引数を明確に伝えることで、適正な見積もりを得ることができ、結果的に費用の最適化につながります。
税理士費用を抑えるには?

松田 光弘
監修税理士からのワンポイントアドバイス
税理士費用を抑える鍵は、日常のコミュニケーションと事前の準備にあります。
日々の取引は会計ソフトへ正確に入力し、証憑類も月ごとに整理して、オンラインで税理士と共有しましょう。チャットツールを導入して税理士とこまめなやり取りを行うことも有用です。
これにより、税理士の移動時間・作業時間が短縮され、結果的に費用削減に繋がります。また、給与計算や請求管理など法人内で完結できる業務と、監査対応や決算・税務申告のように専門的な判断が必要な業務とで、役割分担を明確にしておくことも重要です。
年に一度の決算だけを依頼するより、月次顧問契約を結んで日頃から情報を共有し相談できる体制を築く方が、長期的に見て効率的かつコストを抑えられることも多いでしょう。
介護事業・社会福祉法人の税理士選びでよくある質問(FAQ)
実際によく寄せられる質問と回答をまとめました。
Q. 介護事業に税理士を依頼するメリットは何ですか?
A. コンプライアンスリスクの回避と収益の適正把握が同時に実現できることです。実地指導での指摘事項を未然に防ぎ、処遇改善加算等の適切な会計処理により経営数値の正確な把握が可能になります。また、業務効率化により職員が本来の介護サービスに専念でき、タイムリーな財務・会計データに基づいた経営判断も実現できます。
Q. 社会福祉法人の税理士変更は可能ですか?
A. 適切な準備により変更可能です。期中での変更も可能ですが、決算終了後から新年度開始前がスムーズです。過去3年分の決算書や会計データのバックアップを準備し、新旧税理士間での直接やり取りにより、継続中の案件も含めて適切な引き継ぎを行うことで、業務への影響を最小限に抑えられます。
Q. 介護事業の税理士はオンライン対応していますか?
A. 多くの専門税理士がオンライン対応を行っており、全国どこからでも専門性の高いサービスを受けることができます。Web会議での画面共有による詳細説明やクラウド会計によるリアルタイム連携が可能です。ただし、実地指導立会いなど現地対応が必要な場合の出張費用については事前に確認が必要です。
Q. 社会福祉法人の補助金申請に税理士はどう関わりますか?
A. 税理士は補助金申請に必要な経営数値の作成・資金繰り表の整備で重要な役割を果たします。申請書類に必要な財務データの整理、事業計画書の数値部分の作成、採択後の実績報告に必要な会計データの準備など、数値面での包括的な支援を受けることができます。
まとめ
介護事業・社会福祉法人の経営では、業界特有の複雑な制度への対応が成功の鍵となります。適切な会計処理の実施、実地指導での指摘予防、効率的な経理体制の構築など、専門税理士のサポートにより実現できる効果は計り知れません。
税理士紹介センタービスカスでは、全国4,200所以上の登録税理士から、介護事業・社会福祉法人に特化した専門税理士を完全無料でご紹介しています。現在の顧問料が適正か知りたい、より専門的なサポートを受けたい、税理士の変更を検討しているなど、どのようなご相談でも承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。

- この記事の監修者
- Vmaster税理士事務所
所長 松田 光弘(税理士)
事務所公式ホームページはこちら
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税理士・税理士探し >
- 介護事業に強い税理士の選び方と依頼メリットや費用相場を解説