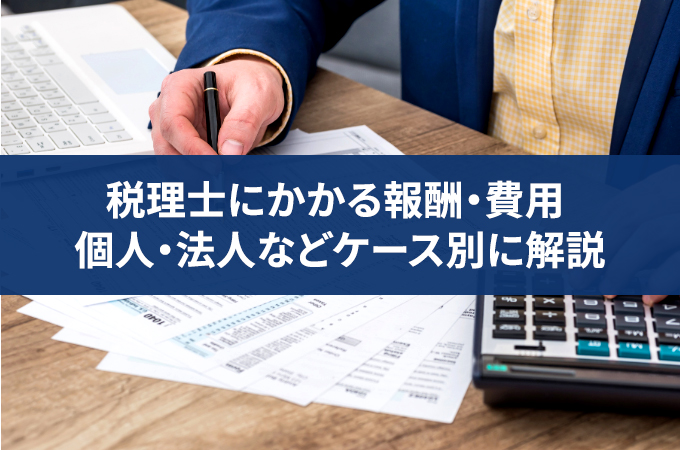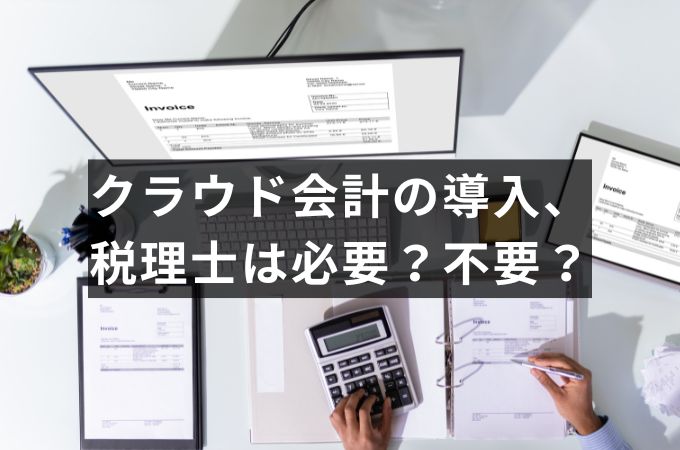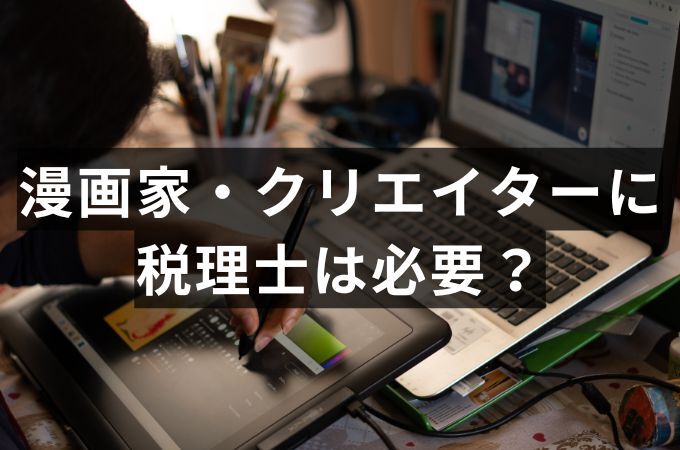管理会計とは?自社での導入方法・税理士の活用でのメリットも

- 最終更新日:
- 2025/09/25

- この記事の監修者
- 髙谷公認会計士・税理士事務所
代表 髙谷 武司(税理士・公認会計士)
管理会計とは
管理会計は、経営者や管理者が経営判断を行うために活用する会計システムです。財務会計が外部への報告を目的とするのに対し、管理会計は社内での意思決定支援に特化しています。
近年、経営環境の変化が激しくなる中で、リアルタイムな経営状況の把握と迅速な意思決定が求められるようになり、管理会計への注目度が高まっています。
管理会計の基礎知識
管理会計とは、社内の経営判断のために会計データを分析・加工して活用する手法のことです。具体的には、売上や費用を部門別・商品別・顧客別に細かく分けて集計し、「どの事業が最も利益を生んでいるか」「コストはどこで発生しているか」「投資すべき分野はどこか」といった経営上の疑問に答えます。
限界利益は売上高から変動費を差し引いた利益で、「この商品を1個追加で売ったら、いくら儲かるか」を示す指標です。例えば、1個1,000円で販売する商品の材料費が300円なら、限界利益は700円となります。
損益分岐点は売上高と費用が等しくなり、利益がゼロになる売上高のことを指します。「最低限、いくら売れば赤字にならないか」を把握できる指標で、月々の固定費が100万円、限界利益率が40%の場合、損益分岐点売上高は250万円(100万円÷0.4)となります。
変動費と固定費の区分により、売上増減が利益に与える影響を正確に把握できます。変動費は売上に比例して増減する費用(材料費、外注費など)、固定費は売上に関係なく発生する費用(家賃、人件費など)です。
これらの指標を組み合わせることで、「どの商品に注力すべきか」「新規事業に投資すべきか」といった戦略的な意思決定が可能になるのです。
財務会計との違い
管理会計と財務会計は、同じ「会計」という名前がついていますが、その目的と性質は大きく異なります。
| 項目 | 財務会計 | 管理会計 |
| 目的 | 外部報告(株主、債権者、税務署など) | 内部の意思決定支援 |
| 法的規制 | 会計基準に従う必要あり | 法的規制なし、自由に設計可能 |
| 報告時期 | 四半期・年度単位 | 日次・週次・月次など柔軟に設定 |
| 情報の性質 | 過去の実績中心 | 未来の計画・予測も含む |
| 詳細度 | 全社の概要 | 部門別・製品別・顧客別など詳細分析 |
| 成果物 | 決算書(貸借対照表、損益計算書など) | 経営分析資料、KPIレポートなど |
ある製造業の会社で、A製品とB製品を生産している場合を考えてみましょう。財務会計では「今期の売上高5億円、営業利益5,000万円」という全社の結果を報告します。
しかし管理会計では「A製品の限界利益率は35%だが、B製品は15%しかない。B製品の生産を縮小してA製品に資源を集中すべきだ」といった、より踏み込んだ分析と提案が可能になります。
また、報告のタイミングも大きく異なります。財務会計は通常、四半期や年度単位での報告ですが、管理会計は必要に応じて日次、週次、月次など柔軟に設定できます。
管理会計を導入するメリット
管理会計の導入は、単なる数字の管理にとどまらず、企業の競争力を根本から強化する戦略的な取り組みです。ここでは導入によって得られる具体的な変化と効果を見ていきましょう。
経営状態の「見える化」と課題発見
管理会計を導入する最大のメリットは、経営状態を数値で明確に把握できることです。「なんとなく儲かっている」「最近売上が落ちている気がする」といった感覚的な経営から脱却し、客観的なデータに基づいた経営判断が可能になります。
飲食店経営では、「今月は忙しかった」という感覚だけでなく、客単価の前月比、来店客数の変化、時間帯別の収益性といった詳細な分析が可能になります。これにより、どの時間帯が最も収益性が高いのか、どのメニューが利益に貢献しているのかが明確になり、具体的な改善策を立てることができます。
製造業においても同様で、従来は「売れ筋商品」として重視していた商品が、実際には材料費や製造工程の複雑さを考慮すると利益率が低い場合があります。一方で、注文量は少なくても高い技術力を要する商品の方が利益率が高いケースも珍しくありません。
KPI管理による継続的改善
管理会計導入のもう一つの大きなメリットは、重要業績評価指標(KPI)による継続的な改善活動です。売上高成長率、営業利益率、顧客獲得コストなど、自社にとって重要な指標を設定し、定期的にモニタリングすることで、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。
管理会計を始める経営者がまず取り組むべきことは?

髙谷 武司
記事監修者からのワンポイントアドバイス
管理会計を導入する経営者がまずやるべきことは、経営課題の把握と導入目的の明確化です。管理会計は、何となく導入してみても、手間ばかり掛かってしまい、経営を改善するには程遠い結果となります。そのため、商品別管理が出来ていない、原価管理が出来ていないなど、経営課題を把握したうえで、当該課題を解決するツールとして、管理会計を導入しましょう。
また、数字に苦手意識がある場合は、まずはKPIを1つか2つに絞ってみてください。それだけでも、十分に経営改善に役立ちます。さらに、社内に経理人材がいるなら、初期の段階から導入に携わってもらいましょう。そうすることで、管理会計の精度が向上するとともに、経営者は意思決定に専念できるようになります。
業績評価や部門別管理の強化
管理会計により部門別の収益性が明確になると、各部門の貢献度を正確に評価できるようになります。これまで「コストセンター」と見なされていた部門が、実際には大きな利益貢献をしているケースや、売上は高いものの利益率を考慮すると課題のある部門が見つかることがあります。
IT系企業では、エンジニア部門とセールス部門の役割分担が曖昧になりがちですが、部門別損益分析により、技術部門が開発した自社ソフトウェアの保守・サポート収入や、技術力向上による開発効率化の効果を数値化できます。結果、適切な評価制度の構築と部門間連携の改善が図れます。
小売業では、店舗別損益管理により、立地条件や商品構成の違いによる収益性の差が明確になります。売上だけでは見えない、坪効率や時間帯別収益性の違いを把握することで、出店戦略や商品配置の最適化が可能になります。
また、予算実績管理を徹底することで、計画と実績の差異原因を分析し、次期の計画策定精度も向上します。なぜ予算を達成できなかったのか、どの要因が影響したのかを明確にすることで、より実現可能性の高い計画策定が可能になります。
経営計画・資金繰りへの活用
管理会計は、将来の経営計画策定と資金繰り管理においても強力なツールとなります。過去のデータ分析に基づいた精度の高い計画立案が可能になり、資金ショートのリスクを大幅に低減できます。
急成長している企業では、売上は順調に伸びていても、売掛金の増加と在庫の積み上がりにより資金繰りが悪化するケースがあります。管理会計により、売掛金回転期間、買掛金回転期間、在庫回転期間を定期的にモニタリングすることで、運転資本の最適化を図ることができます。
特定の取引先の支払いサイトが他社より長い場合、交渉により支払い条件を改善することで、大幅な資金効率の向上が期待できます。この浮いた資金を新規事業への投資に回すことで、さらなる成長を実現することも可能です。
たとえば、製造業における設備投資の意思決定では、投資回収期間、正味現在価値(NPV)、内部収益率(IRR)を算出し、複数の投資案件を客観的に比較評価できます。従来の「勘と経験」による投資判断から脱却し、データに基づいた合理的な判断により、投資効率の向上と失敗投資の削減を実現できます。
管理会計の導入方法と実践ステップ
管理会計の導入は、企業規模や業種、経営課題によって最適なアプローチが異なります。自社で段階的に構築していく方法と、税理士などの専門家のサポートを受ける方法、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自社に最適な導入方法を選択することが成功への第一歩となります。
自社で導入する場合
自社導入は、コストを抑えながら自社のペースで進められる方法です。経営者自身が数字と向き合う覚悟を持ち、段階的にスキルを身につけていくことが重要です。
従業員20名以下の小規模企業、ITツールの活用に慣れている企業、経営者が数字に強い企業、初期コストを抑えたい企業に適しています。
導入の第一歩:現状把握から始める
まず取り組むべきは、現在の経理データの整理と分析です。過去1年分の月次試算表を並べ、売上高、売上総利益、営業利益の推移を確認します。
季節変動や特殊要因を除いた「実力値」を把握することで、改善すべきポイントが見えてきます。次に、勘定科目の見直しを行います。
「雑費」や「その他」といった曖昧な科目に多額の費用が計上されている場合は、内容を精査して適切な科目に振り分けます。これにより、どこにコストがかかっているのかが明確になります。
会計ソフト・ITツールの活用
現代の管理会計において、ITツールの活用は不可欠です。クラウド型の会計ソフトを導入すれば、リアルタイムでの数値把握が可能になります。
自動仕訳機能により、銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取り込み、仕訳を生成できます。これにより、経理作業の効率化と同時に、タイムリーな数値把握が可能になります。
部門別管理機能を活用すれば、売上や経費を部門ごとに集計し、部門別損益を自動で算出できます。予算管理機能では、年度予算を登録し、実績との比較分析が簡単に行えます。
費用相場は、クラウド型会計ソフトが月額5,000円~3万円程度、初期設定・研修費用が10~30万円程度となります。ただし、ツールに頼りすぎることは禁物です。
なぜその数字になったのかを理解し、改善策を考えるのは人間の仕事です。ツールはあくまで情報収集と集計の効率化のために活用し、分析と意思決定は経営者が主体的に行う必要があります。
段階的な導入アプローチ
管理会計を一度にすべて導入しようとすると、現場の負担が大きくなり、失敗するリスクが高まります。第1段階(1~3ヶ月)では月次決算の早期化に取り組み、翌月15日までに前月の試算表を作成する体制を整えます。
第2段階(4~6ヶ月)では部門別損益の把握を開始し、まずは大まかな部門分けから始めて徐々に細分化していきます。第3段階(7~12ヶ月)では予算管理を導入し、計画と実績の差異分析を行います。
初年度は精度よりも、PDCAサイクルを回すことを重視します。第4段階(2年目以降)では、KPI管理、原価計算の精緻化、投資評価など、より高度な管理会計手法を順次導入していきます。
税理士・会計士に依頼する場合
専門家のサポートを受けることで、導入期間の短縮と成功確率の向上が期待できます。特に中規模以上の企業や、高度な管理会計が必要な企業には専門家活用がおすすめです。
従業員20名以上の中規模企業、複数事業・複数拠点を展開する企業、早期に成果を出したい企業、社内にノウハウがない企業に適しています。
税理士と公認会計士の違い
| 項目 | 税理士 | 公認会計士 |
| 得意分野 | 中小企業の実務、税務連携 | 大企業の高度システム、内部統制 |
| 主な支援内容 | 月次決算早期化、部門別損益、資金繰り | グループ経営管理、原価計算システム、業績評価制度 |
| 費用相場 | 月額3~10万円程度 | 月額10~50万円程度 |
| 企業規模 | 中小企業に最適 | 大企業・上場企業に最適 |
なお、公認会計士は税理士登録も可能なため、両方の資格を持つ専門家も多く存在します。この場合、税務業務と監査・会計業務の両方に精通しているため、より幅広い観点から管理会計の導入支援を受けることができます。
税理士は、税務申告業務を通じて企業の財務データを熟知しており、中小企業の経営実態に精通しています。管理会計においては、月次決算の早期化支援、部門別損益の設計、経営分析レポートの作成、資金繰り表の作成支援などを得意とし、特に税務と管理会計を連携させた節税対策の提案が強みです。
公認会計士は、監査業務での経験から、内部統制や業務プロセスの改善に強みを持ちます。上場企業や大規模企業での管理会計導入、原価計算システムの構築、業績評価制度の設計などで力を発揮します。
税理士ができること
月次決算の早期化支援では、経理業務フローの見直しから始まり、締め処理の効率化、チェック体制の構築まで、トータルでサポートします。月次決算を翌月末から翌月10日に短縮することで、迅速な経営判断が可能になります。
経営分析レポートの作成では、単なる数字の羅列ではなく、経営者が理解しやすいグラフや図表を用いた分析資料を提供します。前年同期比較、予算実績比較、同業他社比較など、多角的な分析により、自社の強みと課題を明確にします。
資金繰り予測と改善提案も重要な支援内容です。3ヶ月先までの資金繰り予測を作成し、資金不足が予想される場合は、売掛金回収の促進、在庫の適正化、設備投資の延期など、具体的な改善策を提案します。
KPI設定と管理体制の構築では、業種特性を踏まえた適切なKPIを設定し、定期的なモニタリング体制を整備します。製造業なら製造原価率や不良率、小売業なら在庫回転率や坪効率など、業種に応じた指標を選定します。
どちらに依頼すべきか
売上高10億円以下の中小企業で、既に顧問契約している税理士がいる場合や、税務と連携した管理会計を求める場合、コストを抑えて導入したい場合は税理士がおすすめです。一方、売上高50億円以上の大企業や上場準備中・上場企業、複雑な組織構造を持つ企業、高度な管理会計システムが必要な場合は公認会計士が適しています。
税理士選びのポイント
管理会計の導入を成功させるには、適切な税理士選びが重要です。管理会計に強い税理士を見極めるポイントを押さえ、自社に最適なパートナーを見つけましょう。
管理会計に強い税理士の見極め方
実績と経験を確認することが第一です。同業他社での導入実績があるか、管理会計導入後の成果はどうだったか、具体的な事例を聞いてみましょう。
「売上が向上した」「資金繰りが改善した」など、定量的な成果を示せる税理士は信頼できます。提案力とコミュニケーション能力も重要です。
初回面談で、自社の課題を的確に把握し、具体的な改善提案ができるかを見極めます。専門用語を並べるのではなく、経営者の言葉で分かりやすく説明できる税理士を選びましょう。
料金は税理士事務所の規模や提供するサービス内容によって大きく異なりますが、参考として顧問料は月額3~10万円程度、管理会計導入の初期支援費用は30~100万円程度、継続的な運用支援で月額2~5万円程度のケースが見られます。ただし、これらは目安であり、実際の料金は個別に見積もりを取得して比較検討することが重要です。
相談・依頼時の準備事項
税理士に相談する際は、過去2期分の決算書、直近の試算表、売上明細(得意先別、商品別など)、組織図と部門別人員数、現在使用している会計ソフトの情報、経営上の課題や導入目的の整理といった資料を準備しておくとスムーズです。また、どこまでを自社で行い、どこから専門家に依頼するかを明確にしておくことも大切です。
すべてを丸投げするのではなく、自社でできることは自社で行い、専門的な部分のみサポートを受けるという姿勢が、コストを抑えつつ効果を最大化するポイントです。
税理士への相談前に準備しておくことは?

髙谷 武司
記事監修者からのワンポイントアドバイス
管理会計の導入や運用を税理士に相談する際は、あらかじめ自社の財務会計数値について把握しておくとスムーズです。例えば、各取引に対する会計処理は一貫しているでしょうか?管理会計のベースは、財務会計となります。そのため、ここに不安がある場合は、この点についても税理士に相談すると良いでしょう。
また、管理会計は、財務会計数値以外にも、KPIなどによって様々なデータが必要になります。そのため、営業部や製造部、総務部などからデータを収集する、全社的な取り組みとなります。さらに、KPIなどによって経営の意思決定をすることから、管理会計の導入について経営層へ事前に説明し、協力体制を整えておくことも大事になります。
まとめ
管理会計は企業の持続的成長を支える重要な仕組みです。財務会計が過去の実績報告であるのに対し、管理会計は未来に向けた意思決定を支援し、経営の「見える化」を実現します。
限界利益や損益分岐点といった基本概念の理解から始まり、部門別損益管理やKPI管理を導入することで、データに基づいた戦略的な経営が可能になります。導入方法は自社での段階的構築と税理士などの専門家活用の2つのアプローチがあります。
特に税理士は中小企業の実情を理解した現実的な支援が期待できる頼もしいパートナーです。管理会計の導入は一朝一夕にはいきませんが、月次決算の早期化から着手し、徐々に仕組みを充実させることで必ず経営改善につながります。
経営環境が激変する今こそ、管理会計を活用した科学的経営への転換を図り、自社の競争力強化に取り組んでみてはいかがでしょうか。税理士紹介センターでは、管理会計導入に強い税理士を無料でご紹介しています。
4,200所以上の登録事務所から、お客様の業種や規模、ご要望に最適な税理士をお探しします。管理会計で経営を変革したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
よくある質問
管理会計の導入費用はどれくらい?
導入費用は企業規模や導入方法によって大きく異なります。自社導入の場合、主な費用は会計ソフト費用と必要に応じた研修費用です。会計ソフトは月額数千円から数万円程度のものがあり、研修費用は10~30万円程度のケースが見られます。
税理士に依頼する場合は、初期導入支援と継続的な運用支援の費用が発生します。これらの費用は事務所やサービス内容により幅がありますが、参考として初期支援で数十万円から100万円程度、運用支援で月額数万円程度のケースがあります。
管理会計導入による効果は企業により異なりますが、営業利益率の改善や資金繰りの最適化などの成果が期待でき、適切に運用されれば導入費用を上回る効果を生む可能性があります。
管理会計はどんな会社でも必要?
すべての企業に有益ですが、導入の優先度は企業の状況により異なります。特に売上高1億円超、従業員10名以上の企業では必要性が高くなります。複数事業展開、部門分け、在庫保有といった企業でも導入効果が大きくなります。個人事業主や小規模企業でも、月次試算表の作成や資金繰り表の管理など簡易的な管理会計は実施すべきです。
管理会計を税理士に依頼するメリットは?
税務と連動した総合的な経営支援を受けられることが最大のメリットです。導入期間の短縮(自社単独の1年以上から3~6ヶ月に短縮)、客観的な分析と助言、最新事例やノウハウの活用が期待できます。顧問税理士であれば追加コストを抑えながら支援を受けられる場合もあり、費用対効果に優れています。
会計士と税理士のどちらに依頼すべき?
中小企業の場合は税理士、上場企業や大規模企業の場合は公認会計士が一般的です。税理士は中小企業の経営実態に精通し、限られた経営資源で実現可能な仕組みを提案できます。公認会計士は高度で複雑な管理会計システム構築を得意とします。最も重要なのは資格ではなく、管理会計の実務経験と自社業界への理解度です。
会計ソフトだけで管理会計は十分?
会計ソフトは重要なツールですが、それだけでは不十分です。ソフトはデータ収集と集計を効率化しますが、分析と改善策の立案は人間の仕事だからです。成功のポイントは、ソフトで効率化した時間を分析と改善活動に充てることです。また、勘定科目設定や部門区分、配賦基準など初期設定には専門知識が必要で、税理士などの専門家サポートが効果的です。

- この記事の監修者
- 髙谷公認会計士・税理士事務所
代表 髙谷 武司(税理士・公認会計士)
事務所公式ホームページはこちら
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税理士・税理士探し >
- 管理会計とは?自社での導入方法・税理士の活用でのメリットも