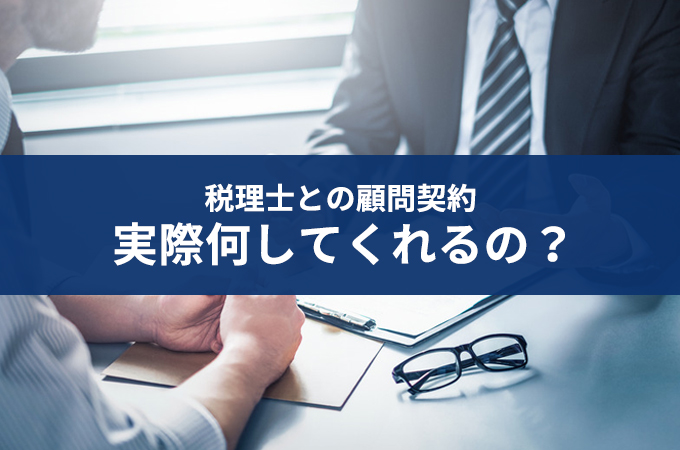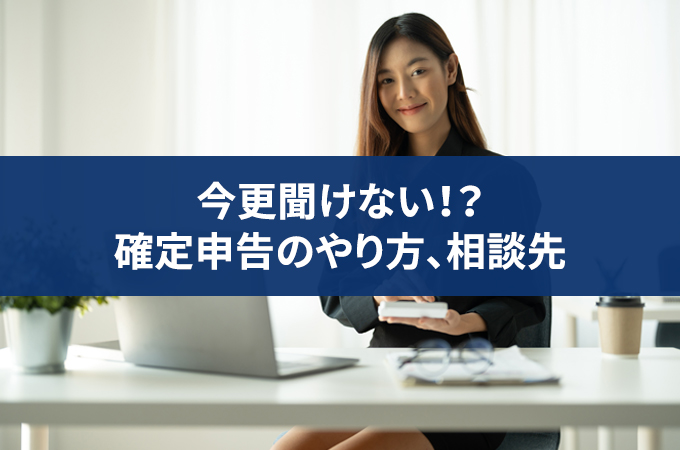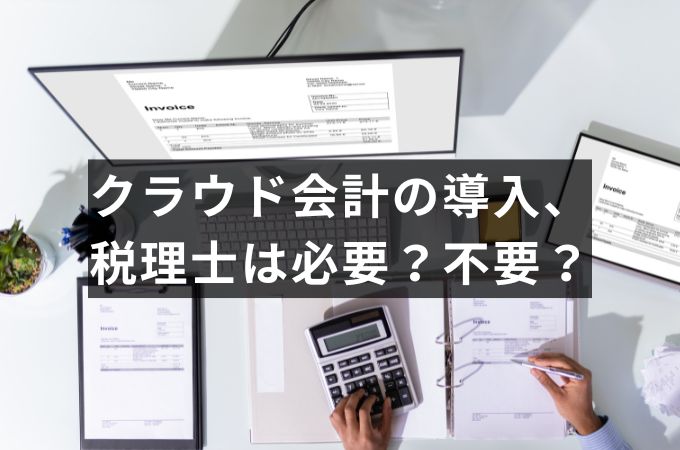税理士の顧問契約とは、月額顧問料を支払って税理士と継続的な関係を築き、記帳代行、税務申告、節税相談、経営アドバイスなどを包括的に受けられる契約です。単発のスポット契約とは異なり、事業の成長段階に応じたきめ細かいサポートが受けられる一方で、年間数十万円のコストがかかります。この記事では、顧問契約の具体的な業務内容、メリット・デメリット、契約すべきタイミングや費用相場について詳しく解説します。
目 次
あらためて「顧問税理士」とは?何をしてくれるのか?
顧問税理士が必要なのは、普通、個人や会社で事業をしている人です。特に会社を設立した場合には、多くの人が税理士と顧問契約を結ぶことになります。
では、彼らは何をしてもらっているのでしょう? 実は「みんな同じ」ではありません。会社の状況や社長の求めるものなどによって、それぞれ税理士の仕事は違います。何をどれだけやるのかで、支払う料金(税理士顧問料)も違ってきます。
税理士の仕事内容とは
そもそも税理士法には、その「独占業務」として、次の3つが定められています。
- 税務代理
- 税務署書類の作成
- 税務相談
税理士としての登録を受けない限り、これらを他人に対して行うことはできません。
1.税務代理
税務代理とは、税理士が納税者に代わって所得税や法人税・相続税の申告等、税に関するあらゆる手続きを行う業務のことです。以下のようなものが税務代理業務にあたります。
- ・所得税、法人税などの各種税目の確定申告
- ・青色申告承認申請などの各種届出、申請
- ・税務調査の立会い
- ・税務署の更生・決定に対する不服申し立て
2.税務署書類の作成
税務署等へ申告・提出するための書類の作成も税理士の仕事です。税務署類とは例えば以下のようなものを指します。
- ・所得税、法人税などの確定申告書
- ・青色申告承認申請書などの各届出書類、申請書類
- ・決算書・中間決算書
- ・相続税申告書
- ・源泉所得税の納付書
- ・年末調整、源泉徴収票
- ・法定調書、償却資産税申告書
なお、税理士に作成依頼した書類のうち、税務署などに提出する必要性がある書類については、作成者である税理士が納税者に代わって提出を行います。
3.税務相談
税理士法によると「税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること」とされています。具体的には節税対策や納税に関する相談を受けて、適切なアドバイスを行うことです。
税理士の仕事は、当然、「税務」が中心になります。
ただ、ひとくちに「税務相談」と言っても、その中身は多岐にわたります。
顧問税理士は、会社の状況を客観的にとらえたうえで、他の顧問先の経験なども踏まえた経営面でのアドバイスを提供することもできるわけです。
この他、経理代行・記帳代行業務や給与計算業務、税務や経営に関するコンサルティング業務等も税理士に依頼することが可能です。これらは税理士の独占業務ではありませんが、専門知識を持つ顧問税理士にあわせて依頼することが多いです。
税理士と公認会計士の役割の違いは
税理士と同様に税務・会計業務を中心として行う職業に公認会計士があります。どちらも日本の国家資格で混同されやすいですが、いったい何が違うのでしょうか?税理士と公認会計士の役割の違いについて説明します。
社会的役割の違い
税理士と公認会計士の大きな違いは、それぞれの独占業務の内容です。税理士の3つの独占業務については先述しましたが、これに対して公認会計士法で定められる公認会計士の独占業務には「会計監査」があります。税務のエキスパートである税理士に対し、公認会計士は会計監査のエキスパートであるといえます。
「会計監査」とは、企業の成績表といわれる財務諸表が適正に作成されているかどうかを第三者の立場からチェックする業務のことです。金融機関や投資家が融資・投資の判断を行うために必要な指標となります。監査を受ける義務があるのは大会社(資本金5億円以上、または負債が200億以上の会社)等のため、主なクライアントは上場企業を中心とした大企業となるという点も、法人・個人を問わず税金を納める必要のある方すべてがクライアントとなる税理士と異なるところです。
どちらに依頼するのがよいか?
公認会計士は、税理士登録をすることで税務業務を行うことも認められていますので、税理士の登録を受けている公認会計士であれば税理士としての税務業務も行うことが可能です。では、顧問契約をする際はどちらに依頼するのがよいのでしょうか?
税理士は監査業務を行うことができないため、上場企業や上場を目指している場合には公認会計士へ監査を依頼する必要があります。ただし、中小企業の場合は公認会計士による監査を受ける必要がほとんどないので、あまり意識する必要はないでしょう。
一般的に税理士の方が税務に関する経験や知識が豊富であるといわれています。
中小企業や個人事業主が節税相談や税務処理を依頼したい場合には、税務のエキスパートである税理士が強い味方になってくれるかもしれません。
もちろん、税理士も公認会計士も個人・事務所によって得意分野に違いがありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
顧問契約とスポット契約の違い
税理士との契約形態には大きく分けて「顧問契約」と「スポット契約」の2種類があります。それぞれの契約形態には独自のメリットとデメリットが存在し、事業の規模やフェーズによって最適な選択が異なります。
顧問契約の特徴
顧問契約は、税理士と継続的な契約を結び、定期的にサポートを受ける契約形態です。月額の顧問料を支払うことで、税務・会計に関する包括的なサポートを受けられます。
顧問契約では、税理士が会社のパートナーとして長期的に関わるため、事業の成長段階に応じたきめ細かなサポートが期待できます。毎月の訪問や定期的な打ち合わせを通じて、会社の状況を深く理解した上でのアドバイスを受けることができるのが大きな特徴です。
スポット契約の特徴
スポット契約は、確定申告や相続税申告など、特定の業務を単発で依頼する契約形態です。必要な時にだけ税理士のサービスを利用できるため、コストを抑えられます。
スポット契約では、その都度必要な業務のみを依頼するため、柔軟性が高く、複数の税理士の中から案件に最適な専門家を選ぶことも可能です。ただし、短期間の関係となるため、会社の詳細な状況把握には限界があります。
どちらを選ぶべきか?選び方のポイント
顧問契約とスポット契約のどちらを選ぶかは、以下のポイントを考慮して決めましょう。
顧問契約が向いているケース
- ・年商が1,000万円を超えている
- ・法人を設立している、または設立予定
- ・従業員を雇用している
- ・複雑な税務処理が必要
- ・経営アドバイスを定期的に受けたい
- ・税務調査のリスクに備えたい
スポット契約が向いているケース
- ・個人事業主で比較的シンプルな税務処理
- ・自分で経理業務を行える
- ・コストを最小限に抑えたい
- ・相続税申告など特定の業務のみ依頼したい
事業の成長段階に応じて、スポット契約から顧問契約へと移行することも可能です。まずは自社の現状と将来の計画を考慮して、最適な契約形態を選択しましょう。
税理士と顧問契約を結ぶ4つのメリット
顧問税理士をつけると様々なメリットが考えられますが、ここでは下記の4点にまとめて解説していきます。
- ・「会社のお金」についての適切なアドバイスが受けられて、節税も実現できる
- ・煩雑な経理・税務申告業務などから解放されて、経営に専念できる
- ・対外的な信用度が高まる
- ・税務調査にも安心して臨むことができる
「会社のお金」についての適切なアドバイスが受けられて、節税も実現できる
事業を安定的に進めていくためには、毎年確実に手元に資金を残し、増やしていくことが大事です。「お金のプロ」である税理士からそのためのサポートを受けられるのは、大きなメリットです。税理士に決算書を見てもらい、収益性や安定性を客観的な目線からアドバイスをもらい、一緒に組み立てていくことができます。
また、対象となることを知らず節税できたはずなのに見逃した、反対に「やりすぎ」・「対象とならないものを含めた」ことによって、追徴課税(※1)を課せられた、といったリスクを回避できるのも、大きなメリットと言えます。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 申告のみを税理士に依頼するスポットでは短期間のお付き合いですので、会社の実状・構想の把握には限界があります。顧問契約により定期的・長期におよぶ依頼者と税理士の携わりをもって、一生涯に渡る適切なアドバイスを受けることが可能となります。
- フジハラ税理士社労士事務所
代表 藤原宗和
煩雑な経理・税務申告業務などから解放されて、経営に専念できる
特に個人事業や小規模の会社の場合、帳簿付けなども含めて税務に関する作業を税理士に「丸投げ」すれば、そのために費やしていた時間やエネルギーを100%仕事に振ることができるでしょう。経理担当者を置かずに済み、その分のコストを削減することも可能になります。
対外的な信用度が高まる
顧問税理士が付いていれば、財務状況についての金融機関や取引先の信用度は高まります。税務の専門ではない個人が税務申告した書類と、税理士が作成したことを証する税理士の署名が付されている申告書類とでは、税務署の印象も変わるでしょう。
税務調査にも安心して臨むことができる
申告内容について疑問がある場合、税務署は任意で調査に入ることがあります。
顧問税理士がいる場合、調査の連絡はまずその税理士に入ります。
事前の書類の準備や調査当日の立ち合いなども頼めるため、心理的負担から解放され、税務署に言われたままを認めてしまい税金を納め過ぎるといった事態も回避できます。
税務調査にスポットで対応してくれる事務所もありますが、「自分のことをよく知ってくれている」税理士ならば、より心強いのではないでしょうか。
税理士と顧問契約を結ぶデメリットはコスト(顧問料)
一方、デメリットもあります。ズバリ、コストがかかることです。
顧問契約を結ぶ場合、税務申告に関わる報酬とは別に、月額の顧問料を支払わなくてはなりません。顧問料は売上規模や事業所への訪問回数、作業量、事務所の定めるオプションの利用などによって違ってきますが、おおむね法人で月額30,000円~、個人の場合は15,000~30,000円程度が相場となっています。年間にすればけっこうな出費になります。顧問契約を行うか、契約した場合にどこまで頼むのかは、今説明したメリットとの見合いで考えていく必要があるでしょう。
税理士との顧問契約を結ぶタイミング
税理士との顧問契約を結ぶ代表的なタイミングとして、次の4つが挙げられます。
個人事業主から法人成りする時
「法人成り」とは、個人事業主が会社を立ち上げ、個人事業主のころから行ってきた事業を継続することです。
個人事業主と法人では、適用される税法から申告書の作成内容まで大きく異なります。一般的に、個人事業よりも法人の方が経理作業は複雑になるほか、法人税の計算や申告書の作成も、税法の知識がないと簡単にはできなくなります。
個人事業主では自力で申告書の作成や経理作業ができていたとしても、法人では難しいでしょう。
また、節税対策についても、法人では適切な効果を得るためには決算前だけではなく、個人事業主以上に普段から取り組む必要があります。
そのため、個人事業主から法人成りするタイミングで、税理士と顧問契約を結ぶことが多いです。
事業規模の拡大に伴う経理・税務の負担増加時
事業規模が拡大すると、作業量が多くなるので経理作業や税務が煩雑になります。事業規模の拡大が続けば、どこかで経営者や経理担当者だけでは事務作業が追い付かなくなり、間違いが起こる可能性が高いです。
そこで、負担が増加し事務作業が追い付かなくなる前に税理士と顧問契約を結べば、経理や税務などの正確性が担保されます。
また、自社で経理作業や税務を行っていたリソースを新規展開する事業などに充てることもできるので、会社の成長にもつながります。
融資や助成金申請に伴う財務書類の作成が必要な場合
事業を続けていく中では、融資や助成金などを利用する場面が出てきます。しかし、融資や助成金などを申し込む際には、様々な書類が必要となり、財務や経営の状況、資金繰りの計画など財務に関係する書類も少なくありません。
審査に通るための財務書類の作成には、会社の財務や経営の状況に詳しい専門家の助けが必要です。そこで、融資や助成金申請に伴う財務書類の作成が必要なタイミングで税理士と顧問契約を結ぶことも多いです。
税務調査の通知を受けたときに備えるための契約
税務署から税務調査の通知を受けた時も、税理士と顧問契約を結ぶタイミングのひとつです。
税理士には、税務調査の立ち合いのみを依頼することもできますが、それでは一般的な税務調査の対応になってしまい、自社の状況に応じた対応をすることができません。税理士と顧問契約を結ぶことで会社のことを良く知ってもらえ、より適切な税務調査対策が可能となります。
顧問契約を結ぶ時の注意点
顧問契約を結ぶにあたり、次の3点に注意しましょう。
請け負ってくれる仕事内容を確認する
まず、税理士に確認しておくべき事項として、どんな仕事を依頼できるのかということです。税理士は顧客の税務代理や税務書類作成を行いますが、そこに至るまでには記帳や月次決算の書類作成など、さまざまな経理業務が必要です。また、事業を営んでいると、資金繰りを考えたり、金融機関に融資を申し込んだりする局面があります。事業を進めるうえで直面するさまざまな業務について、どこまでお願いするのか税理士と相談しながら決めましょう。たとえば、日々の記帳業務から決算業務まで依頼することもできますし、会計ソフトを導入している会社なら決算・申告業務だけを依頼してもよいでしょう。
顧問料を確認する(別料金になる仕事内容も確認する)
顧問契約をする前に、かならず顧問料は確認しましょう。上述したように、顧問料に相場はありますが、業界全体の規程などはないため、各税理士が自由に設定しています。後で述べますが、月額の顧問料と各種業務に関するオプション料金という料金体系をとっている税理士が多く、顧問契約を結んでどのような業務を依頼するかによって、支払う報酬は変動します。顧問料の中にどのような業務を含むかも、税理士によって異なります。また、税理士は顧問先の年商も考慮して報酬を算出するので、依頼する業務と発生する料金について、自社のケースならどれぐらいかかるか、税理士と話を詰めておきましょう。
税理士との契約書の内容を確認する
顧問契約を結ぶと、業務契約書を取り交わすこととなります。委任する業務の内容や報酬額、契約期間について確認しておきましょう。契約期間については、契約更新の取り決めもチェックしましょう。
顧問契約に必要な費用感
税理士と顧問契約を結ぶ場合は、顧問料が発生します。税理士顧問料は、法人か個人事業主か、また事業規模、業種・業態、依頼する業務の範囲や訪問の回数、相談の頻度等によって決定・変動します。
一般的な税理士顧問料の相場としては法人で月額30,000円~が目安とされています。加えて、「記帳代行」や「給与計算」「年末調整」業務は、通常の顧問業務とは別にオプションとして提供されることが多く、基本の顧問料にこれらのオプション費用を追加した金額が、税理士へ月々支払う顧問料の金額になります。また、決算時には別途決算料が発生します。決算料は月額顧問料の約4~6カ月分が一般的といわれており、年額100,000円~が相場といわれています。
また、消費税の申告については決算料とは別で年額30,000円~が相場でしょう。
事業の売上が大きくなれば取引数も多くなり、税理士の業務量や責任も大きくなるため顧問料も高くなる傾向がありますし、さまざまなオプションを追加すればその分顧問料も高額になります。料金設定は事務所によって異なりますので、比較・検討してみることをおすすめします。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 顧問料をはじめ税理士報酬料金については、ホームページに記載されていることも多いので確認してみましょう。なお、料金の安さばかりを重視してしまいますと、きめ細やかなサービスやアドバイスについて期待できない場合があります。
- フジハラ税理士社労士事務所
代表 藤原宗和
個人事業主は税理士と顧問契約をすべき?
個人事業主の場合、経費処理もシンプルなケースも多く、顧問税理士が必要かどうか迷う方も多いでしょう。決して安くはない顧問料が財務を圧迫してしまうのでは本末転倒ですから、そこは慎重に検討しなければなりません。
頼む必要の無いケース・必要のあるケース
あえて顧問税理士が必要の無いケースから述べれば、それは「売上規模がまだ小さく、事業主に会計、経理に関するスキルが、ある程度はある」状況と言えるでしょうか。売上が小さければ、申告に必要な作業の一定部分は自分で対応出来るからです。
しかし、事業規模が大きくなって、そうした作業に手足を取られるような段階になった場合には、思い切って顧問契約に踏み切ったほうがよいかもしれません。
顧問税理士をつける売上の目安は1,000万円
もちろん業種や事業の状態などによって異なりますが、顧問税理士を頼む売上規模の1つの目安は、1,000万円と言われています。ちなみにこれは、個人から法人に切り替えるべきタイミングでもあるのです(※2)。
税理士事務所と税理士法人の違いとは
税理士法人と税理士事務所は何が違うの?と疑問を持たれる方も多いかと思いますが、業務内容に違いはありません。税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つの独占業務がメインになります。
| 税理士事務所 | 税理士法人 | |
| 形態 | 個人事業主 | 法人 |
| 有資格者数 | 代表が税理士なら開業可能 | 2名以上の税理士の所属が必要 |
| 支店 | 支店展開できない | 支店展開できる |
| 代表が業務を行えなくなった場合 | 事務所を閉鎖(サービス停止) | 組織運営は継続できる |
税理士事務所と税理士法人の違いは、「個人事業主」か「法人」か、という点です。
税理士事務所は、税理士が「個人事業主」として運営しています。一方、税理士法人は税理士法に基づき2名以上の税理士を社員として共同で設立した「法人」です。税理士法人は会社として組織化されており、支店を展開することが可能です。
そのため、一般的に事務所としての規模が大きくなる傾向にあります。
ちなみに税理士事務所と会計事務所の違いに関しては、名称(呼び方)の違いのみで、この両社について組織形態や仕事内容に特別な違いはありません。
税理士事務所の通称が会計事務所であると考えてよいでしょう。
税理士事務所と税理士法人、どちらに顧問を依頼すべきか?
前述したように、税理士事務所と税理士法人も税理士の行う業務内容に大きな違いはありません。
税理士事務所は税理士が1人で運営している場合も多く、そのような事務所であれば所長である税理士に直接対応してもらえます。同じ「経営者」としての目線からアドバイスがもらえたり、意思決定が早いというメリットがあります。また、比較的料金に柔軟性がある場合も多いといえます。
その一方で、税理士が事故や病気・高齢になった等の理由で業務が行えなくなった場合にサービスが停止してしまうという点や、税理士が1人で対応できるサービスの範囲には限界がある、という点はデメリットとして考慮しておくとよいでしょう。
税理士法人に依頼する際のメリットとしては、税理士が複数名在籍しているため、不測の事態が発生しても組織としてカバーできる体制が整っているという安心感があります。また、税理士法人にはさまざまなスキル・経験を持った税理士・スタッフが在籍しているので、複雑な案件等多様なケースに対応することが可能です。
一方で、税理士に直接対応してもらえない可能性がある点や、個人で運営する税理士事務所に比べて意思決定に時間がかかる点はデメリットとなる場合があります。
どちらもメリット・デメリットがあり、各事務所によっても得意分野が異なるので、自社の状況やニーズにあった事務所を選ぶことが一番大切です。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 職員を雇用している税理士事務所も多く、その場合はサービスの範囲が広い反面、所長税理士ではない職員が担当者となる可能性が高いです。また、税理士法人には社員税理士2名だけの組織もあります。契約前にホームページなどで職員数を確認することも大切と言えるでしょう。
- フジハラ税理士社労士事務所
代表 藤原宗和
税理士と顧問契約を結ぶまでの流れ
では、実際に税理士と顧問契約を結ぶ場合はどのような手順で進めるのでしょうか?せっかく顧問契約を結ぶのであれば、能力はもちろん人柄なども含めて、それにふさわしい税理士に出会いたいものです。チェックしておくべきポイントもあわせてご紹介します。
1.要望を整理して税理士を探す
税理士と顧問契約を結ぶ前にまず、税理士にどんな業務を依頼したいのか、その目的と内容を明確にしておきましょう。「帳簿付けから丸ごとすべてをお任せしたい」「節税対策のアドバイスが欲しい」「法人化を検討している」…など事業の規模や状況によってそれぞれ異なります。税理士にサポートを頼みたいポイントをまとめておくと探しやすくなります。
税理士によって、経験や得意分野は異なるので、自社の規模や業種・要望にマッチする税理士を探す必要があります。インターネットで検索する・知り合いに紹介してもらう・近所の税理士に問い合わせる…など探し方もいくつか方法がありますが、自社にとっての「よい税理士」とはどのような税理士なのか…迷ったら、税理士紹介サイトを活用するのも1つの方法です。
2.税理士と面談をする
顧問契約したい税理士が見つかったら面談を行います。この面談の際に疑問点などをクリアにしておくことが大切です。以下のようなポイントを抑えておきましょう。
- ●依頼できる業務内容・範囲
- ●打ち合わせ・訪問頻度
- ●顧問料が適正かどうか
- ●オプション業務の内容や価格
- ●自社の業界への理解があるか
- ●コミュニケーションツール(手段)
- ●人柄や相性面 など
基本契約でどこまでフォローしてもらえるのか?オプション業務の料金はどのくらいか?もし年度の途中で解約したら、違約金は発生するのか?なども含めて、きちんと詰めておきましょう。もちろん、条件面だけではなく相性がよいかどうかも面談で見極めましょう。経営のパートナーとしてコミュニケーションがとりやすかったり、相談がしやすく、税理士だからといった高圧的な態度ではなく、丁寧に返答してもらえたりする相手かどうかも顧問税理士を選ぶ際のひとつの指標となります。
3.税理士報酬の見積書を取る
面談が終わったら、見積もりや具体的な業務内容を提示してもらうことができます。面談時に相談した内容が反映されているか見積書を確認し、業務内容を追加・変更したい場合や、税理士報酬が高いと感じる場合などは交渉をしましょう。
双方が納得出来たら契約へ進みます。
4.顧問契約を交わす
いよいよ顧問契約を結びます。顧問契約書を交わしましょう。
顧問契約書の書式に特に決まりはありませんが、おもに以下のような内容を記載します。
- ●税理士へ依頼できる業務内容
- ●税理士顧問料と支払方法
- ●オプション業務の料金
- ●契約期間と解除方法 など
税理士に顧問業務を依頼する際、契約書を交わさず口頭で依頼を行うケースも存在します。しかし、契約内容が曖昧になることで後々トラブルに結びつく可能性があります。トラブルを回避するためにも顧問契約書を交わすことをおすすめします。
1.顧問税理士を変更するタイミングを決める
顧問税理士を切り替える時期を決めるにあたり、まずは現・顧問税理士との契約書を確認しておきましょう。契約書には契約を解除する際の取り決めが書かれており「●カ月か月前までに解除の申し出がない場合は自動更新」などと書かれていることもあります。契約書で定められた期間以外の解除には、違約金が発生する場合もあるので、注意しましょう。
契約書の内容を踏まえ、現・顧問税理士との契約終了日や、新たな税理士との顧問契約開始日を決めます。顧問税理士を切り替えるタイミングとしては、下記のいずれかが最適です。
- 現・顧問税理士との契約終了日にあわせて新しい税理士と契約開始
- 法人税申告書の提出後、または修正申告終了後
- 税務調査完了後
2.現・顧問税理士に契約解除を告知する
契約内容に従い、現・顧問税理士に契約解除を伝えます。
この際、顧問税理士の心証を悪くしないように配慮が必要です。預けていた書類やデータを返却してもらい、新しい税理士に引き継がなくてはならないからです。
「大口の取引先からの紹介で」など、やむを得ず解除することに理解してもらうよう求め、今までのサポートに感謝する気持ちを忘れずに伝えましょう。
3. 現・顧問税理士から必要なデータ・書類を回収する
決算書や総勘定元帳、仕訳帳、登記簿謄本、定款など、現・顧問税理士に預けている資料やデータ・書類を返却してもらいます。
返却してもらったデータや書類は、新しい税理士へ引き継ぎます。
4. 新しい顧問税理士を探して契約する
現・顧問との契約期間が終了するまでに、新しい顧問税理士を探して契約します。
顧問税理士がいない期間が生じないようにするには、現・顧問税理士との契約解除を決断した直後から新しい税理士探しを始める必要があります。
まとめ
事業展開を、数字の面でフォローしてくれる顧問税理ですが、「誰でもよい」というものではありません。自分のニーズを明確にして、それに応えられる人を選ぶことが、なにより大事になります。
記事監修者 藤原税理士からのワンポイントアドバイス
申告を大前提に、そのうえで料金も控えめに、という条件ではスポット依頼が最適ではありますが、事業経営はその場限りというわけではありません。
末永く多角的にサポートをしてくれる顧問税理士の存在は欠かせません。
また、事業経営に専念できるようにお手伝いしてくれる存在という観点においては、営業や組織作りでもっとも慌ただしくなる起業初期でこそ、結果的に顧問税理士が居てくれたのでスムーズにスタートできた、という経営者の声は多く、特に法人の設立時はその設立よりも前の段階から顧問税理士を探しておくことが大切でしょう。
顧問税理士は依頼者の財産状況から個人的な事情なども詳細に知り得る、士業のなかでも飛びぬけて依頼者と関わる深い存在です。一生涯のお付き合いとなることも多いので、顧問税理士の選択は慎重な判断が求められます。
近年はホームページで詳しい案内がある税理士事務所も多くなりましたが、特に比較・検討を行うためには税理士紹介サービスなども利用して、自らに最適な条件の税理士を探してもらうことも良いでしょう。
よくある質問(FAQ)
顧問契約とスポット契約の違いは何ですか?
顧問契約は月額顧問料を支払って継続的にサポートを受ける契約形態で、記帳代行から経営相談まで包括的なサービスが受けられます。一方、スポット契約は確定申告など特定の業務を単発で依頼する契約形態で、コストを抑えられますが継続的なサポートは受けられません。
顧問契約の料金相場はどれくらいですか?追加料金は発生しますか?
法人の場合、月額顧問料は30,000円~が相場です。個人事業主の場合は15,000~30,000円程度です。決算料(年額100,000円~)や記帳代行、給与計算、年末調整などはオプション料金として別途発生することが多いです。
どのタイミングで税理士と顧問契約を結ぶべきですか?
主なタイミングは、①個人事業主から法人成りする時、②事業規模の拡大に伴う経理・税務の負担増加時、③融資や助成金申請に伴う財務書類の作成が必要な場合、④税務調査の通知を受けた時です。売上1,000万円が一つの目安とされています。
顧問契約でどこまでの業務を依頼できますか?
税理士の独占業務(税務代理、税務書類作成、税務相談)に加えて、記帳代行、給与計算、年末調整、経営相談などが依頼できます。基本の顧問料に含まれる業務範囲は税理士によって異なるため、契約前に確認することが重要です。
顧問契約を結ぶ際に注意すべき点は?
①請け負ってくれる仕事内容の確認、②顧問料と別料金になる業務の確認、③契約書の内容確認が重要です。特に、基本料金に含まれる業務範囲、オプション料金の詳細、契約期間や解除方法について事前に明確にしておきましょう。
顧問税理士は変更できますか?変更時の注意点は?
顧問税理士の変更は可能です。まず現在の契約書で解除の取り決めを確認し、適切なタイミング(契約終了日、申告書提出後、税務調査完了後など)で変更しましょう。預けている書類やデータの返却を受け、新しい税理士への引き継ぎを円滑に行うことが重要です。
個人事業主でも顧問契約は必要ですか?
個人事業主の場合、売上規模や事業主の会計スキルによって判断が分かれます。売上1,000万円が一つの目安とされており、事業規模が大きくなって経理・税務作業に手足を取られるようになった場合は、顧問契約を検討する価値があります。
顧問契約の解約・解除はどうすればいいですか?違約金は発生しますか?
契約書に記載された解除条件に従って手続きを行います。多くの場合、数カ月前の事前通知が必要です。契約書で定められた期間以外の解除には違約金が発生する場合があるため、契約前に解除条件を確認しておくことが重要です。