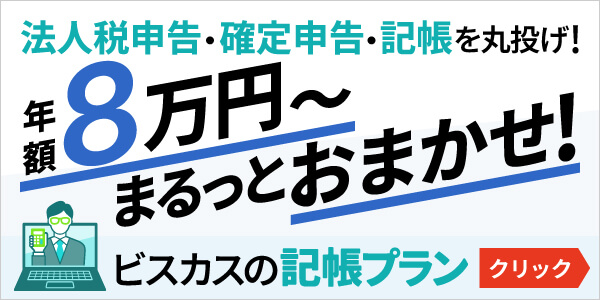記帳代行は税理士に依頼すべき?メリット・費用・選び方を徹底解説
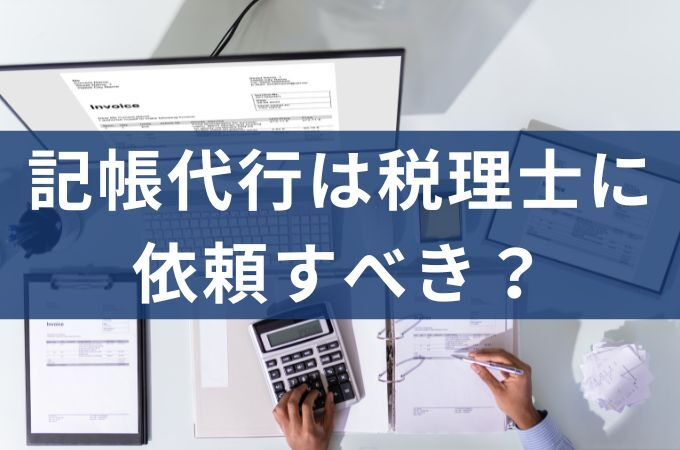

- この記事の監修者
- 髙谷公認会計士・税理士事務所
代表 髙谷 武司(税理士・公認会計士)
記帳代行とは?税理士に依頼するポイント
記帳代行とは税務申告に必要な帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)の作成を外部に委託するサービスで、税理士に依頼すれば記帳から税務申告、経営相談まで一貫したサポートが受けられます。記帳代行と経理代行の違い、税理士に依頼するメリット・デメリットを理解することで、自社に最適な選択肢が見えてきます。
記帳代行とは?
記帳代行とは、税務申告に必要な帳簿作成を、税理士などに委託するサービスのことです。もともと「記帳」とは、売上や経費などの取引を正しく仕訳し、帳簿に記録する作業を指します。
実際には税務申告や決算業務などと一体化していることが多いため、「税理士に丸投げしている」という言い方をされるケースも少なくありません。ただし、一口に「丸投げ」と言っても、日々の現金取引を記録する「現金出納帳」だけは自分(自社)でつけてそれ以外をすべて専門家に任せる場合と、現金出納帳の作成も含めて完全にお任せする場合があります。
記帳代行と経理代行の違い
記帳代行と似たサービスに「経理代行」がありますが、両者には明確な違いがあります。
「記帳代行」は仕訳入力〜帳簿作成を外部委託するサービスです。
「経理代行」は、記帳に加え、請求書発行・入金管理・支払処理・給与計算など経理全般を含みます。
いわゆる「丸投げ」は俗称で、記帳のみ〜決算・申告までの範囲設定は契約次第です(現金出納帳を自社で持つかどうかも個別合意)。
どんな企業に向いているか
どちらが向いているかは事業規模や状況によって異なります。小規模事業で記帳だけを外注したい場合は記帳代行が適しており、中規模以上で経理業務全体の負担を減らしたい場合は経理代行が選択肢となります。
記帳代行が必要な理由として、事業を行う以上は帳簿の作成が「義務」であることが挙げられます。2014年以降は白色申告でも記帳や帳簿の保存が義務化され、青色申告は複式簿記による記帳が必要な反面、最大65万円の特別控除など節税メリットが大きいのが特徴です。そこで、手間のかかる記帳業務を外注してしまい、本業に集中するために記帳代行を活用する事業者が増えています。
記帳代行を依頼するメリット・デメリット
記帳代行を外部に委託することで本業への集中や人件費削減が実現できますが、社内にノウハウが蓄積されにくい、リアルタイム性が低下するといった課題もあります。メリットとデメリットの両面を理解した上で判断しましょう。
記帳代行のメリット
本業に集中できることが最大のメリットです。記帳作業は直接的に利益を生むわけではないものの、時間と手間がかかるため大きな負担となりがちです。税理士に任せれば、貴重なリソースを本業に専念させることができます。
人件費削減になる点も見逃せません。業務拡大に伴い、伝票処理や仕訳計上などの事務負担が増えると、社内で新たに経理担当を雇う必要が出てくるケースもあります。しかし、記帳代行を利用すれば、追加採用せずに現行人員で経理を回せるため、人件費の大幅な増加を抑えられる可能性があります。
記帳の品質が上がることも重要です。税理士は会計・経理の専門家ですから、取引内容を確認しながら的確な仕訳を行ってくれます。インボイス制度や改正電子帳簿保存法など、法改正にも柔軟に対応してくれるため、記帳の品質を常に高いレベルで維持できます。
不正防止やガバナンス強化の効果もあります。第三者が記帳を担当することで、内部での不正や横領を抑止する牽制効果が働きます。
記帳代行のデメリット
社内にノウハウが蓄積されにくい点は長期的な課題です。将来的に内製化を考えている場合、外部委託期間が長いほど移行が困難になります。
リアルタイムで数字を把握しづらいことも注意が必要です。会計事務所が仕訳・試算表をまとめるのに2〜3か月かかることもあり、その間に経営環境が変化してしまうと、タイムリーな判断が難しくなるでしょう。
どこまで外注し、どこを自分たちで行うかを事前にしっかりと整理し、税理士とコミュニケーションを取ることが重要です。
税理士に依頼するメリット・デメリット
税理士に記帳代行を依頼すれば、記帳から税務申告、経営相談までワンストップで対応してもらえる一方、費用は記帳代行業者より高めになります。税理士ならではの付加価値を理解し、費用対効果を見極めることが重要です。
税理士に依頼するメリット
税務のプロとしてワンストップ対応できる点が最大の強みです。税理士は記帳代行に加えて、確定申告や決算書類の作成・提出まで一括で依頼できる税務のプロフェッショナルです。「税理士には税務代理権がある」ため、税務署への申告や複雑な税法上の手続きも任せられます。個人事業主の青色申告であれば、記帳から節税対策までカバーできるので、65万円の特別控除などによる大きな減税効果を得られる可能性も高まります。
税務調査の際にも安心です。税理士に依頼していれば、帳簿の正確性が保たれ、税務署からの指摘にもスムーズに対応できます。日頃から税理士のチェックを受けることで、不備や誤りを早期に防ぎ、必要な書類も適切に整備できます。結果として、税務調査時のリスクを大幅に軽減できるでしょう。
さらに、税理士は経営全般のアドバイザーとしても頼りになります。単なる記帳代行にとどまらず、節税対策や資金繰り、最新の税制改正・インボイス制度への対応など、事業運営に役立つ実践的なアドバイスを受けられます。日常の疑問や不安も専門家の視点で解消でき、経営判断の精度向上にもつながります。
金融機関や税務署からの信頼も高く、融資申請時や税務調査時に税理士が関与していることで、書類の信憑性が増します。
税理士に依頼するデメリット
費用が割高になりやすい傾向があります。税理士へ「丸投げ」に近い形で依頼するほど、費用は高くなるのが一般的です。また、料金体系は「1仕訳あたり○○円」や「月額○○円で仕訳数は上限○○件」といった具合に、事務所ごとで大きく異なります。オプションの有無によっても最終的な金額が変わるため、総合的に見て適正価格かどうかを判断しにくい面があります。
また、社内に経理のノウハウが残りにくい点は記帳代行業者と同様の課題です。将来的な内製化を見据える場合は、定期的に記帳内容の説明を受けるなど、知識移転の機会を設けることが重要です。
税理士目線でアドバイス!税理士に依頼するメリット

髙谷 武司
税理士からのワンポイントアドバイス
税理士から見た、税理士に記帳代行を依頼するメリットを2つご紹介します。
1つ目は、税務調査を見据えて記帳が行われることです。証憑に基づいて正確に記帳されるのは勿論のこと、それ以上に重要なのは、税務調査におけるリスクをなるべく低減するよう、仕訳が入力される点にあります。例えば、仕訳の摘要に補足を入力しておくなど、税務調査をスムーズに進めるための対策が取られます。
2つ目は、経営や節税のアドバイスがより的確になることです。取引先や摘要の入力が疎かになると、データを基にしたアドバイスの質が低下します。一方、税理士が記帳する場合は、証憑を直接確認することになるため、試算表の解像度が増し、より的確なアドバイスが可能となります。
記帳代行は税理士以外にも依頼できる?
記帳代行は税理士だけでなく専門業者やフリーランスにも依頼可能で、それぞれ価格や対応範囲、品質に違いがあります。年商1,000万円を超える場合や税務申告も含めて依頼したい場合は税理士が適していますが、小規模で記帳のみを依頼する場合は記帳代行業者も選択肢となります。
記帳代行業者・フリーランスのメリット・デメリット
記帳代行業者やフリーランスは税理士より価格が安く柔軟な対応が期待できますが、対応範囲が記帳のみに限定され、品質やセキュリティにばらつきがあります。それぞれの特徴を理解して選択しましょう。
記帳代行業者の特徴
記帳代行業者は、仕訳帳や総勘定元帳など記帳に特化した代行サービスを提供しています。具体的には「領収書や請求書の内容をもとに帳簿を作成する」ことがメインで、税務相談や給与計算などの周辺業務は基本的に含まれません。
記帳業務に絞って依頼したい場合、コストを抑えながら必要最低限のサポートを受けられる点が大きなメリットです。料金相場(参考)は税理士より低めで、仕訳数100枚で1万円程度、200枚で2万円程度が目安です。
記帳代行業者・フリーランスのデメリットと注意点
対応範囲が記帳のみに限定されるため、税務相談や決算業務は別途依頼先を探す必要があります。記帳・決算・申告をそれぞれ別の業者に依頼すると、トータルコストが割高になる可能性があります。
品質やセキュリティにばらつきがあることも課題です。大手の記帳代行業者であれば一定の品質が期待できますが、個人事業主やフリーランスの場合は実績や評判の確認が重要です。
税理士法違反のリスクにも注意が必要です。税理士資格を持たない者が税務相談や申告書作成を行うことは違法です。記帳代行業者やフリーランスは記帳業務のみを請け負う範囲であれば問題ありませんが、境界線を理解しておく必要があります。
税理士に依頼することをおすすめする理由
課税売上高1,000万円超の消費税課税事業者や、税務申告・決算も含めて依頼したい事業者には税理士が最適です。節税対策、サポート体制、セキュリティ、実績面でも税理士には大きなアドバンテージがあります。
※原則、基準期間=前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。特定期間判定や任意の課税選択、インボイス登録などの例外もあるため、該当可否は個別確認が必要です。
税理士への依頼をおすすめするケース
事業規模が年商1,000万円を超えている場合は、消費税の課税事業者となり税務が複雑化します。この段階では記帳だけでなく、税務アドバイスも含めて税理士に任せる方が安心です。
税務申告や決算業務も一緒に依頼したい場合は、最初から税理士と顧問契約を結ぶことで、業務の一貫性が保たれ、やり取りもスムーズになります。
節税対策や経営相談を重視する場合も税理士が適しています。単なる記帳作業ではなく、経営判断の材料となる財務分析や、税負担を最適化するための提案を受けられます。
税理士・記帳代行業者・経理代行業者の比較
それぞれのサービス内容や特徴を比較すると、依頼の範囲やコスト、サポート体制に大きな違いがあります。
税理士事務所は、記帳業務から税務申告、税務相談まで一気通貫で対応可能です。幅広いサポートな分、費用は高めですが、税理士資格保有者が担当し、税務調査なども安心です。
記帳代行業者は、記帳作業がメインで、提携税理士がいれば申告も可能です。記帳に特化する分、比較的安価ですが、帳簿作成が中心で税務相談は範囲外です。
経理代行業者は、給与計算・支払処理・請求書管理など経理全般をアウトソーシングできます。業務範囲が広い分やや高コストで、経理負担を大幅軽減できますが、税務関連は別途対応が必要です。
サポート体制やセキュリティの面では、組織体制が整った税理士事務所が安心です。担当者が不在でも別のスタッフが対応できる体制や、情報管理体制が確立されています。
クラウド会計への対応については、近年は税理士事務所も積極的に導入を進めており、freeeやマネーフォワード、弥生会計オンラインなどの主要ソフトに対応している事務所が増えています。
記帳代行を税理士に依頼する場合の費用・料金相場
税理士への記帳代行費用は仕訳数に応じて変動し、200枚までで月額1万5,000円程度が相場です。顧問契約に含まれるケースと記帳のみのスポット契約があり、年商規模や消費税の課税状況によっても費用が変わります。追加費用が発生する条件を事前に確認することが重要です。
税理士・業者ごとの料金相場と内訳
税理士の記帳代行費用は仕訳数によって大きく異なり、記帳代行業者や経理代行業者と比較すると高めですが、税務申告までカバーする点を考慮するとコストパフォーマンスは良好です。
税理士に依頼する場合の費用相場
税理士に記帳代行を依頼した場合の料金相場(参考・目安)は以下の通りです。あくまで相場の一例ですが、税務申告や顧問契約など他の業務とまとめて依頼すると記帳代行が割安になることもあります。
- 仕訳数〜200枚:1万5,000円
- 仕訳数201〜300枚:2万円
- 仕訳数301〜400枚:2万5,000円
- 仕訳数401〜500枚:3万円
- 仕訳数501枚〜:3万5,000円
記帳代行業者・経理代行業者の料金相場
記帳代行を専門に請け負う業者は、比較的低価格に設定しているのが特徴です。目安としては「仕訳数100枚で1万円」「200枚で2万円〜」といった料金形態が一般的で、記帳に特化している分だけ税理士事務所よりも費用を抑えられるメリットがあります。
経理代行業者の場合「仕訳数100枚までで1万円」「200枚までで1万5,000円」「300枚までで2万円程度」が目安です。請求書管理や支払処理、給与計算といった経理全般をまとめて任せられるため負担が大幅に減りますが、税務申告まで含める場合は別途税理士との連携が必要になり、追加費用が発生することもあります。
決算申告料金とオプション費用
決算申告料金は、月額顧問料の3〜6か月分が目安です(業種・年商・訪問頻度・申告種類で増減)。顧問契約を行わず、決算申告のみを依頼する、いわゆるスポット契約の場合は、年に一度の決算時に決算申告料を支払います。
給与計算や年末調整については、事務所により設定が異なります。年末調整は従業員1人あたり3,000円〜5,000円程度が一般的です。
費用が変動する主な要因と見積もり時の注意点
記帳代行費用は仕訳数、資料の整理状況、消費税対応、クラウド会計の利用有無などによって変動します。見積もり時には基本料金に何が含まれ、どのような場合に追加費用が発生するかを明確にしておきましょう。
費用が変動する主な要因
仕訳数(取引件数)は最も大きな変動要因です。月間の取引件数が多いほど作業量が増えるため、費用も高くなります。飲食店や小売業など現金取引が多い業種は仕訳数が増加しやすい傾向があります。
資料の整理状況も料金に影響します。領収書がきれいに整理され、取引内容のメモがあれば作業効率が上がり、費用を抑えられます。逆に資料が不足していたり、乱雑な状態で提出すると、整理作業の追加費用が発生する場合があります。
消費税の課税事業者かどうかも重要な要因です。消費税の課税事業者になると、仕訳時に課税区分の判定が必要になり、作業が複雑化します。年商1,000万円を超えて課税事業者となると、課税区分やインボイス対応で作業は増え、記帳代行費用も上がりやすくなります。
見積もり時の注意点と安さだけで判断するリスク
クラウド会計ソフトの利用有無によっても変わります。クラウド会計を導入していれば、銀行口座やクレジットカードの取引が自動連携され、税理士側の入力作業が減るため、費用が割安になる傾向があります。
年末調整や決算業務の有無は、年間トータルコストに大きく影響します。記帳代行だけなら月額1万5,000円でも、決算申告で別途10万円〜15万円、年末調整で5万円〜10万円かかると、年間コストは大きく跳ね上がります。
見積もりを取る際は、基本料金だけでなく、どこまでが含まれているか、追加費用が発生する条件は何かを明確に確認することが重要です。
記帳代行サービスの料金は事業者ごとに異なり、「仕訳数当たりの単価が安い」からといって必ずしもお得とは限りません。業務範囲やサポート体制によっては追加費用が発生する場合や、コミュニケーション面で不満が出る可能性もあります。料金だけでなく、業者の実績・サポート範囲・追加費用などを総合的に検討し、自社に最適なサービスを選ぶことが大切です。
記帳代行を税理士に依頼する流れと必要な準備
税理士への記帳代行依頼は、問い合わせから契約、資料提出、記帳処理、納品まで通常1〜2週間のサイクルで進みます。必要書類を事前に整理し、クラウド会計を活用することで、業務効率が大幅に向上し費用削減にもつながります。
税理士への依頼から完了までのフロー
問い合わせから完了までは7つのステップで進み、契約前のヒアリングで業務範囲や費用を明確にすることがトラブル回避の鍵となります。
依頼の流れ
1. 問い合わせ・初回相談
まず税理士事務所に問い合わせを行い、初回相談の日程を調整します。多くの事務所では初回相談を無料で実施しています。この段階で事業内容、取引規模、現在の記帳状況、依頼したい業務範囲などを伝えます。
2. ヒアリング
税理士側が詳細なヒアリングを行い、月間の取引件数、使用している会計ソフト、資料の整理状況、決算月、消費税の課税状況などを確認します。この情報をもとに最適なプランを提案してもらえます。
3. 見積もり提示
ヒアリング内容に基づいて、具体的な見積もりが提示されます。月額顧問料、記帳代行費用、決算報酬、オプション費用など、項目ごとに明細を確認しましょう。
4. 業務委託契約の締結
見積もり内容に納得できれば契約を締結します。契約書では、業務範囲、報酬額、支払い時期、納期、秘密保持、契約期間、解約条件などを確認してください。
5. 資料の提出
契約後、毎月定期的に必要書類を税理士事務所に提出します。提出方法は、郵送、訪問時の手渡し、オンラインでのデータ共有など、事務所によって異なります。
6. 記帳処理
税理士側で仕訳入力と帳簿作成を行います。処理期間は通常1週間〜2週間程度ですが、月次決算まで含む場合はもう少し時間がかかることもあります。
7. 記帳結果のチェック・レポート
記帳が完了すると、試算表(貸借対照表・損益計算書)や仕訳帳などが納品されます。定期的な面談がある場合は、この際に財務状況の説明や経営アドバイスを受けられます。
提出が必要な書類と準備のポイント
領収書、通帳コピー、請求書など日々発生する書類を月ごとに整理して提出することが基本です。資料が整理されていれば税理士側の作業時間が短縮され、結果的に費用の削減につながります。
必要書類一覧
記帳代行を依頼する際に提出が必要な主な書類は以下の通りです。
- 領収書・レシート:経費を証明するため、すべての経費支出について必要
- 請求書・納品書:売上・仕入を確認するため、発行分と受領分の両方が必要
- 通帳のコピー:入出金履歴の裏付け資料として必要
- クレジットカード明細:カード経費を計上するために必要
- 現金出納帳:現金管理を明確にするため(自社で作成している場合)
- 給与明細・源泉徴収簿:給与計算や源泉税の処理が必要な場合
書類整理のコツ
整理のポイントとしては、月ごとにクリアファイルや封筒で分けておく、レシートは台紙に貼る、取引内容が分かりにくいものにはメモを付ける、といった工夫が有効です。
資料を時系列や取引先ごとに分類しておくと、代行業者がスムーズに仕訳を行えるだけでなく、確認や修正のやり取りも最小限で済むでしょう。また、経理に関する過去のデータや会計ソフトの設定情報などもまとめておくと、引き継ぎがスムーズになり、導入後すぐに本来の業務へ集中できます。
クラウド会計・オンライン対応のメリット
クラウド会計を活用すれば銀行取引が自動連携され入力作業が削減されるだけでなく、税理士とリアルタイムで情報共有でき、書類の郵送も不要になります。freee、マネーフォワード クラウド、弥生会計オンラインなどが代表的で、月額1,000円〜3,000円程度の利用料で大幅な業務効率化が実現します。
主なメリットとして、
- 銀行口座やクレジットカードの自動連携によるAI仕訳で入力作業が削減され、記帳代行費用も抑えられること
- 税理士と同じソフトにアクセスできるため最新の財務状況をいつでも確認できること
- 領収書をスマホで撮影してアップロードするだけで郵送が不要になること
- 全国どこからでもオンライン対応可能になること
が挙げられます。クラウド上にデータが保存されるため、パソコンの故障やデータ消失のリスクもありません。
記帳代行を税理士に依頼する際の注意点とよくある失敗例
契約時には料金体系、サービス範囲、納期、追加費用の発生条件を明確にし、運用時には資料の整理と期限厳守を心がけることがトラブル防止の鍵です。
契約・運用時に気をつけるべきポイント
料金体系とサービス範囲は、基本料金に何が含まれるか、仕訳数の上限、月次決算・税務相談の対応範囲を文書化して明確にします。納期と追加費用は、試算表の提出期限(例:翌月10日まで)と、仕訳数超過や資料不備時の追加費用条件を事前に確認しましょう。事務所の体制として、担当者不在時のバックアップ体制、同業種の実績、セキュリティ対策、契約期間・解約条件も確認が必要です。
よくある失敗例とその対策
書類不備:
領収書の紛失や取引内容不明により追加費用が発生。対策は受け取り後すぐにファイリングし、不明なものはメモを残すこと。
業務範囲の誤解:
税務相談や決算業務が含まれると思っていたが別料金だったケース。対策は契約時に業務範囲を具体的に文書化すること。
納期遅延:
資料提出の遅れや繁忙期で試算表が遅れるケース。対策は資料提出期限の厳守と、繁忙期(2月〜3月、5月)を考慮した余裕あるスケジュール設定。
記帳代行の依頼でトラブルになるケースとは?

髙谷 武司
税理士からのワンポイントアドバイス
記帳代行でトラブルになりやすいのは、納期と料金です。
納期で言うと、まず、依頼者からの資料提供が遅いケースがあります。税理士側は、スケジュールに合わせて人員を確保しています。そのため、資料の提供が遅れると、適切な人員の確保が困難になり、仕訳や試算表の納品も遅れることになります。一方、税理士からの納品が遅れるケースもあります。この場合は、試算表のデータ確認が遅れるため、経営に活かすことが難しくなります。
また、期末付近になると、資料の提出が遅れることにより、記帳代行の業務負荷が大きくなることがあります。この場合、追加で特急料金などが請求されるケースがありますが、事前の説明がないなど、トラブルに発展することがあります。
まとめ
記帳代行を税理士に依頼することで、記帳業務の負担軽減だけでなく、税務申告や経営相談まで一貫したサポートを受けられます。単なる作業代行ではなく、事業の成長を支えるパートナーとして税理士を活用することで、本業に集中しながら適切な税務処理と経営判断が可能になります。費用面では記帳代行業者より高めですが、税務のプロとしてワンストップ対応できる点や、税務調査への安心感、経営全般のアドバイスを受けられることを考えれば十分な価値があるでしょう。まずは複数の税理士事務所に相談し、自社に合った料金体系とサービス内容を比較検討することから始めてみてください。
専任のコーディネーターが最適な税理士をご紹介する「税理士紹介センター」では、記帳代行に強い税理士を無料でご紹介しています。事業規模や業種に応じた税理士選びから、費用面の相談まで、丁寧にサポートいたします。
よくある質問
Q:記帳代行は税理士と業者どちらが良い?
年商や事業目的によって最適な選択肢は異なります。年商1,000万円超の課税事業者や税務申告も含めて依頼したい場合は税理士が適しており、小規模で記帳のみを低コストで依頼したい場合は記帳代行業者も選択肢となります。記帳・決算・申告をトータルで考えたときのコストと手間を比較して判断しましょう。
Q:記帳代行の費用はいくらかかる?追加料金はある?
税理士に記帳代行を依頼する場合の費用相場(参考・目安)は、仕訳数200枚までで月額1万5,000円程度、300枚までで月額2万円程度です。追加料金は仕訳数の超過、資料不備、イレギュラーな取引の処理などで発生するため、契約時に発生条件を明確にしておくことが重要です。
Q:どんな書類を用意すればいい?
領収書・レシート、通帳のコピーまたはネットバンキングの明細、請求書・納品書(発行分・受領分)、クレジットカードの利用明細、現金出納帳(作成している場合)が基本的な必要書類です。従業員がいる場合は給与明細や源泉徴収簿も必要になります。月ごとに整理してファイリングし、取引内容が不明なものにはメモを付けることで、税理士側の作業がスムーズになり費用削減にもつながります。
Q:クラウド会計と連携できる?
多くの税理士事務所がfreee、マネーフォワード クラウド、弥生会計オンラインなどの主要クラウド会計ソフトに対応しています。銀行取引の自動連携により入力作業が削減され、リアルタイムでの情報共有やオンライン対応が可能になり、書類の郵送も不要になります。ただし、クラウド会計ソフトの月額利用料(1,000円〜3,000円程度)が別途発生する点は考慮が必要です。
Q:いつ依頼するのがベスト?
創業時・開業時、年商1,000万円超の課税事業者になったとき、仕訳数が増加して経理業務に割く時間が増え本業に支障が出始めたとき、融資申請前、税務調査の通知時が主な依頼タイミングです。特に消費税の課税事業者となる年商1,000万円超のタイミングや、記帳業務が本業の負担になってきたと感じたときは、早めに税理士への依頼を検討しましょう。

- この記事の監修者
- 髙谷公認会計士・税理士事務所
代表 髙谷 武司(税理士・公認会計士)
事務所公式ホームページはこちら
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税理士・税理士探し >
- 記帳代行は税理士に依頼すべき?メリット・費用・選び方を徹底解説